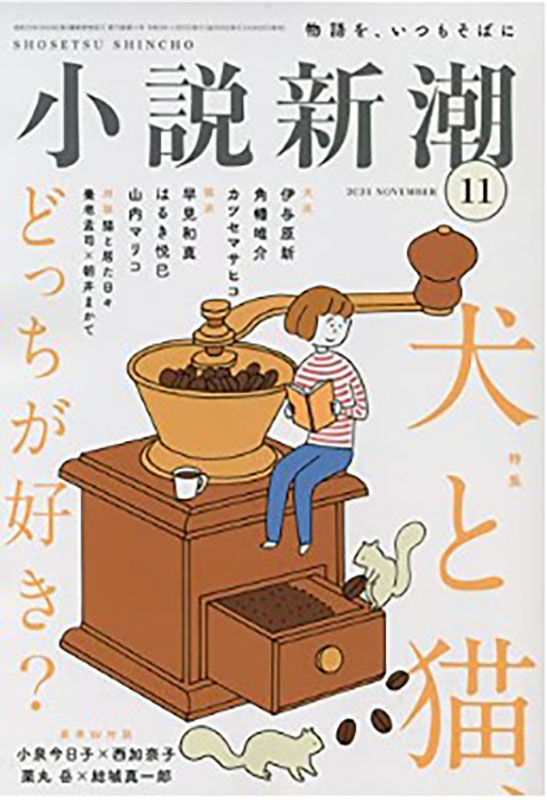
ちょっと前に上野のパンダちゃんが中国に返還されましたわね。ニュースを見てるとすんごい泣いてる人が多いのよ。「シャンシャンちゃん、ありがとう」とかむせび泣いていらっしゃるの。
しょっちゅう思うのは、街頭インタビューなのにどうしてこんなに視聴者が求めるドンピシャなアンサーをする人がいるのかってことね。当然多様な答えが返ってきたでしょうが、たくさんインタビューしてセレクトしてるわけよね。もし反中国系のメディアがあればそういった文脈で前フリを作り、街頭インタビューもそれに合わせた内容のアンサーにするでしょうね。あ、アテクシ、メディアの偏向報道を批判しているわけでも、パンダちゃんが嫌いなわけでもございませんことよ。むしろパンダちゃん大好き、かわいいもの。
ただマスメディアが伝えるのは文字通り〝マス〟つまり大多数の主流派意見が多ございます。マイノリティ(少数派)意見を発信することこそマスメディアの役割とお考えになる向きもあるでしょうが、主流派の意見(オピニオン)がはっきりしていないと問題軸が見えて来ないところがあります。
アテクシ少し前に関節炎で整形外科に通っていましたのよ。痛みって当たり前ですが人と共有できません。めったにそんなこと起こらないので、アテクシとしたことが大慌てで「痛いよぉぉぉっ」とお医者様に駆け込んだわけです。
で、どーなったかといふと製薬会社が作ったB5判くらいのカラー印刷を渡されて、「あなたの症状はここに書かれている通りです。それほど珍しい症状ではありません。治療方法もパンフに書かれている通り。よほどのことがない限り手術とかは必要ないでしょう」と言われたのでした。
これも当然と言えば当然なんですが、「あー人間の身体って基本、同じなのねぇ」と思いましたことよ。例外を言い出せばきりがないですが、コロナに罹ってもインフルでもマジョリティの症状は同じ。放射能とか一酸化中毒とかでもレッドゾーンに達すれば人間の身体は耐えられません。比較的健康である限り無意識的にであれわたしたちは、社会のマジョリティに属しているわけですわ。
病気で食べられなくなった人は「テレビってなんて食べ物番組が多いのかしら」ってよく言いますわね。身内に不幸があった時なんかも、テレビなんかはいかに死や病気のイメージを避けているのかがわかるような気がする時があります。それはそれでいいことだと思いますのよ。まずマジョリティを認識することって大切ですわ。そうしないとマイノリティとの対立軸はもちろん、融和点の形も見えてこない。
アテクシ、文学は基本、弱者の表現だと思っております。社会的弱者のための表現という意味ではなく、一時的な心情的弱者の領域を含みます。またそれはマジョリティに対立するマイノリティのための表現という意味ではなく、マジョリティとマイノリティの中間にある表現であることが多いと思います。よほど特殊な心理的・肉体的状況に置かれた主人公でない限り、完全にマイノリティに属してマジョリティに対立する人って少ないですわ。マジョリティに属しながらマイノリティとして疎外されている、あるいはマイノリティですがマジョリティへの憧れや希望を持っていることが圧倒的に多いわけですから。
小説が多くの読者を獲得する場合は圧倒的にグレーゾーンを描いた場合が多いですわね。つまりマジョリティとマイノリティの対立を意識的に捉え、そのグレーゾーンの世界を描くわけですわ。そこからどちらに抜けるか、あるいは抜けずに留まるのかは作家様次第。簡単に言えば小説、特に大衆小説の場合、作家様が高い社会性を持っていないと読者の心を〝ツカム〟ことが難しいってことですわ。
「フクスケ」
ドッグフードをなかなか食べず、人が食べているものばかり羨ましそうに見ていた。刺身を食って全身の毛が嘘のように抜けたこともあった。考えてみれば変なものばかり食べていた。
「ねえ、フク」
若いうちは他の犬への対抗心がすごくて、相手がどんな大型犬だろうが、構わず吠え散らかした。なぜか女の人にだけ甘え上手で、姉貴の友達にはすぐに、腹を見せていた。俺にはそんな仕草、ほとんどしてくれなかったのに。
「ありがとうね」
何度も頭を撫でていると、少しずつ温もりが手に返ってくるような気がする。でも、フクの名前を呼ぶたび、脳や心は、その死を実感していく。涙が溢れ出して、鼻水も、母さんの比じゃないほど垂れ出した。それでも俺は、何度も何度も、フクの名前を呼んでいたかった。
カツセマサヒコ「笑う門」
カツセマサヒコ先生の「笑う門」は父親から十三年間飼っていた犬のフクスケが死んだと連絡を受けた大学生の僕が、久しぶりに実家に帰った短編です。
犬や猫のペットを飼ったことがある人には身につまされるというか、あるあるの経験ですわね。アテクシは実家で猫を飼っていましたが、子猫の頃は家族全員で猫の気を引こうと必死で、あの手この手を使って疲れ果てたことがよくありました。
まあペットは言ってみれば無償の愛を注ぐことができる対象です。ただ生き物ですから飼い主の愛に対して反応してくれたり、無視されたりするのがいいところなのよ。もちろん飼い主より先に死ぬのも言ってみればペットの重要な役割です。「笑う門」の俺のようにわんわん泣いたりするわけです。だけどそういう経験って人間の生活の中で実はそんなに多くないのです。
「先に子供が亡くなるのは、親不孝だと、よく言いますよね」
「はい」
「あれはね、嘘です。嘘というかね、親の勝手な言い分です。生死についてはね、順番なんて関係ないですよ。もちろん、流す涙の量も、関係ないです。結局、残された人は、その人なりに残された事実を悲しみながら、亡くなった人を忘れないように生きることしかできないんですよ」
日が少しずつ、高くなってきていた。澄んだ薄い空は夏のそれよりもずいぶん高く感じられて、そのことを強調するように、米粒ほどの大きさの旅客機が、遠くでゆっくりと飛んでいた。
「フクくんにも、そんな気持ちでいてあてげくださいね」
「いや、家族と飼い犬じゃ、またちょっと」
「いえいえ、違わないです」
三重原さんは、どこか晴れやかな目元を見せて言った。
「うまく泣けなくても、あなたは辛かった。ご両親も、辛かった。そうやってね、悲しみとか苦しみは、他者と比較するものじゃなくて、当社比でいいんですよ」
上空を小さな鳥が二羽、飛んでいった。さっき見た鳥と同じだろうか。ピピピ、ぴぴぴ、と嬉しそうに鳴いて、その姿はすぐに見えなくなった。
(同)
僕は父親から近所に住む三重原さんという方の息子が三十四歳の若さで亡くなったと聞かされます。親しくはなかったですが、三重原さんのお兄ちゃんとして憶えている人でした。僕は実家に泊まり、翌日フクスケとよく散歩した道を辿ります。その途中で三重原さんに会う。三重原さんは「フクくんのこと、聞きました」「いい子でしたねえ、よく、懐いてくれていました」と僕に話しかけ、亡くなった息子のことを話し始めたのです。
三重原さんの話は人間の死がペットのように単純なものではないことをよく表しています。三重原さんのお兄ちゃんがどういう亡くなり方をしたのかは書いてありませんが、若くして亡くなっても年老いて亡くなっていても同じことです。人間はペットとは時の流れ方が、自分にとっての生の厚みが圧倒的に違う。
近親者が亡くなってわんわん泣くのは当たり前と言えば当たり前ですが、それでも泣いても泣ききれないようなところが残る。ペットのように悲しみを決して純なものにすることはできないのです。様々な後悔や申し訳ない気持ちをずっと抱えたまま生きていくしかありません。その悲しいけど傷のように残り、消しても消しきれない傷としか言いようのないものが近親者の死です。それがよく表現されています。人間だけが抱えることができる本質的にグレーの領域です。
今もこうして、フクがいたから姉貴は泣いていて、母さんは笑っている。
母さんが、ティッシュ箱を姉貴に渡した。
「フクは幸せものだね」
そう言った母さんを見て、俺も親父も、少しだけ笑った。
「四人、あー、五人か? 揃うもの久しぶりだし、酒でも飲むか」
普段はアルコールを嫌う親父が、また、らしくないことを口にした。
(同)
僕の父親は極度の出不精なのに、僕が実家に泊まるというと寝間着を買うために「一緒にユニクロでも行くか?」と言います。父親としては異例の提案です。姉が帰ってくると「酒でも飲むか」と言い出します。
小説はクライマックスである僕と三重原さんの会話を挟んでペットのフクスケの方に戻ってきます。フクスケがペットとして僕の家族に果たした役割、その影響がきっちり回収されています。フクはいいペットだったということですね。
佐藤知恵子
■ カツセマサヒコさんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


