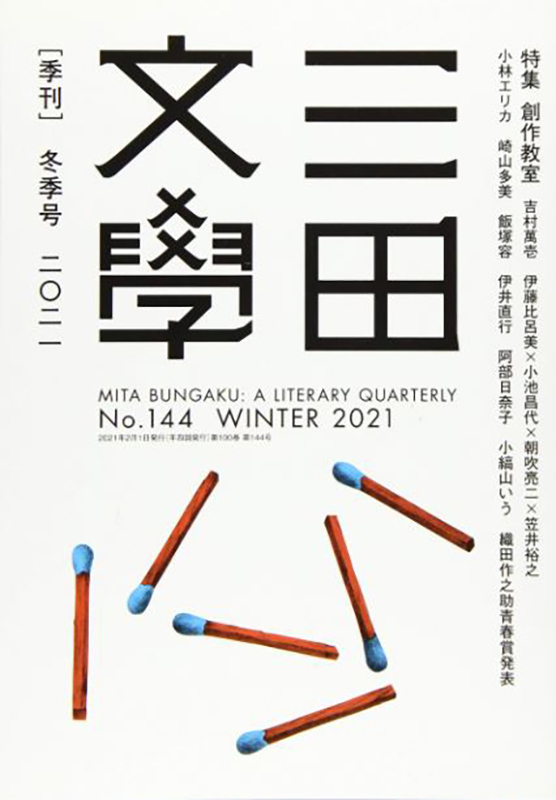
今号の巻頭小説は小林エリカさんの「交霊」。マンガ家で小説家でもある作家である。ストーリーテーラーとしては申し分のない実力をお持ちだ。俗な言い方になるが作品に知的なスパイスを散りばめるのにも長けておられる。有名文学賞などの素晴らしいお墨付きがあるから読めと言われても「これは修学旅行で強制的にやらされる座禅の修行ですか」と言いたくなるようなクソつまらない純文学小説は、どう考えても今の世の中、下火にならざるを得ないだろう。小説は事件が起こる物語であり、かつ作家がどうしても表現したいテーマがあることで読み進められるかどうかが決まる。純文学的アトモスフィアなど糞食らえですな。
この女はイカサマだ。
彼女はひとりごちた。
女の年は幾つくらいだろうか。口元の皺や顎のたるみからすれば五十歳近くだろう。袖に大きなパフがついたブラウス、黒のタックがきいたロングスカート。如何にも地味な格好をしている。コルセットを無理やりきつく締めているせいで、胸の包みボタンがいまにもはちきれそうで目立ってみえた。
女の名前はエウサピア・パラディーノ。
イタリアからやってきた女霊媒師。
(小林エリカ「交霊」)
小説は交霊術の会場から始まる。エウサピア・パラディーノは十九世紀末の実在の人物だ。その場面に「彼女」がいる。最初の主人公である。彼女はパラディーノという、詭弁家でもあった霊媒師を「この女はイカサマだ」と見抜く。ではこの小説はインチキ霊媒師の手口を見破る物語なのだろうか。違う。世紀末のパリから物語が始まるので外国を舞台にした時代小説なのだろうか。それも違う。霊媒師も世紀末パリも、この小説でほかにも多く使われている小道具に過ぎない。
あの女――マリ・キュリー――の家は、パリ13区ケレルマン大通108にあった。(中略)
彼女は部屋の真ん中で、あの女とその夫が科学について議論しながら夜の営みに励むのをじっと眺めた。(中略)
喜びの声を漏らすあの女は、ときどき枕元の青白い光を放つ小瓶に手を触れた。
妖精の光。(中略)
というのも、妖精の光と呼ばれるそれ――放射性ラジウム――は、かつてはだれの目にも見えず、その存在をだれひとりとして信じなかったらしいから。(中略)
目に見えなかったものが、見えるようになる。
やがて霊という存在も、科学者たちの力で目に見えるようになるかもしれない。
(同)
主人公の彼女はパラディーノの交霊会に出席していた夫婦の後を追って家に行く。マリ・キュリーはキュリー夫人である。夫のピエールとともにノーベル賞を受賞した科学者だ。マリは放射能(radioactivity)の名付け親でもある。ではこの小説はフクイチ原発事故以来小説で盛んに用いられるようになった放射能問題を扱っているだろうか。それも違う。キュリー夫妻が放射能を発見した後、レントゲンなどでそれまで見えなかったものが見えるようになった。また夫のピエールは交霊に強い興味を示してもいた。主人公はキュリー夫妻によって「やがて霊という存在も、科学者たちの力で目に見えるようになるかもしれない」と期待する。なぜなら彼女は霊だからである。
彼女は孤独だった。
生きていたときも孤独だったが、死んでも孤独だった。
いつだってその人生は無視されどおしだ。
親からも、兄弟からも、友人からも、嫌々結婚した夫からも、自分が産んだ息子からさえ。(中略)
だれかほかの霊の仲間に会えるかもしれない。彼女は墓場や病院へまで出かけていったが他の霊と会ったことさえ一度もなかったのだ。
(同)
彼女は生きている間も孤独で、亡くなった後も孤独である。霊になってもまったく仲間に出会うことがない。人間界を彷徨い続け、人間たちの声を聞き営みを見るが、誰一人彼女に気づいてくれない。生きている人間たちはいつの時代も霊の存在を疑いながら信じ、霊界と交信したいと望んでいるにも関わらずである。つまりこの小説のテーマは人間の孤独である。それによってこのフィクショナルな設定が人間存在の根源的なテーマにつながる。
それは母がひたすら録音していた霊の声のデータだった。
幾つか再生してみると、それぞれ別の霊の機械翻訳された声があった。
果たして、何のために母は霊の声を集め、録音していたのかは、わからない。(中略)
声が言った。
この女はイカサマだ。(中略)
それが後年、私がここに書き記すことになる、彼女の話である。(中略)
いま、ここにこうしてここに彼女の話を書き、その声をなぞりなおすことで、私はどこか心の底で安堵する。
そうするときにだけ、ふたたび彼女がこの世界に生きているような気がするから。(中略)
私は大きく息を吸い込む。
両方の手をキーボードの上に広げ、タイプする。
明るい部屋で、いま私は、なんのインチキも、特殊な技能も、機械もなしに、霊と交わっていた。
(同)
最後のどんでん返しは、それまで主人公で語り手だった彷徨う霊の「彼女」の話は、この小説を書いている「私」の亡くなった母親が、パソコンに溜め込んでいた音声データの文字起こしだということである。
日本で霊と交信できるマシンが発明された。声で霊とで交信できるのだ。マシンは一大ブームを巻き起こし世界中で売れたが、いつのまにかそれも下火になってしまった。猫語犬語翻訳機と似たようなもので、交信はできても真偽不明だからやがて飽きられてしまったわけだ。
ブーム真っ盛りの頃、私の母は母の母(私の祖母)と交信したくてマシンを使った交霊会に出席していた。霊とは交信できなかったが、そこで知り合った男との間に私を妊娠した。男は母にも私(娘)にも興味がなく、霊との交霊マシンを渡して母娘の前から姿を消してしまった。母は一人で私を育てながらマシンを使って密かに霊と交流し続けていた。そのデータを母の死後、私が発見し、その内容を文字に書き起こしたのである。もちろん母がストックしていた霊との交信の真偽は不明である。
ただこの途中まで落とし所が難しい小説は〝母〟によって着地点を見出している。霊に関しては存在すると言っても存在しないと言っても小説は成立する。素材としてはどちらでもかまわないわけだ。ただ多かれ少なかれ現世を孤独に生きる人間精神は高次のなにかを求めている。そして小説である限り、それは現世を少しだけ超脱しながら現世に戻って来なければならない。
死ねないまま現世を漂う彼女と自分を棄てた男からもらった交霊マシンを使い続けた母、そしてその母が残した音声データに聞き入りそれを文字に起こすわたしの存在(孤独)は底の方で繋がっている。ただこの物語は母-女の物語でなければ説得力を持たないでしょうね。短編だが贅沢に素材を使った小説である。
池田浩
■ 小林エリカさんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■










