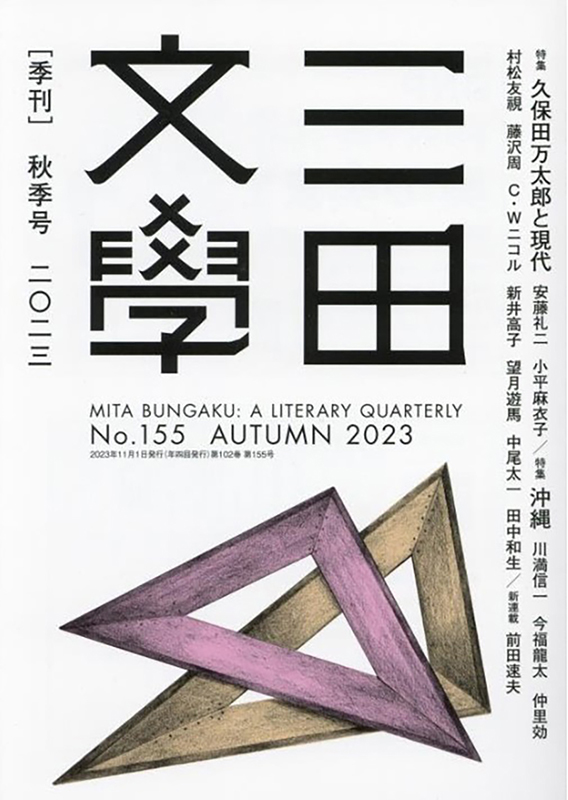
今号の小説は村松友視さんと藤沢周さんの二本。大物と中堅作家の並びで三田文學では珍しく新人作家の小説はナシ。村松さんは昭和十五年(一九四〇年)生まれなので今年で八十三歳におなりです。八十代でもお若い方はたくさんいらっしゃいますが、年齢的にはもう大家ですね。久しぶりに村松さんの小説を読んだなぁという気がします。
『龍王閣』という小説で、ある大手雑誌の独身編集者が忙しい月刊文芸誌の編集部に転属になることが決まり、それを機に会社近くのアパートを借りる。その名前が龍王閣。時代設定は安保闘争真っ只中の一九七〇年。風呂が岩風呂風だったり襖が鏡張りと奇妙な間取りの部屋とある。ただ怪異モノではない。私小説とも違う、淡い感じの、うーん、これも純文学なんだろうな。
主人公は友人に頼まれて、警察から追われているという学生を部屋に匿うことになる。学生は言葉少なで自分がどんな活動をしているのかはほとんど語らない。学生を匿うくらいだから主人公は当時の反体制運動に共鳴している。が、勤め人の淡い共感でしかないので学生に根掘り葉掘り尋ねたりしない。学生は数日主人公の部屋にいて「お世話になりました」という書き置きを残してふっといなくなってしまう。小説のクライマックスは主人公の「俺の次の役は何なのかな?」という呟き。戦後の動揺する社会の中で、受け身のまま事件が降ってくるのを待っている市井のサラリーマンを描いた小説だと言えましょうか。
で、本当に本当に申し訳ないのですが、現役感がないな、と思ってしまった。小説の時空間が一九七〇年なのはなんら問題ない。しかし二〇二三年に一九七〇年代を舞台にした小説を書くのなら切迫した理由が必要だ。それが感じられない。世相にそれなりに敏感に反応しながら行動を起こせない主人公の姿は村松さんにとって大きなテーマになり得るものなのだろう。ただ、これも本当に申し訳ないのだが共感できない。同世代に向けた小説なのかもしれないが勢いがない。
正直に書くと、小説家はいつまで現役でいられるのだろうと考えてしまった。小説は原則、現世の物語である。現世の色恋と金が小説の原動力だと言っていい。現代小説なら風俗を取り入れ、過去が舞台なら社会システムは違うがそこで現代と変わらぬ普遍性を探し出して表現しなければならない。しかしずっと現世的妄執を維持するのは難しい。たいていの小説家は小説を書く以上、いつまでも生臭くあろうとする。そこに若い頃とは質の違う背伸びが見え隠れしてしまったりする。だが『龍王閣』のように色恋金抜きで小説で枯れ切るのも、これはこれで難しい。小説の難しさですねぇ。
――俺は、こんげとこで、相撲なんて取ったことねえわや。何言うてん。
おそらく、学校や町で喧嘩ばかりしていた息子の素行のせいで教師に呼び出されたことや、柔道部にいたことなどが、母親の中で奇妙な記憶となって定着してしまったのだろう。
――何言うてんのう、あんた。最後にもの凄い強い相手とやって、意気投合して、ほら・・・・・・。
すでにあの時は、母親は特養の施設に入っていたはずだ。墓掃除に一緒に行ったかは忘れてしまったが、施設で外出許可をもらって弥彦神社に参拝に来た時のことだ。
一体、誰の、何の話と混同していたのか。あるいは、母親が見た夢なのかもしれないが、私も相手も赤い褌をつけていて、ぶつかり、ねじり、締め上げ、投げ合い、それでも決着がつかなかったのだという。
――赤い褌って・・・・・・何だや、鬼、みてらねっかや。
――鬼、わらね。
そうこともなげにいって、私の顔を見上げ、面白そうに目尻に幾重もの皺を寄せたのだ。
藤沢周「外道丸」
藤沢周さんの「外道丸」は亡き母を巡る一種の私小説。父親はすでに亡くなっている。一種のというのは実体験にフィクショナルな設定が付加されているからだ。赤い褌を締めた鬼がそれに当たる。ただ主人公の私は鎌倉住みだが新潟の実家を頻繁に訪ね、できる限り母親の介護をしたのでの鬼のような息子ではない。
・・・・・・老母がなぜ弥彦神社の相撲場で、妙な妄想を喋り出したのか。ようやく分かったような気がする。あえて辛辣な冗談を言って試したとも思えるし、認知症であの地に伝わる話が、本人の中では現実となっていたとも考えられる。いずれにしろ、息子は、赤い褌をつけた「鬼らわ」ということだ。
もう一本煙草に火をつけて、ゆるゆると弱く煙を吐き出した。誤嚥性肺炎で入院して、胃ろうにするかどうかと院長と相談を何度もしているうちに、母親は亡くなった。自分でも驚くほど悲しさを微塵も感じず、涙の一粒も零さなかった。「最後まで介護をやったから、悔いがないということだな」と言ってくれた友人らもあったが、私にはそうは思えない。
――ほんに、あんたは、馬鹿らわねえ。
そんな言葉を仏となったばかりの母親から聞いたような気がする。最後の最後まで気の休まらぬ介護に明け暮れさせたのは、むしろ逝ってのちに悲しみとさせないためだったか。老母からの行李いっぱいの文のようなものであったかもしれない。
同
私は墓掃除のために故郷の新潟を訪れ、所要があって京都に回る。京都の居酒屋で相客から大江山の酒呑童子と茨城童子は越後の出だと聞かされる。しかも母親といっしょに見た弥彦神社で二人が相撲を取ったという伝承があるのだという。その伝承を母親が知っていて、私が弥彦神社で相撲を取っていたという妄想になったのではないかと思う。
また相客は酒呑童子と茨城童子は美男子で、村の若い娘からたくさんの恋文が届いていたのだと言う。その恋文を酒呑童子が焼き、血で書かれた恋文を茨城童子が舐めた瞬間に二人は鬼になったのだと。この話を聞いた居酒屋の女主人が、恋文は「母親が書き続けたんとちゃうやろか」「言うこと聞かんと、迷惑かけてんのやろ? せやから、若いオナゴの振りして、これやめたって、あれせんといて、ほなら、なんぼでも身をまかせますぅ、言うてな」と口を挟む。私は母親が介護で私を悩ませたのは、「逝ってのちに悲しみとさせないため」の「行李いっぱいの文のようなものであったかもしれない」とも思った。
「大丈夫ですか」
なんでまた自分は若い女性などと思ったのだろうか。腹の内で唸りながら歩道に転がったトマトやパックの豆腐などを拾って、手渡そうとした。
「すんまへん。袋が破れてもうて・・・・・・」
その老女が俯かせていた顔を上げた時、思わず息を呑んだ。
・・・・・・おふくろ!?
放心したまま、拾った品や日傘を渡していると、膝か腰が悪いのかゆっくりと痩せた体を起こした。ワンピースの広がった胸元から骨の影が浮き出て、必死に買い物袋を縛る細い腕の静脈のふくらみや、節くれた指・・・・・・。
「ほんま、おおきに・・・・・・」
まじまじと老いた女性の顔を見ると、目も鼻も口もまるで老母とは違った。違ったが、母親本人だと思っている自分がいた。
同
翌日私は一条戻橋に行く。居酒屋の相客から渡辺綱が茨城童子の腕を伐った場所であり、亡くなったと思われていた文章博士・三善清行が息子の祈禱で息を吹き返した場所でもあると聞いたからである。一条戻橋は「古来、「あの世とこの世をつなぐ橋」とも言われてきた」。私は橋で買い物袋の中身をぶちまけてしまった老女を助ける。「おふくろ!?」と思う。ここがこの小説のクライマックスでしょうね。
藤沢周さんは芥川賞作家だが近作の『世阿弥最後の花』などでいわゆる中間小説もお書きになる意欲的作家である。「外道丸」にも鬼、酒呑童子、茨城童子、戻橋など複数の仕掛けが施されている。ただ鬼が荒ぶる私の心の象徴なのか、成敗されなければならない心の闇なのか、今ひとつはっきりしない。私が新潟から京都に移動したように、次々にイメージが湧きそれが転々としてゆくならもっと淡い心理の流れの書き方の方がふさわしかったかもしれない。主題は母親をどんなに献身的に介護し心配しても必ず残ってしまう私の悔いである。それは強烈なものであるはずだが物語を膨らませるための仕掛けでかえって曖昧になってしまったような気がする。妄言多謝。
池田浩
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


