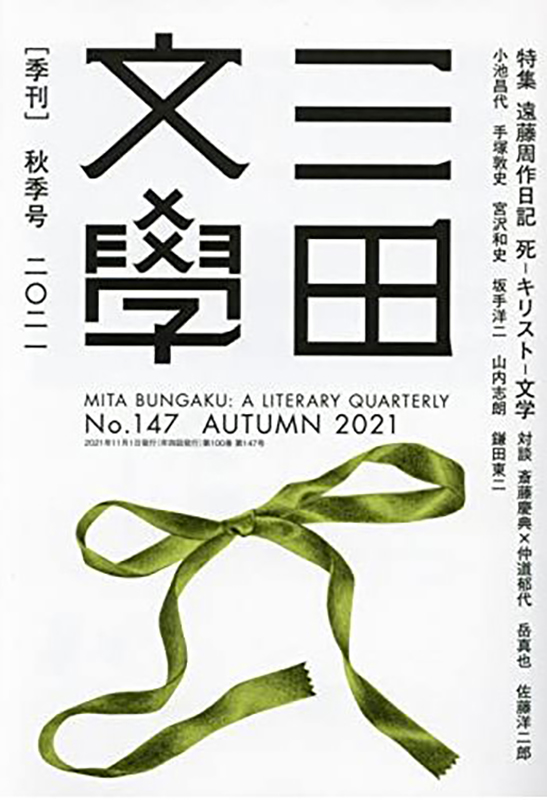
三田文學さんは今号も百花繚乱ですねぇ。どんどんその傾向が強くなっていく感じ。詩や小説ばかりでなく、戯曲、音楽、映画、短歌批評、文芸批評、民俗学批評なども掲載されている。THE BOOMの宮本和史さんの琉球歌謡歌詞論、岡進平さんの浅草芸能史論と盛りだくさんだ。ただどうも統一感が見えないんだなぁ。文芸誌はよく特集ページを組むが、言い出しっぺが一人いて編集部員が協力するのが普通である。三田文學は編集部員(?)が何人かいて、特集の代わりにそれぞれがそれぞれの興味に沿って〝推し〟の短い原稿を掲載している感じ。編集長が強力に雑誌を束ねているわけではなく合議制だから中心がない。だから華やかだが何をやろうとしているのかイマイチわからない。慶應在学者と卒業生中心になるのは当然だが、じゃあ今の三田文學の屋台骨というかスターは誰かというと見当たらない。吉増剛造さんでないのは確かかな。
だいぶ前に詩人の方と話す機会があったが、吉増さんは今じゃ詩壇の超大物らしい。それで三田文學発行人が吉増さんなのかと納得した。しかしまーなんか違和感がありますね。僕の吉増さんのイメージは「徹子の部屋」には出演させられない人というものだ。徹子さんに「アナタ、幽霊見えたりキツネが憑いたりするんですってね。ちょっとやってみて」と言われて切り返せる人だとは思えない。つーかそんなことを言い出しそうな人には絶対近づかないタイプだろうな。理解者やファンの前にしか姿を現さないという意味ではカリスマかもしれないけど、社会性に難があるんじゃなかろか。そこが大物といってもゴロウ・デラックス(稲垣吾郎さん司会だった)に出演できる谷川俊太郎さんとの違いかな。表舞台に立たせられない詩人が詩壇の超大物でいいのかな、という気はちょっとする。
こんなことを書くと今はすぐディスったとか総攻撃にあったりするが、「そんなこと言うの、ヒドイよー」と言われても根本的な違和感が消えるわけではない。吉増さんはどこかのインタビューで「詩人になるのが目標だ」という意味のことをおっしゃっていたが、この詩人の本質をよく表していると思う。杓子定規に言えば詩人になるのが目的であって詩を書くのはその下位にある。これはどのあたりからだろう、『オシリス、石ノ神』あたりからの傾向じゃなかろか。僕らの吉増さんの印象は『黄金詩篇』や『頭脳の塔』で、軽やかに現代消費社会を言語消費してゆくような疾走感がウリだった。当時はまさかちょっとうさん臭いシャーマニズム詩人になるとは想像できなかったな。もちご本人は幽霊が見えるともキツネが憑くともおっしゃってないですけどね。でも未必の故意で超常性を援用している気配は濃厚にある。ま、ヴォワイヤンとか一昔前の詩人のパブリックイメージですな。
ただま、時代は吉増さんの方向に進んでいるわけで、これだけ文学が斜陽産業になっているのに小説家になりたい、詩人になりたいという人がけっこういる。夢いっぱいなのはいいことだが、現実が見えているとはぜんぜん思えない。詩人で現代詩ふうの作品を書いていけば飯が食えないどころか詩集を出すお金にも事欠くようになる。詩集はほぼ100パーセント自費出版です。若さをかわれて企画出版で調子こいてても、年とってまでそれを維持できる人はほぼいない。小説家で純文学を志しても芥川賞宝くじに当選するのは夢見たいな出来事で、そこが頂点となってたいていの作家は文壇から消えてゆく。んなこたぁ見てりゃわかるだろと思うのだが、どーも見えないというか見たくないようだ。
詩人になること、小説家になることが目標の作家は足元危うい。詩人のような格好をして詩人のような話し方をして詩人だねぇという生原稿を書いてニッチに生きのびている吉増さんは例外というか、あまり目標にしてはいけない作家であって、作家はダメ出しを喰らいながらイヤというほど原稿を量産しなければ生き残れない。実働八時間で週五日働いてる人と同じくらい働かなきゃならんということである。フリーランスで生きていきたいなら労働時間はもっと長くなる。気がついたら詩人や小説家と呼ばれているというのが本道だ。そうなれば詩人や小説家と呼ばれること自体どーでもいいというか気にならなくなる。詩人や小説家と呼ばれたいという目標自体が間違っている。慶應は元々は実業の大学だから、そのあたり文学青年少女をちゃんと指導しておられると思いますけど。
富山吉広は二十代の初め、西船橋の須賀谷祐子のアパートに身を寄せていたことがある。あの晩、彼は学生運動をやっている友人のアパートにいた。いざ寝ようとしていると、突然、二人の男が侵入してきて、いきなり角材を振り回してきた。それを腕に受け激しい痛みが走った。
なんとか逃げ切ったが、自分の部屋には戻ることができない。それで彼女の住む西船橋に向かった。都心にいては危ないと考えたのだ。祐子とは集会で知り合い、アパートまで送っていったことがある。寄って行くかと声をかけられたが遠慮をした。彼女にはつきあっている男性がいて、ややこしい関係になってはという気持ちもあった。
佐藤洋二郎「かさぶた」
佐藤洋二郎さんの「かさぶた」は二十枚ほどの短編である。主人公は富山吉広という大学生で、時代は一九六〇年代末の学生運動真っ盛りの時期。吉広は熱心ではないがその頃の学生の一人として学生運動に参加していた。友人の家にいたとき、内ゲバで二人の学生が雪崩れ込んできて角材で腕を殴打され骨折した。友人の家はもちろん都内の自分のアパートに帰っても危ういと感じた吉広は、さほど親しくない西船橋の須賀谷祐子を頼ろうと咄嗟に決めた。祐子とは「集会で知り合い、アパートまで送っていったことがある」だけの薄い関係である。ただその際、祐子に「寄って行くかと声をかけられた」とある。彼女は誘う女だと示唆されている。うまい小説の始まり方である。
「それを俺に預けろ。するとものの五分もしないうちに金持ちになる」
男はじっと千円札を見つめた。これを渡すと明日から喫茶代もなくなるじゃないか。吉広は思案した。
「こいつなのさ」
男は改めて赤鉛筆で無印の競走馬を指した。
「いいですよ」
吉広は急に相手がいじらしくなって、つい返答をしてしまった。すると相手は太い指を伸ばし、財布の千円札を抜いた。
「楽しみにしていな。半分はあんたにやっから」
同
祐子のアパートに転がり込んだが特にすることがない吉広は、なんとなく競馬場に行く。競馬場に行ったのは初めてだ。そこで男に声をかけられ有り金全部の千円を貸すことになる。初対面の男で賭け事で身を持ち崩した男だと造形されている。金を貸した理由は「急に相手がいじらしく」なったからだが強い理由ではない。魔が差したと言うべきか。男は絶対当たるからと言って馬券を買いに行った。当たれば半分やるとも約束した。馬券は当たった。当然男は現れない。そのまま当たり馬券を換金して吉広の前から消えてしまった。
アパートに帰って祐子に騙された話をすると、彼女は「いいことをしたんじゃない」「ひょっとしてその人の人生がまた変わるんじゃない?」と言った。彼女は影のある女性である。理由はわからないが彼氏と別れ、大学も辞めて故郷に帰ろうとしている。心に傷を負っていることはなんとなくわかるがそれが何かは小説では明らかにされない。
「あなたたちはいいわ」
なにと比較しているのか。自分のどこがいいのか。吉広は祐子を見つめた。
「抱く?」
彼は聞き間違いかと思い押し黙った。ようやく理解して見つめ返すと、彼女の目の奥に強い光があった。
「記念に」
祐子は口元をゆるめた。
「申し訳ないよ」
彼女はすぐに返答をせず気を抜いた。
同
祐子のアパートに居候し始めてしばらくして吉広は彼女から誘われた。彼はやんわり断った。というか一歩踏み出す勇気が出なかった。そのまま居候が終わるまで祐子との肉体関係は生じなかった。
彼はその馬券を持ったまま馬場に出た。(中略)
競馬馬たちが一斉に飛び出した。(中略)
そのうち夕暮れの電光板に数字が点った。吉広は点った数字と持っている馬券を見比べた。当たった? 一瞬茫然とし、もう一度数字を照らし合わせた。当たった。自然と声が洩れた。それからまた馬場に陽が落ちる光景を見つめていたが、配当金を知らせるアナウンスがあった。十万円。あの時と変わらない金額だった。彼は動揺しなにも考えられなかった。
同
小説の大団円は吉広が祐子を懐かしんで昔千円を騙し取られた競馬場に行き、騙された時と同じ数字の馬券を買って騙された時と同じ賞金を得たという流れである。このオチは半ば必然的なものだが、これもうまい小説のまとめ方である。こういった小説を量産できれば喜ぶ読者は大勢いるだろう。短編としてお手本にできる作品だ。
小説は基本的にオーソドックスなものである。佐藤さんの「かさぶた」を例にすると、学生運動の詳細や主人公と祐子との微妙な関係をユーモアを交えたドタバタとして描き、最後に馬券が当たったという流れにすれば浅田次郎風のエンタメ泣きモノ小説ができあがる。また祐子の苦悩を穿鑿せずあえて彼女の荒んだ心に沿った激しいセックスをする、物わかりがよくて女にとって都合が良い繊細な男を登場させれば村上春樹風のサラリとしたシティー小説の流れになる。ただ基本的な小説の書き方は揺るがない。細部のリアリティが幹であり枝をどこに広げるかによって作家個々の作風が生じる。
池田浩
■ 佐藤洋二郎さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■










