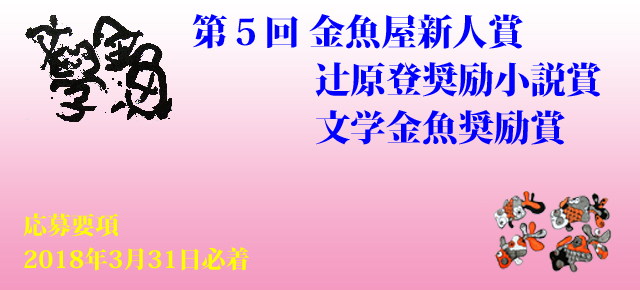大篠夏彦さんの文芸誌時評『文芸5誌』『No.108 加藤秀行「キャピタル」(文學界 2016年12月号)(後編)』をアップしましたぁ。加藤秀行さんのようにスーパー資本主義世界の最前線に立つビジネスマンの中から、文壇・詩壇を見回してもほぼ唯一、正面から現代的問題に取り組もうとする作家が現れたのは象徴的出来事かもしれません。
日本の中心には〝何もない〟。それはデータセンターの中枢で、アリサと裕樹が見た光景と同じだ。世界の中心であるはずなのに、そこにも何もなかった。データセンターのコンピュータ群を見ながら、裕樹は「ここは永遠を前提としている。発展ではなく成長で、現実ではなく観念だ。そしてどこかに伸びてゆく。永続的な成長。僕はその感覚をなぜ懐かしく思ったのか分からなかった」とある。
裕樹が認識したように、わたしたちの現代社会は中心があり、しかもその中心は空虚だ。だが混乱しているわけではない。霞ヶ関で見た落ち葉のように、それは「見えない円を描くようにくるくると動い」ている。それはもはやわたしたちにとって、「懐かしく思」えるほどの光景だ。つまり現代社会の本質は、確実に〝構造〟としては認識把握できる。さらなる問題は、この構造を統御している原理のようなものは存在するのか、あるとしたらどのようなもので、それはわたしたちをどこに導くのかということである。このアポリアは超難問だ。
大篠夏彦
完全な戦後の子供として、1970年代後半から文壇・詩壇に現れた作家たちは、多かれ少なかれ戦後文学を仮想敵にしていました。今から振り返れば、〝終わった・滅んだ・そうじゃない〟と言っていれば済むようなところがあった。それは長い長いモラトリアムだったと思います。しかしもう否定形では済まない。はっきり焦点を見極めなければならない。加藤さんのような作家が現れたことで、文学の世界の潮目は変わってゆくでしょうね。
文壇でも詩壇でも純文学系の本は売れていません。その理由は昨日大篠さんが書いておられたように〝作家にテーマがない〟からだと思います。実際西村賢太氏のように、他者には関わりのない私小説を書いていても、明確なテーマを持っていればそれなりの部数を売り上げている。つまり極論を言えば、本が売れない、読者がそっぽを向くということは、実質的に純文学というジャンルが消滅しかかっていることを示唆しています。
文学金魚が純文学系メディアでありながら、本を売ること、読者がつくことを重要視しているのはそのためです。これもはっきり言うと、今の文壇詩壇の重鎮は、とっくの昔にテーマを見失ってしまった作家たちで占められるようになっています。それはいっこうに構わない。ただいっしょに沈むのがイヤなら、作家は強い覚悟を持って、同時代の現代文学を作り上げてゆかなければなりません。文学者は文学にのみ忠実であればいいのです。
■ 大篠夏彦 文芸誌時評 『No.108 加藤秀行「キャピタル」(文學界 2016年12月号)(後編)』 ■
■ 第05回 金魚屋新人賞(辻原登小説奨励賞・文学金魚奨励賞共通)応募要項 ■
第05回 金魚屋新人賞(辻原登小説奨励賞・文学金魚奨励賞共通)応募要項です。詳細は以下のイラストをクリックしてご確認ください。
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■