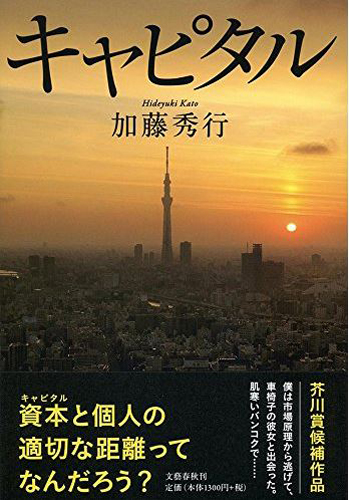
「七年間もファームにいると言ってたわね。そんなに長く続けた理由はあるの」(中略)
「特に無い。もしかしたら理由が無いから続けていたのかもしれない」
「好きなものはなに」
「折り目正しいもの。サステイナブルなもの。魔法」
「魔法?」
「効果が分かるけど構造が分からないもの。自分の理解の及ばないものに惹かれるんだ」
「ふうん・・・嫌いなものは」
「不確実性」
「この次は何がしたい」
「次?」
「次よ」
僕はまた考えた。
「まさにそれを考えているところなんだ。ファームに戻るべきか、戻らざるべきか。七年間も過ぎていまだにモラトリアムにいると気づいたよ」
静かな間が空いた。
「もう少し踏み込んで話を聞いてもいいかしら」
「もちろん」
「あなたはこれまでの人生で、後戻りできない場所で意志決定したことがある?」
後戻りできない場所?
(同)
アリサはビジネスエリートらしく、セキュリティのしっかりした富裕層向けの病院に入院している。足を骨折して当分不自由なだけの知的な若い女性だ。いわゆる株屋と呼ばれた人々が、金の力を振りかざして型破りに生きる時代はとうの昔に終わっている。ビジネスエリートの多くが難関大学で高い教育を受けている。文学を含む様々な趣味に精通している人も多い。しかしそういった優秀な人間のほんの一握りしか、文学を始めとする他の業界に参入してこない。資質の問題はあるが、降りることのできないビジネスレースをひた走っているからでもある。
しかしアリサは降りた。少なくとも高野の会社の内定を断ることで、それまでのキャリアを中断すると決めた。アリサは裕樹に「あなたはこれまでの人生で、後戻りできない場所で意志決定したことがある?」と聞く。アリサは後戻りできない場所で意志決定したのであり、裕樹はそんな経験がない。だから小説はアリサがなぜ降りたのか、裕樹はなぜレースから降りられないのかを問い始める。それは現代の一種の教理問答だ。
彼女の家は郊外の地盤がしっかりした土地を大量に保有していた。都心から車で通える範囲だが、都心に通うには不便なので土地は安い。幹線道路が走り、土地の値段が上がる。次にまた似たような土地を買う。次の幹線道路が走り、土地の値段が上がる。勝利の方程式のようなものだ。上に載るものは時代に合わせて変わる。でも土地は動かない。時代に合わせて一番値段がつくものを載せていけばいい。
「それはもう巨大な建物よ。洪水、地震、津波、火事、テロ、ありとあらゆる可能性をできる限り排除した場所にあるの。工業団地の一角を占めてる。(中略)みんな何かを作ってる。その観点から言うと、ウチだけ何も作ってないわね。持っていて、貸しているだけ。それでデータセンターがうまくいって、会社は上場した」
「上場?」
「そう。タイで上場しているわ」
「知らなかった」
「言ってないもの。知らないでしょう」
(同)
会話を重ねるうちに、アリサの家が、タイで有数の不動産業者だということがわかる。中国の混乱を嫌ってタイに逃れてきた祖父母の事業を受け継ぎ、主にアリサの母親が巨大な不動産事業にまで育てたのだった。「土地は動かない。それが祖母と母に共通した認識だった」とある。しかも両親と祖母はすでに亡くなっている。双子だったアリサの姉も交通事故でこの世を去った。アリサは大企業のただ一人の相続者で、しかもタイには相続税がないのだという。
土地神話はもちろん今でも存在する。しかし高止まりした土地は、決して魅力ある投資対象ではない。土地神話とは担保価値と値上がり神話ということだが、上物事業含みで昔から所有していた土地が値上がりしたというケースでない限り、土地投資で大きな利益を得るのは難しい。現実には数十年間に一度起こるか起こらないかのわずかなチャンスを狙うしかなくなっている。アリサの家はそういう幸運に恵まれた。だがアリサも裕樹も、天から降ってくる幸運を待つほど甘いビジネスマンではない。先進国はもちろん、新興国でも土地神話は終熄しつつある。土地神話ビジネスはもう古いのだ。
アリサが所有しているデータセンターは、インターネット社会では世界の中心とも呼べる施設だ。もちろん世界各国に点在しているが巨大なものは少ない。世界中のどの場所にあってもいいわけだから、投資効率から言えば先進国よりも政情が安定した、天災の少ない新興国が望ましい。またそこから生み出される利益は不動産投資などの比ではない。遙かに利回りの高いビジネスだ。アリサと裕樹はデータセンターを見にゆく。現代の世界の中心を訪れるのである。
「あなたの場所には行けるのかしら」
少し冷たさを増した風に強く吹かれていると、一瞬ごとに自分が更新されていく気がした。常に新しい場所にいて、淀まず、流れていく。そのことをどう判断していいか分からなかった。失くしているようでもあり、何かを得ているようでもあった。事実として僕は息苦しいくらいのフローの中にいた。その中で差分を感じ続けている。髪がなびき、冷たい風が頭皮を撫でていく。大きく息を吸うと、しめった、燃えた匂いを含む空気が僕の胸を満たした。目の前の冷えた平野が、鉄筋の間から、丸々と僕の胸の中に移動してきたような気がした。
「分からない。もう少しで行ける気もするし、もう一生行けないような気もする」
「一生行けない場所なんかあるのかしら」
「分からない。もはや行き方すら分からない場所があることは事実だ」
「行き方」
「あるいは戻り方」
「記憶を風に乗せて、どこかでまたキャッチできたらいいのにね」
「魚みたいだね」
「魚?」
(同)
巨大なデータセンターの屋上で、周囲の景色を見ながらアリサと裕樹は、かつて自分がいた場所、これから行きたい場所について話をする。しかしそのどちらもはっきりと言葉にできない。人間はホームと呼ばれる場所をしっかり把握しているからどこかに行けるのであり、どこに向かっているのかわかっているから、戻る場所を認識できる。しかし本質的に世界が変わろうとしている現代社会では、ホームも未来の場所もあやふやだ。青臭い言い方をすれば、アリサと裕樹は〝我らはどこから来てどこに行くのか〟を話し合っている。
文学史的なことを言えば、加藤氏の小説文体は村上春樹を思い出させる。従来的な小説の書き方と比べれば現実感が希薄なのに、以前よりも深くわたしたちの現実に食い込んでくるような描写である。それは戦後文学がまだ力を持っていた時期に、村上氏が捉えた現代的感受性の方向が、正しかったことを示唆している。また加藤氏のような作家が現れたことは、村上春樹氏的な文体文学が、更新され始めていることをも示唆しているだろう。
春樹氏の小説主題は場当たり的だ。秘密結社でも謎の宗教団体でもいい。文体の快感を際立たせるための物語要素として主題が選択されている。しかし加藤氏の小説では大きな出来事は起こらない。アリサと主人公の裕樹が恋に落ちることはないし、小説的行き詰まりの打開や飛躍を求めて、ほとんど唐突にセックスし始めることもない。加藤氏の文体が捉えようとしているのは、現実感が希薄としか認識できない現代世界の本質である。つまり加藤氏の小説には明確なテーマがある。
アリサは高野先輩のファンドの内定を断った理由を、自分で説明すると言って裕樹といっしょに日本を訪れる。高野とアリサの面会、それにアリサが内定を断った理由は、まがりなにりも完結しなければならない小説〝作品〟が要求する一つの虚構に過ぎない。小説をまとめるためには、最低限でもそういった操作が必要なのだ。その意味で「キャピタル」という作品を手放しで秀作と評価することはできない。しかしほとんど初めて、現代社会の本質に食い込もうとする作家が現れたのは確かなようだ。
アリサを拾って、霞ヶ関に向かった。「中心が見たい」とアリサが言ったのだ。(中略)
「ここが中心?」
誰もいない坂を上りながらアリサはそう呟いた。
「どういう意味かによるけど、そうだね、おおむね中心と言えると思う」
「人がいないのね。住んでる人がいないのかしら」
「国会議員しか住んでない。後はホームレスかな」
「似たようなものね」
アリサは膝に肘をつきながらそう言った。
空気が冷たくて、その中を引っかくような音を立てて落ち葉が動いていた。交差点では、落ち葉以外は何も動いていなかった。落ち葉は見えない円を描くようにくるくると動いた。
空はくっきりと青く、交差点の白い線はくっきり白かった。すきとおるような空気の匂いがした。
(同)
日本の中心には〝何もない〟。それはデータセンターの中枢で、アリサと裕樹が見た光景と同じだ。世界の中心であるはずなのに、そこにも何もなかった。データセンターのコンピュータ群を見ながら、裕樹は「ここは永遠を前提としている。(中略)発展ではなく成長で、現実ではなく観念だ。そしてどこかに伸びてゆく。永続的な成長。僕はその感覚をなぜ懐かしく思ったのか分からなかった」とある。
裕樹が認識したように、わたしたちの現代社会は中心があり、しかもその中心は空虚だ。だが混乱しているわけではない。霞ヶ関で見た落ち葉のように、それは「見えない円を描くようにくるくると動い」ている。それはもはやわたしたちにとって、「懐かしく思」えるほどの光景だ。つまり現代社会の本質は、確実に〝構造〟としては認識把握できる。さらなる問題は、この構造を統御している原理のようなものは存在するのか、あるとしたらどのようなもので、それはわたしたちをどこに導くのかということである。このアポリアは超難問だ。
アリサは彼女の家は、姉によって巨大な資産を築いたのだと言う。事業を左右するような大きな投資をする際には、必ずと言っていいほど幼い姉が正しい未来を示した。「彼女の得体の知れない能力」とある。双子なのにアリサにそんな能力はない。しかし姉を含む家族が生み出した遺産を継承しなければならない。未来はアリサの肩にかかっているということだ。だがどこに向かうのが正しいのかは、アリサや裕樹、つまりわたしたち普通の人間にははっきりわからない。しかしグルグルと円を描く現代社会の平面から超脱するには、直観に裏付けられた飛躍が必要なのは確かだろう。(了)
大篠夏彦
■ 加藤秀行さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


