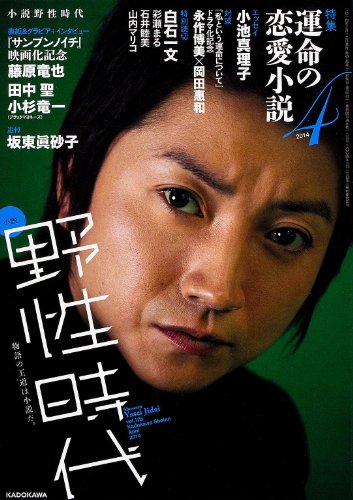「運命の恋愛小説」という特集。であるが、いきなりのアンチクライマックスで、小池真理子のエッセイに「最近は、無難な恋愛の小説が売れている」とのこと。小池センセイのおっしゃることだから、きっとそうであるに違いない。しかし、それって語義矛盾そのもの。
恋愛小説もエンタテインメントの一種だとすると、ミステリーなどと同じようなお約束の構造がなくてはならない。つまりは三角関係とか、恋路を邪魔する障害物とかがあって、それを押しのけるところがクライマックスになるはずだ。押しのけるべきものがないのが無難な恋愛で、はなから小説にならないはずなのだが。
せいぜい互いの駆け引きですれ違いが起きる、ぐらいのことだとすると、クライマックスはセックスシーンにしかならない。それはジャンル分けとしては、手の込んだポルノであり、恋愛小説ではない。性的趣味はさまざまなので、前置きの長い物語性がないと、という指向もあり得るだろう。繰り返される性交は「無難な恋愛」そのもので、その相手を見つけるに過ぎないなら、それも「無難な恋愛」だろう。それは小説ではなく情報とかデータ、せいぜいノウハウ本だ。
セックスは繰り返されるもので、そうなればクライマックス性は相対化される。ポルノとは本来的に常同性のもので、小説よりも単なる映像に向いている。「運命の恋愛小説」が過去のものになり、「無難な恋愛小説」が主流だというのは、本当のところは恋愛小説そのものが過去のものになっている、ということではないか。
恋愛小説は、多く女性が読むものであった。ポルノは昔から男性のものだったが、恋愛小説がポルノ化したということは、女性たちの嗜好もそのように変わっていった、ということだろう。一口に言えば、慎みがなくなったということだが、女の子をつかまえて非難するより前に、社会そのものがこうむった変化を考えるべきだ。憧れの職業に、いまやキャバクラ嬢が名指される世の中だ。
もちろん江戸期もまた、花魁のブロマイド浮世絵が出回ったのだから、風俗がもてはやされるということはいつの世にもある。キャバクラ嬢も女郎も、疑似恋愛を時間いくらで売る商売だから、目方で量れる分だけ「無難な(疑似)恋愛」である。勘違いして刺したりする男がいたりするのは、恋愛小説ではなくサスペンスである。と言っても、売春婦が殺されるというのは、本筋の話の枕にしか使われないが。
今の世の中にだって、江戸期と同様に、風俗嬢とは袖触れ合うことのない女性はいる。ただ、封建制の失われた世で、もともと風俗嬢としているべき者が、一般的な存在として認知されようとしている、ということなのだ。経験値の浅いボクら男にはその区別はつかないし、いずれ気楽に付き合えるのだから別にソンはない。女たちにとっても多様なあり方が可能になるのだから、足を引っ張る必要もないわけだ。
恋愛概念はそもそも明治から大正期、キリスト教とともにもたらされたものだ。相手を理想化する思考の構造がクライマックスを生む。そんな文化に触れられたのは、当時のアッパーだけである。「無難な恋愛」とは矛盾に満ちた妙な言いようで、つまりは恋愛以前、庶民による土着の色事というものに近いのだろう。
水野翼
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■