安井浩司参加初期同人誌を読んでいると、秋田から大学進学のために上京した安井氏(以下敬称略)が、多くの刺激を受けて作家として成長していく姿が浮かび上がってくる。上京直後の昭和29年(1954年)から30年(55年、18・19歳)にかけて安井は、『牧羊神』や『青年俳句』などの同人誌で作句活動を行っていた。しかし31から32年(56・57年、20・21歳)になるといったん俳句活動から遠ざかり、自由詩の創作に傾倒したようである(『N0.010 『現代行動詩派』『ぽぷるす』』『N0.011 『KLIMA』』参照)。だがやはり安井は俳句に戻ってくる。
安井は昭和38年(1963年、27歳)に処女句集『青年経』を上梓するが、33年(58年)から37年(62年、22~26歳)までの5年間の俳句活動がその土台になっている。この時期に安井は複数の同人誌を刊行し、結社誌に寄稿している。わかっているものだけということになるが、それをまとめると以下のようになる。
■同人誌■
・『貌』 柴田三木男との二人誌。昭和33年(1958年)創刊。通刊巻数と終刊時期は不明。
・『黒』 安藤三佐夫ら若手俳人による同人誌。安井は昭和35年(1960年)刊の第12号から同人参加するが、この号をもって『黒』は終刊。
・『砂』 柴田三木男を編集・発行人とする同人誌。昭和37年(1962年)から40年(65年)にかけて通巻14号を刊行。
■結社誌■
・『群蜂』 榎本冬一郎主宰の結社誌。安井は昭和33年(1958年)から34年[59年]にかけて、秋地一郎と大石豪夫のペンネームで俳句を投稿している。
・『琴座』 永田耕衣主宰の結社誌。安井は昭和34年(1959年)に秋地一郎として同人参加。37年(62年)には本名で再参加し、以後平成9年(1997年)の終刊まで同人。
このうち『貌』と『琴座』は今回お借りした資料には含まれていない。未見だが恐らく『貌』が安井にとってのターニングポイントになったろうと想像される。『N0.009 『青年俳句』(後半)』で紹介したが、柴田は『僕らの仲間、安井浩司は俳句から転落し』と書いて、安井に痛烈な批判を浴びせかけた俳人である。
同人誌『砂』の項の資料で紹介するが、柴田は安井との関係について『小学校、中学校、高校と、彼とはつねに机を並べて来た僕らには、兄弟以上の親しさと、無遠慮さがある』と書いている。柴田の安井批判には、子供の頃からの畏友が俳句を離れ、試行錯誤を重ねていることへの苛立ちがこめられていたようである。
少し脇道にそれるが、『砂』を読んでいる限り柴田は優れた資質を持った俳人だと思う。安井が自分の中で渦巻く創作意欲に筋道をつけられず試行錯誤を重ねていたのに対し、『青年俳句』時代から柴田の理論(評論)と作品は明快だった。
人型の星博ちだるい夜の架橋
埋葬のどっとなだれる花の崖
ある仮説の狭い海面碁石が占む
屈葬の父と同じ重さの乾く咽喉
山巓のひかる死が見え瓦礫積む
誰か死ぬ反古反る夜の豊かな海
告白の虹となる海際のわが射程
(『特別作品 射程 20句』より 『砂』No.4 昭和37年[1962年])
柴田の作品には〝前衛〟意識がある。ある確信をもって従来の俳句伝統から断絶しようとしている。ただそれは異質な言葉(単語)を組み合わせて、あえて作品で一つの意味内容を喚起させないというモダニズム的手法の弊害も併せ持っている。引用作品を読めば明らかなように、柴田の作品は三角形を為す言語操作で作られている。『屈葬の父』と『乾く咽喉』を両端に置いて、それを『同じ重さ』で連結するという手法である。
だがこの手法はいずれ頭打ちになるはずだ。言葉の意味伝達内容を無化する姿勢が単語への依存度を高め、やがて空疎な言葉遊びとして空転し始めるからである。実際、この手法を活用した自由詩の多くのモダニズム詩人が、言語遊戯的な空虚に陥っていった。
しかし逆に言えば、柴田的なモダニズム手法に作家の観念主題を付加すれば、作品は意味的な深みを獲得することができる。それは同じ有季定型俳句でありながら、大方の写生俳句が挨拶程度の意味内容しか持たないのに対して、芭蕉俳句には一貫した思想を読み取れるのと同様である。
『砂』の同人は多かれ少なかれ前衛意識を持っていたが、彼らとともに安井が、俳句の技法ではなく、自己の主題を表現するための手法を編み出していったのは確かだろう。なお柴田についてはその後の活動内容は不明である。俳句から去られたのか、あるいは別名で活動されたのかもしれない。
本題に戻れば同人詩誌『貌』と同時期に、安井は結社誌『群蜂』に投句している。これも柴田が『群蜂』同人であったことが縁になったようだ。『群蜂』は40ページの月刊誌で活版印刷である。『牧羊神』や『青年俳句』時代の安井は寡作だったが、この頃には処女句集『青年経』に向けての精力的な句作が始まっている。
安井は『群蜂』に『秋地一郎』名義で40句を、『大石豪夫』名義で41句を投句している。このうち『青年経』に収録された句は4句(秋地一郎から3句、大石豪夫から1句)である。わずか10パーセントしか句集には採られていない。岡野隆さんが『唐門会所蔵作品』で論じておられるような厳しい選句眼は、この頃からのものだったようである。
芝居来て偽銃鳴る町青嵐
性感じつつ向日葵の確かな闇
鳩と少年入り消え硝煙臭き森
男女来て西日はげしき無傷の海
*
蛇の縞すべらす崖へ五月の海
遠花火沖を暗くし怒る島
石像の双肩も焼け夏日果つ
(大石豪夫作品 『群蜂』昭和33[1958年]年8月号)
確認できる限り、安井が『群蜂』に最初に投句した作品は大石豪夫名義の7句である。安井が言葉の意味とイメージ連鎖で作句していることがわかるだろう。『偽銃』は『硝煙』に、『性』は『男女』に展開する。『海』は『沖』を呼び起こし、『花火』は『夏日』へと変わる。安井は理知的俳句作家だが、作句においては自己の観念的主題をできるだけ希薄にして、その〝虚〟の中心の周囲に様々な言葉を張り巡らせ、そこから自在に言語を組み合わせる方法をとっている。ただ安井はその痕跡を、句集にまとめる際に完膚無きまでに消去してしまうのである。
また昭和30年(1955年)に『青年俳句』に発表した句は、『春銀河かの青年の聲吸ひけむ』『母癒えし便り麦の穂伸びそろふ』といった素直なものだったが、3年後には実に複雑な言語表現に変貌している。前衛俳句と呼ばれる一連の試みは、もの凄く単純化すれば、最短といわれる俳句形式を保持したまま、そこで従来の俳句文学にはない意味やイメージを表現したいという作家の欲望から生じている。安井もその意味で前衛俳句作家である。ただ単に新たな表現地平を切り拓きたいのなら形式は自由詩の方がふさわしい。俳句前衛には、俳句でなければならない〝根源的理由〟が必要とされる。
冬山挽き来て睡むる色ない巨き足
銃口もつ黒い一団沼にかたまる葦
橋上に老人生きて水の奔流の青さ (①『青年経』)
飢えのはてに尿すぐつたり夜の運河
(大石豪夫作品 『群蜂』昭和34[1959年]年2月号)
充血の手が這い都市の陰花植物
夜の湾口にたゞよい射精する烏賊ら
死者に触れし翅音巨船の白昼(まひる)の蛾 (①『青年経』)
花火見仰ぐ路上に飢餓の犬押さえ
(秋地一郎作品 『群蜂』昭和34年[1959年]6月号)
昭和34年(1959年)2月号と6月号に投句された大石豪夫、秋地一郎名義作品である。各4句から1句ずつ処女句集『青年経』に採られている。その選句基準は繊細だ。大石作品後半3句は水のイメージで書かれている。ただ『冬山挽き来て』『銃口もつ』『飢えのはてに』の3句が描写句であるのに対して、『橋上に老人生きて水の奔流の青さ』だけが『老人』と『水の奔流の青さ』を対比させた観念的意味内容を持っている。
秋地作品は『闇(陰)』が主題だが、今度は観念的主題よりも言語操作が優先されている。『闇(陰)』という主題の中で、『死者に触れし』の句が最も修辞的に高度なのだ。『死者』と『白昼』(明暗)を対比させ、『翅音』を『蛾』で受けることで視覚だけでなく音を喚起させている。また『巨船』が死の闇を効果的に修飾しているのは言うまでもない。
安井の場合、このような選句基準は、連作ごとに、あるいは句集ごとに様々に変わる。ただ安井の連作手法は重要である。それは本質的には正岡子規の写生俳句と変わらない。子規は目の前の事物を詠み尽くし、もう言葉が枯れたと感じられる地点からさらに表現を推し進めて新たな俳句を生み出そうとした。安井はいわば前衛的連作手法を採っている。一気に生み出された連作句の中から、その頂点を為す作品が句集に収録されているのである。
鶴山裕司
■『群蜂』掲載安井浩司・大石豪夫作品■

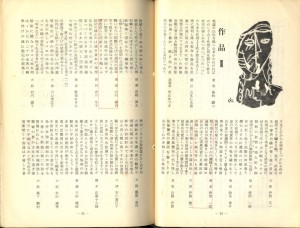
* 『群蜂』昭和34年[1959年]3月号 投稿欄
【秋地一郎作品】
風飢えて鳥がのぞける森の傷
河口荒れつつ睡る女らの巨きな足
台風来つつ夜空に生えて青いビル
日向へ鳥かたまり火薬搬ぶ山
(『群蜂』昭和33年[1958年]9月号)
台風雨来つゝ屋上に鼠の死
沖荒れていたり犬飼う暗き柵
受胎了ふ闇突きあげて遠花火
担送車に寝て見る炎空の巨き掌は
(『群蜂』昭和33年[1958年]10月号)
遠く山鳩不眠の頭に渦まく青
遠い湾に船火事だるい足生え睡る
西日の巨塔へ登る仲間よざらつく肺
アンテナの触角生えて雪来る街
(『群蜂』昭和33年[1958年]11月号)
崖へつらなる夜は送電塔の青ばむ死
父亡くて台風圏のやわらかい樹
冬の海見て来て麻薬吸わす腕
暗渠越える脚の青年へ鼠の死
(『群蜂』昭和33年[1958年]12月号)
少女の脚へ銅線からまり遠い戦火 (①『青年経』)
青い海から突風少年の細胞殖える
夜の地下室に銅線の渦鼠死ぬ (①『青年経』)
椅子らつぎゝゝロープで繋がれ火がない地下室
(『群蜂』昭和34年[1959年]1月号)
疲労のはてに夜空渦まく青い気流
闇へひらく排気筒白い飢えしずもる
飢えと疲れのかたまりひらく湾の花火
女身充ちきて夜風に塑像(トルソ)の破片鳴る
(『群蜂』昭和34年[1959年]2月号)
陸で踏まれたヒトデの内臓揺れる巨船
過剰の足が夜空搔きいる蛸壺惨め
砂丘のはてに突風死者の足裏攻め
青海一枚描いた祖父等にも流血
(『群蜂』昭和34年[1959年]3月号)
電波とぶ夜空へ鋭器となる青年
腸管うかぶ夜空で転身する電車
鼠つぎつぎ沈んだ運河米を買いに
焦土堀返すこの眼で黒痣の太陽狙い
(『群蜂』昭和34年[1959年]4月号)
ビルで盗った銀線で煙突の首しめよう
明日へつながる腸管過労の星まつる
巨大な壁に磔りつく青年無形の銃
硝煙つまつたこの脳ついばむ森の鳩
(『群蜂』昭和34年[1959年]5月号)
充血の手が這い都市の陰花植物
夜の湾口にたゞよい射精する烏賊ら
死者に触れし翅音巨船の白昼(まひる)の蛾 (①『青年経』)
花火見仰ぐ路上に飢餓の犬押さえ
(『群蜂』昭和34年[1959年]6月号)
【大石豪夫作品】
芝居来て偽銃鳴る町青嵐
性感じつつ向日葵の確かな闇
鳩と少年入り消え硝煙臭き森
男女来て西日はげしき無傷の海
*
蛇の縞すべらす崖へ五月の海
遠花火沖を暗くし怒る島
石像の双肩も焼け夏日果つ
(『群蜂』昭和33年[1958年]8月号)
咽喉かわき夜の中央に在る巨塔
夏空へ炎え上るとき樹の傷荒し
花火撥ねし高さへ都会の巨きな黒
(『群蜂』昭和33年[1958年]9月号)
獣撃って咽頭鹹し夜の沼
蝶の死へ傾しぐ喀血のごとき空
町の空乾きどの家も火薬創る
夕煙見倦く位置屋上に回る木馬
降誕祭地下食堂に指煮える
道化いま赤き頭蓋を地上に置く
(『群蜂』昭和33年[1958年]10月号)
夜の砂丘掌に葬列の風残る
遠花火父死ぬときの巨き泡
誰か居て枯樹の裏側夜雪積む
夜雪降り積む自我像の眼の閉じねば
(『群蜂』昭和33年[1958年]11月号)
夜の玻璃硬くて薔薇の蔓の死へ
地に曝す死者の蹠夏野へ向く
夜の壁に蟻ら軍服がうつむく列
夜光時計の地下に浮遊す色なき手
(『群蜂』昭和33年[1958年]12月号)
黒蟻の列に跨る誕生日
青空の皺縦に濃く土竜の死
青春の指みな鳴らす蛇の衣
貧漁の船過ぐ余波が余波押して
中空へ焼きつく花火静かな受胎
(『群蜂』昭和34年[1959年]1月号)
冬山挽き来て睡むる色ない巨き足
銃口もつ黒い一団沼にかたまる葦
橋上に老人生きて水の奔流の青さ (①『青年経』)
飢えのはてに尿すぐつたり夜の運河
(『群蜂』昭和34年[1959年]2月号)
赫いそらへ両肺ひろげた過労の電車
足で揉まれた夜空偽銃はせつなく鳴る
白い闇突く奔流過労の腰崩さず
満腹淫らに造船きりきり鷗とぶ
*
乞食が寝る路地の厚さ勲章嵌め
遠い湾に胎児ら泳ぐビルの灯攻め
何処か流血おおきく闇搔く火傷の蛾
夜空突きあげ苦しい排泄ひらく花火
(『群蜂』昭和34年[1959年]3月号)
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
