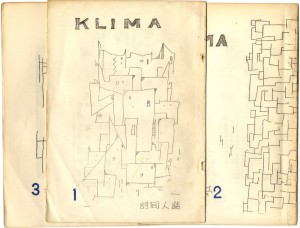 安井浩司氏からお借りした『KLIMA』は第1号から3号までの3冊である。3号以降も雑誌が刊行されたのかは確認できていないが、『KLIMA』第3号は昭和32年(1957年)12月31日の発行である。33年(58年)頃から再び安井氏の俳句活動が活発になるので、3号刊行後、しばらくして終刊したのではなかろうか。創刊号『後記』にあるように『〈KLIMA〉はドイツ語で、風土と云う意味である』。
安井浩司氏からお借りした『KLIMA』は第1号から3号までの3冊である。3号以降も雑誌が刊行されたのかは確認できていないが、『KLIMA』第3号は昭和32年(1957年)12月31日の発行である。33年(58年)頃から再び安井氏の俳句活動が活発になるので、3号刊行後、しばらくして終刊したのではなかろうか。創刊号『後記』にあるように『〈KLIMA〉はドイツ語で、風土と云う意味である』。
『KLIMA』はB4用紙をホチキスで中綴じした、ガリ版刷り12ページの簡素な雑誌である。ただ原稿執筆、編集、ガリ版刷り、製本までを安井氏一人でこなしている。安井氏のほかに3人から5人の同人が参加しているが、実質的に安井氏の主宰誌である。一篇だけだが詩論も掲載されている。安井氏の最初期の批評であり、また自由詩について書いた数少ない評論でもある。『KLIMA』刊行当時、安井氏がそうとうに自由詩に夢中になっていたのは確かである。
その影が 死のようにそっとやって来るとはかぎらない
その影が いつも背後にあるとはかぎらない
頭上や、眼の前いっぱいに、立ちふさがる
(中略)
人は、何処からやって来たか
それは、その影と影が触れあった接点からだ
人は、何処へ消えて行くのか
それは、人と人との隙間 大きな落窪に
横たわっているその影へ溶けこんでいくのだ
(中略)
その影とは 一体何であるか
その影とは 一体何であるか
誰も答えはしないだろう
だが、それとは別に――
新しい世界を用意する、無数のその影がある
(『その影の世界』部分 『KLIMA』第1号 昭和32年[1957年])
安井氏の詩の書き方はこなれている。俳句や短歌を書き慣れた作家が自由詩を書くと、知らず知らずのうちに俳句・短歌的発想や語法に縛られるものである(自由詩の作家が俳句・短歌を書いても同様の事態が起こる)。しかし安井氏の作品にはそれがない。言葉が伸びやかに繰り出されている。
作品『その影の世界』では『影』とは何かが探究されている。『影』は人間の生死を司る原理である。ただそれだけではない。「その影とは 一体何であるか/誰も答えはしないだろう/だが、それとは別に――/新しい世界を用意する、無数のその影がある」とあるように、『影』は新しい世界を創出する源でもある。
『その影の世界』から読み取れるのは、安井氏の思考が高度に抽象的だということである。明治から昭和前半にかけて、表現の根底に個人的トラウマを据えた作家は意外なほど多かった。たとえば寺山修司は出生のコンプレックスを抱えており、それと裏腹の、故郷喪失者であり父親不在の孤独を時に鮮烈な抒情として表現した。しかし安井氏にトラウマと呼べるものはない。彼の思考は原理に向けて一直線に進んでいく。
海に向って
大人は限りなく己れの悲歌を綴り
子供はそれを唱いつゞける
だが人は死に
海はたゞ、それが在るがまゝだけなのだ
浪が打ち
崖が砂塵をあげて 人の胸から崩れる
それさえ 当然のように――
海は睡らない 決して
海は睡ることはないのだ
(『海・悲歌(――十月二十六日 弟を失いて。)』部分 『KLIMA』第2号 昭和32年[1957年])
『KLIMA』第2号に発表された『海・悲歌』には、『(――十月二十六日 弟を失いて。)』という副題がある。『KLIMA』にそれに関連する記事はなく、年譜にも記載がないので確認できないが、文字通り読めばこの年安井氏は実弟を失われたようだ。
ただ『海・悲歌』は単純な追悼抒情詩ではない。『海』と『悲歌』の2つの概念の対比、あるいは対立として書かれている。肉親を失った悲しみにより、何かが「浪が打ち/崖が砂塵をあげて 人の胸から崩れる」。しかし「それさえ 当然のように――/海は睡らない 決して/海は睡ることはない」のである。「人は死に/海はたゞ、それが在るがまゝだけなのだ」とあるように、海は人間の死を相対化する。
簡単に言えば安井氏は悲しみの先にある何ものかを見据えている。作品『その影の世界』で描かれた『影』と同様に、矮小で脆弱でもある人間存在を超えた、より大いなる存在に視線を向けているのである。
今述べた二作品は、何らかの実験を行っているとは僕には思えないのである。いやこの二作品のみではない。この作品に隣りあい、背を向け腹をつき合わせている莫大な作品が、惰性の列の彼方で作られていると云う感じに僕は常に襲われる。
(『作品について』部分 『KLIMA』第2号 昭和32年[1957年])
おそらく僕たちに最も必要なものは勇気だろう。革命の炎の前に立っているようなごく単純な勇気・・・・・・およそ創作以前に於て僕たちが無意識に求めているのはこいつではないだろうか。
(『KLIMA』第3号『後記』部分 昭和32年[1957年])
前回の『N0.010 『現代行動詩派』『ぽぷるす』』で書いたように、昭和30年代は『戦後詩』や『現代詩』の、綺羅星のような詩集が怒濤のように刊行された時期である。しかし安井氏は『詩学』や『現代詩』といった商業詩誌に発表された作品に不満を洩らしている。毎月刊行される雑誌にそうそう秀作が掲載されるわけがないと言ってしまえばそれまでだが、不満は詩人たちが、『何らかの実験を行っているとは僕には思えない』点にある。
同様の事柄を『KLIMA』第3号の『後記』で、『おそらく僕たちに最も必要なものは勇気だろう。革命の炎の前に立っているようなごく単純な勇気』と安井氏は書いている。安井氏が詩には『実験』が必要であり、それを可能にするのは『勇気』だと考えていたことがわかる。またそれは『創作以前に於て僕たちが無意識に求めている』本源的な欲求である。
安井氏が自由詩を書き続けていたらどうなっていたのかという問いは、興味深いが今では藪の中である。ただ少なくとも加藤郁乎よりは優れた詩人になっただろう。郁乎の作品は、詩と銘打ってあっても俳句を行分けして長くしたものに過ぎない。詩は確かに作家の『これは詩である』という宣言(デクレアメント)によって成立する。しかし最低限度の閾はある。何ごとからも、何ものからも『自由』であることである。
自由詩は上田敏らの翻訳詩から始まるヨーロッパ移入文学だが、移入直後から既存の日本文学との習合が始まった。蒲原有明から北原白秋に到るまで、自由詩は語彙や音感(五七調など)、発想法に到るまで濃厚に短歌の影響を受けていた。それを白秋門下の吉田一穂は『詩人は短歌的原罪を負っている』と表現した。それを断ち切ったのが同じく白秋門下の萩原朔太郎である。彼の詩はそれまでの詩にも、それ以降の詩にも似ていない。朔太郎の思想に支えられた独自の表現である
朔太郎以降に自由詩は、作家個々に切り離され、孤立した表現となった。『戦後詩』、『現代詩』、『抒情詩』といったタイプ分けはできるが、詩人たちは本質的に他の詩人と異質である。それは個々に新たな表現を求める『前衛』であることが、自由詩のアポリアだということを示している。そのためどんなに巧みに粧っても、他者模倣、自己模倣に走った作家の作品は自由詩の歴史から消えていく。短歌・俳句といった伝統詩を擁する日本では、世界の変化を敏感に察知し、それによって日本語の表現を更新することが自由詩の存在理由なのである。
安井氏が『KLIMA』で書いた『実験』『勇気』『革命』という言葉は、彼が自由詩の本質を理解していたことを示している。だから彼は自由詩を書く際に俳句的表現から自由でいられたのである。安井氏がなぜ自由詩の創作を止めたのかはわからない。しかし作家には逃れがたい資質というものがある。優れた作家は必ずと言っていいほど自らの資質に合った表現ジャンル、表現形態を選ぶものである。安井氏も彼の資質に最も合った俳句に戻ったということだろう。ただ安井氏は、自由詩に打ち込んだ成果を俳句芸術に持ち込んでいる。
安井氏はのちに、『私にとって撃つべき魂とは、限りなく遠くにあり、限りなく大きくあるべきであった。(中略)魂とは、つまり私たちの言葉の営為の標的とは、謎と変容にみちた、元来、そういうものではなかったろうか』(『渇仰のはて』昭和五十三年[一九七八年])と書いている。この言葉は直接的には俳句表現に向けられたものだが、そこには詩的『前衛』たらんとする安井氏の決意がこめられている。
安井氏は俳句作家だが本質的な意味での『詩人』である。彼の『前衛』意識は俳句文学の原理に向けられ、また一方で誰も試みたことのない未踏の表現にも向けられている。安井氏にとっての伝統は既存の遺産を引き継ぐことではなく、日本文学の原理としての俳句像を探究することである。それは必然的に新たな表現方法を作家にもたらす。安井俳句は確かに俳句だが、誰も読んだことのない独自の作品を生み出すことを指向している。
1960年代から70年代にかけての俳句と自由詩の蜜月時代以降、俳句から『前衛』の意識は失われている。俳句における前衛とは、いかにも俳句的事態なのだが、今では古典となった高柳重信的前衛をなぞることであるかのようだ。またそこには本質的に前衛芸術でしかあり得ない自由詩の衰退が影を落としている。しかし日本文学のように長い伝統を持つ芸術では、各ジャンルの本質はそう簡単には変わらないだろう。
写生であろうと重信だろうと、伝統を振りかざせばかざすほど俳句芸術は衰退する。そして自由詩は『前衛』としての矜持を取り戻さない限り、いずれ漢詩のように日本文学から消えていくはずである。それを回避するためにはそれぞれの文学ジャンルが、それぞれのジャンルの特性に基づいた『前衛』表現を追い求めるほかにない。安井氏の前衛は、そのための一つの方途を示唆しているように思う。
鶴山裕司
■ 『KLIMA』第1号書誌データ ■

・判型 B5版 縦25.3センチ×横18センチ(実寸)
・ページ数 12ページ
・製本 ガリ版刷り、中綴じホチキス留め
・刷色 黒一色
・表紙イラスト 長沼仁毅
・奥付(原文のまま)
昭和32年11月1日発行
編集・発行人 安井浩司
発行所 東京都北多摩郡小金井下染谷1059富士見寮内安井方 くりま詩話会
・同人 伊藤満 井坂義昭 碓井耕一 清水重雄 塙三郎 安井浩司
【 『KLIMA』第 1 号 安井浩司作品 】
その影の世界 安井浩司
太陽が腐りはじめる頃だけではない
薔薇が闇をまとう頃だけではない
真昼 人のポケットのなかで
生ぬるい息づかいをしながら
その影は 何時でも
何処にでもきまって存在している
太陽の裏側にはりつき
獣の筋肉のなかでのた打ち
人と人のかぼそい隙間に その影は
のけ者のように声をしのばせて
ありきたりの空気を吸って、寄生している
男が女たちに仕掛けた罠のように
父が子等を打ちまくる鞭のように
容赦なく、居座り あるとき
その影は 時計針の型で、時間にひそみ
地球のかたちのまゝ 円い地面へしがみついている
その影は 眼に見えないものだけではない
手足の触角をすりぬけるものだけではない
その影は すべて実在のなかに生き
白雲や鳥、屍や人間と久しい対話をする
うすい枯色のシーツの中で、男と交渉する
独裁者のように支配し、新しい思想のように
街中をくねってあるく
――そして
人は、その影に追われ
人は、たえずその影を追いつめているのだ
高速路を走るスピードのように
背をさかのぼる車体の重量を覚え
流れない運河の秘密におびえながら
人は、その影に重さなり 愛し略奪し
汚物のように捨てゝは
影から影へとのり移っていこうとする
その影が 死のようにそっとやって来るとはかぎらない
その影が いつも背後にあるとはかぎらない
頭上や、眼の前いっぱいに、立ちふさがる
たとえば あの蒼白なビルディングの総体
まぶしい太陽のまるい貌
猫のようにけたゝましい救急車
それらが、その影の一部分であったり
その影のすべてであるかも知れない
また――
さむい街路で突然行き倒れた乞食
アスファルトの上で死んでいる犬
そのわきに黒くうずくまっているのは
もはや、その影ではない
それは、その影が分泌した排泄物だ
それは、その影が捨てゝいった感傷と云うものだ
人は、何処からやって来たか
それは、その影と影が触れあった接点からだ
人は、何処へ消えて行くのか
それは、人と人との隙間 大きな落窪に
横たわっているその影へ溶けこんでいくのだ
影のなかへ 両腕が落ち、頬骨が枯れて
鼻梁が花びらのようにとび散っていく
人は、その影に隠れ
人は、その影におびえる
人は、その影を耕やさない
人は、その影が何であるかわからない
だがその影は ぶらんこのように
直立した脊椎へ 背後から不意に交わり
無数の手から手へ 伝達文のようにわたって歩く
その影とは 一体何であるか
その影とは 一体何であるか
誰も答えはしないだろう
だが、それとは別に――
新しい世界を用意する、無数のその影がある
【 『KLIMA』第 1 号 安井浩司後記 】
○〈KLIMA〉を創刊した
〈KLIMA〉はドイツ語で、風土と云う意味である。
こゝに集った人達は、初めて詩を書きだしたという連中が多い。碓井、安井が一、二年前から書いていたと云う程度である。従って、作品群が現代詩の水準に遠いと云われてもたいして不思議がらない。たゞ意欲があるのみだ。僕たちは何かを求めている。その何かにつき当てるために足で歩く。その過程が〈KLIMA〉である。
○〈KLIMA〉は毎月発行することにしている。そして月に一度合評会・研究会を開いている。もし、僕らのグルッペに参加したい方があったら発行所に申し込んで下さい。
■ 『KLIMA』第2号書誌データ ■
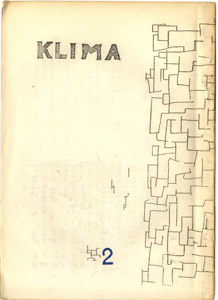
・判型 B5版 縦25.3センチ×横18センチ(実寸)
・ページ数 12ページ
・製本 ガリ版刷り、中綴じホチキス留め
・刷色 黒一色
・表紙イラスト 長沼仁毅
・奥付(原文のまま)
昭和32年12月1日発行
編集・発行人 安井浩司
発行所 東京都北多摩郡小金井下染谷1059富士見寮内 安井方 くりま詩話会
・同人 伊藤満 井坂義昭 碓井耕一 清水重雄 安井浩司
【 『KLIMA』第 2 号 安井浩司作品 】
海・悲歌(――十月二十六日 弟を失いて。) 安井浩司
死を誘う影のように――
潮が渇いた砂へ満ちてきた
太陽は地と海水の裏側を這い
眞昼の副射熱から醒めた
冷えた水母たちが 青い光の群となって
黒い沖へ、沖へと流れていく
巨きな屍が浮きだすように
浪跡がそれに続いている
水藻がかたい岩に生え
つめたい流れへ、無数の触角をのばしながら
水面を渡る風の重さを感じている
夜は海の上にやって来た
人の声が消え
飛行機が睡りへ赴き
荷車のひめいがとだえた
そこでは、まるで何事も無かったかのようになめらかな
灰白質の砂丘がどこまでも続き
潮がめに見えない浸食を始める
漂流して来た兵士の肉体の砕片や
赫い緒をつけた下駄の片足が
そこへ、打ち上げられる
浪が打ち 泡が散る
砂が崩れる
近くで見てはいけないように 茫大な砂壌作用が
そこに存る
水平線は視界から外れ
月は隈限をわずかに泳いでいった
暗い沖では
たゞ冷えた妻と一人の男の映像が
影絵のように通過するだけだろうか
死んだ胎児をかゝえた女が薄らぎ
やがて、コミニストで胸病みの男が消滅する
海上に雨が立ち
こゞえた霧が走って行く
重い叫びがおし黙り
そこには過去だけが 腐食した鉛塊のように
沈んでいる
冷い気温が、広い水面から
粉のように徐々に降りてゆき
縞模様の魚類を包むところ
そこには、腐った男たちのむなしい現在が
海底に甦る
人が永遠だと信じつゞけた処
死者の現在 人の魂の海底が拡ろがる
岩は岩を摑み
桜貝の口が股のように開かれる
錆びた銃と湿った弾が用意される
おびたゞしい虫の死骸が珊瑚樹にはり附いていく
そこにはもはや
海上の霧雨は打たない
人の死や生ぬるい血液も流れて来ない
夜は空を全てはりめぐり
闇が水底へ打ち響くように浸透していった
だが直■ 人の残していった海の悲歌は
この広大ななか 何処にあるのだろう
水母の背の一点にあるのだろうか
海に向って
大人は限りなく己れの悲歌を綴り
子供はそれを唱いつゞける
だが人は死に
海はたゞ、それが在るがまゝだけなのだ
浪が打ち
崖が砂塵をあげて 人の胸から崩れる
それさえ 当然のように――
海は睡らない 決して
海は睡ることはないのだ
* ■は読み取れなかった。
【 『KLIMA』第 2 号 安井浩司関連記事 】
落書 〈仲間・SKETCH〉
安井浩司
詩は一年前から書いているが、くりま誕生と共に事ム屋になってしまった。歯科大学にセキを置き、骨の数などかぞえるのに興味がある。
【 『KLIMA』第 2 号 安井浩司詩論 】
作品について 安井浩司
いま、現代詩は非常に貧困であると云われる。いや決してそうではない。現代詩はむしろ従来の詩を超えた一つの過渡期に立っていて、新しい作品が試みられているから、作品に於けるある程度の混沌さは致し方がない。現在は量より質が大切なのであって、質そのものが低下しているとは断言すべきでないとも云われる。この事については、勿論両者の言い分にも肯かれる所があり、一方を全く否定するこてゃ出来るものではないと僕は思っている。しかし、我々が詩読者の立場にかわって考えた場合、いづれの時代にせよより多くの良い作品を欲するのが現実であろう。
日頃、眼を通す作品群のなかに、二三の良い作品があるにせよ残りの幾百幾千の詩が何か読者の心を捉えるものでないならば、読者は現代詩に対して疑いや不信の感を持つのは当然となるだろう。
もし、詩読者が現代詩は貧困であると云うなら、それは選ばれることなき厖大な亡霊的詩作品に原因しているものであると云える。これらの作品が読者の心を汚して、現代詩は衰弱していると云う観念が植えつけられていく。そして、現状の詩界がまさにこのようでありはしまいか、と僕は今の所少からずそう考えているのである。
確かに一ヶ月発表される莫大な詩作品の中に、数篇の読み応えのある作品が在ることを認めよう。しかし、貧しい作品のまた何と多過ぎることだろう。
僕は毎月〈詩学〉や〈現代詩〉を愛読しているが、しかし読み了えてその都度失望する作品が半数以上である。日頃尊敬する先輩の作品をその雑誌でみて、自分の同人誌や詩集には良い作品を選んで載せ、綜合誌への寄稿は駄作でも載せてかまわぬとでも考えているのではないか。と云う思ってはいけないような疑問さえ持ちかねないのである。
実際に、例えば〈詩学〉十一月号に発表されている田中冬二氏の〈東京の夜〉と云う作品は、僕が失望を感じた一つである。
ほしぐさと馬小屋の匂いの 田舎のあんち
やん ねえちやんたちの あこがれのネオ
ンの灯の美しい東京の町
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
その事に ふんぞり返り 或は乙にすまし
ているのは
足利尊氏 吉良上野介 弓削の道鏡 高橋
のお伝ちやん
みな一癖も二癖もある奴ばかりだ
地位と銭儲と色欲の権化
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
と云うセリフで終始するのであるが、実際にこの作品は肯けなかった。この詩は〈時勢は悪の花ざかり〉でも語ろうとしているらしが、一面のナニワブシ調とでも云いたくなる。このような言い回しに堕ちたものであると云われても致し方がないだろう。もし、この詩の作者が、このような云いまわしに表現の狙いがあるとすれば、僕はその眞意が全くわからなくなるし、一般読者は更に現代詩へ疑惑を深めるのは明白であろう。決して面白い表現でもなければ、特別の効果を実験しているとも考えられなかった次第である。
同じく〈現代詩〉十一月号に〈麻薬取締〉と云う天野美津子氏の作品がある。
重くたるんだ都会の神経
貧困の巣くう軒々へ
一人逃亡!
急を告げる伝令が飛ぶ時刻
汚れた新聞紙にくるまって出て来た
茶色の壜と白い粉末状の結晶が
証拠品
なかの一連を掲げてみたが、この作品も同様に、僕には面白くなかった。第一に詩の内部構造より、言葉そのものに屈託を感じてしまうのである。
この詩に限らず、こんにち否定的要素をもつ言葉が、あまりにも無雑作に用いられてはいないだろうか。このような言葉を用いるとき、それだけで物質のネガティブな部分を描き得たと信じやすい言葉こそ、この否定的要素をもつ言葉であって、それだけでは何ら余分な修辞でしかないのだ。
更に深い関係に於てそれらを捉えるべきであって、単に事象を並列に捉えた〈麻薬取締〉で終っては、僕はこの作品に何の感動も覚えない。むしろ、生な宙に浮いた言葉だけが後味悪く残るだけだ。
先ほど、現代詩が過渡期なればある程度の混沌は致し方がないと述べた。もし現代詩が実験的な作品を通じて混沌としているのであれば、我々は何らかの期待の意味でその事を認め得るであろう。
しかし、今述べた二作品は、何らかの実験を行っているとは僕には思えないのである。いやこの二作品のみではない。この作品に隣りあい、背を向け腹をつき合わせている莫大な作品が、惰性の列の彼方で作られていると云う感じに僕は常に襲われる。
はたしてこれでよいのだろうか。
僕は、現代詩の詩人たちは、少くともみな秀才に違いないと思い、その実力を信じている。勿論、尊敬もし、敬意を払わずにはいられないが、このようなポピュラーな綜合誌(詩学、現代詩、ETC)に載っている作品群が、依然かような詩でうずめられているとしたら、僕はいつまでも綜合誌そのものへの疑問を、一つの悲しみを持ちつゞけねばならないだろう。
(安井浩司)
【 『KLIMA』第 2 号 安井浩司後記 】
-ROOM-
○KLIMA一号を発刊するや否や、上毛文芸の須田宏氏から厚い励激の手紙と批評文を頂いた。その中に、KLIMA詩作品は〈有名詩人の一節を盗んでいる〉ものがあると云う言葉が研究会の話題となり、反省を行い、盗用と模倣について論じられた。KLIMA一号作品は、盗用はないが、章句の一般類型化した作品が多過ぎる云う結論を得た。
○二号を作った。今回は、前号に比して作品が低調のように思う。たしかに残念なことではあるが、しかしそれだからと云って悲しむことはない。一気に初めての人間が良い作品をかけるものではないから。だが、そこに何らかの苦闘の跡がなければ、何の意味もないのは云うまでもない。各同人の奮闘をのぞむ次第だ。
○伊東氏と塙氏の欠席が、今号に打ゲキを与えたのは残念だったが、両氏へ次号に期待しよう。なを三号は一月一日発行の予定で、原稿〆切は十二月五日である。
■ 『KLIMA』第3号書誌データ ■

・判型 B5版 縦25.3センチ×横18センチ(実寸)
・ページ数 12ページ
・製本 ガリ版刷り、中綴じホチキス留め
・刷色 黒一色
・表紙イラスト 長沼仁毅
・奥付(原文のまま)
昭和32年12月31日発行
編集・発行人 安井浩司
発行所 東京都北多摩郡小金井下染谷1059富士見寮内安井方くりま詩話会
印刷所 くりま詩話会KLIMA印刷部
・同人 伊藤満 井坂義昭 碓井耕一 清水重雄 安井浩司
【 『KLIMA』第 3 号 安井浩司作品 】
夏 安井浩司
広場をわたると
数条の道が 白い塵をあげて
肩怒らした祖父の 胸毛へつゞくようだ
戦さで焼かれた焦土には
夏草がいち面に噛みあっていて
むらさきの屍たちを あらく包んでいる
かわいた風が
蜻蛉の群を 双掌いっぱいに盗っていく
あのカンカン帽を斜めにかむった少女は
誰だったろう
おもいおもいの流れに沿って
時間は、木の葉のように浮き
少女の名前が 崖へこぼれていく
誰にも見られてはいけない
たとえば、この夏の大地の痕
野茨のなかに置きわすれた 少女の下着
むきだしにしたうすい胸の 兵士たち
風は、それらを
季節に向って投げかえし
灼けた地
死をよそおう 夏
愛は、犬の眼球のように渇き
人々は、小さい股で石ころを
そっと蹴ってあるく
いまは、青くかくれた空の肌に
白雲の号外が 飛ばない夏だ
愛
すっかり刈り取られて
枯木のようにむなしい姿
墓地が見える 砂丘に立って
お前がくしづけているのは
あれは髪ではない
抜け堕ちえいく肉かれた葉の数々
秋陽にふるえながら 欠けていく指骨
それらを埋めようとして
はげしく吹きまくる
砂と風へ
石のようにひたすらかまえて
この抵抗に 悶えているお前
もうこゝへ朝はやって来ないだろう
粉のような鉄のかけらも
お前の落ち凹んだ胸をさけて
ながい眠りから醒め
眞昼の白い塵から解き放たれた
お前の姿勢
おゝ お前は立つ あやふく
自らのわずかな筋肉で
一つの愛を支えながら
車輪のように炎え立つ、一個のいのち
この氷のような抵抗を支えながら
その欠け堕ちた貌
むしり取られた胸の皮膚
氷河の上をわたり歩いて来た この細せた
白い一本の肉体
いらだたしいまでに沈黙する意志
おゝ、何とむましい仕業だ
一つのいのちのために そこには
幾多の変質がやって来るだろう
無数の血管を流れながら、そのものは
この重みが何であるか
うすい耳の底をながれる 光のように
お前はそれを知っていない
たゞあつい熱のように感ずるだけだ
おびたゞしい愛の実在をくまどる この限界の
外から崩れおちる肉のかけら
内に激しく胎動するもの
それらへ何のかゝわりもないように
お前は立っている――
渇いた砂丘で 薔薇いろの風へ
無防の胸をやさしく開きながら
おゝ、お前だけが勝ち取った 愛の桎梏の中で
病理解剖
あんな男を瞠ると
生身のまゝ病理解剖してみたくなる
のだ。
猫背で
股をカニのように突っぱる
自称コミニストだが
大した嘘も云えない
笑うと
娼婦のような金歯をひからし
何処でも見かける
病的だ!
あいつのどこが腐っているか
ヒストリカルな臓器はなにか
病理解剖台の上にしばりつけて
蛍光灯のギラつく下で
全身の皮を深皮から根こそぎに剥いでみたい
のだ。
【 『KLIMA』第 3 号 安井浩司後記 】
○初冬の風が、脳髄まで浸みこむようだ。寒気が手や足を取りまきはじめる。枯葉が吹き流れていく。三十二年もこれで全て終るわけだ。もう僕らは何の未練も持たない。
○KLIMAは十月に創刊されはや三号を数え得る。うすっぺらい貧しい同人誌。このような恥いに耐えながら、僕たちは己が詩に対して何らかの期待を持ちつゞけていればこそ、このものと共に歩みつゞけている。
○おそらく僕たちに最も必要なものは勇気だろう。革命の炎の前に立っているようなごく単純な勇気・・・・・・およそ創作以前に於て僕たちが無意識に求めているのはこいつではないだろうか。
○来年はKLIMAも何かのかたちで飛躍したい。各同人の奮起を祈る次第だ。
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
