 安井浩司氏蔵の『青年俳句』第4号(昭和29年9月20日発行)の表紙には、『乞御参加』という書き込みがある。恐らく編集発行人の上村忠郎が書いたのだろう。第5号(昭和29年12月1日発行)にも青年俳句会の印が捺された「御参加を乞う」というメモが挟み込まれていた。『青年俳句』は同人制をとる俳誌で、『牧羊神』中心メンバーである寺山修司や京武久美は早くから参加していた。しかし安井氏はあまり積極的ではなかったようである。ようやく第6号(昭和30年3月10日発行)の『消息』欄に『新参加・・・安井浩司(東京都)』の文字が見える。ちなみに大岡頌司もこの号から新同人になっていて『大岡頌司(廣島)』と記載されている。
安井浩司氏蔵の『青年俳句』第4号(昭和29年9月20日発行)の表紙には、『乞御参加』という書き込みがある。恐らく編集発行人の上村忠郎が書いたのだろう。第5号(昭和29年12月1日発行)にも青年俳句会の印が捺された「御参加を乞う」というメモが挟み込まれていた。『青年俳句』は同人制をとる俳誌で、『牧羊神』中心メンバーである寺山修司や京武久美は早くから参加していた。しかし安井氏はあまり積極的ではなかったようである。ようやく第6号(昭和30年3月10日発行)の『消息』欄に『新参加・・・安井浩司(東京都)』の文字が見える。ちなみに大岡頌司もこの号から新同人になっていて『大岡頌司(廣島)』と記載されている。
しかし同人になっても安井氏は『青年俳句』にほとんど執筆していない。安井氏が『青年俳句』に書いたのは、第7号(昭和30年7月15日発行)の一度きりのようだ。この号で安井氏は20句を発表している。
不思議なMemoryなど 安井浩思*1
冬銀河かたく離郷の靴むすぶ
流れゆく雪魂十九の戀を斷つ
琴の音の夕べ梅枝をこぼれ匂ふ
朝東風に嘶くや仔馬の四肢緊めて
坂の隙より吹きこむ花びら牛癒えよ
白くゝゝ母の衣干され春の雷
身にあまる春光母を呼びに出て
春日が育てゝチエリーの園の戀
春星につらなる寮の窓灯る
春銀河かの青年の聲吸ひけむ
旅愁濃し車窓に夕べの山燒く火
遠きひと戀ふとき春の雁光る
ひと憶ふ日の雲たかく春の嶺
岩に立ち遠き記憶の帆を還す
耕牛の尿うすみどり地にたまる
額ひろき祖父よ青田にあまねき日
母癒えし便り麦の穂伸びそろふ
野の花のとりどりワタつく歸省かな
逢曳も焦土タンポポワタはじく
潮騒をこめて漁村のキビ熟るゝ
*1 安井氏のペンネームの一つ。
(『青年俳句』第2巻第2号通巻第7号[昭和30年7月15日発行])
『冬銀河かたく離郷の靴むすぶ』『春銀河かの青年の聲吸ひけむ』などの句に表れているように、遠い観念と地上とを結びつけようとするかのような姿勢は見られるが、まだ安井氏は試行錯誤の真っ最中である。それは『浩思』というペンネームからも読み取れるだろう。安井氏は思索的作家だが、思想だけで俳句作品を書くことはできない。ありきたりな句は書きたくないという思いがかえって句を複雑にしてしまっている。内面の表現欲求を的確に言語化するための方法をつかみかねている様子がうかがえる。
安井氏が『青年俳句』同人になった昭和30年3月は、寺山らの第一次『牧羊神』が終刊になる時期に当たる。前回取り上げたように、寺山は『青年俳句』第19・20合併号(昭和31年[1956年]12月10日発行)で俳句訣別宣言を書いているが、それに歩調を合わせるように安井氏も様々な試みを行っていた。それを裏付けるように、次のような文章が『青年俳句』に掲載されている。
さて、僕の仲間たちと僕のことから書き出そうか。中学三年の時、野呂田柊炎子(註-野呂田稔のこと)、工藤春男、安井浩司らとともに回覧雑誌「せゝらぎ」を発刊した。俳句、短歌の同人雑誌で、我我の手で刷ったガリ版の小冊子であった。勿論すぐ廃刊。その後、四人は能代高校へ揃って入学した。僕と柊炎子はすぐ文芸部へ入部し、当時一級上の武田伸一、上村忠郎、また二級上の土橋柚子雄(麦)らと知り合った。しかし僕らが二年に審級した時、忠郎は八戸高校へ転校し、消息を絶った。僕らを俳句へ没入させたのは、この頃である。「こがも句会」なる句会を作ったのは、たしか高校二年の終りころであり、更に「極光帯」という新聞紙の様な機関誌を作った。未だ、僕は俳句には不熱心で、半分あそんでいた。高校卒業(昭和二十九年三月)と同時に、柊炎子、春男、浩司を中心に、伸一、それに青森高校を同じく卒業した寺山修司らと、同人誌「光冠」が誕生した。無理矢理に会員の列に加えられた僕だったが、俳句のもつ不思議な魅力に惹かれ、抜きさしならぬ所まで来た。真剣に句で苦しみ、如何にあるべきかを考えさせられた。この頃「青年俳句」へ参加したのであるが、俳句を意識し、一つの主観をもって、今では曲りながりにも進んでいる。
僕らの仲間、安井浩司は俳句から転落し、工藤春男、野呂田柊炎子は同人誌「黒鳥」を創刊した。僕は一つの考えのもとに、幼年よりの文芸仲間と、訣別した。更に大いなる未来が開らけて来るのを感じて――多分僕は大木になるだろう。いや、ならなければなるまい。
(柴田三木男『朝への道』『青年俳句』第3巻第6号通巻18号[昭和31年9月10日]発行)
柴田氏については詳細な経歴は不明だが、彼の文章から『青年俳句』主宰の上村忠郎は能代高校から青森八戸高校に転校していること、安井氏ら能代高校組が中学時代から様々な同人俳誌を発行し、高校卒業後は青森高校の寺山らと『牧羊神』以外にも『光冠』などの同人俳誌を刊行していたことがわかる。ただ昭和31年(1956年)当時、柴田氏は安井浩司は俳句をもうやめてしまったと認識していたらしい。次回以降で取り上げるが、31年(56年)から32年(57年)にかけて、安井氏は自由詩の同人誌を複数刊行している。それが柴田氏には『安井浩司は俳句から転落』したと映ったようだ。
寺山や京武、それに安井は『青年俳句』同人になったが、積極的に関与した気配はない。『牧羊神』的な俳句革新とは距離を置いた穏やかな『青年俳句』に、あきたりないものを感じていたためではなかろうか。それに対し柴田氏は、『青年俳句』第18号に『特別寄稿』の扱いで作品を発表している。引用の『朝への道』はそこに添付された文章である。柴田氏は『僕は一つの考えのもとに、幼年よりの文芸仲間と、訣別した』と書いているが、彼と『牧羊神』同人との間になんらかの軋轢があったのかもしれない。若い作家たちが、親しく付き合うのと同時に、激しく競り合い、時にいがみ合うのは今も昔も変わらない。ただ『俳句から転落』したと書かれた安井氏は、心中穏やかではなかったろう。
大岡頌司は『青年俳句』参加後、精力的に作品を発表している。以下、手元にある『青年俳句』に発表された大岡の俳句をすべて掲載しておく。
廣島 大岡頌司
母不遇不遇の明日へ菜を漬ける (『遠船脚』)
潮引いて現(あ)れくる岩へ移る鳥
稲架に鳴る潮風海のかなしみか (『遠船脚』)
(『青年俳句』第2巻第1号通巻6号[昭和30年3月10日]発行)
麦秋 大岡頌司
萬緑に蔭なき車死を誘ふ (『遠船脚』)
すかんぽや童のくれし大きな声 (『遠船脚』)*1
草履の土乾きて軽し麦の熟れ (『遠船脚』)*2
茶を沸す痛き煙に麦熟れり (『遠船脚』)*3
野の傷は野で癒ゆ麦の熟れし中 (『遠船脚』)*4
植込みの意図噴水の憩われず (『遠船脚』)*5
ぎんやんま繁れど郷里の山低し
夏雲や内海「海の彼方」なし
七夕や軒の暗さに犬飼はれ (『遠船脚』)
短夜の闇がつきゆく漁火に (『遠船脚』)*6
(『青年俳句』第2巻第3号通巻8号[昭和30年8月15日]発行)
地の果て 大岡頌司
青みかん見えて見えざる沖を指す (『遠船脚』)
母亡き児ブドウの粒をたべ減す (『遠船脚』)*7
蝉の尿(しと)潔し樹間に光りたち (『遠船脚』)
蝉鳴いて弥勒菩薩の木目を彫る
蟻の列曲る「地の果て」への曲り (『遠船脚』)*8
片蔭に説く地の紙に石のせて (『遠船脚』)
旱星涙は天にも地にもなし (『遠船脚』)*9
かぶと蟲売るアセチレンの灯に今日掛けて
(『青年俳句』第2巻第5号通巻10号[昭和30年10月15日]発行)
知られざる灯 大岡頌司
沖に仂く漁夫秋暁の影長し (『遠船脚』)*10
掌に豆腐切る夕寒は子を泣し (『遠船脚』)*11
手錠の手また鳩笛の掌にかえれ
鳩笛は夕来る笛胸疼し (『遠船脚』)*12
× ×
磯龍の目に秋暁の光滿つ (『遠船脚』)
茸盗み来て谷川の瀬に遊ぶ
蟷螂殺す目馴しものに海の青 (『遠船脚』)*13
鎌磨ぎの海みては汗かゝざりし (『遠船脚』)*14
聳らざるふるさとの山茸まろし (『遠船脚』)
× ×
短日やレンガの家の知らざる灯 (『遠船脚』)*15
(『青年俳句』第3巻第1号通巻11・12・13号[昭和31年1月1日]発行)
住込みの下駄 大岡頌司
古びたる住込みの下駄土間色に
菓子を焼く暑き竃辺に葉書来る (『遠船脚』)*16
自転車の荷の綱御所と伸一訪う
職のなき不安よ百合の花枯るゝ (『遠船脚』)*17
○ ○
握鋏の親しき秋の彼岸来る
カバンは筆入の鳴る音稔田を帰る (『遠船脚』)*18
通草垂れて子のスカートの小さき拡がり
銀杏の青き割れた葉教師恋う
御百札のソロバンと椎の実に育つ
(『青年俳句』第3巻第7・8号通巻19・20号[昭和31年12月10日]発行)
*1 定稿では『声』は旧字の『聲』。
*2 定稿では『軽』は旧字の『輕』、『麦』は旧字の『麥』。
*3 定稿では『麦』は旧字の『麥』。
*4 定稿では『麦』は旧字の『麥』。
*5 定稿では『図』は旧字の『圖』、『憩われず』は旧字の『憩はれず』。
*6 定稿では『つきゆく』は『つき行く』。
*7 定稿では『母亡くてぶだうの粒をたべ減す』に改稿。
*8 定稿では『「地の果て」』の「」なし。
*9 定稿では『旱星涙以前の渇き胸に』に改稿か。
*10 定稿では『仂』は旧字の『働』。
*11 定稿では『泣し』は『泣かし』。
*12 定稿では『鳩笛はゆふべ來る笛胸痛し』に改稿。
*13 定稿では『目馴し』は『目馴れし』。
*14 定稿では『鎌磨ぎ』は『鎌研ぎ』、『かゝざりし』は『かかざりし』。
*15 定稿では『煉瓦の家われの知らざる灯が寒し』に改稿か。
*16 定稿では『辺』は旧字の『邊』、『来』は旧字の『來』。
*17 定稿では『枯るゝ』は『枯るる』。
*18 定稿では『筆入の鳴る』は『筆入が鳴り』、『帰』は旧字の『歸』。
確認できた限りということになるが、大岡は『青年俳句』に40句を発表し、内27句が昭和32年(1957年)刊行の処女句集『遠船脚』に収録されている。大岡は30年(56年)6月に故郷広島を離れ、京都の文福堂製菓に住み込みで働き始めた。翌31年(57年)8月には上京して蒲田のマシュマロ工場の住み込み従業員になった。
『古びたる住込みの下駄土間色に』『菓子を焼く暑き竃辺に葉書来る』は大岡の菓子職人としての生活が下敷きになった句である。また『自転車の荷の綱御所と伸一訪う』の『伸一』は、後に金子兜太氏の『海程』で活躍することになる武田伸一氏のことである。京都時代に大岡は、立命館大学に在学中だった武田氏をしばしば訪ねて俳句などの話をしていた。
大岡俳句についての考察はいずれ別の機会に行いたいが、決して多作ではなかった大岡の句集未収録句は貴重だと思う。『夏雲や内海「海の彼方」なし』『手錠の手また鳩笛の掌にかえれ』といった句には、撞着的表現によって言葉と観念の深部に到り着こうとする彼の手法がよく表れている。その逆に『潮引いて現(あ)れくる岩へ移る鳥』『ぎんやんま繁れど郷里の山低し』などは、大岡がときおり好んで詠んだ素直な叙景句である。しかしいまひとつ納得できないので句集に収録しなかったのだろう。句集に収録された同手法の句と未収録句を比較すれば、彼の創作の秘密の一端が見えてくるのではないかと思う。
結論めいたことを言えば、『青年俳句』は『牧羊神』と併走するように刊行し続けられた雑誌で、第一次『牧羊神』終刊後は、ポスト牧羊神的な位置にあって当時の若い俳人たちの作品を掲載した。しかし雑誌自体の主張はあまりなく、若い俳人たちを緩く束ねていたようだ。『青年俳句』は作品を定期的に発表できる場という位置付けだったのではあるまいか。
それに対して『牧羊神』には、俳句を革新したい、新しい試みを行いたいといった前衛的指向が全同人の共通理解として存在していたように思う。安井氏は『牧羊神』でも『青年俳句』でも決して主力同人ではないが、主力ではなかったからこそ、『牧羊神』的前衛性を最も真摯に受けとめていたのではないかと思われる。その後の前衛に対する解釈は大きく異なってしまうが、その意味で寺山と安井は最も『牧羊神』的な同人である。当人たちにとっては腐れ縁と言うべきなのかもしれない。
鶴山裕司
■ 『青年俳句』第2巻第2号通巻第7号(昭和30年7月15日発行)掲載 安井浩司作品 ■
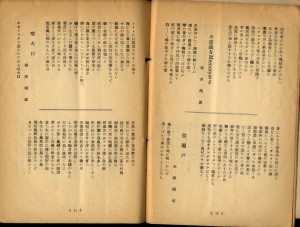
■ 『「観光市」と伸一さんと私のこと-休憩断片-』大岡頌司(『青年俳句』第3巻第7・8号通巻19・20号[昭和31年12月10日]) ■
* 以下のエセーは『青年俳句』第3巻第7・8号通巻19・20号(昭和31年12月10日発行)の巻頭に掲載された。大岡が京都時代の武田伸一氏との交流を綴った文章である。なお『観光市』は『青年俳句』第3巻第1号通巻11・12・13号(31年1月1日発行)に発表された武田氏の連作俳句30句を指す。初期の大岡の文章として資料的価値があると思うので、以下に全文を掲載しておく。
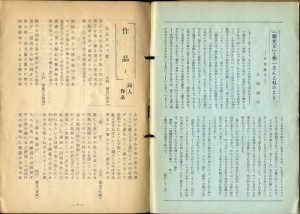
もう少し寒くなると、ちょうど一年前のあの頃になる――。
大佛次郎の「帰郷」に書かれた様に、京都には特有の家のくらさがある。伸一さんの下宿も、その特有のくらさのある部屋であつた。しかも私が訪ねたのは、ほとんど夜だつたが、このくらさ(註-「くらさ」に傍点)は昼間のものばかりでなく夜の方が切に感じられた。青い蛍光灯のスタンドがついていても、華やかでないから不思議なものである。
「観光市」は、彼が夏の休暇に帰省してから冬の休暇近くまでの作品を、日頃書きためた手帳から抜き出したものである。だから特別に力んで作られたものではない。それにこの一連の作品の中には、著名俳人から好評あつた句もたくさんあつて、今さら下手な鑑賞文や意慾に対する批評等はしないことにする。それよりも問題なのは彼が二度も三度も書きかえたり、編集の間に遅れてはと速達便をしたりして付した「ある奇妙な誕生」と題するつぶやきに似た一文である。彼が一番言いたかつたのは「――社会性――批判を根本にもたなければならぬと思うが、余りにも狭い型にはめられたうらみがないでもない。――」と云う。つまりこつことと実作化を試みつゝあるところを、いきなりジヤーナリズムによつて変に問題化された「社会性ごと」の嫌いのことである。
その頃私は菓子屋と云う、おそらく古い考えの内に働いていた。そしてそこでのいろいろなことのぶちまけをするために、月に一、二度は伸一さんの下宿を訪うこ冃とに決めていた。ともすれば恐ろしい考えにのびる孤独の考えを浄化させては、すつかり更けた星空を見ながら「こゝは京都」等と心に聞かせ、西大路を■(註-読み取れず)町から御池角まで下つたものである。
濁らない少年の様な伸一さんの声は不恰好にお茶をいれながら何度も私をうなづかせた。学生であるさびしさはいつも根に秘められていたが、時々はげしく具体化する双掌や指先の真剣さは京都の町のしづまつて、ときどき来る丸太町線の市電が終電近いところにまで続いた。
「――またぞろ駄句の誕生が続くだろう」と、うれしがる伸一さんに期待出来てならないし、それと一緒に「銭湯」や剃刀を買う句を作る伸一さんがなつかしくてならない。
都落ちする日。ホームにかけつけてくれた伸一さんの「急だつたね・・・」と口ごもる二人の会話が、いつまでも生々しく私の胸から去らない。頭の上に黒い行李を乗せて、小さく腰を下した私は、別れにもらつた包みを開いてみた。扉に
芽吹く一樹機関区給水塔濡れて聳つ 伸一
と染めた小さな冊子であつた。
(昭和31・9・20)
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
