フェスティバル / トーキョー12主催作品
岡崎芸術座『隣人ジミーの不在』(鑑賞日:11月5日)
於 あうるすぽっと
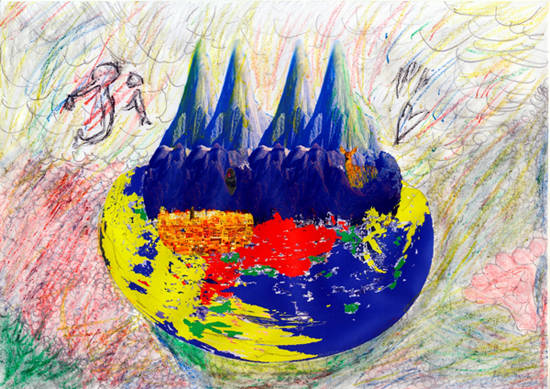
(c)神里雄大 (c)Yudai Kamisato

(c) 富貴塚悠太 Yuta Fukitsuka
作・演出 神里雄大
出演 武谷公雄
稲継美保
山縣太一(チェルフィッチュ)
美術 神里雄大
照明 黒尾芳昭
音響 高橋真衣
舞台監督 寅川英司+鴉屋
衣裳 天神綾子
映像 ワタナベカズキ
撮影 富貴塚悠太
演出助手 小野正彦
英語翻訳 門田美和
韓国語翻訳 李 丞孝
制作 急な坂スタジオ
協力 梅山景央、植松侑子
広報協力 precog
製作 岡崎藝術座
共同製作 フェスティバル/トーキョー
助成 公益財団法人セゾン文化財団、芸術文化振興基金
主催 フェスティバル/トーキョー、岡崎藝術座
本作のテーマはタイトルの通り「隣」にあると思われるが、しかし不在する「隣」への問題意識は、跳ね返って「私=自分の不確定」を問い返す。岡崎芸術座主宰で本作作者の神里は、「隣」が「私」との関係にある相対的な概念だという。
「もしも隣がいなかったら、自分はどうして自分を評価したり反省したりそもそも認識したりできるのだろうか。」(F / T 12プログラム紹介の「創作ノート」に寄せたステイトメント)
「隣」とは誰(何)か、その境界線は「私」の輪郭線によって決定される。「隣はいつでも『自分ではないもの』だった。」「隣は『自分ではないけど、なんかわかる』ものであると思われる。」これらも神里のことばの引用だ。「隣」と「私」は同時に発生する。だから「隣」が不在となるとき、まず疑われるべきは先行する「私」の不在なのである。
その意味で、本作はヤマオの「私」が錯乱していく過程とも捉えられる。開演時、舞台にはヤマオとウミコの夫婦が登場する。「まずは髪に触れる……」ヤマオ役の山縣は髪をなでるような動作をするが、ウミコ役の稲継の髪には触れない。二人の役者は触れ合うことなく服を脱がし、セックスに移行する。行為の詳細は発話される。冒頭のこのシーンによって、本作における役と役者の振る舞いの「ずれ」や「遊び」が予報されている。岡崎芸術座の演劇がしばしば「チェルフィッチュ以後」と区分けされる所以にも思い当たるところだ。こうした「ずれ」を可能にするのは、ヤマオがウミコ(稲継ではなく)を認識し、ウミコもヤマオ(山縣ではなく)を認識し、劇の世界を共有しているためだ。
それが徐々に崩壊していく。生まれた子が黒人であったことに、ヤマオはウミコの浮気、しかも以前から疑っていたダンス教室のパートナーだけでなく、どこの誰とも知れない黒人との浮気があると思いこむ。妻と自分に隣接しながら不在の「隣人ジミー」とはこの黒人のことを示唆している。休憩時間を挟んだ上演の前半部は、少なくともそう見えるように作られている。
しかし後半部、前半のドラマに覆われていた本作の中核があらわになる。ドラマの背景も明かされる。アジア連合のような国際構造、増殖するガイジン、本土のただならなさと避難先の沖縄、そして就職難。我々の現在とも端々でリンクした不穏な近未来が設定されていることがはっきりしてくる。しかし本作の関心は未来の日本の事情を暗示することではないだろう。山縣が突然顔を青黒く塗って登場する。そしてヤマオの色覚障害が明らかとなる。
青黒い素顔、色覚障害という種明かしによって、ヤマオの前半部での発言とその台詞/テキスト(黒人の子供など)は不信を招く。後半部で観客の目にあらわとなったヤマオが本当なら、前半部で稲継、観客と共有されていたヤマオ/劇世界はなんだったのか。ヤマオの主観が可視化された世界だったと考えるのが妥当だろう。そして休憩を挟んだ後半部では、主観の盲点を暴いた非主観としての「客観」が舞台を構築する。「客観」の世界ではヤマオの主観が歪んでいること、つまりヤマオの「私」は主/客の間で「ずれ」て「ぶれ」ていることが露呈するのだ。
こうしたヤマオの「私」の解体は、役の解体とも同期して、自己不確立の錯乱は極限に達する。ヤマオは保険リサーチャーのミヤザトと盗難の調書作成のために待ち合わせするが、ミヤザトはウミコ役稲継の一人二役で演じられる。彼女に連れられて舞台上を右往左往と彷徨しながら、異様に長い道のりを喫茶店へ向かうとき、ヤマオはミヤザトが柵をまたぎ、ぬかるみを渡る(ように演じる)のを真似して後をついていくが、その演技の所在なさは、もはや共有されるべき劇世界の柵もぬかるみもヤマオには見えていないかのようだ。そして喫茶店で向かい合い、ミヤザトをウミコと同一視する瞬間、ヤマオは舞台に実在する稲継を見る。「こんどこそおれたちの子供をつくろう」。これに前後して、ヤマオがミヤザトの腕をつかみ、愛撫し、ミヤザトもそれに感じてしまうくだりがあるが、この場面もまた、冒頭のウミコとの場面と相対した逆転現象を示している。
劇の最後は、喫茶店(ここもヤマオに言わせればガイジンだらけなのだが)で突如始まる落語会で締められる。上演中に舞台裏に集合したエキストラがぞろぞろと出てくると、ヤマオとミヤザトを取り囲んで座り込み、舞台上の観客となる。「なんかガイジン多くないですか!?」そうだろう、彼らエキストラは台本/テキストすら持たない部外者なのだ。
落語が終わり、ガイジンたちが退場すると、ヤマオとミヤザトはぽつりと舞台に取り残され、一言も発することなく、そのまま幕引きの暗転を迎える。取り残されたのは、いまや彼らが劇世界において不在するからだ。一言も発しないのは、もはや、劇世界そのものが不在するからだ。それは台詞/テキストの最初の不信から始まっていたのではなかったか。役を含めた劇世界を観客の想像力に構築するのは発話される台詞/テキストであり、発話された台詞/テキストはそのために全編において信用されなければならない。
もう一度、冒頭の場面に立ち戻る。触れずして脱がし、発話によって行為となしたあの場面では、台詞と役者の身体と観客の間で、たしかに劇世界が共有されていた(それはおもにヤマオの主観で構築されていたが)。だから発話された行為と目に見える具体的行為の「ずらし」が成立していた。ところが、ヤマオの台詞に不信が起こり、それがヤマオの「私」を不確定にし、その解体の手が役にまで達し、後半部の「客観」の世界でヤマオの目は劇世界と現実の境を侵犯した。ミヤザトに稲継を見、エキストラをガイジンと見破った。ここで劇世界は破綻したのだ。しかもそれは神里が創作した台本に忠実に破綻したのである。劇世界は落語とその観客、台本を持たぬガイジンとともに消える。演技もせず、舞台上に座り込み、与えられた役もあいまいな彼らとともに消える。役は残らず、台詞もない、中断。その意味では、ミヤザトはガイジンらとともに退場しても良かったのだ。発話されることの無い台詞の予感のなかで、不確定に想像されうる劇世界の住人として。
テキストの不信という要素は、上演中の字幕/テキストにおいて最も明確となっただろう。英語・韓国語の字幕はそれまで忠実に台詞を翻訳していたが、落語においてはその発話量、速度、言葉遊びの翻訳不可能の壁にあたり、状況説明も満足に行えないほどの機能不全に陥っていた。これはノン日本語ネイティブの観客にだけ向けられていた訳ではなく、日本語字幕公演の試みが裏付けるように、あらゆる観客に向けられている。字幕テキストを頼りにした場合、落語特有の幕引き、つまり「オチ」を舞台上の観客と同じように認識することができない。舞台上の、つまり劇世界の観客の拍手などを目にし、落語の終わりは「遅れて」認識されるのだ。その瞬間、やはり劇世界は不在する。認識されるのは、もうそこにはない、遅延した、不在の過去である。もちろん、字幕の設置目的は聴覚障害を持つ観客にも開かれた公演を目指してのことだろう。しかしそれはテキストの不信・不全が劇世界を破壊する様をも可視化した装置でもあったのだ。
現実の認識というのは、あるいはつねにこういうものかもしれない。「隣」を認識する前に「私」を認識する前に、「『私』とはなにか」というテキストが存在する。そのテキストが信用できるなら、我々の現在は劇世界化して見えるようになる。テキストが信用されないとき、我々はヤマオと同じ錯乱状態になる。
しかし、「私」の錯乱はそう悪いものでもなく、実は「隣」の有り様など「私」の劇世界の有り様に依るだけのもので、つまり主観に依るものにすぎないのだという神里の主張に舞い戻って、それを裏付ける。本作の上演は、つねにその出発点に舞い戻るのである。そして、中断する。確信犯的な上演失敗だ。「隣」を認識するために信用できる強度を持ったテキストが、つねにどこか不在している。そして「隣」という「現在」の認識は、我々が夢見がちな統一的な劇世界の彼方に保留されている。しかし、そのような劇世界を認めてしまっていいのか。この問題点はナチュラリズムを通過した現代演劇の根幹が抱くテーマとなる。
星隆弘
■ 『フェスティバル / トーキョー12』公式ホームページ ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
