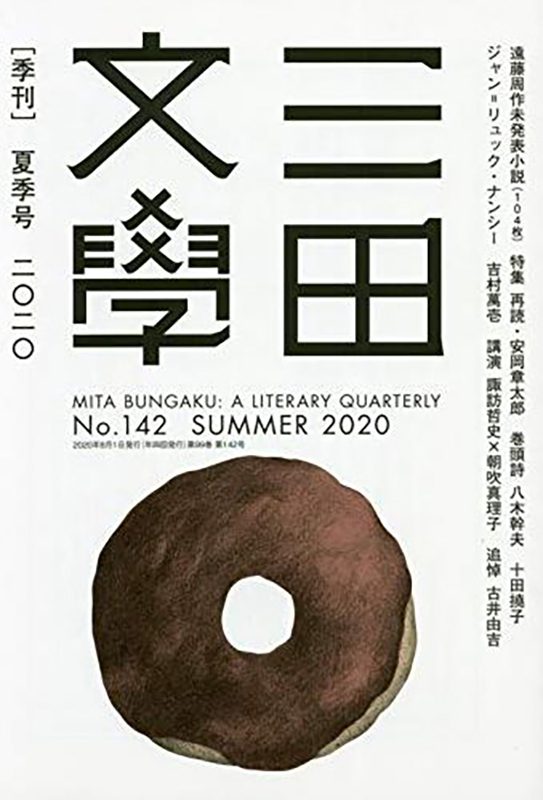
三田文學は実質的に慶応大学が刊行している大学文芸誌だから、慶応出身者の作品や業績の顕彰が優先させるのは当たり前のことである。今号には遠藤周作の未発表小説が掲載され、安岡章太郎特集が組まれている。また西脇順三郎の詩を巡るイベント「アムバルワリア祭」の講演が再録されている。いずれも慶応大学出身の文学者である。
慶応出身者以外から見れば、これは偏向に見えるかもしれない。しかし三田文學と同じような偏向はどの雑誌にも存在する。純文学小説誌に大衆小説作家の作品が載ることはほとんどないし、その逆も真である。また各誌はそれぞれ作家を抱えていて、新人賞受賞作家などをずっとフォローアップしてゆくのは義務のようなものだ。過去に売れた小説を掲載してくれた作家も大事である。よほどの話題性でもない限り、ポッと出の縁もゆかりもない作家が、特定の雑誌で優遇されることはない。
つまり三田文學は、その誌名から慶応大学の雑誌ということがすぐわかるので、いわゆる偏向が目立って見えるだけのことである。雑誌ごとにお抱え作家がいるのと同様に、慶応出身者にとってはとてもありがたい雑誌である。ただこれは文学の世界の現実の話であって、文学そのものとは関係がない。
三田文學はミニマルな文芸誌なので、今の文芸誌が置かれた状況が他誌よりわかりやすい面がある。編集部がポスト・モダニズム思想を重視しているのは明らかで、関連評論や翻訳がほぼ毎号のように載る。しかし新しさを感じない。その理論に精通しているかどうかは別として、現代ではポスト・モダニズム思想は現実社会で常識化している。前衛的な思想を模索するなら、現実世界のさらに先をゆくポスト、ポスト・モダニズム思想を探らねばならないわけだが、過去のポスト・モダニズム思想の祖述に終始している。
小説だけでなく、短歌や俳句、自由詩への目配りも怠っていない。しかしそれが焦点を結ばない。編集部だけの責任ではなく著者にも問題があるわけだが、結局はそれぞれの詩のジャンルに逼塞していて外に溢れ出すような力がない。編集部に共通パラダイムを作り出そうという姿勢はあるのだが、そのヴィジョンがなかなか見えてこないのだ。これは三田文學だけでなく他誌にも言えることである。それだけ文学で現代社会を捉えるのは難しく、文芸誌に現代的存在意義を与えるのは困難である。
三田文學は上田敏顧問、永井荷風主幹で創刊された。荷風を主幹に推薦したのは森鷗外である。鷗外は帝国大学卒だが、小倉左遷の際に陸軍を辞して慶応で教えるという道に一時心を動かされたようだ。慶応には縁の深い作家である。この顔ぶれを見てもわかるように、三田文學は当時文壇を席巻していた自然主義文学ではなく、帝国文学と並んで芸術至上主義的な路線の雑誌だった。特に初期はその傾向が強く、特定の作家たちが雑誌の屋台骨だった。
三田文學が同人誌評を引き継いだ純文学誌の文學界はもっとはっきりしている。今文藝春秋社から刊行されている文學界は、創刊当時は編輯同人制を採っていた。宇野浩二、廣津和郎、川端康成、林房雄、小林秀雄らである。戦中に発禁処分を受け断絶したが、戦後復刊され、昭和二十四年(一九四九年)から実質的に文藝春秋社刊の商業文芸誌になった。これとは別に、明治中期に島崎藤村、戸川秋骨、上田敏らが参加していた同人誌、文學界がある。
戦前の文学雑誌は同人誌や編輯人制を採っていることが多かった。戦後に商業文芸誌が刊行されたが、文學界を代表とするように、作家たちが主体になった同人誌・編輯同人制の雑誌と地続きだった。
なぜそんなことが起こったのかというと、パラダイムが存在したからである。戦前の文学は欧米から流入する新たな文学を吸収消化するのに大わらわだった。写実主義、浪漫主義、自然主義など次々に新たな文学が花開いた。それは日本の古典文学とマージされ、戦後になってさらに魅力的な作品を生み出した。一方で戦後には戦後文学という共通パラダイムが存在した。物心両面の敗戦からの復興を文学は描き続けたのだった。
このような文学の共通パラダイムが今の文学の世界にはない。それが作家の活動はもちろん、文芸誌の運営をも困難にしている。戦後文学華やかな時代、つまり戦後文学というパラダイムが存在していた時代には、小説家、詩人、批評家を問わず、原稿を発注して雑誌に掲載すれば、茫漠とではあるが一定の共通基盤(世界認識)が自ずと見えた。しかしそれが今では機能しなくなっている。
各ジャンルで活躍している作家から原稿を集めれば、華やかにはなる。だが共通点が見い出せない。かつては商業文芸誌に原稿が掲載されるのは達成感のある名誉だった。それもなくなりつつある。ある文学的理想(ヴィジョン)に沿って作家がセレクトされているのではなく、作家と文芸誌の現世的都合が透けて見えるようになってしまっているのである。この難しい事態はそう簡単には変わらない。ただ変えられなければ間違いなくますます文学は衰退してゆく。ありとあらゆる方策を試してもいい時期になっているのである。
三田文學は他誌と同様に編集長を置いているが、三田文學会に所属する文学者とのゆるい編輯同人制を採っている。ただ誌面を見ていると、雑誌に力を及ぼすことができる編輯関係者が一定ページを分け合って、それぞれが好きな誌面を作っているという感じが否めない。雑誌を貫くようなヴィジョンが見えないのだ。困難な時代にはある作家がもっと強権的な力で雑誌を作るのも一つのあり方だろう。
ほとんどの作家は雑誌の存在意義に興味がない。自分が生き残るのに精一杯である。だが結局は現代社会を反映した一定のパラダイムを作り上げなければ、文学界全体の盛り上がりはない。編輯関係者の顔が見えやすい三田文學は、新たな文学を作り上げた戦前の文芸誌のように、他誌よりも現代的文学パラダイムを作りやすいかもしれない。
「しかしここにきて、我々の秩序世界が狂ったリアルに追いつかれた。君みたいに、脳がツルツルの人間が言葉の力を水のように薄めたせいかも知れない。だったら自業自得だ。確かに昔は、こんなに言葉に頼っていなかった可能性がある。護符や呪文や語りによって黒い物を懐柔し一体化することに、彼らは遙かに長けていたのかも知れない。しかし時代と共にそんな力は衰退した。その代わりに我々は、もっと確実で効率のいい科学技術を得た。文字を無限に増やせる印刷機の発明以来、輪転機はずっとフル稼働だ。そしてIT革命だ。物量で勝負だ。大量生産大量消費。ガチャンガチャンガチャン! おいっ! 何をしているんだ!」
吉村萬壱「フェイク」
今号には小説短編三作が掲載されているが、技術的にも内容的にも小説として成立しているのは、言いにくいが吉村萬壱さんの「フェイク」だけだった。二年間浪人して、これで最後と決めた三度目の公務員試験に挑む主人公が、試験直前に見る悪夢のような世界を描いた作品である。常識的に捉えれば統合失調症か、ドラッグの幻覚でもたらされるような世界が描かれている。もちろんそれだけではない。
主人公は得体の知れない巨大な黒い物に追い回されている。また自分の内部にも黒い物を飼っている。ときおりこめかみなどから触手を出すそれを愛撫し、引き毟ると自慰をする時のような快感がある。巨大な黒い物は主人公だけでなく、アパートの隣の部屋に住む老人や、たまたま知り合った人なども飲み込んでゆく。ついには世界全体に疫病のように黒い物が蔓延してゆく。
主人公が「昔は、こんなに言葉に頼っていなかった可能性がある。護符や呪文や語りによって黒い物を懐柔し一体化することに、彼らは遙かに長けていたのかも知れない。しかし時代と共にそんな力は衰退した」と言っているように、黒い物は言語以前の呪術的世界のことである。少なくともそれを含む。
この黒い物の存在と力を感じる主人公は、必然的に現代社会から脱落してゆく。主人公ばかりではない。黒い物が疫病のように拡がるのは、現代社会の言葉が臨界点に達していて、原初的な闇のエネルギーを何らかの形で取り入れるか、そこに回帰せざるを得ない行き詰まりを示唆している。しかしそんなことが可能なのだろうか。
玄関を開けて外に出てみると、そこにガスタンクほどもある巨大な黒い物がいて、剥き出しの内臓を対流させていた。思わずこめかみに触れてみたが、穴はない。その時、脳の繊維など一度もこめかみの穴から出てこなかったのだ、と気付いた。髪の毛を掻き上げながら、誰も裸ではなかったし、爆死もしておらず、つまり世界が何も変わっていない可能性を考えてみた。そして、それはあり得る、という結論に達した。(中略)
巨大な黒い物は、懸命に内臓を出し入れしながら精一杯存在感を誇示していたが、「もういいよ」と呟くと瞬時に消えた。(中略)
辺りを見回すと、そこには玄関扉があり、家の壁があり、塀があり、電柱があり、アスファルトがあり、雑草があり、乗ってきた車があった。それらは余りにも何の変哲もなく、平凡で、鉄のように頑丈で、何があっても微動だにしない現実そのものだった。
(同)
当然だが主人公は悪夢から覚める。現実世界に戻ってくる。それはこの短編小説の必然的な帰結だ。ただ吉村さんの作品では多くの場合、主人公は落伍者として社会の底辺に沈んでゆく。それは作家にとっては一種の愉楽なのだろうが、自らが立てたテーマへの敗北でもある。もっとご自身のテーマに自信を持ち、ポジティブに攻めてもいいのではあるまいか。つまりもっともっと残酷に社会の底辺に沈んでもよい。そこに活路があるかもしれない。この作家は現代的なテーマを有している。
池田浩
■ 吉村萬壱さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■







