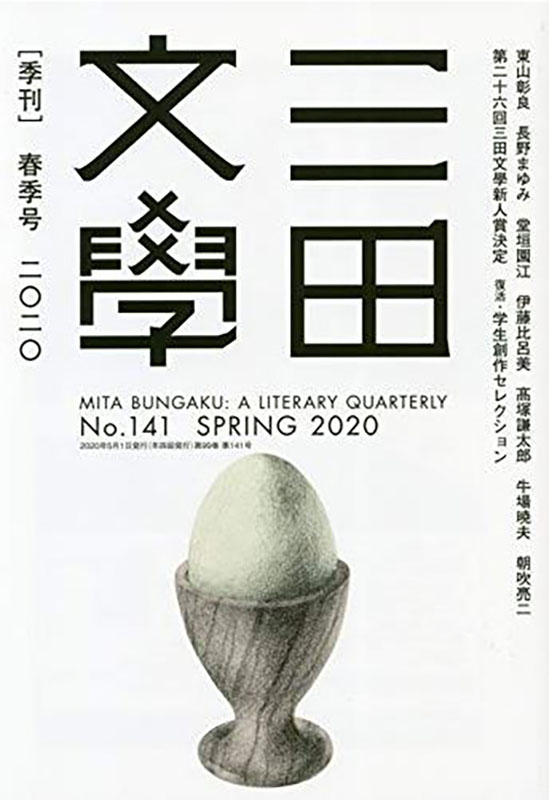
春季号は第二十六回三田文學発表号で、小森隆司さんと田村初美さんが受賞なさった。小森さんは一九五九年、田村さんは一九五一年生まれなので高年齢作家の受賞である。小森さんの受賞作「手に手の者に幸あらん」は前衛的作風、田村さんの「とぼくれホタル」はオーソドックス小説タイプなので、なかなかいい組み合わせかもしれない。
新人というとどうしても若い作家を期待してしまうが、人間それぞれ〝時アリ〟である。五十代でも八十代でも作家デビューできる。ただ年齢が上がれば上がるほど、メディアはもちろん読者が作家に求める要望は高くなる。筆力があり作品の質も高くなければならないわけだ。高齢作家が可能性いっぱい、夢いっぱいの二十代三十代作家と決定的に違う点はそこだ。デビューしてから思いっきり迷い試行錯誤する時間は残されていないわけですね。
闇に包まれた六畳の和室の中、掃き出しの窓の障子は朧な浅黄色だった。外は満月であることが窺える。東村ユキエは布団に横臥したまま手を伸ばしてほっそりと障子を開けた。月の明かりが差し込んだそこだけ、新畳とみまがう若菜色になった。畑の雑草も屋根の庇に糸を張った団子蜘蛛の巣も闇の中に潜み、漆黒の山の上で黄金に輝く丸い月は、空にほうり投げられた毬のようである。
「なっとまあ、くっきりとした月やこと。春やとゆうのに、今晩は朧月とは違うんやのう」
屋根の庇の先に見える月を眺めて、ユキエはつぶやいた。
(田村初美「とぼくれホタル」)
凝りに凝った、練りに練った文体である。正直なところ一昔前の小説という感じがする。もちろん小説を読み通せばその理由は理解できる。主人公のユキエは老年で枯れている。春夏秋冬の自然の巡りに身を委ねている。ユキエの心象は自然と一体なのだ。しかし平穏な生活を送っていても事件が起こるから小説である。
六年ほど前にユキエは魚を買いに行ったことがあった。店内中央には平置きの冷蔵陳列ケースがあって多くの種類の生魚が並べられてあった。ユキエはその中からカレイの切り身を三切れ注文した。店番をしていた経営者の妻は、奥にもっといいのがあるからと言い、魚を捌く調理場に入っていって、ユキエが希望したのと同じカレイの切り身を三切れ包んで持って来、売ってくれたのであった。持ち帰って煮たところ、カレイは鍋の中でバラバラに煮崩れて粥状になってしまった。(中略)一般の人たちに売るわけにはいかず被差別部落民であるユキエに売ったのではないだろうかと考えたが、いやいや被害妄想かもしれないと打ち消しもした。
(同)
読み進めてゆくとユキエが被差別部落の人だという記述が出てくる。ここで「うぬぬ」と唸ってしまう読者は多いでしょうね。昨今は揚げ足取りが盛んなので〝あくまで文学の世界では〟と留保を付けなければならないが、文学の世界では沖縄・被差別・在日・LGBTといったマイノリティ作家、あるいはそれを主題にした作品は評価が甘くなる傾向がある。内情を赤裸々に書けば情報だけでも価値がある。
「とぼくれホタル」に即せば淡々と生きるユキエが部落問題とどう関わるのか、読んでいてわからない。もちろんそれは読み進める原動力にもなるわけだが、ユキエの生活描写から言って社会的差別問題には踏み込まないはずだ。ならばなぜ被差別を持ち出したのか。被差別というわたしたちの喉に突き刺さる社会的問題とユキエの生きざまが、どうもうまく並列してくれないのである。
「私な、大阪にはもう住んでないんや。今、東京に住んどるんや。再婚したんや。再再婚てゆうべきなんかなぁ。もうかれこれ三か月になるわ。相手の男性の名前は目黒仁志。仁志も再婚でな、私より十四歳も年上なんや。香織のことを話したらな、香織を引き取ったらどうや、香織を東京に連れてきて一緒に住もに、てゆうてくれとんのさ」
話しはじめると、重い荷物を背負っていた旅人が一個ずつ荷を降ろしていくかのように、美和子の表情は軽くなっていく。香織の方に身を乗り出して
「もちろん香織の気持ちが一番大事や。香織がこの家に残りたいか、東京に行きたいか、決めるのは香織自身や」
(同)
小説のメインプロットは、ユキエの一人娘・美和子の再々婚である。美和子は二番目の夫との間に香織をもうけたが離婚してしまい、香織をユキエに預けて大阪で一人住まいをして働いていた。仕事を安定させていずれ香織と同居するためだったが、そんな生活がもう十年も続いている。香織は十四歳の中学二年生になっていた。
美和子が帰省するのはいつもは盆と正月だが、イレギュラーに帰ってきて、再々婚した、ついては娘の香織を東京に引き取りたいと言う。親のユキエになんの相談もなくすでに再々婚していて、十年のブランクを経て香織を引き取りたいというのはそれなりに衝撃的である。しかしこれが大問題に発展することはない。それによって自然と一体になって生きるユキエの生活が壊れてしまうなら、ユキエは最初からもっと気の強い、自我意識の強い女性として描かれていたはずだ。実際、美和子の再々婚はあっさり受け入れられ、香織は母と新しい父と暮らすために東京に引っ越していった。
もちろん部落出身という理由で、美和子が小学生から中学生頃まで学校でイジメられていたというユキエの回想もある。ただそれは一昔前のことで、ユキエの住む田舎でも差別はじょじょに改善されつつある。孫の香織が学校でイジメられたことはない。当事者でない読者は部落や被差別が出るとどうしても身構えてしまうところがあるが、この小説にとって社会問題は小道具である。
ユキエは東京に行く香織に「ほいでも、ホタルには出会わんやろ。ホタルはおらんやろ」と言う。ユキエの住む田舎でも自然環境の破壊によってホタルはもういなくなっていたので、香織は「ホタルは、ここにもおらん」と即答する。このスリップされた祖母と孫の会話に小説のテーマがあるのは言うまでもない。
翌日早朝、ユキエは尼崎を発って中谷村に帰った。タケシに別れを告げることもしなかった。夜、我が家の前に立ち、空を見上げた。月は寸分の欠けもない満月だった。「わたいは、また逃げたんや。辛抱が足らんさかい。弱虫やさかい。また逃げてしもたんや」声に出さずに満月に語りかけた。姉から聞いたのであろう、タケシから中谷村のユキエのもとに封筒が届くようになった。何度封筒が届いても封を切らず、読むことはなかった。文字を知らない身では読めるわけはなかった。返事の手紙も書けるわけはなかった。封筒が届くたび、折りたたんで小物入れの引き出しに入れた。七通目の封筒を最後に、タケシから封筒が届くことはなかった。(中略)ユキエは周囲の大人たちに勧められるまま、中谷村で生まれ育った幼馴染みである誠二と結婚した。
(同)
「ああこの落とし方か」という感じである。小説後半になって、ユキエが子供の頃からで激しいイジメにあい、学校にろくに行かなかったので非識字者だということが明らかになる。尼崎で働いていた若い頃にタケシという男が好意を持ってくれたが、ユキエはタケシが大学生であることに引け目を感じた。タケシがなにげなく本を貸してくれたが、ユキエにとっては恐怖でしかなかった。ユキエはタケシの好意に応えることができなかった。黙って尼崎を去った後にタケシから手紙が来たが、読めないので封も切らなかった。しかし老年になるまで手紙は大事に取ってある。
封印されたまま読めない手紙が〝ホタル〟と同義であるのは言うまでもない。その淡い光は痛切だが遠い過去の思い出であり、未来へと続く希望でもある。小悦最後でユキエは季節外れのホタルを見る。「ホタルや。香織、ホタルやどよ。こんな遅がけに生まれてまあ。とぼくれホタルやのぉ」というユキエの言葉は、東京で新しい生活を始める香織への餞別である。辛い人生だったがユキエの今の生活には希望の光がある。
新人賞応募作品ということもあるのかもしれないが、約百枚の「とぼくれホタル」には小説の材料が詰まっている。いささか詰め込み過ぎという気がしないでもない。草花と同じようなユキエの生を描くなら、人間世界で起きる事件は少ない方がいい。その代わり小説はもっと短くなる。再々婚した娘の美和子の生を掘り進めるなら、当然ユキエは主人公でなくなる。人生に翻弄される美和子にとっての、静かな定点のサブ登場人物になるはずだ。また非識字者の苦しみと喜びを描きたいなら小説の文体そのものを考える必要がある。
非識字者というのは文学にとって魅力的な題材である。様々な小説展開が可能だ。非識字者は書き文字言語で世界を捉えていない。文字にとらわれない豊穣な世界を持っている。それを表現するのに「とぼくれホタル」の文体は懲りすぎている。メリハリが必要だ。ユキエの非言語的世界と外の言語世界との落差が文体として表現されていれば作品の魅力は増す。コンスタントに小説を書いてゆくためには題材を詰め込み文体に凝るのではなく、薄めることも大事だ。そうすれば作品を量産できる。
「ごめん、ちょっとだけいい?」
「ん? どうしたの」
「ユウが言ったみたいに、今、やりたいことをやろうと思って」
彼は何が起こるのかさっぱり見当もつかない様子だった。萌は軽く握っていたこぶしを膝の上にのせた。手とワンピースの生地が触れている部分が熱を帯びている。彼女は悠の目をしっかりと見つめた。
「・・・・・・告白の返事を聞かせて。高校のときの」
彼の黒い瞳は一瞬見開かれたが、思ったよりも冷静だった。
「私のこと、どう思ってた?」
「・・・・・・そうだよね。俺はちゃんと答えてなかった」
(中澤朱花「雨上がりの頃には」)
今月号には「学生創作セレクション」として中澤朱花さんの短編小説「雨上がりの頃には」が掲載されている。大学生になった女の子が高校時代に好きだった男の子に偶然再会して、高校時代の告白の返事を聞くというプロットである。
きちんと書けているがこの小説一作で中澤さんの力量を計ることはできない。男女を問わず若い作家にとって恋愛は大問題である。小説でそれが主題になるのは当然だ。こういった小説を何編書けるのか、中編・長編として展開できるのかで作家の力量は決まってくる。
ただ現世を描く小説には艶が必要である。この艶はどうしても色恋と結びついており、若い作家の専売特許という感じだ。ほのぼのとして艶やかな小説には魅力がある。老若男女を問わず読者に受け入れられやすいのも確かである。
こういった小説の艶は作家が年を取ると失われがちになる。しかし小説にはどうしても読者の生理感覚に強く訴えかけるような艶が必要だ。老残の色恋はあまりゾッとしないが恋愛以外の艶もある。高齢作家は小説の艶、瑞々しさにも意識的でなければならないでしょうね。
池田浩
■ 金魚屋の本 ■



