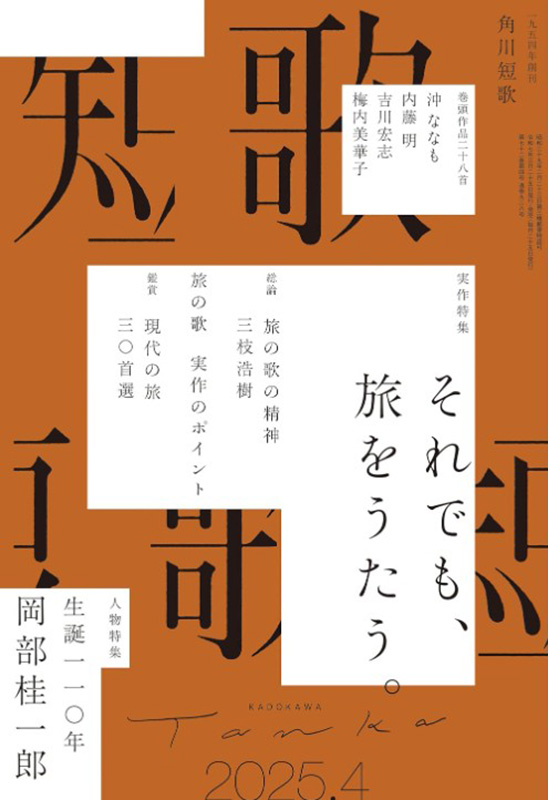
「人物特集 生誕一一〇年 岡部桂一郎」が組まれています。こういう特集はとてもいいですね。作家は結局過去の優れた作品を創作の糧にしてゆくしかありません。若い頃は右見て左見て上見て下見て自分の立ち位置のようなものを決めてゆくわけですが年を取るとどんどん左右と下が欠落してゆく。左右は同時代作品で下は自分より明らかに劣る作品です。一番危険なのは同時代作品と横並びになってしまうこと。そんな気配を感じたら自分だけ抜け駆けした方がいい。それが根っからの自己中である創作者の正しい姿勢です。
もう二十年くらい前ですが『ヴェロニカ・マーズ』というアメリカドラマがありました。保安官の父親を持つ女子高生のベロニカが素人探偵になって事件を解決してゆくドラマでした。ある回でベロニカは事件解決のために学校の文芸部に潜入しなきゃならなくなります。どうやって潜り込もうかとしばらく考えたあと「思春期のテーマって自殺願望・承認欲求・親との葛藤・恋愛とセックスよね」とつぶやきサラリと詩を書き上げます。それを文芸部の顧問の先生に見せると激賞されあっさり部に溶け込めたのでした。最果タヒさんのような才女であります。
同時代・同世代は似たような作風になりやすい。特にわたしはこう思うこう感じるの短歌や基本的に花鳥諷詠の写生から逃れられない俳句はそうです。常に同時代・同世代作品に気を配る必要はあります。その一方で独自の作風を模索し続けある時期を過ぎると誰がなんと言おうと自分独自のスタイルになっているのが理想です。そうなると見ぬ世の友の作品が参考になることが多くなります。
岡部桂一郎さんは大正四年(一九一五年)神戸市生まれ平成二十四年(二〇一二年)没。享年九十七歲。徴兵に引っかかる世代ですが結核で免れました。山崎方代さんの盟友です。僕は山崎さん絡みで岡部さんの歌を少し読みお名前を記憶していただけで良い読者ではありません。今回の特集は岡部さんの七冊の歌集(未刊歌集・遺稿集を含む)を七人の歌人の先生方が論じておられます。必要十分ですね。作家は一二作でも後世の人が読んでくれる作品を残せればもって瞑すべしです。
胎動にまなこ細むる數億のおみなの群やわが死にし後も
光なき明日というともおろおろと頼まんものを君ゆさぶるな
冷えびえと机の面のひろがれる一點より影負いてくる朱の茶碗
もろもろの蟲なくことも終りたる草むらの根にあかつき白む
かがやきて透くばかりなる石ころに陰毛くろきおみなたちたり
煉瓦色のジャケツきこみし青年が歩道に出て來にし無よ
岡部桂一郎歌集『綠の墓』より
最初の作品集には作家の生地が出やすいですが岡部さんの作風ってこんな感じだったっけと思ってしまいました。総論「人と時代 時代の体現者―岡部桂一郎の生きた時代」で大井学さんが「短歌研究」誌に発表された岡部さんの「素枯れたる萱原てらす稲妻やこの宵ふかく精漏れて出づ」を巡って村松英一と山下陸奥の間で論争があったと書いておられます。村松さんが「「精漏れて出づ」というような下等な語感では失敗と言はざるを得まい」と批判し山下さんが反論した。まあ当然の批判ですが反論できないことはないという歌ですね。
ただ第一歌集でも「かがやきて透くばかりなる石ころに陰毛くろきおみなたちたり」の歌があります。単にエロチックな歌だとは言えそうにありません。座りの悪い歌ですが「精漏れて出づ」と同様にとても奇妙な読後感というか手ざわりがある。「煉瓦色のジャケツきこみし青年が歩道に出て來にし無よ」にあるように岡部さんには無常というよりデスパレートと表現した方がいいような頽廃無常の心性があります。それが奇妙に生々しいイメージを生んでいる。確信的な座りの悪さで奇妙な歌でしょうね。
とめどなく他界の木の葉 現世の木の葉ちりくるこの夕闇に
ただひとりわれの近づく午後の沼 葦騒然と道ひらくかな
食べかけの善光寺小布施の栗の菓子 灯火に照れり人遠ざかる
あの坂をのぼって家に帰りたい 汽笛がぽーっと鳴っている坂
歌人の先生方が各句集から秀歌を選んでおられますが一字空きの歌は四首だけです。二つに割る(切る)必要があった歌ですが外界事物は現実そのものではなく内面化されています。岡部さんの歌は基本的に観念の歌であり写生吟行的な視線の移動がほとんどありません。
うつし身はあらわとなりてまかがやく夕焼空にあがる遮断機
天井にひとつの紐の下りつつ寝ねたるのちの暗黒に垂る
ただよえるもの笛ならし前世の夕ぐれどきを豆腐屋が来る
石手寺は初めてなれど前の世の見知らぬ父と二人来し寺
魂はしずかに死をばなぜている友の寐顔を見てわれは去る
まっすぐの道が枯野に通りたるその定型の歌はよからず
あの世ありこの世もあれど地続きで竹林の昼帽子落ちてる
笛吹の川の瀬の鳴る空の下徒手空拳の大きお握り
技術的には切れを指摘できるでしょうが岡部さんの歌は本質的に切れないのべつ調だと思います。光と闇あるいは現世とあの世が一体になった境地からヌルリと歌が生み出されている。特に「石手寺は初めてなれど前の世の見知らぬ父と二人来し寺」は奇妙ですね。普通なら読者をしんみりとさせる歌題を「前の世の見知らぬ父」と遠くに投げている。父母未生以前本来の面目が岡部さんの歌のテーマだったようです。
鶴山裕司
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


