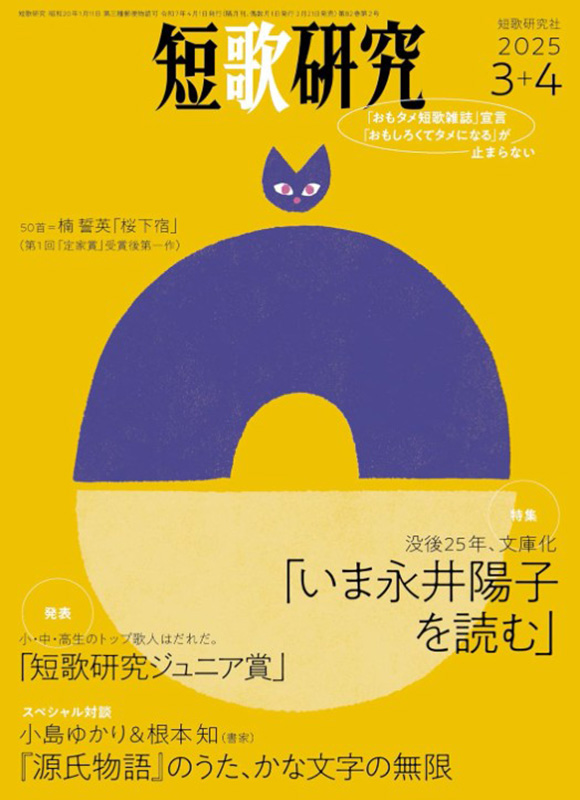
ひまはりのアンダルシアはとほけれどとおほけれどアンダルシアのひまはり
永井陽子『モーツアルトの電話帳』
歌人は元より一般読者にも絶大な人気を誇りながらなぜか新刊本で手に入る歌集・エッセイ集がすべて絶版になっている永井陽子さんの歌集『永井陽子歌集♯『モーツアルトの電話帳』その他』と『永井陽子歌集♭『てまり唄』その他』が石川美南さん編で短歌研究文庫として出版されました。これで比較的気軽に永井さんの歌業の全体像を知ることができるようになりました。唯一の散文遺稿集『モモタロウは泣かない』も是非文庫化していただければと思います。今号は文庫版『永井陽子歌集』出版を記念した特集が組まれています。
永井陽子さんは昭和二十六年(一九五一年)愛知県瀬戸市城屋敷町生まれで平成十三年(二〇〇一年)死去。享年四十八歲。生前刊行した歌集は七冊で没後遺歌集『小さなヴァイオリンが欲しくて』が刊行されています。第一歌集『葦牙』上梓は昭和四十八年(一九七三年)で第七歌集『てまり唄』は平成七年(九五年)刊ですから三年おきくらいに歌集を出しておられます。精力的に仕事をした歌人ですね。
永井短歌については様々な切り口で語ることができると思います。ただ絶対に動かない点を確認しておけば永井さんは「ひまはりのアンダルシアはとほけれどとおほけれどアンダルシアのひまはり」一首で短歌史に残る歌人です。もっと言えば「ひまはりの」は戦後二十世紀短歌が生んだ最高傑作の一つです。永井文学を代表する一首だというだけでなく現代短歌を代表する歌だと言っていい。
誰が読んでもどう読んでも同じですが「ひまはりの」は意味伝達内容としては恐ろしく単純です。ヒマワリが咲き誇るスペインアンダルシアの地は遠く感じられるという意味しか伝達していない。にも関わらずほとんどの人が読んだ瞬間に名歌だと気づく。アンダルシア地方はヒマワリ畑で有名ですがそれはどうでもいい。作家が本気でアンダルシアのヒマワリに憧れていたとも思えない。しかしこの歌は得られないものの希求だということは瞬時に読者に伝わる。
ある意味痴呆的な歌だとも言えるわけですが俳句で類似した作品があります。加藤郁乎「昼顔の見えるひるすぎぽるとがる」です。この句の意味伝達内容も呆れるほど単純。しかし一瞬で名句だとわかる。
永井「ひまはりの」はリフレーンを使い郁乎「昼顔の」は「ひ」「ほ(ぽ)」とハ行の音を多用しています。どちらも口に心地よい作品ですが決定的違いもあります。「昼顔の」は読者の心の中に視覚的〝像〟を呼び起こします。ポルトガルと呼ばれる土地に昼顔の花が一輪咲いている光景が目に浮かぶ。こういった視覚的〝像〟を結ぶのは郁乎句だけではありません。ほとんどの名句がそうです。
芭蕉「古池や蛙飛び込む水の音」や蕪村「菜の花や月は東に日は西に」という句も読者の心の中で簡単に像を結びます。子規「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」もそう。優れた俳句は物質的像を結ぶことが多い。それには理由があります。
俳句は「わたしはこう思うこう感じる」を表現する自我意識文学ではありません。窮極は日本文化の根底にある調和的かつ循環的世界観を表現するための非―自我意識文学です。それは無宗教だと言われる日本人が持っている宗教と呼べるほど強い世界観です。ただこの調和的かつ循環的世界観は意識的努力では表現できません。俳句が非―自我意識文学だということはそういうことです。俳句の名句は〝生まれる〟ことがあるのであって意識的に〝生み出せる〟ものではない。
俳句はアプリオリに存在している日本の調和的かつ循環的世界観の写生像です。意識的に写そうとしても上手くいかない。しかし作家意識が無意識領域に入り込みふと俳句と呼ばれる無意識的世界観に重なってしまうことがある。それは必ず調和的かつ循環的世界観の言語像になる。そうなると俳句はもう優れた風景画のように一字一句動かなくなる。
例えば志賀芥子「獺祭忌明治は遠くなりにけり」と中村草田男「降る雪や明治は遠くなりにけり」を比べてみれば一目瞭然です。芥子「獺祭忌」の方が先に詠まれたわけですが草田男が上の句を「降る雪や」に変えた途端にこの句は的を射抜いた。表現の審級がガラリと変わった。剽窃云々の批判は別としてこの二句は俳句の恐ろしさを表しています。
なぜ郁乎句を持ち出したかと言うと俳句が〝像〟であるのに対し短歌が〝調=ちょう・しらべ〟であることを「ひまはり」の歌が端的に表しているからです。「ひまはり」の歌は五/七/五/五/十の破調ですがそれを気にする者はいない。短歌でしか表現できない調が読者に強烈に訴えかける。
文学批評らしくないことを書くと「ひまはり」の歌は読者の心の琴線を揺らします。読者の心が揺れて「ひまはり」の歌に共振するのです。心などというあやふやなものを文学批評で持ち出すのは御法度ですがそうとしか言いようがない。
名句が明瞭な像となるのに対し名歌の本質は人の心を揺らす調=ちょう・しらべです。紀貫之『古今集』仮名序に「ちからをもいれずして、あめつちをうごかし、めに見えぬおに神をもあはれとおもはせ、をとこをむなのなかをもやはらげ、たけきもののふの心をもなぐさむるは、うたなり」とある通りです。「ひまはり」の歌は最も単純な形で短歌の原理的な力を表現した。短歌の本質が〝歌(調)〟であることを示した。この短歌のアイデンティティは何があっても変わらない。黙読書き文字の前衛短歌時代を経た二十世紀短歌でなければこれほど単純かつ明瞭に短歌の原像を表現できなかったでしょうね。
ゆうぐれに櫛をひろへりゆうぐれの櫛はわたしにひろはれしのみ
『なよたけ拾遺』
あはれしづかな東洋の春ガリレオの望遠鏡にはなびらながれ
『ふしぎな楽器』
秋の陽をかばんに詰めて帰り来るをとこひとりと暮らすもよけれ
『モーツアルトの電話帳』
生きることがさびしい時に聞こえくるこの世のいづこ水の漏る音
『てまり唄』
この世からさまよひ出でていかぬやうラジオをつけてねむる夜がある
『小さなヴァイオリンが欲しくて』
文学の世界は残酷です。勝ち負けはないとは言え頭抜けた作品を書いてしまった者が人々の記憶に残る。永井さんの歌業では「ひまはり」の歌が突出しています。この歌の高みから彼女が残した秀歌が様々に読み解かれてゆく。誰も口語であるか文語であるかなど気にしない。傑作は結局は作品そのものに帰ってくる言語道断な表現だからです。
鶴山裕司
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


