『牧羊神』第7号は昭和30年(1955年)1月25日発行である。29年(54年)7月31日発行の5号から隔月刊を宣言しているので、約2ヶ月遅れの刊行である。この号も寺山の文章で始まっているが、『牧羊神宣言』はない。『梟について-三十代との区別-』という四百字詰め原稿用紙8枚ほどの評論が掲載されている。『牧羊神』は10代作家による俳句革新を掲げて出発したが、いつの時代でも、どんな場合でも永久革命など起こるはずがない。編集・発行元を東京に移した5号から、寺山は10代作家独自の表現内実を考え続けていた。『梟について-三十代との区別-』は、寺山による最初の状況論的世代論である。
戦争自体がおそろしくはあるが美しい思い出にすぎぬ僕らの、そして敗戦直後がジャングルのように荒れつつもうれしかった僕らの「生きよう」とする意識だけが第一で他の場での傷ついた旧兵士、三十代のオジサンたちとは違う世代がこれからの時代を背負おうとしているのだ。「ロマン戦争」がはじまるかも知れぬ。けれども僕らは世間知らずなのではなく、夕刊的、ダイジェスト的な部分を排してもっと根本的に生きようとしているのである。(中略)
イッヒローマン(一人称私小説のこと)――それも然り。創作された世界は空間的であると同時に一切の社会を超え、自己の生活さえも超え、その上で尚も生活くさいある一面を必要とするだろう。しかし「揺れる戦後」二千句(角川書店の『俳句』『揺れる戦後』特集に掲載された二千句の作品のこと)からは何も出ない。そして三十代以降からは「傷」の見せあいと同世代の握手以外の何の新鮮さも出ないであろう。まさに暗礁の世代。そしてその彼らが新人のような顔をして松川事件などに俳句性を求めている間、俳句は静止のままにちがいない。
十代を代表して一寸口をひんまげて言おう。「もう止してくれ、そんなヒステリックな時間への抵抗や、生活描写による世紀錯誤の私小説俳句などは芸術ではないのだ。そして結社なども早々にさようなら、さようならだ。」
(『梟について-三十代との区別-』 寺山修司 『牧羊神』 NO.7。資料的意義があると思うので、全篇を本稿末尾に活字起こしして掲載してある)
 『梟について-三十代との区別-』は、当時俳壇の注目を集めていた『社会性俳句』への批判として書かれている。生き残った従軍経験者によって形成されつつあった戦後の詩壇・文壇では、明治維新以降の西洋文化移入の歪み(いわゆる『近代の超克』)や、壊滅的な戦争をもたらした戦前の政治・社会体制の検証と批判が急務だった。また当時は社会主義思想によって資本主義体制の矛盾を解消できると考える知識人が多かった。それらが入り混じった形で社会批判意識をストレートに作品で表現する『社会性俳句』が生まれたのである。自由詩の世界では『戦後詩』、小説文壇では初期の『戦後文学』が同様の文学潮流(エコール)である。
『梟について-三十代との区別-』は、当時俳壇の注目を集めていた『社会性俳句』への批判として書かれている。生き残った従軍経験者によって形成されつつあった戦後の詩壇・文壇では、明治維新以降の西洋文化移入の歪み(いわゆる『近代の超克』)や、壊滅的な戦争をもたらした戦前の政治・社会体制の検証と批判が急務だった。また当時は社会主義思想によって資本主義体制の矛盾を解消できると考える知識人が多かった。それらが入り混じった形で社会批判意識をストレートに作品で表現する『社会性俳句』が生まれたのである。自由詩の世界では『戦後詩』、小説文壇では初期の『戦後文学』が同様の文学潮流(エコール)である。
寺山は自分たち10代の世代は社会批判に積極的に背を向けるのだと言っている。『梟について』で寺山が使っている『時間』というタームは同時代の社会状況を指す。『時間』(同時代的社会状況)に対立するのは『空間』というタームである。単純な物理的空間という意味ではない。それは芸術が作り出す理想『空間』のことである。この芸術的理想空間には現実とは異なる時間が流れている。寺山の論理は『牧羊神』第6号掲載の『光への意志』とほとんど変わらないが、一つの確信へと近づきつつある。
『戦争自体がおそろしくはあるが美しい思い出にすぎぬ僕らの、そして敗戦直後がジャングルのように荒れつつもうれしかった僕らの「生きよう」とする意識だけが第一で他の場での傷ついた旧兵士、三十代のオジサンたちとは違う世代がこれからの時代を背負おうとしているのだ』という寺山の言葉は、なぜ彼が時代のスターになっていったのか、その理由を雄弁に語っている。寺山の言葉は戦争美化を叩き込まれ、その悲惨を知らぬまま、英霊となる夢をぷつりと絶ちきられた世代を代表している。また戦禍で焦土になった街に立ったときの、すべて失われたが、すべてがここから新たに始まるのだという、若い世代の高揚感を素直に表現している。
寺山は芸術的理想空間について、『創作された世界は空間的であると同時に一切の社会を超え、自己の生活さえも超え、その上で尚も生活くさいある一面を必要とする』と説明している。『田園に死す』などの映像作品を想起してもらえれば、寺山が芸術で何を表現しようとしていたのかがわかるだろう。寺山の芸術的理想空間は『一切の社会を超え』るという意味で超現実(シュルレアル)であり、『その上で尚も生活くさいある一面を必要とする』点で極めて土俗的である。寺山作品はこの理想的超現実とそれを生み出す母体である土俗の間を往還している。しかし彼は理想的超現実にも土俗にも表現の核を置かなかった。寺山が映像(演劇・映画)では作品を完成できたのに対し、完結した形ではほとんど詩集や句集をまとめられなかった理由がここにある。
よく知られているように寺山は自己作品引用癖の激しい人だった。若い頃に作った俳句や短歌を何度も何度も映像作品などに登場させた。恐らく寺山は、言語創作作品を一冊の本にまとめることの意味を理解できなかったのだろうと思う。寺山にとって言語創作作品は超現実(シュルレアル)と土俗の間を往還する一瞬の光(イマージュ)であればそれでよく、言語的探究を積み重ねることで理想や土俗の本質に迫ろうとする姿勢はなかったのである。夢見る少年の幻想と言ってしまえばそれまでだが、寺山的幻想は、確かに高度経済成長以降の日本に根深く存在した時代の雰囲気(アトモスフィア)でもあった。
少年の時間 寺山修司
父と呼びたき番人が棲む林檎園
黒髪に乗る麦埃が婚約す
わが内に少年ねむる夏時間
わが歌は波を越し得ず岩つばめ
勝ちて獲し少年の桃腐りたる
蹴球を越え夏山を母と見る
目つむりて雪崩聞きおり告白以降
二重瞼の仔豚呼ぶわが誕生日
時失くせし少年われに草雲雀
野茨つむわれが詐せし少年に
車輪の下はすぐに郷里や溝清水
草餅や故郷出し友の噂もなし
方言かなし菫に語り及ぶとき
夏井戸や故郷の少女は海知らず
亡びつつ巨犬飼う邸秋櫻
(『牧羊神』 NO. 7 )
『牧羊神』第7号で寺山は、『少年の時間』と題した15句を発表している。寺山作品は少年(あるいは青年)俳句だと言えるが、彼は『青年文学』のプロだ。『目つむりて雪崩聞きおり告白以降』、『方言かなし菫に語り及ぶとき』などで表現されているように、彼は少年の心理・様態を完全に相対化して捉えている。また戦後社会は様々な困難を抱えていたが、幾度も戦争を繰り返した戦前までに比べれば、平和な『わが内に少年ねむる夏時間』だった。しかし生きている限り、人は眠りからいつかは覚めなければならない。
芸術は決して時代状況と無縁ではない。それどころか鋭敏にその影響を受けている。寺山的『青年文学』は俳句以外の芸術ジャンルでも確認できる。戦後に登場した自由詩の作品は『現代詩』と呼ばれることが多いが、それは高度経済成長の時代状況を反映している。戦後の一時期、詩人たちは言葉には無限の表現可能性があると深く信じたのである。寺山のように理想と土俗の間を往還する詩人は少なかったが、詩人たちの間に戦後的荒廃を越える理想はあるという、裏付けのない超現実(シュルレアル)への憧憬が蔓延していた。『現代詩』がシュルレアリスティックであることには理由がある。
ただ青年文学が成立するためには、大人の文学が存在しなければならない。大人の文学とはこの時代は戦後文学のことである。そして戦後文学は単純化して言えば、戦争により生死の境を体験した者たちによる思想文学である。なんらかの形で戦争体験を表現の基盤としている以上、良くも悪くも戦後文学は強靱である。戦後の子どもはそのような特権体験に依拠する大人に対して、無防備で脆弱かもしれないが、美しい夢を見る今ひとつの特権を打ち立てた。20世紀末に起きたほとんど戦後文学の全面瓦解というべき現象は、戦後文学者たちが戦争体験に基づく思想を、体験を越えた高次思想にまで昇華できなかったことから生じている。しかしそれにより、戦後の青年たちの夢も無残に潰えたのである。
気泡の文学 大岡頌司
水に書く気泡の文字母亡き日
掌の木の実吾だけが知りあたたかし
オゾンばかり吸って小鳥の声潔し
母不遇不遇の明日へ茄子漬ける
ゴム草履落とす木の実の落ちし地へ
(『牧羊神』 NO. 7 )
大岡頌司は『牧羊神』第7号で『気泡の文学』の表題で5句発表している。うち『水に書く気泡の文字母亡き日』(定稿では「母なくなる」)と『母不遇不遇の明日へ茄子漬ける』(定稿では「菜を漬ける」)は処女句集『遠船脚』(昭和32年[1957年]刊行)に収録されている。残り3句は全句集未収録句である。大岡文学の重要主題である『母』が登場していることが注目される。大岡の実母は産後の肥立ちが悪く、彼が1歳の時に亡くなった。大岡は作品で母を描き続けたが、それは次第に実在の母の像(イマージュ)を越えてゆく。万物の創造の源であり、世界創造の原理としての母性へと象徴主義的な変化を遂げてゆくのである。
刈田の電柱 安井秋思郎
こきざみに牛曳き帰る原爆忌
原爆忌土塀厚きに夕陽沁み
春の雪ゆたかに兵舎の屋根低し
爆音や刈田の電柱泥はげし
おろかにも未熟な柿を芯より喰み
(『牧羊神』 NO. 7 )
安井浩司は『安井秋思郎』のペンネームで5句を発表している。第6号の大岡の作品『原爆忌』9句に影響されたかのように、作品に『原爆忌』を詠み込んでいる。当時の彼の心境は『おろかにも未熟な柿を芯より喰み』に表現されているだろう。ペンネームを使い、他者の作品から簡単に影響を受けていることからいっても安井はまだ試行錯誤の途上にある。安井は比較的裕福な家庭に育っており、母子家庭だった寺山や大岡のように、少年なりにどうしても表現したい表現の核を持っていなかった。すべての可能性を試すのが初期の安井の姿勢である。この試行錯誤はおよそ10年後に処女句集『青年経』(昭和38年[1963年])を刊行する直前まで続いている。
なお安井氏からお借りした『牧羊神』は今回取り上げた第7号までである(7号以降は所有しておられないとのことだった)。寺山は『第十号でもって第一次を終刊として僕ら(寺山や京武のこと)は俳句とはなれた』(『空には本』昭和33年[1958年])と書いているので、寺山らが積極的に関係した『牧羊神』は10号で終刊のようである(その後、第二次、三次『牧羊神』が創刊されたようだ)。つまり寺山主宰の『牧羊神』の実質的活動期間はわずか2年足らずだったことになる。しかしそこに濃密な時間が流れていたことは、本稿をお読みいただければある程度わかっていただけたのではないかと思う。『牧羊神』以降、寺山はその短い人生を予感させるように、慌ただしく俳句や短歌の世界から遠ざかっていった。
なお『牧羊神』第7号後記の『Post』で寺山は、『次号の編集は京武久美、近藤昭一、田辺未知男らの希望により青森に一任することにした。その次は奈良の女子陣へまわりそうである。この号の遅れた理由は全国学生俳句祭の整理と「俳句研究」への文章、「短歌研究」への作品創作にかけて内職の家庭教師やらが重なったことが主因である』と書いている。寺山は前年の昭和29年(1954年)に第2回『短歌研究新人賞』を受賞しているはずだが、『牧羊神』にその報告はない。ただ寺山が5号から始めた編集・発行作業を他の同人に任せることにしたのは、『牧羊神』以外の媒体への執筆活動が忙しくなったからでは必ずしもない。29年冬に、寺山は結局はそれによって命を落とすことになるネフローゼを発症したのである。
安井氏所蔵の『牧羊神』第7号巻末には第8号の原稿募集要項が掲載されているが、『送り先 青森市筒井新奥野近藤昭一』が青色の万年筆の棒線で消され、『立川市錦町1の46川野病院11号室 寺山修司』と書かれている。恐らく安井氏の書き込みだろう。寺山は昭和33年(1958年)まで入院生活を送り、退院すると演劇を中心としたジャーナリズムの世界で仕事をするようになった。安井氏が処女句集『青年経』を上梓するのはそれから5年後の昭和38年(63年)、俳句作家として明確に寺山に対峙し、自信をもって訣別し得るのはそれよりもまだ先のことになる。
鶴山裕司
■ 『牧羊神 NO.7 十代の俳句研究誌』書誌データ ■
・判型 B5版変形 縦24センチ×横17.5センチ(実寸)
・ページ数 20ページ
・刷色 本文スミ一色(黒色)、表紙は赤、黄、黒色の3色刷り
・イラスト(作者不明)
・奥付(原文のまま)
昭和30年1月25日発行
発行兼編集人
埼玉県川口市幸町1-39(坂本方)
寺山修司
印刷人
群馬県富岡市富岡1706
小林万吉
発行所
埼玉県川口市幸町1-39(坂本方)
牧羊神俳句会
牧羊神 VOL.7
・MEMBER (二九・七・一〇現在) 総数38人(これも原文のまま)
京武久美(青森)、福島ゆたか(東京)、北村満義(東京)、近藤昭一(青森)、松井牧歌(川崎)、松岡耕作(福岡)、山形健次郎(北海道)、秋元潔(横須賀)、野呂田稔(秋田)、南ひろし(東京)、丸谷タキ子(奈良)、石野佳世子(奈良)、金子黎子(川崎)、雫石尚子(神奈川)、金子瑛(東京)、後藤好子(北海道)、吉野和子(神奈川)、岩井久代(奈良)、宮村宏子(奈良)、上木かずよ(北海道)、伊東レイ子(青森)、乙津敏を(東京)、黒米幸三(東京)、戸谷政彦(東京)、林俊博(北海道)、中西久男(青森)、田辺未知男 (青森)、橘川まもる(青森)、森谷義明(東京)、大岡頌司(広島)、大沢清次(群馬)、安井浩司(東京)、木場田秀俊(長崎)、上村忠郎(八戸)、川島一夫(福島)、広瀬隆平(船橋)、川北憲央(東京)、寺山修司(埼玉)
■ 『牧羊神 NO.7 』掲載 寺山修司の『梟について-三十代との区別-』 ■
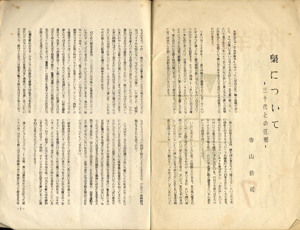
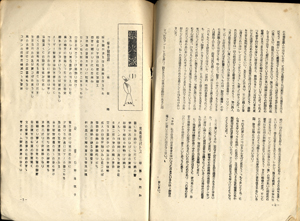
梟について-三十代との区別- 寺山修司
太宰治の『二十世紀旗手』の中に「たんぽぽの花一輪の信頼が欲しくて、チサの葉いちまいのなぐさめが欲しくて一生を棒に振った。」という章がある。もしそう云う言い方が許して貰えるなら僕らの信頼の対象はたゞ空間という場に於ての十代という世代による結集のことだけであろう。
つまりはこうである。・・・・・・僕らは疲れた歯車のようにあくせくとしてギコギコと廻ってゆく現代時間の音にはどうしてもやり切れずに一つのロマネスクを設定する。そして時間――つまりうんと俗な沢庵が一本七円であったり、母親の足袋の穴のインチが広がったりしたなどということとは常に距離をおいたところに僕らの文学境を置くのである。僕らはだから空間を創作の場とする。そして実作することによって常に時間から空間への移転を目ざしているのである。
僕らの目指す生活は、例えば少年たちが「開けゴマ」といったときに開扉を許可するように一つの神話によって約束されてゆくのである。僕らの少女はだからベアトリーチェと呼ばれるし、「あの日」というのはいつも集会する土曜日と決められている。けれども僕らはむろんなべやきを好み沢庵を食べ、そして不条理と猟との関係などにも小首をかしげる時間を持っているのだ。
いかに生きるか――それが第一の問題なのである。生と死と愛をのぞいて何の主題が現代に存在するものか。愛しうるか、という問に反問しつねに悩み、そして愛の永続性を考え、決して「生まれてすみません」などと云わないように僕らの出発は組み立てられており生活は時間と空間のまん中にいつも行儀わるく「おあづけ」しているといってもよかろう。十代・・・・・・僕がこの文章を書くことさえ考えようによってはコッケイかも知れない。なぜならこれは僕の、いや僕らの、「時間」に対する飛入りであり本懐を超えた道化になることだからだ。しかし道化になれるのは優越を許されることだし、僕が云わねば十代はいつのまにかサーカス小屋の入口の猿にされてしまうだろうからである。ときに時間に没入して自己をたしかめねばならないほど現代はうらぶれているとは何とかなしいことか。これはまさしく果し状、しかも三十代の俳人及び歌壇のお歴々に物申すものである。
はじめに戦後俳句(こんな云い方は僕らが無戦派だからだ)がいかにナンセンスでるか――ということからはじまる。角川の「俳句(十一月号)」でやった「揺れる戦後」二十句はモチーフとしての戦後のカオス状態が如何にもよく表現されている。そして「詩学」の大島博光やその他の「ビキニ」「松川事件」にあらわれたように三十代俳人たちはよろしく社会性をうたうことを強調している。以前北園克衛氏が「作家」の詩壇時評で「もし詩人が詩でビキニに抗議しなければならぬとすれば下駄屋は下駄で、畳屋は畳でそれに抗議せねばならぬだろう」といためつけ「薔薇科」の後記でも青木ひろたか氏あたりが同じことを述べていた。
北園克衛氏のネオ・クラシズム的傾向を僕は必ずしもよろこぶばかりではないがしかしその言葉は全く真理の「ある面」をついていると思うし、僕はその部分には敬意の帽子を脱がねばならぬようだ。なぜヒステリックに時間を阻止しようとするのか。だから一体時間は静止するとでも思うのか。
人々は百も二百も吉田政権その他が汚職やらその他色んなことをしでかしているのは承知していたし再軍備の無意味さも知ってるのだ。だからどうなってこれが選挙にあらわれるかというとやっぱり地方ではそんなことを知ってても日頃お世話になる保守党に一票を投じるし、吉田政権は七年も椅子にすわっていることができたのではないか。もし人たちがそれらに反逆するときは創作する精神ではなく生活する人間の場で抵抗し、ほんとの人間の声で、たとえば選挙や、選挙運動などで戦ってもらいたいものだし、作品の中でビラの文句を見せられるのはどうしてもやりきれない。やりきれない。
戦争自体がおそろしくはあるが美しい思い出にすぎぬ僕らの、そして敗戦直後がジャングルのように荒れつつもうれしかった僕らの「生きよう」とする意識だけが第一で他の場での傷ついた旧兵士、三十代のオジサンたちとは違う世代がこれからの時代を背負おうとしているのだ。「ロマン戦争」がはじまるかも知れぬ。けれども僕らは世間知らずなのではなく、夕刊的、ダイジェスト的な部分を排してもっと根本的に生きようとしているのである。
僕らのヒューマニズム。――左様、僕らは徴兵令がしかれたって征くもんか。けれども僕らはそれを時間の中で理由を作って拒否するほどの類常識人ではないので、それらを規定すれば規定した国家をけるだろう。時間がいくら厳重なアミをはろうと僕らは他の次元で生きるに違いない。首相がだれでもかまわない。僕ら次の世代は日本国に住んでるのではなくて現代に住んでいるのであり時間の中での針同志喧嘩にまきこまれるほどほどの暇はもちあわせていないのだ。それよりも根本的に愛し得ない理由を考え、精神を失くしてみせたりまた死からの逃避のためのロマネスクを現実に近づけたりするだろう。首相も大臣も裁判官もどうでもいい。生きることであり、そして隣人を愛し得るためにはロレンスの「アポカリプス」も振ってみることだ。われわれ芸術家は一切の時間的なものを軽蔑すべきであろう。特に詩人、つまり散文家でない僕らにおいては力道山や吉田首相や、マリリン・モンローが社会におよぼす影響などというものは「創造の魔神」の中で当然蹴飛ばさなければならぬ。好んで「群衆」の中に入りこもうとする人は類俗人であり、彼等は詩を創って人に何かを与え得る価値などどこにももちうる訳はないではないか。社会的、時間的事象をうたっても、それが「群衆」でなくなるとき、それらが自己の中で生活するときにいたってすべての詩人が誕生するときだ。沢庵が詩になることはむろん可能だ。けれどもそのときに沢庵はどう生きるかというテーマのたどりつきの点においてのモチーフとしてあるいはロマネスクの材料としてであり「私」の生活描写のための実感としてではもはやおしまいだ。
イッヒローマン――それも然り。創作された世界は空間的であると同時に一切の社会を超え、自己の生活さえも超え、その上で尚も生活くさいある一面を必要とするだろう。しかし「揺れる戦後」二千句からは何も出ない。そして三十代以降からは「傷」の見せあいと同世代の握手以外の何の新鮮さも出ないであろう。まさに暗礁の世代。そしてその彼らが新人のような顔をして松川事件などに俳句性を求めている間、俳句は静止のままにちがいない。
十代を代表して一寸口をひんまげて言おう。「もう止してくれ、そんなヒステリックな時間への抵抗や、生活描写による世紀錯誤の私小説俳句などは芸術ではないのだ。そして結社なども早々にさようなら、さようならだ。」
とこう書いてくると、変なよみ方をする同志諸君があるのではないか。――と心配になってきた。戦争やその他時間の内部でのナンセンスに僕は人間として絶対否定の立場をとっていることは同世代の諸君も知る通りであるし、実作がそれを証明してきた。
たゞ病原菌は創作作品の中での抵抗ではんくて、絶対者として、作家の倫理の中での抵抗であるといいたかったのであり、この章のむすびにジイドの日記の一章をひいておこうと思う。
『今日、私の作品に社会事象がはいりこんできているのは〝創造の魔人〟が退いたからにほかならない。』
おしまい。
■ 『牧羊神 NO.7 』掲載 寺山修司作品 ■

■ 『牧羊神 NO.7 』掲載 安井浩司と大岡頌司作品 (『創火派(Ⅱ)』 同人作品欄) ■
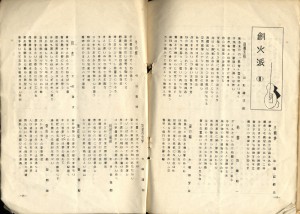
■ 『牧羊神 NO.7 』 後記 『Post』(寺山記) ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
