No.121『柳宗悦没後60年記念展 民藝の100年』
於・東京国立近代美術館
会期=2021/10/26~2022/02/13
入館料=1,800円[一般]
カタログ=2,600円

久しぶりに気楽に楽しめる美術展でありました。日本民藝館は東京駒場にあり、言うまでもなく柳宗悦創設である。読みやすいのでどうしても「そーえつ」と言ってしまうが正しくは「むねよし」です。開設は昭和十一年(一九三六年)。財団法人だが戦前に開設された数少ない私設美術館の一つである。岡山倉敷の欧米美術コレクションで有名な大原美術館(昭和五年[一九三〇年]開館)設立の実業家・大原孫三郎の援助で開設した。本館・新館・西館(旧柳邸)があるが本館と新館が展示室になっている。本館は東京大空襲でも焼けなかったので建物自体が今や美術品のようなものである。
東京という地価のバカ高い土地柄を考えると日本民藝館の敷地はえっらい広い。しかしまあ美術館としてはこぢんまりしている。規模では公設美術館にはとうていかなわない。民家に近い建築なので展示スペースは限られ展示方法もイマドキではない。そこが日本民藝館のいいところでわざわざ駒場まで行こうかという気になるのだが、主要なコレクションをまとめて見てみたいなと思ったりもする。それを実現したのが今回の展覧会である。柳らの最初のコレクションからアイヌ、沖縄まで民藝館所蔵の代表的コレクションが展示されていた。

ロダン夫人
オーギュスト・ロダン作 一八八二年 ブロンズ 高二三・三×幅一七・五×直径一八センチ 大原美術館蔵(白樺美術館より永久寄託)
よく知られているように柳は大学は帝大哲学科卒だが学習院高等学科の出である。学習院が天皇家の子弟育成のために設立された学校であるのは言うまでもない。天皇が神格化されていた戦前には貴族や実業家など一握りの良家の子弟しか入学できなかった。宗悦は海軍少将で貴族院議員も務めた柳楢悦の息子(三男)である。当時のボンボンの一人だった。
柳は学習院時代に志賀直哉、武者小路実篤、里実弴、正親町公和、細川護立(民主党政権で総理大臣になった細川護熙さんのお祖父さん)らと同人誌「白樺」を創刊した。日本では珍しい倫理を重んじ理想を追求する高踏派文学者集団だった。美術にも関心が深く「白樺」同人はロダンに強い関心を示した。その中心が柳でロダンと文通し「白樺」でロダン特集を組んだ。そのお礼になんとロダン本人から三体のブロンズ彫刻が贈られたのだった。「ロダン夫人」はその一点である。
当時としては当然だが初期白樺同人の関心は欧米に向けられていた。欧米文学・美術が圧倒的先進性を持つものとして捉えられていたのである。柳の初期作に大部の『ヰリアム・ブレーク』(ウィリアム・ブレイク)がある。ブレイクに関心を持ったところが柳の勘の良さで、ブレイクは敬虔なキリスト教徒だが度が過ぎてそれを突き抜け、むしろ異端的な世界本質を直観的に幻視した詩人だった。東洋思想に近い汎神論的世界観を持った詩人だったのである。独自の画風の宗教画家でもあった。柳の『ヰリアム・ブレーク』は最初期のブレイク研究書だが、その東洋思想にも通じる汎神論性もあってブレイクは今でも日本で人気の高い詩人である。
ウルトラリッチとまではいかないが、ボンボン集団だった白樺派同人たちは寄贈されたロダン彫刻を中心にした美術館開設を夢見ていた。白樺美術館である。そのために寄付金を募ってセザンヌの油彩画も購入した。白樺美術館は残念ながら実現しなかったが柳らは早い時期から美術館建設を目論んでいた。

染付秋草文面取壺(瓢形瓶部分)
朝鮮半島 朝鮮時代 十八世紀 高一二・八×直径一一・八センチ 日本民藝館蔵
「染付秋草文面取壺」は民藝館所蔵で最も有名な作品の一つである。大正三年(一九一四年)に浅川伯教(つい「はっきょう」と呼んでしまうが「のりたか」が正しい)がロダンの彫刻を見せてもらうために千葉我孫子の柳邸を訪問した際にお土産として贈った作品である。完器なら瓢箪形の徳利だが、上部が破損していたのでそれをきれいに取り除いてある(骨董用語で「すり切り」という)。なんの変哲もない壺(しかも残闕)に見えるだろうが秋草文の朝鮮陶器はもの凄く数が少ない。貴重な上に伯教-宗悦という伝来の箔がついたわけだから、市場に出れば最低でも三桁の後半まで行くでしょうな。
伯教は稀代の朝鮮陶磁の目利きとして知られる。現在大阪市立東洋陶磁美術館蔵で、旧安宅コレクションの染付辰砂蓮花文壺(朝鮮陶磁の最高峰の一つと言っていいでしょうね)などは伯教旧蔵品である。弟は巧で朝鮮で総督府林業試験技師を勤めながら朝鮮陶磁と民具を蒐集した。現地の朝鮮人に愛され尊敬された数少ない日本人でもあった。著作の代表作に『朝鮮の膳』がある。食事などに使うお膳を取り上げたマニアックな図入り本である。四十歳で夭折してしまったが葬儀で友人代表として挨拶したのが柳だった。柳は伯教を通して巧と知り合ったが巧の方が親しい友人になったようだ。
骨董の目利きにはよくあることだが伯教は目はいいが文章はイマイチだった。朝鮮陶磁関連の文章もそれなりに書いているが学問的裏付けという点でも美学面でも独自性を発揮できたとは言い難い。数ある朝鮮陶磁の中から優品を見つけ出した(選び出した)目利きとして知られているのである。これに対して弟の巧の文章は冴えていた。物から文化の本質へと進んでゆける精神の持ち主だった。宗悦が伯教より巧と親しくなったのは当然ですな。
ここでは柳にフォーカスするが、初期は欧米に視線が釘付けだったがそれは根深い欧米コンプレックスの裏返しでもあった(この日本人の欧米コンプレックスは戦後の一九八〇年代頃まで続いた)。ただ欧化主義が国是となるのと同時に国粋主義が勃興したように、柳も早い時期から東洋文化(美術)に目覚めていた。そのきっかけとなったのが伯教から贈られた染付秋草文面取壺だった。当時は朝鮮陶磁といえば高麗青磁で白磁や染付の朝鮮陶磁は比較的安価だった。柳は浅川兄弟と知り合ってから朝鮮に渡るようになり自身でも朝鮮陶磁の優品を集めた。大正十年(一九二一年)には李王朝旧王宮の景福宮内に朝鮮民族美術館を開館した。白樺美術館は開設できなかったが柳らが創設した最初の美術館である。
日本が朝鮮を併合したのは明治四十三年(一九一〇年)だが大正八年(一九一九年)に三・一独立運動が起こるなど、併合に対する現地の反発は強かった。総督府はそれを厳しく取り締まったが昭和に入って日本が本当に貧すれば鈍する状態になった時期に較べればまだ緩かった。柳は『朝鮮人を想ふ』などを発表して朝鮮文化を称揚し日本の同化政策を批判している。そういった発言がまだ許された時期でもあった。柳らの意図とは別に日本政府側から見れば朝鮮民族美術館開館は、一種の融和策として許可されたと言っていいだろう。柳らは政府内に様々なコネを持つ良家の子弟でもあった。

地蔵菩薩
木喰五行上人作 享和元年(一八〇一年) 木彫 高六九・六×幅二三・九×直径一九・四センチ 日本民藝館蔵
柳の偉業の一つに木喰仏の発見がある。柳が見出す前から木喰仏は存在していたので発見というのはコロンブスのアメリカ大陸発見と同様に今ではちょっとおかしいかもしれないが、とにかく木喰仏を世に広く紹介したのは柳である。木喰は江戸後期の遊行僧で修行のために彫って奉納した仏像が日本各地に残されている。
朝鮮陶磁器と木工品などの面白さを知ってから柳は視線を国内に向けるようになった。木喰仏だけでなく伊万里や唐津などのいわゆるお国焼や庶民が使った生活用具、それに加えて欧米の生活に根ざした宗教絵画や家具、陶磁器などを次々に紹介していった。柳は関東大震災を機に京都に転居したが、そこで知り合った陶芸家・河井寛次郎や濱田庄司らが柳に協力した。また学習院時代からイギリス人芸術家バーナード・リーチと親しかったが(後に陶芸家として知られるようになる)、欧米民衆アートはリーチの協力で集められていった。大正から昭和の初めにかけては柳らにとって〝新しい美の発見〟の時期だったと言ってよい。
柳らが〝新しい美の発見〟に夢中になれたのは、まあはっきり言えば彼らのいた上流社会と庶民生活に相当な差があったからである。戦後の昭和四十年代くらいまで東京などの大都市と地方ではかなりの文化的・経済的な差があった。大正、昭和の初めにかけてはなおさらだった。生きるのに手一杯の庶民は美術どころではなかったのである。
寺社仏閣で長い間守り継がれてきた仏教遺物などは別として、庶民が使う陶磁器や民具は実用を離れて初めてその美しさ、面白さが目に見えてくるものである。新しい便利な製品が出回るようになり、古い道具類が用済みになった時にふと「ああ面白い形をしてるな」「けっこう美しいものだったんだな」と気づくのだ。物を実用道具としてではなく色や形の面白さとして眺められる目の転換が必要である。柳らはそんな目を持っていた。
柳らは焼物、漆器、布、家具、道具類に至るまで次々に新しい美を〝発見〟していった。僕もその一人だがさしてお金はないが骨董・古美術が好きといった人々が比較的安価な値段で買えるような物を発見・紹介していったのだった。今現在骨董市場で取り扱われている品物のほとんどは柳らが真っ先に世の中に紹介したと言っても過言ではない。
なお民藝=民衆的工藝という言葉は大正十四年(一九二五年)に柳、河井寛次郎、濱田庄司が紀州旅行中に生まれた言葉である。翌十五年(二六年)には柳、寛次郎、庄司に富本憲吉を加えた四人連名で「日本民藝美術館設立趣意書」が配布された。長年の夢である日本民藝美術館の開設に動き出したのだった。また民衆的工藝という定義ができてから民藝の概念はまたたく間に広く一般にも滲透した。特に都市部の富裕層の間で民藝運動に賛同する人々が数多く現れて「民藝ブーム」が起こった。柳はその中心にいたわけで、大正から昭和初期にかけてが民藝運動の最初の全盛期だった。

「月刊民藝」第一巻第九号「たくみ特集」
昭和十四年(一九三九年)十二月発行 個人蔵
紆余曲折を経て昭和十一年(一九三六年)に東京駒場に日本民藝館が開設したわけだが、それに先駆けて六年(一九三一年)には雑誌「工藝」が創刊された。創刊号と第二号は青山二郎と石丸重治の編集である。青山二郎は小林秀雄や白洲正子の骨董のお師匠さんで古美術の目利きとして知られる。石丸重治は美術評論家で小林と同人誌「山繭」(中原中也が参加していたことで有名)も主宰していた。日本民藝館が開館した三年後の十四年(三九年)には日本民藝協会季刊誌「月刊民藝」が創刊された。柳の民藝運動は多くの人たちの賛同を得て協会まで作られるようになっていたのである。
図版は「月刊民藝」第一巻第九号「たくみ特集」に掲載されたいわゆる「民藝樹」である。民藝運動の三本柱を表した図としてよく知られている。真ん中の日本民藝館が本拠地の美術館である。右側の日本民藝協会は出版部である。「工藝」「民藝」の雑誌を刊行し関連書籍を刊行する。左側は「たくみ工藝店」で日本各地の民藝品や個人作家の作品を販売する。たくみ工藝店は民藝運動の熱心な協力者・吉田璋也が鳥取で開いていた店だが昭和八年(一九三二年)に東京西銀座に移転した。

ににぐりネクタイ(デザイン指導・吉田璋也)
向国安処女会(鳥取県)ほか制作 デザイン昭和六年(一九三一年) 絹製 縦一三二・八×横五・二×厚〇・三センチ 鳥取民藝美術館蔵
ににぐりネクタイは屑繭で紡いだ糸(ににぐり糸)を織ったネクタイで、吉田璋也がイギリスの毛糸ネクタイからヒントを得てデザインした製品である。たくみ工藝店で販売されて人気商品だったのだという。
昭和初期には民藝運動は古い民具などを蒐集展示するだけでなく、日本各地の民芸品に新たな息吹を吹き込んで特産品として販売する運動にまで発展していた。河井寛次郎や濱田庄司、富本憲吉らは今では陶芸作家として有名だがこの時期は各地で陶芸指導するなどして新たな民芸品の創作に尽力していた。この日本民藝館をいわば総本山として民藝品を月刊民藝などで紹介し、各地の特産民藝品を販売するシステムは基本的には戦後まで一定の効力を持って存続した。昭和五十年代くらいまでは日本各地の商店街に一軒ぐらい民藝品屋があった。
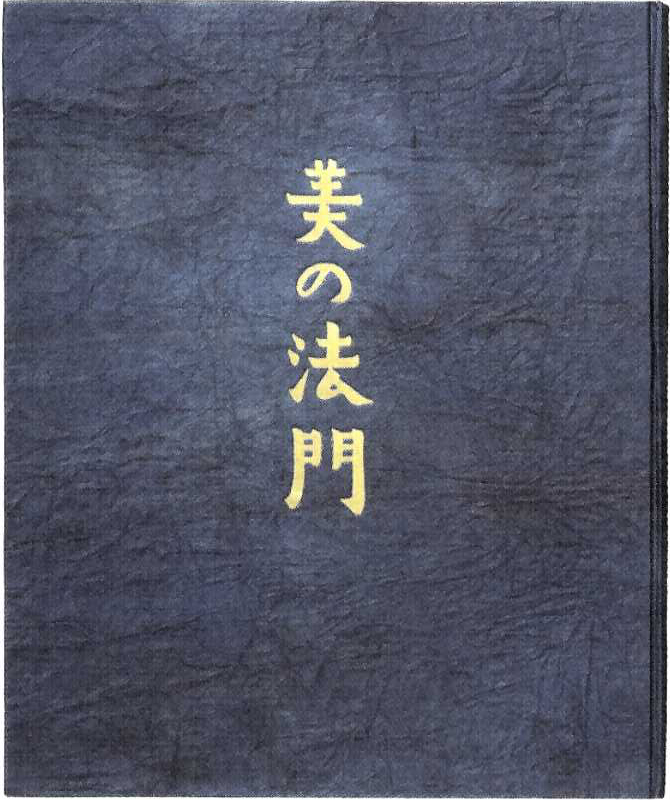
柳宗悦著『美の法門』(私家版)
昭和二十四年(一九四九年)刊 日本民藝館蔵
太平洋戦争中は挙国一致体制になり、文化人も様々な形で戦争協力を求められた。工芸の世界でも「大日本工藝会」が発足したが日本民藝協会は解散しないまま参加を認められた。工藝振興という形で祖国に貢献すればよかったのである。
もちろん柳は工藝家ではなく文筆家である。戦争協力しなかったとは言えないが、戦意高揚のための文章を盛んに書いたとまでは言えない。シュルレアリスムに傾倒していた瀧口修造は治安維持法違反容疑で特高に検挙されたが(まったくの誤解で瀧口はノンポリだった)、とっくに欧米美術から日本中心の東洋美術に興味を移していた民藝運動家はほとんど無傷で戦争時代を乗り切ったと言っていい。そんな柳が昭和二十四年(一九四九年)に発表したのが『美の法門』である。柳後期の代表作でもある。
柳は浄土三部経の中核経典『大無量寿経』を読んで「無有好醜の願」を「(仏の国では)美醜の区分がない(溶解する)」と解釈し、それが民藝運動の本質だと考えた。柳は宗教家(宗教哲学家)でもあった。「美の国を具現するためには、どうあっても民衆と美とを結び、生活と美とを近づけねばならないのです。その時民藝が有つ使命がいかに大きいかを了得されるでしょう」「かかる王土の具現には、衆生の済度が約束されていなければならない」といった言葉が柳の思想をよく表現している。
柳は民衆工芸品を「下手物の美」「雑器の美」などとも呼んだが、一貫してその中に無心の美を見ていた。無名の工芸家が無心で作る物は美しい。そういった無心は必死に生きる人々の日々の生活の倫理でもある。無心の営みは人間の良き意志であり、人間存在の目標や救済にもなり得ると説いた。柳の言葉は敗戦で傷つき目標を失いがちな人々の心に訴えかけるものを持っており、戦後に再び民藝ブームが巻き起こった。
ただ柳の民藝思想が結局は〝美〟という抽象的観念に留まり続けたのも確かである。柳生前から民藝批判は頻繁に発せられており、柳没後にはさらに厳しい批判が何度も寄せられた。現代では「いまさら民藝批判ですか」という感じさえするほど手垢のついた批判である。それほどムキになって批判しなくてもいいんじゃないかとは思うが、柳民藝批判にまったく根拠がないわけではない。
柳が活躍した大正から昭和初期は、政財界の旦那衆が美術・古美術界を牽引した時代だった。展覧会場には柳を中心とした「人物相関図」が掲げられていて、明治・大正・昭和初期の美術界の大物の名前がズラリと並んでいた。しかしその中に益田鈍翁を始めとする旦那衆の名前はない。それもそのはずで、民藝はウルトラリッチで古美術の名品などを買い漁る旦那衆へのアンチテーゼとして生まれたという側面がある。旦那衆が見向きもしない民間工芸(芸術)に光を当てたのが柳民藝運動だった。「下手物の美」「雑器の美」といった呼称がそれをよく表している。
ただ鈍翁らの旦那衆は優れた美術品を買い上げるための下部組織のようなものを持っていた。決して評価が確定した高価な美術品だけを買っていたわけではない。彼らの美意識は柳に勝るとも劣らないほど優れたものだった。鈍翁の場合、美術の懐刀は柏木貨一郎らだが、貨一郎系の民間の目利きの流れに位置するのが浅川伯教や青山二郎らだった。ただ彼らは初期民藝運動に関わっただけですぐに運動の中心から離れてゆく。民間の目利きだけではない。白樺同人だった志賀直哉は大の古美術好きで知られるが、じょじょに柳と距離を取っていった。表立って批判することはなかったが、その姿勢に対しては「また例の柳の〝美の講釈〟が始まったか」といったうんざりした気配がある。民藝批判でよく言われるように、民藝運動に柳宗悦教のようなカルト的精神性がつきまとうのは確かである。
結果的に柳民藝運動を支えたのは河井寛次郎、濱田庄司、バーナード・リーチ、芹沢銈介、黒田辰秋らの工芸家たちと、式場隆三郎や吉田璋也といった民藝運動によって地場産業を活性化させようとした素封家たちだった。文筆家ではない工芸家たちにとって柳の説く崇高な民藝理念は彼らの作品価値を社会的に押しあげる実際的なメリットがあった。郷土愛に満ちた素封家たちにとっても同様である。また美術館、雑誌、販売店舗の三位一体の「民藝樹」を是とした柳にとってもそれが目標の一つだった。
まあはっきり言えば、崇高かもしれないが柳の説く〝美〟が深みに欠ける薄っぺらいものだったのは確かである。何を見ても結局は美に収斂してしまう。もちろん民藝運動の功罪を言えば功の部分の方が圧倒的に大きい。失われてゆく民間工芸(芸術)を蒐集し保護したのは柳らの大きな功績である。出版活動でそれを深く世の中に浸透もさせた。ただ僕も民藝運動の一環として出版された『ルーマニアのガラス絵』や『李朝民画』などの大型本を持っていて楽しく〝見た〟が〝読む〟箇所はほとんどなかった。なぜそういった民間工芸(芸術)が生まれたのかといった視点が民藝運動には欠けている。美しいだろ、それでいいじゃないかといった姿勢がほとんどなのだ。
民藝運動は民俗学の確立期にも重なっていて、柳と柳田國男は一度だけ対談している。柳田は民俗学は「過去の歴史を正確にする」ための学問だと述べ、柳は「かくあれねばならぬといふ世界に触れていく使命」を担うのが民藝だと言った。柳田は物だけでなく民間伝承の蒐集によって過去――日本人の精神の本質を探求し、柳は民藝に茫漠とした理想を夢見ていたということである。しかし庶民が苦しい生活の中で生み出した民藝品が純粋に無私の作品であり人間の理想的営みであるのかどうかは疑問が残る。ゴム長靴が欲しいけどお金がなくて買えない人に「その藁靴いいよ」と言っても理解してもらえないだろう。

藁靴
山形県 昭和十年代(一九四〇年代) 藁製 縦二六・七×幅九・一センチ 日本民藝館蔵
そういった議論はさておき。民藝運動が出版物も含めてそこから浅くも深くも日本文化を探ってゆける土台を作ったのは確かである。展覧会には日本民藝館所蔵の名品がズラリと並んでいた。物フェチにはたまらない展覧会で、人ぞれぞれ惹きつけられる作品があるだろう。ただ展覧会を通覧すると柳の人生が彼を驚かせてくれる〝発見〟の連続だったことがよくわかる。発見することが難しくなっても柳は新たな美の発見に憑かれていたようなところがある。もちろん柳宗悦没後60年の現代は発見し尽くされた世界であり、そこからわたしたち独自の発見なり思想なりを見出してゆかなくてはならない。
鶴山裕司
(2021 / 12 / 23 19.5枚)
■ 鶴山裕司さんの本 ■
■ コンテンツ関連の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■








