
原田節と谷川賢作のユニット「孤独の発明」の新アルバム『永遠にやって来ない女性』、その第一声を聴いた瞬間「ああ、地上に戻ってきた」と思った。それまで2019年にリリースされたDivaの『よしなしうた』を飽かず聴いていたのだ。『よしなしうた』の第一音の天上へ抜けるただならぬ予感とは対照的な、実家に戻ったような安堵感と、ふと微笑みが漏れる雰囲気がある。
谷川賢作氏の作品のレビューのたびに、同じことを書いているかもしれないが、それは同じことを強く思うからだ。音と声と言葉の意味はすべて一体だ。決して切り離すことはできない。だから第一音、第一声で直観するのだ。その世界観と構成を。それはもちろん制作の意図そのものであり、いきなり伝わるのは紛れもなく傑作の証しでもある。
冒頭、温かなフルボディというべき原田節の声で「鯵が一ぴき/おひるのおさらの上についている」(室生犀星「鯵のうた」部分)と語られる。文字通り、実家の光景だ。鯵がお皿に「ついている」というのも少し昔の言い方で、懐かしい。室生犀星からこっち、我々の世代などでは使わなくなった。ちなみに最近よく耳にする「イメージがつく」という言い方は誤用ではないかもしれないが、だらしなくて嫌だ。「つく」以外の動詞(湧く、など)を考えるのは面倒、と言わんばかりである。「お皿に鯵がついている」というのは、「給食にプリンが付いている」というのとも意味が違う、ごく品のある言い方だ。
そしてこの家は、お昼ご飯のときに父親もいる。勤め人でなく、作家とか開業医とか、あるいは多少裕福な家の雰囲気も漂う。「うまそうだね/どこの海の鯵だろうとお父さまがいう」と、「鯵はこんにちはという」。「みんなびっくりして顔をあわす」のをおかしがっているのは鯵とのことだが、腹話術でも使ったのか、「ぼく」の仕業に違いない。どうしてかといえば、最後に「さて/ぼくの家の夕食は/きっちり六時からはじまります」という詩句である。夕飯のときにもイタズラしてやろうかという坊っちゃまの意図が伝わってくる。
この最初の曲で、それこそ実家の湯船に浸かったようにほっとすると同時に、我にかえるような、目が覚めたような気もする。音楽の、あるいは我々の日々の思考の抽象性、天上へ向かう思いから醒めるのだ。たとえばDiVa『よしなしうた』の冒頭、巨大な物差しが草原に立っていて「いったいなにを はかっていたのか」(谷川俊太郎「かがやく ものさし」部分)。そしてひざまずき、涙する。どうやら消しゴムをなくしてしまったことへの懺悔のようだ。これが〈神〉のメタファーであることは、詩句の意味以上に、ヴォーカルまこりんのこの世のものとは思えない突き抜けた透明性が示している。そのような素晴らしい天上の音楽からも、目覚める瞬間はやってくる。地上に降りた、楽しいとりどりの音楽によって。
二曲目は、さらに暢気な日常の挨拶めいた言葉からはじまる。「春はいいね/だけど春は/おなかがへるね/金平糖のような/虫がいないかね。」(室生犀星「春のうた」部分)と。ヴォーカルの女声はやはり透明だが、神や天使ならぬ〈人〉を思わせる。ここに歌われる言葉も小鳥のものとして語られているが、最後の「ひと声なくと/隣近所の庭が明るくなる」という詩句はその家の主人のものにすり替わっているようだ。誰にとっての「隣近所」なのか、という意味で。そこからの「ホーホケキョ」は、だから〈人〉の耳に届いて、その家の隣近所を明るくしたと聴こえる。
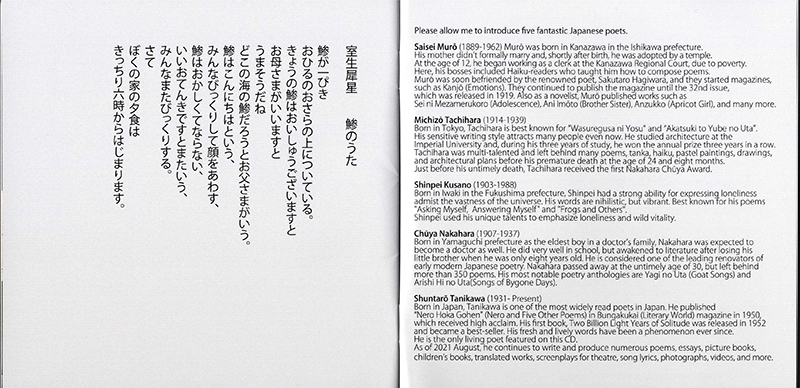
詩であるかぎり、それは〈人〉のものである。そして人であるかぎり、人はその可能性を拡大し続けようとする。言葉を、音楽を、また絵を使って〈人〉の輪郭を曖昧にし、拡げ続けるのだ。鯵の中に、ウグイスの中に入り込み、やがて自身がなり変わる。猫や虫を観察しながら、それになり変わる。音楽がそれを促し、融合させるのだ。であれば、それが室生犀星であれ、谷川俊太郎であれ、中原中也、草野心平であれ、ひとつのものだ。
楽曲の合間にはフランス語の「夢見るシャンソン人形」(セルジュ・ゲンスブール)が挟まっている。聞く者の頭の中に、わ・た・しは夢見るシャンソン人形~♪という日本語訳が重なりながら響くだろう。そこに女性のリズミカルな話声も加わり、男声と、そして日本語訳での我々の既視感とが互いに溶けあう。
アルバムは我々の肉体と同様に構造物であり、ひとつの世界だ。融合の果て、あるいはその合間に反転し、突出する異和がなくてはならない。
「お時計の中にはニハトリが住まない/お魚の内臓に燐寸で青く燈を点けろ/円周率を数へるために鼠を飼ひます/ピーターさんは海へ泳ぎに出かける」(立原道造「お時計の中には」部分)、あるいは「忘れてゐた/いろいろな単語/ホウレン草だのポンポンだの/思ひ出すと楽しくなる」(立原道造「手製詩集 さふらん」より『忘れてゐた』)――これらのモダンな詩句は異和を生む。しかしあくまでこの世界の、楽しい豊かさとしての異和である。そのことは言葉でなく、音楽そのものが示す。
たとえば「くろいもりのなかの いっぽんのきが/おおいと さけんだが/ほかのきは へんじをしない」(Diva『よしなしうた』より谷川俊太郎「おおい」部分)といった、徹底した異和とは色が違う。その色を示すのは、音色としか言いようがない。「おおい」の最終部「ほうちょうは ゆうべむすめのゆびを/きずつけたことばかり おもっていた/あざやかなあかいちが ふきだして/ほうちょうが うっとりとなったことを/きは しらない」は、アルバム中の最高の音楽性を表わす。聴く者もこの「ほうちょう」のごとく、気が遠くなるようなペンディング、抽象空間に浮遊する。この現世への異和には一切の迷いがない。それはまた谷川俊太郎という詩人のどこまでもきっぱりした距離感をも伝える。
だがアルバム『永遠にやって来ない女性』の者たちは寄り集まったまま、ずっとこちら側にいる。猫はしばしば登場し、鳥であったり、かまきりであったり、焼かれた鯵であったり、いずれも〈人〉の視線の先に、この地上に留まっている者たちだ。永遠にやって来ない者を、ひたすら待つ側にいる。
ああ それをくりかへす終生に
いつかはしらず祝福あれ
いつかはしらずまことの恵あれ
まことの人のおとづれのあれ
(室生犀星「永遠にやって来ない女性」部分)
室生犀星の家族の団欒にはじまり、春の訪れ、草野心平のさむい秋を経て、地上に中原中也の雪が降ってくる。その雪にとざされた中でも最後まで、この世の生きものの痕跡をみる。
雪にのこした足あとは
いのちのしるしけものみち
しるべもなしに踏み迷う
生きとし生けるものはみな
(谷川俊太郎「生きとし生けるものはみな」部分)
地上に生きる我々は、地上で終わるのだ。
小原眞紀子
■ 孤独の発明(原田節&谷川賢作)2nd CD「永遠にやつて来ない女性」PV ■
■ DUOユニット 孤独の発明 CD『永遠にやって来ない女性』 ■
■ 谷川賢作さんのCD ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■











