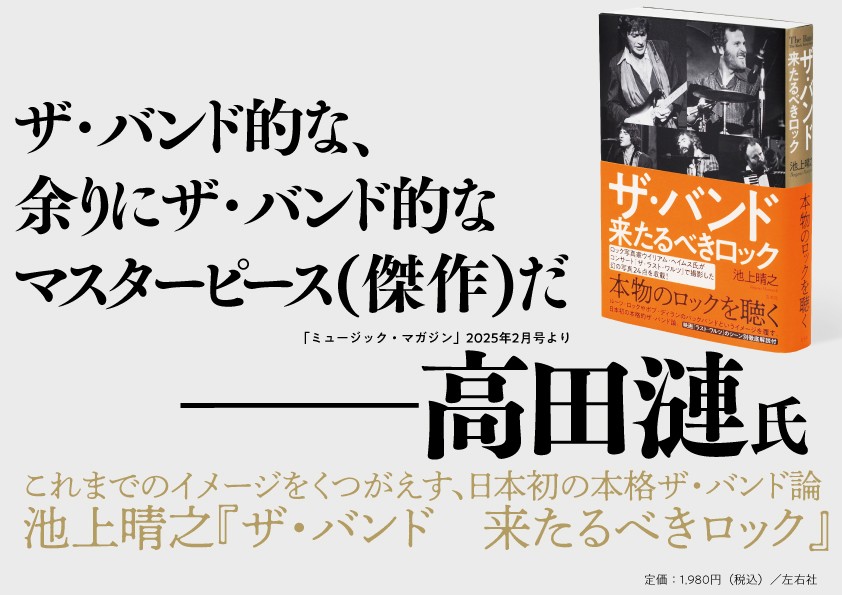週に何回かジャズクラブに行っていた時期がある。不思議だったのは、クラブにある同じピアノを弾いているのに、ひとりとして同じ音色のピアニストがいないことだった。乾いた音、重い音、深い音、軽い音……それはまるで人の声のようにひとりひとり異なる音色だった。
谷川俊太郎の朗読と谷川賢作のピアノ演奏による『聴くと聞こえる』(2025年)という2018年10月に浜離宮朝日ホールで行われたコンサートライヴ録音のアルバムを聴いて、まずそのことを思い出した。
思い出したことは、もうひとつある。大学生の頃、友人が図書館から借りてきた『自作朗読による日本現代詩大系』(1969年)という4枚組のレコードを聴いたことだ。日頃、詩集で読んでいた現代詩人たちの自作朗読を興味津々で友人と聴き始めたのだが、大半は退屈な朗読だった。印象に残っているのは、ある詩人が静謐な自作詩を朗々と読み上げたことだ。その力強い声は、彼がフランス文学に影響を受けた詩人になる前に海軍士官であったことをぼくに思い起こさせた。またある詩人は奇妙な裏声で朗読し、その作為的な声は彼の詩作品の本質を図らずも顕わにしているように思えた。
意外だったのは、文字で読むと難解な現代詩が、自作朗読で聴くと案外わかりやすかったことだ。W・H・オーデンは「詩は本質的に話されることばであって、書かれたことばではない。ことばの実際の音で聞かない限り、人はその読んでいる詩を把握できぬ」(「人間のことばと神のことば」『第二の世界』中桐雅夫訳)と述べているが、これは黙読を前提として書かれている日本語の現代詩にも当てはまるのではないだろうか。
『聴くと聞こえる』で、谷川俊太郎は自作の詩と散文を朗読しているが、その朗読はとてもナチュラルだ。俳優による詩の朗読を聴いていると、演技的な表現に気恥ずかしくなることがある。朗読者が、「詩は本質的に話されることば」であることを理解していないからだろう。谷川俊太郎の地声による自然な朗読を聴いていると「詩は本質的に話されることば」であり、「ことばの実際の音で聞かない限り、人はその読んでいる詩を把握できぬ」ということを実感する。
このライヴで最初に朗読されるのは「音楽のとびら」という散文である。後半には、こんな一節が出てくる。
言葉は精神と肉体を分ける。精神すなわち肉体、肉体すなわち精神という言葉をわれわれは未だ、或いはすでに持ち合わせない。
「言葉は精神と肉体を分ける」とはデカルト以来の心身二元論を指しているのだろうか。もしそうだとすれば「精神すなわち肉体、肉体すなわち精神」というのは「心身一如」ということになるだろう。だが、「精神すなわち肉体、肉体すなわち精神」という「言葉」を「われわれは未だ、或いはすでに持ち合わせない」というのは、どういうことなのか。「未だ、或いはすでに」とは、どういう意味なのか。文字で読めば「未だ」と「すでに」は矛盾した表現であり、「精神すなわち肉体、肉体すなわち精神という言葉」の意味もよくわからない。
しかし、谷川俊太郎の朗読でこの一節を聴くと、「精神すなわち肉体、肉体すなわち精神という言葉」をわれわれは「未だ」あるいは「すでに」持ち合わせないという「意味」が直感的に理解できるのだ。この一節は散文でありながら、朗読によって詩となったと言ってもよいだろう。この文章の最後はこうだ。
(……)音楽は、その発生の初めから未来的なものであり、いまだに未来的なのである。それは未だ解かれてない謎と等価なのだ。
音楽は、おそらくひとつの予言なのだ。
音楽が「未来的なもの」であり、音楽が「ひとつの予言」であるとは謎めいた言葉だが、これは、音楽の本質について語られた、最も詩的な言葉であろう。しかし、この朗読で聴くべきポイントは、この言葉だけではない。注目すべきなのは、先ほどの「言葉は精神と肉体を分ける。精神すなわち肉体、肉体すなわち精神という言葉をわれわれは未だ、或いはすでに持ち合わせない」という文章に続けて谷川俊太郎が「ところが」と言った瞬間に、予期せぬタイミングでピアノの音がきらめき始めることだ。
この瞬間は、『聴くと聞こえる』という作品で最も劇的な一瞬だろう。谷川賢作は「ところが音楽に表れている人間存在は正にその、言葉のとらえきれないものとして在る」ということを正にピアノで表現しているのだ。「音楽の中では在るとはっきりしているのに、言葉として、即ち考えとしては無いに等しいものは、いくらでも在る」という声に重ねて聴こえるピアノの音が、谷川俊太郎が言葉によって伝えようとしている「もの」をはっきり示している。
そして、ここで興味深いのが、この朗読に続けて「旅2 てふてふ」という谷川賢作の作品が演奏されたことである。おもしろいのは、この「旅2 てふてふ」という曲が、「旅2」という谷川俊太郎の詩の朗読に先立って演奏されたことを、谷川俊太郎も意識していなかったことだ。詩の朗読の「前」に、その詩に応える曲がすでに演奏されていたのだ。音楽が未来的なものであり、音楽がひとつの予言であるということを、谷川賢作はこの演奏によって聴衆に示したと言ってもよいだろう。
この後は、谷川俊太郎の楷書体の端正な朗読に対し、谷川賢作が草書体の自在な表現で応えていく。「旅8 言葉」に対しては自作曲の「旅8」を、武満徹に捧げた「音の河」という詩に対しては武満徹作曲の「Be Sleep Baby」を演奏する。
音楽のようになりたい
音楽のようにからだから心への迷路を
やすやすたどりたい
音楽のようにからだをかき乱しながら
(中略)
音楽のように死すべきからだを抱きとめ
心を空へ放してやりたい
音楽のようになりたい
この「音楽のように」と題された詩に対し、谷川賢作が選んだのは「ベサメ・ムーチョ」だ。「私にたくさんキスをして」という意味のタイトルが付けられた、メキシコの作曲家コンスエロ・ベラスケスの作品である。ほとんどアコーディオンにも聴こえるピアニカによって、この有名なラテンの名曲が演奏されていくのだが、意表を突いて、曲の終盤ではピアニカとピアノのひとり二重奏になる。息を吹き込むことで音になるピアニカの音と、打鍵によるアクションで音になるピアノの音がダンスを始め、静かに抱擁したところで演奏が終わる。続けて「このカヴァティーナを」という詩には自作曲の「Old Grandma’s Quiet Smile」が、「泣いているきみ」という詩にはプレスリーの「ラヴ・ミー・テンダー」が演奏される。
最後に朗読されるのは「音楽の前の……」という詩だ。
この静けさは何百もの心臓のときめきに満ちている
この静けさにかけがえのないあの夜の思い出がよみがえる
(中略)
この静けさに音は生れ この静けさに音は還る
この静けさから聴くことが始まりそれは決して終わることがない
この詩に応える演奏はなく、カリンバのイントロで始まった『聴くと聞こえる』というコンサートライヴ・アルバムは、途中、二人の会話や聴衆との和やかなやり取りを挟みながら、カリンバのアウトロで「音楽の前の」「この静けさに音は還る」。なぜ、谷川賢作はイントロとアウトロにカリンバの演奏を入れたのだろうか。その理由はわからないが、このイントロとアウトロが、「この静けさから聴くことが始まりそれは決して終わることがない」ということをリスナーに意識させることは間違いない。
最初に引用したオーデンの「詩は本質的に話されることばであって、書かれたことばではない。ことばの実際の音で聞かない限り、人はその読んでいる詩を把握できぬ」という言葉には続きがある。
そして、その詩の意味は、詩に用いられていることばと、それを聴いている人の反応の間の所産である。
(「人間のことばと神のことば」)
『聴くと聞こえる』という作品がライヴ録音である意味はここにある。谷川俊太郎の朗読に耳を傾けている聴衆の息遣いを通して、われわれは「詩の意味」が産まれる現場を聞くことができるのだ。
クラシックのコンサートを聴きに行くたびに感じるのは、ホールによって驚くほど響きが異なることだ。その意味では、ホールがひとつの楽器だと言ってよいだろう。しかも大きなホールでは、座る席によって聴こえる音の印象がまったく変わってしまう。およそ500席の浜離宮朝日ホールは繊細な音の響きが聴き取れる室内楽用ホールなので、谷川賢作が演奏するピアノの響きの美しさがホールの隅々まで伝わったはずだ。
耳を澄まして音楽を聴けば、このピアノのピュアな響きの中から聞こえてくるのは、紛れもなく詩人に語りかけるピアニストの声そのものなのだということに気づくだろう。
池上晴之
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■