一.ブランキー・ジェット・シティ
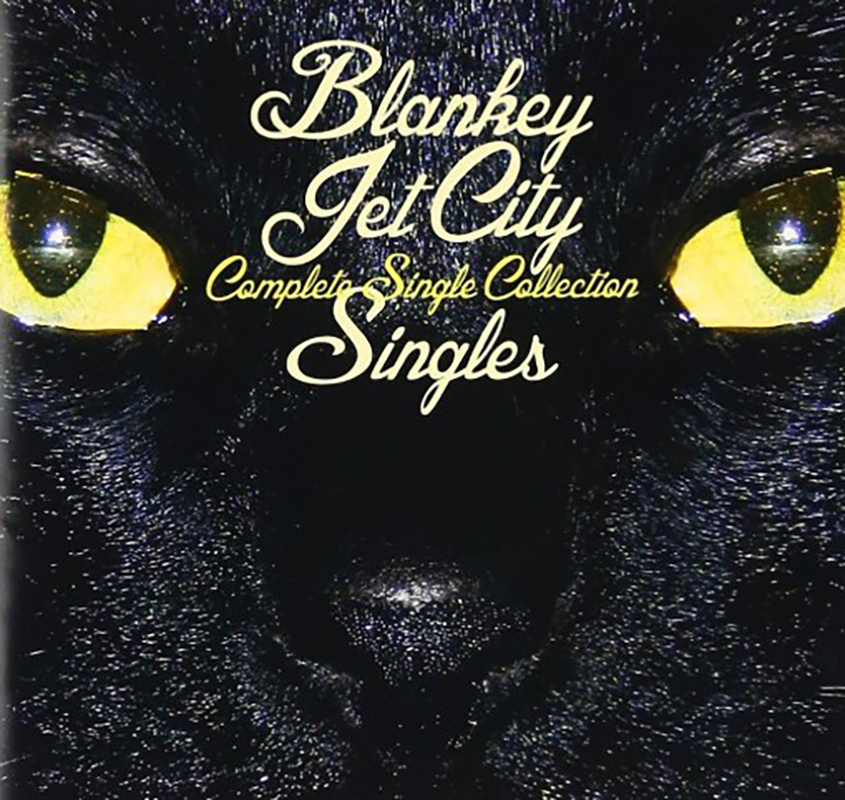
昔からよく注意されるが、呑んでいる時はあまり食べない。角打ちで6Pチーズ齧っているのがベスト。そもそも酒抜きの外食を滅多にしない。過去、労働環境的に毎日ランチを外で済ますことはあったが、そこに楽しみは求めないタイプ。明日はアレを食べてみよう、明後日はアソコに行ってみよう、なんて前向きさはなくルーティン重視。座席も昨日と同じがいい。なので呑む時も料理メインにはならない。なるのは法事の時くらい。食べ慣れない料理に、違う銘柄の瓶ビール。それはそれで風情が、なんて思うのは加齢のせい。ちなみに先日、このフレーズを「カレーの精」に聞き間違えていただいた。なんて美しい。呑み屋の話はこうじゃないと。翌朝起きたらスッカラカン。それが一番。
料理に関しては、するけど不得手。作るものが不味い、ということではなく全体的に覚束ない。レシピどおりに作れば何とかなるので完全にレシピ頼み。「適量」なんて書いてあるともうダメ。頼むよ、こちとら不得手なんだから。ちゃんと何グラムか言っとくれ。料理を通じて納得できたのはスパイスの威力。戦争を引き起こしてしまうだけのパワー、確かにある。殺菌作用等々は勿論、たった1グラムで味があんなに変わるとは。
先日朝から赴いたのは上野のスパイスショップ。その際、せっかくだからと一駅前の鶯谷で下車。昼前から呑める中華屋「T」で一杯やりましょう。密集するラブホやマッサージ屋をくぐって入店すると、諸先輩方はもうマイボトルで宴の真っ最中。此方はメニューが豊富なので大瓶を頼んでから暫し悩む。出した結論は羊肉串焼き。その味は予想以上のスパイシー。鼻先にすぐ汗が。でも旨い。クセになるヤツ。ボリュームも程よく、二串でちょうど大瓶一本(当社調べ)。期せずしてスパイス探しの前にスパイスの洗礼を。
レコードというのはその名の通り「記録」なので、奏者の変化が確認可能。例えば国内パンク黎明期の立役者、アナーキー。デビュー盤『アナーキー』(’80)の音質は低音部がかなり控えめで、聴き心地はシャリシャリ。最初は正直なところ物足りなかったが、二、三枚目はどっしりしている。片や英国パンクの代表格、クラッシュもデビュー盤は音色がチープでドライだが、続くセカンド『動乱』(’78)はウェッティー。変化の要因は様々だが、奏者自身より録音方法/機材など外部の変化に拠る方が多いように思える。印象深かったのはブランキー・ジェット・シティ。期待が大きすぎた為か、デビュー盤『レッド・ギター・アンド・ザ・トゥルース』(’91)はスピーカーに膜を数枚張ったような遠さ/もどかしさがあった。それを痛快に引っ剥がしたのが二枚目『Bang!』(’92)。とにかく音が生々しい。要因はプロデューサーの交代。彼らの音をやるなら俺しかいない、と立候補した土屋昌巳の影響大。当時フロントマンの浅井健一がピックの持ち方を教わったと話すほど。本当、音があんなに変わるとは。
【小麦色の斜面 / BLANKEY JET CITY 】
二.人生 (ZIN-SAY!)
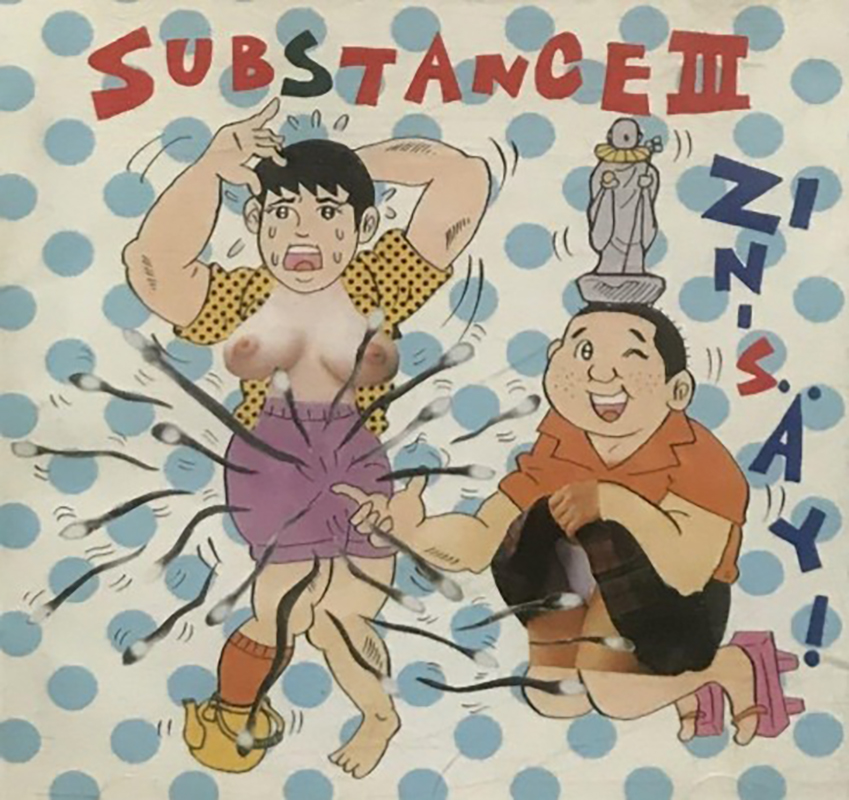
学生の頃、小腹を満たそうとコンビニへ立ち寄った時、かなりの高確率で手作り感の強い惣菜パンをチョイスしていた。柔らかいラップに包まれた見覚えのないパン。大変不適切であるけれど、個人の意図を尊重して当時のままお伝えするならば、そこに感じていたのは「怪しさ」。作り手の顔が今にも浮かびそうなメイドバイ素人的雰囲気と、そもそもどうして?という出自のミステリーにやられ何度となく手を伸ばしていた。その名残りで今も大手ファーストフード店には滅多に行かないが、惣菜パンはたまに買い求める。実は羊肉串焼きで汗が滲んだ後、上野へ行く前に思い出した店がある。パン屋の「M」。人気店なので昼前に売り切れるメニューもあり、一度無駄足を踏んでいる。時間は十時半前と少々微妙だったが、徒歩数分なのでトライした結果……ドロー。即ち開店しているが目当ての品はナシ。見れば半分以上の品が売り切れ。では、とボリューミーな「メンチカツ」をチョイスし、酒の肴にとテイクアウト。これ一本で大瓶二本はいけそう。
最初の音楽体験ならぬサブカル体験はナゴムだった。正式名称、ナゴムレコード。脚本家として紫綬褒章を受章したケラリーノ・サンドロヴィッチ主宰の自主制作レーベル。彼の描く刺激的な雑誌広告を立ち読みしたり、安価なソノシートを買ったりとランドセルに相応しいチープな摂取を楽しんでいた。リリースするバンドの多くは「怪しさ」を擁していて、それこそが一番のお目当て。人気があったのは大槻ケンヂ(当時はモヨコ)率いる筋肉少女帯、そして電気グルーヴの前身バンド、人生。本当にクレイジーな集団だと思っていたので、近所に彼らの連絡先「人生ひみつ基地」があることが本気で少し嫌だった。メンバーのピエール瀧(当時は畳)がコンプラまみれの昨今、薬物による不祥事を経ても尚変わらず、いや何なら以前より順調に俳優として活動していることは本当に痛快。
【カランコロンの唄/ 人生(ZIN-SÄY!)】
三.タニア・マリア
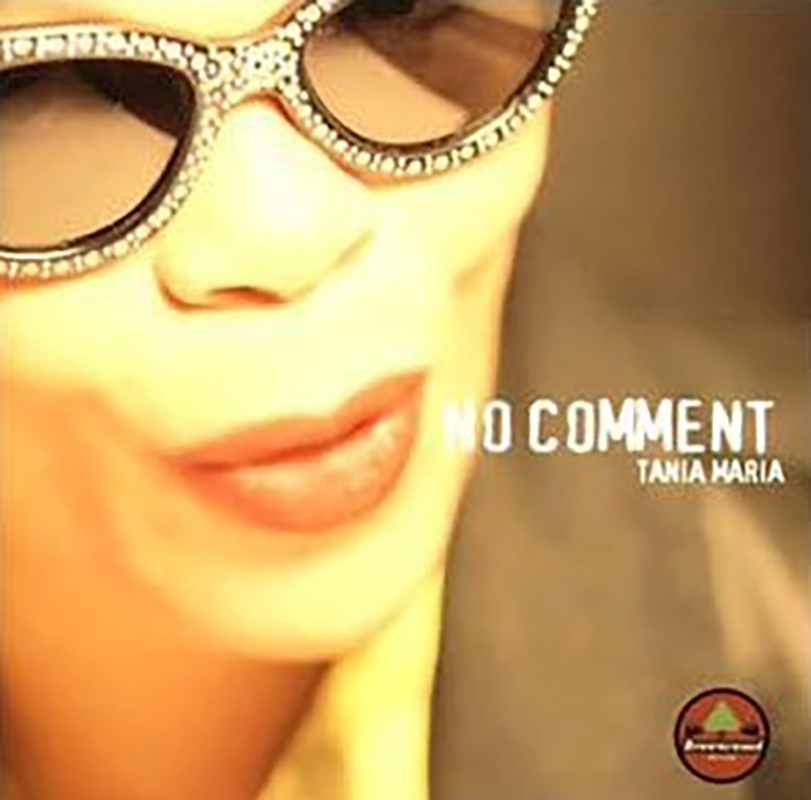
少々遠いが足を伸ばしてしまう秋津の立飲み『N』。先日も夕方前からカウンターは満員。初老の男性客が隣に滑り込んだ。此方は客の名前を聞いて対応する方式。名前を聞かれた隣客が「タナカ」と告げると、いつも元気なママさんが「先客いるからBね」と。B? いまいち仕組みが謎だったが、数分後「これ、タナカBさん」と皿が来た。成程。それから数十分、彼は略され「Bさん」に。段々とやかましくなる喧騒の中、「キムチ頼んだの誰~?」とママさん。隣の彼は躊躇なく「Bです!」と挙手。これもまた痛快。そして美しい。
ずいぶん長く聴いているのに、どう紹介すればいいのか迷うのがタニア・マリア。ブラジルのジャズ・ピアニスト、というだけでは何か言い足りない。少々突飛だが頭に「天才」と付けると丁度良いかも。それでも足りないけどね。彼女は矢野顕子やスティービー・ワンダーのような分析不可能な才能の塊。痛快なピアノ・ユニゾン・スキャットを数秒聴けば伝わるはず。
【 Zé / Tania Maria 】
寅間心閑
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


