ひらがなのつらなりをながめている。ひらがなのつらなりにはこんなふうに いちじあけがほどこしてあるもののそれだけでたりないので ひらがなのかたまりをみつけて、意味を分節化することで詩に意味を探す。そうしながら耳はDiVaの歌に傾けている。おなじひらがなのつらなりをながめているのに、どうしてこうもちがうのだろう。私の目が読み、私の抑揚が伝える詩のリズムや音階は、DiVaのそれとはかけはなれていて、このひらがなのどこからその歌声やってくるものなのか、私にはとてもわかりそうにない。
作詩者谷川俊太郎とDiVaと〈私〉とが詩をまんなかにして向き合っているような想像をする。三者の目線は詩を挟んで出会うことがないから、コン=センサスというようなものは生まれようなく、詩人によってひらがなに固定された詩の向こうには果てなき地平があり、歌い手によって歌われた詩の向こうには果てなき地平があり、〈私〉によって分節化された詩の向こうには果てなき地平がある。
たとえば5曲目に収録された『かえってきたバイオリン』という詩。〈私〉からみるとその詩は静謐で、焚き火の枝のパチパチと爆ぜる音が白い息に混じるのだが、DiVaの楽曲においてはバイオリンの演奏とスキャットが帰り来たる者を祝う。10曲目に収録された『かえる』。へびに飲まれたかえるがもう一度ほんきになっていおうとした「けけこ」の響きを〈私〉は知る由もないが、DiVaによってその心残りが残響のように歌われる。〈私〉のなかでひらがなと意味が結びついてつくられるイメージと、〈私〉の外側から別の装いで渡来する詩のイメージとが、どちらが正しいとかそういういがみ合いをすることもなく、出会うともなしにすれちがっていく。
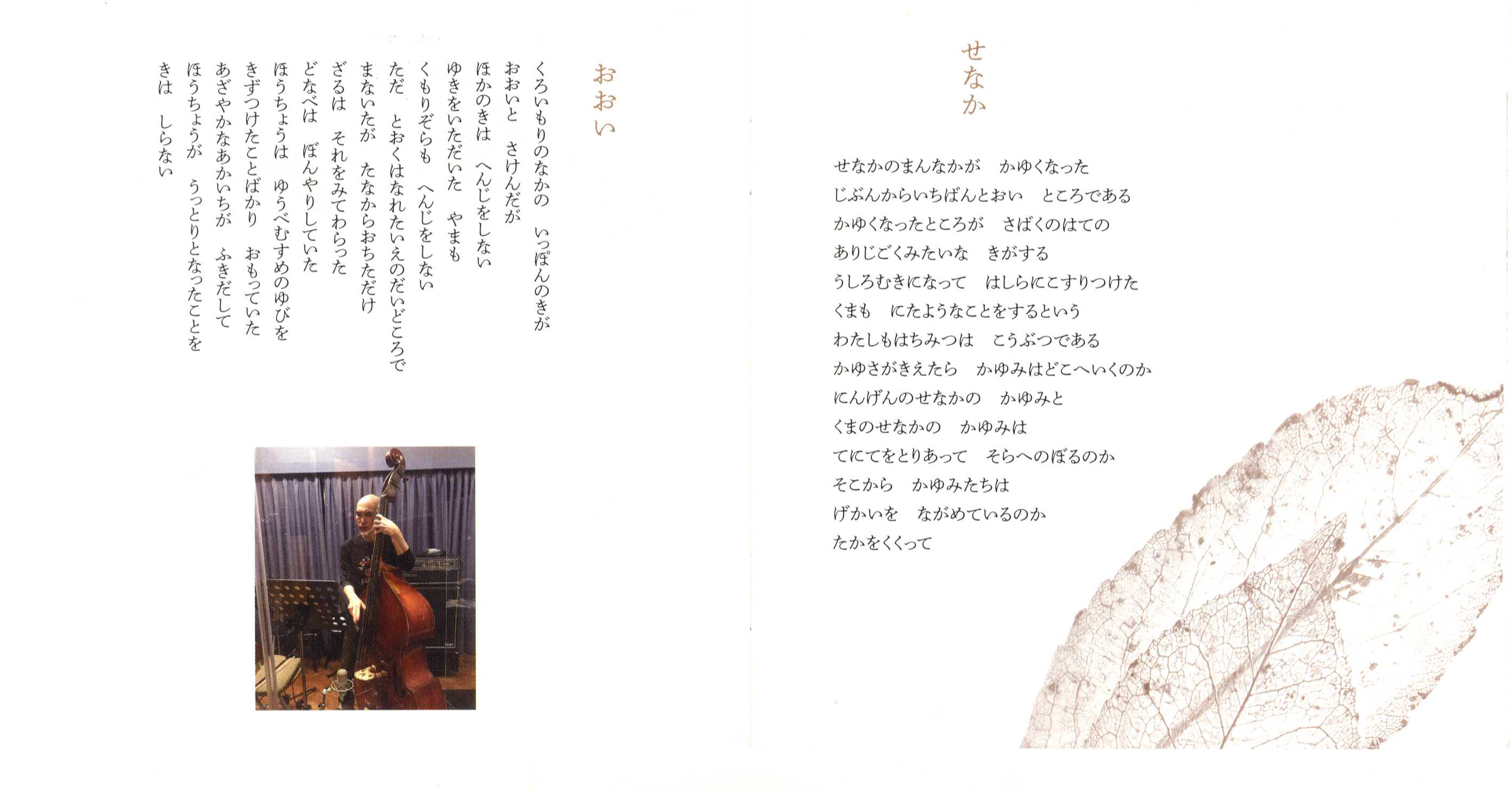
音楽ジャンルのなかにポエトリー・リーディングと呼ばれるものがある。トラックに乗せて詩を朗読する類の楽曲群がそこに属し、系統としてはラップミュージックに近しい。詩に曲をつけるという試みといえば一般にそうした楽曲作りのことだ。あるいは歌詞のなかで既存の詩を引用するとか。いずれにしてもトラックありき、というのが詩と音楽の出会いの紋切り型だ。
DiVaの試みはそれとはすこし異なる。詩を詩としていかに歌うか、まず詩がある。表記された文字が歌になるときには、音が漢字を脱ぎ捨てる。表音文字であるひらがなだけで構成された詩は、きっと歌声と相性がいいのだろう。おなじひらがなのつらなり 〈わたし〉がいみをもとて てん、や まる。をうったりしてよくようをつけていたおなじひらがなのつらなりに うたいてはべつのしかたで きりこみをいれたり おとをひきのばしたりしている。そうして形成された〈私〉とのずれ、作詩者とのすれちがい。そこに詩を飾ろうとか応用しようとかいうケチな了見はない。詩が詩のあるがままにふるまうためのひとつの遊び場をあたえている。
21曲目に収録された『歌われて』という詩は、作詩者と歌い手の〈私〉が共に発した声明だ。まんなかで跳ね回る子どものようなひらがなたちを眺める親たちの、ほんのりと憂いを帯びたひそひそ話。その目は片方で詩を眺めながら、もう片方で外の様子を伺っている。詩を眺め、歌に耳を傾けているとき、〈私〉は詩が自由にあそべるようにかくまう保護者の一員となっているのに気がつく。ひらがなたちがひらがなのままであるために、〈私〉が属する、漢字だらけの外側にはみ出て、取り返しのつかない分節化を施されないように。つまり、〈私〉からも遠ざけるために、〈私〉はその連帯に参加しているのだ。
詩を徹底的に分節化し、詩を躾けてしまったら、詩は〈私〉の意のままになり、〈私〉の代弁をはじめるだろう。まず〈私〉があれば、もうそこには〈私〉しかいない。その孤独から〈私〉を、詩を守るために、詩を歌にあそばせよう。DiVaはその恰好の担い手だ。
星隆弘
■ DiVaのCD ■
■ 金魚屋の本 ■







