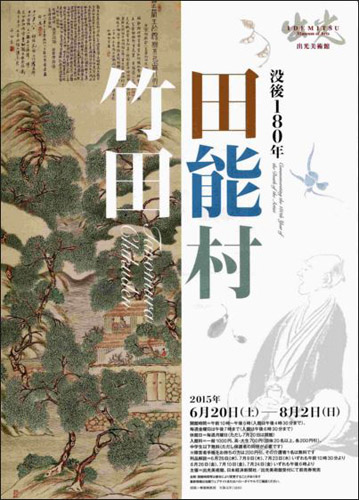
於・出光美術館
会期=2015/06/20~08/02
入館料=1000円(一般)
カタログ=2000円
田能村竹田は豊後国(現・大分県)に生まれた南画家(文人画家)である。安永六年(一七七七年)に生まれ天保六年(一八三五年)に五十九歳(数え年)で没した。文化・文政から天保時代にかけては江戸文化の爛熟期である。江戸文化最後の光の時代だと言ってもいい。一般によく知られているところでは、浮世絵が最も発展し大衆化した時期である。また漢詩(江戸時代に詩と言えば漢詩を指した)だけでなく国学や史学も大きな盛り上がりを見せた。竹田の親友に頼山陽がおり、山陽の『日本外史』は尊皇攘夷運動に大きな影響を与えた。竹田はまた大坂の大塩平八郎とも交流があった。天保八年(一八三七年)の大塩の乱は、幕藩体制崩壊の序章とも呼べる出来事だった。竹田は江戸文化最後の興隆期であり、変化の序章の時期でもある時代に活動した作家である。
竹田は武士である。小藩だが豊後国岡藩の侍医の次男として生まれた。父の跡を継ぎ岡藩に出仕したが医者にはならず、儒者として学問を専攻するよう命じられた。岡藩の先輩儒者・唐橋君山が編纂を開始した『豊後国志』を引き継ぎ享和三年(一八〇三年)に完成させている。ただ若い頃から絵や漢詩に強い関心を示し、絵は江戸の谷文晁に教えを請うている。享和元年(一八〇一年)に『豊後国志』編纂準備のために江戸に向かった時は、大坂の木村蒹葭堂を訪ねた。蒹葭堂は町人だが、膨大な蔵書と珍しい古物や新渡の文物コレクターとして広く文人の間に知られていた。また蒹葭堂は客好きで、蒹葭堂の家は文人らが交流を深めるサロンの役割を担っていた。竹田もその一人であり、若い頃から同時代の文人らと手紙などを介して活発に交流していた。
竹田は二十九歳の時に眼病を病み、その治療も兼ねて二年間、長崎や京都に遊学した。この時に早くも隠居の決意をしたのだという。実際に藩に隠居が認められたのは文化十年(一八一三年)三十七歳の時だった。二年前の文化八年に岡藩で専売制度に反対する農民一揆が起こり、竹田は藩政改革の建白書を二度にわたって藩に提出したが、受け入れられなかったことも原因になったと言われる。しかし竹田はどう見ても官僚向きの人ではない。江戸落語で若隠居はだいたい四十歳くらいである。当時の平均寿命は五十歳を切っていたとはいえ、若隠居はまだ気力・体力が十分にある年齢だから吉原で羽目を外せたのである。竹田隠居の三十七歳は隠居にはちょっと早いが、画業に専念する余力は十分あったろう。念願の隠居だったのではないかと思う。
隠居に際し、竹田は藩から休息料二人扶持を与えられた。もちろん生活に十分な俸禄ではない。そのため以後は南画家として数寄者に絵を売って(譲って)暮らしてゆくことになる。ただ同時代人の岡田米山人・半江、浦上玉堂・春琴親子らと同様、当時の南画家はあくまで自分の理想世界を描く画家だった。それを理解を示し買い求める風雅な人々がいたのである。頼山陽や菅茶山らの学者や詩人も似たようなものである。著書を出版するといっても当時は著作権という概念がなく、原稿は買い取りでたいした収入にはならなかった。彼らは文筆に専念できたわけではなく、塾を開き門弟らを指導しながら執筆活動を行っていた。

『柳閣暁粧図』

同 拡大図
一幅 絹本着色 天保元年(一八三〇年) 縦一三九・五×横五一・五センチ
『柳閣暁粧図』は竹田五十四歳の晩年の作で、代表作の一つでもある。大幅の絵なのだが図版では細部まで見えにくいだろう。柳の新緑に包まれた山中の屋敷の中で、鏡を見ながら朝の化粧をする女が右下に描かれている。「暁粧図」、つまり朝方に化粧をして身支度を調える女性の姿を描く画題で、中国の「仕女図」をふまえている。絵の上の方に書かれている賛も竹田の筆である。今回の展覧会図録では絵の解説だけでなく、賛の読み下し文も巻末に収録されているのだがこれはまことにありがたい。学者でなければ賛を正確に読み解くのは難しいが、南画の場合、賛が読めなければその魅力は半減してしまうからである。
賛は冒頭に「芝蘭は深林に生じ、人無きを以て芳からずんばあらず」(大意「霊芝や蘭は森の奥に生えて、人がいなくても開花して芳香を放つ」『孔子家語』)が篆書で書かれている。これが画題である。次に竹田の亡兄・田能村観瀾の七言絶句がある。竹田は漫然と観瀾の詩集を読んでいたら、この絵にぴったりの詩があったので追記したと書いている。それから般若心経の全文が続く。最後に絵を坂上桐陰に見せたら気に入ったので譲った、この絵が良い人の元におさまって自分も嬉しいとある。
竹田は賛を四回に分けて書いたわけだが、まず「暁粧図」の画題で絵を描き、それが亡兄の詩を思い出すきっかけになった。般若心経を記して亡兄を弔い、最後に絵を桐陰に譲った経緯を書いた。なお桐陰は伊丹の蔵元「剣菱」の主人で、竹田や山陽とも交流のある文人だった。竹田はこの作品を天保元年七月から十二月にかけての長い旅に携えてゆき、伊丹で桐陰に譲ったことがわかっている。自信もあり思い入れ深い作品でもあったのだろう。
与謝蕪村や谷文晁の美術展評でも書いたが、現代人の目には南画の良さが伝わりにくい。竹田の『柳閣暁粧図』にしても、パッと見ればどこにでもある山水画に映るだろう。乱暴に言えばその通りなのだ。同じような画題を扱った作品は無数にある。南画はヨーロッパ絵画のような、あるいは明治維新以降の絵画のように、作家の自我意識を直截に表現した絵ではない。むしろ作家の自我意識(オリジナリティ)を極限まで削ぎ落とし、自由な表現の余地などほとんどない定型にまで表現を押し込めて、その後、ほんのわずかだが決定的な自我意識表現を付加するのである。
竹田の場合、細かく丁寧に描かれた樹木や山、家などの描写に彼の自我意識が表現されている。また代表作を見ればわかるがその色遣いは独特だ。中間色と言ってよいような、目に優しい色で樹木の葉や山の青が表現されている。墨色も独特である。強い黒ではなく、グレーがかった墨色を出すのが竹田の南画だ。一幅の絵が全体として一つの調和世界を構成している。もちろん竹田が西洋絵画的な写生を全く知らなかったわけではない。彼は長崎留学の際にヨーロッパ絵画の影響を受けた南蘋派の画法を学んでいる。しかし南画を描く際は写生技法は重要ではない。南画は文人画とも呼ばれるように、作家の内面を描く絵である。
「芝蘭は深林に生じ、人無きを以て芳からずんばあらず」という賛(画題)は、誰も見ることのない深林でも霊芝や蘭は芳香を放つという意味である。それが山の中で一人化粧をする女の姿として表現されている。賛に従えば、もちろん絵の中の女に夫はいない。女は誰かに見せるためではなく、自分の身体と心を引き締め、清浄な一日を過ごすために朝の化粧をしている。それが竹田が理想とした心的世界である。
竹田は自ら望んで隠居した武士である。社会的にはもはや無用者だと言って良い。しかしだからこそ、現世の雑事に惑わされずに高潔な精神を保つことができるのだというのが当時の南画家たちの姿勢だった。竹田が本格的に活動を開始する少し前の天明時代に与謝蕪村や池大雅が現れた。日本の本格的南画の系譜は彼らから始まる。幕末には社会的無用者こそが至高と呼べるような明透な精神的境地を得られるのだという思想があり、社会全体がそれを肯っていた。それだけ現世的な苦しみが大きく、社会が大きな矛盾を孕んでいた時代でもあったのである。また同時に幕末の江戸社会はそれなりに豊かであり、世を捨て高潔な精神を探求する南画家たちが、細々とであれ画業で暮らしてゆける時代でもあった。

『清谿深遠図』
一幅 紙本墨画 文政十年(一八二七年) 縦一三七・七×横四一・七センチ
『清谿深遠図』は文政十年の長崎遊学中に、友人・道文淵の依頼で描かれた。竹田五十一歳の作だが、彼のいわゆる代表作が次々に生み出されるようになるのは天保元年頃から没年の天保六年までである(竹田五十六歳から五十九歳)。竹田は長崎留学で本場の中国絵画と技法に触れ、「最早絵をば止めようかと思ひ申候位也」とまで思い詰めたことが知られている。もちろん『清谿深遠図』にも竹田らしさは表現されている。丁寧で繊細な描き込みは竹田ならではのものだ。しかし竹田はさらなる画業の進歩(深化)を求めていた。
『清谿深遠図』には上方に竹田の長文の賛がある。図録の読み下し文によると、この中で竹田は、「この画幅は、わたしに家屋や橋を描いてもよいが、人を描いてはならないという制約を加えて出来たものだ。その制約の真意は、どんどんひろげて見て行きながら、心が画中に飛んで、あちらこちらの楼閣で、自分自身が主人となり、そこからの眺望を独り占めにする気分を味わわせようというのであろう」と書いている。『清谿深遠図』には山水しか描かれていないがその主は竹田であり、彼の自我意識が絵の中に偏在している。
竹田は「わたしの絵は、下手くそなもので、ただその時々の感興を寄せるだけで、君子人の賞翫するようなものではない」とも賛で書いている。過剰なまでの謙遜が込められた言葉だが、竹田が自分の画業に満足していなかったのは確かである。江戸期を通じて、たとえ西洋絵画の技法を知っていても、画家たちが規範としたのは中国の古典だった。簡単に言えば孔子を始めとする儒者が説く、人間はもちろん動植物までもが一つの調和を構成している理想世界が規範だったのである。それは実現不可能だが、究極の理想世界には違いなかった。
江戸の文人たちは、この理想世界に少しでも近づくために過去へと思考を遡らせていった。未知の思想や技術を追い求めるのではなく、過去の古典を精査・精読することで新たなものを生み出そうとした。それが近世までの東アジア圏の知識人の方法だった。ただ幕末になるとその思考が強い論理性を帯びてくる。竹田の山水画の理解などもその一つである。相変わらず中国古典の理想世界を憧憬し、思考の最終形としては神仙的な悟り(飛躍)を至高としていたが、幕末知識人の批評意識は鋭い。

『果蔬草虫図巻』(部分)
紙本墨画淡彩 文政三年(一八二〇年) 縦二七×横四〇六センチ
『果蔬草虫図巻』は文政三年に、故郷竹田で二ヶ月病床に臥せった後に描かれた図巻である。四メートル近い紙に様々な草花や野菜、虫たちが描かれている。その多くを病み上がりの竹田が、手元に実物を置いて写生したのは明らかである。この図巻には頼山陽の跋がある。山陽は「竹田は人物が愚かで、心根も愚か、面目も愚かで、筆遣いも愚かだ。愚かな中にずるがしこさを秘めているのだが、人はそれに気づかない。(浦上)春琴の筆使いはずるがしこさばかりで、おろかさが見えない点で、竹田にひけをとっている」と書いている。
この言葉に対して竹田は、「頼山陽がわたしをからかって癡(愚かの意味)と言い、さらに黠(ずるがしこいの意味)と評した。春琴居士を評して云うには、ずるがしこい人は愚かになれない。言いたい放題にののしって、わたしを翻弄することこのありさまだ。この言葉はそのまま本人に返したい。自分だけ高見にあってなんということをいうのだ。反論の言葉を記しておく」と書いている。
浦上春琴は玉堂を父に持つ南画家である。竹田が一番年かさで、春琴は二歳年下、山陽は四歳年下である。当時は今よりもさらに生まれ年にうるさかったはずだが、竹田と山陽がそれを意に介さない付き合いをしていたことがわかる。また山陽は春琴に内緒で跋を書いたわけではない。跋冒頭で山陽は、春琴の家で『果蔬草虫図巻』を見たと書いている。春琴が跋を読むことを十分意識していた。多少冗談めかしてはいるが、山陽の批評は歯に衣着せぬ率直なものである。
竹田は「愚か」だが、「愚かな中にずるがしこさを秘めている」のであり、春琴の「筆使いはずるがしこさばかりで、おろかさが見えない点で、竹田にひけをとっている」という山陽の批評は正鵠を衝いている。作品を比較すれば一目瞭然だが春琴の絵は美しい。技巧は竹田よりも上だろう。しかし山陽は美や技巧を評価しない。南画(文人画)において一番重要なのは、愚かなまでにその精神世界に没入することであり、技法(ずるがしこさ)はその中でわずかに発揮される要素に過ぎない。それは南画の世界で、ほとんど稚拙な殴り描きのように見える玉堂(春琴の父)の作品が最高とされていることからもわかる。南画の評価基準は西洋絵画とは異なる。

『梅花書屋図』
紙本墨画淡彩 天保二年(一八三二年) 縦一七三・六×横六三・八センチ
『梅花書屋図』は天保三年十一月に、旅先の九州中津で曾木士功のために描かれたことが賛からわかる。巨大な軸である。旅先ゆえ絵の具や筆も限られていただろうが、丁寧に描かれた淡い色彩は竹田ならではである。竹田のように描き込むと普通は絵がうるさくなってしまうものだが、すっきりとしてある清涼感を感じ取ることができる。山並みも梅花も家屋も細かく描写されているが、一枚の絵の中で調和した世界を形作っている。
竹田の場合は隠居だが、古くはそれを「世捨て」と言った。平安時代初期に成立し、在原業平をモデルにした『伊勢物語』には「むかし、をとこありけり。そのをとこ、身をえうなき物に思ひなして、京にはあらじ、あづまの方に住むべき國求めにとて行きけり」とある。平安の昔から江戸に至るまで、「身を用無き者に思いなして」芸術の世界に生きた人々が大勢いた。いつの世でも栄達と富貴を喜ぶ現世においてそれは脱落である。ただ数々の優れた文学や絵画が、それが必ずしも厳しい現実世界からの逃避ではなかったことを示している。
極論を言えば竹田を含む南画作品は、一度にたくさん見ても得るものはない。気に入った一幅の絵を、できれば間近で床に掛けてじっくり見つめるのが良い。この作家を何を棄て、何を得ようとしたのかを腑に落ちるまで眺め、理解しようと努めるのである。南画作品は分析してゆけば必ず何かの本歌(お手本)にたどり着く。賛はもちろん絵も言葉で説明することができる。ただ優れた南画の本領が、すべての言葉を理解した上で開ける無(語)の世界にあるのは言うまでもない。
鶴山裕司
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


