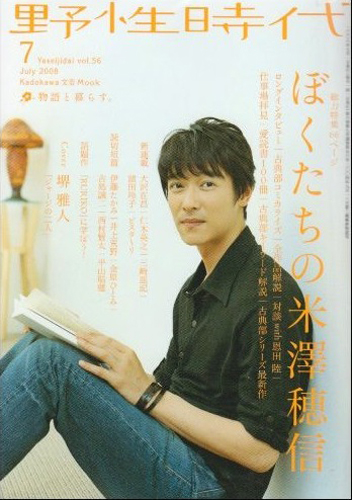西村賢太の連載、「一私小説書きの日乗~野性の章~」がこの上なく “ 文学 ” である。しびれてしまう。何に、と問われると困るのだが、その “ 私性 ” に、と答えるべきなのだろうか。私小説の本質は確かに、日記にあると思う。そして日記の本質とは、日々、事も無しというところにある。それらの日々は極く私的であり、同時に普遍的である。誰の日々も変わらないと言えば、変わらない。
変わらないのに、なぜ西村賢太の日記を読みたいのだろう。それはたとえば「私の」日記とどこが違うのか。
日記が普遍的に持つものは、もしかすると “ 日記性 ” というものかもしれない。日々、事も無しという雰囲気だけが、誰の日々にも共通してあるのだ。ひとつひとつの出来事、食べた物、会った人に差異があるのは当然のことだ。しかし、それは差異なのか。日記文学にアプローチするとき、欠かせないのはこの「これらの差異は、果たして差異なのか」という一種の達観のようなものだ、という気がする。我々はそう、たいして異ならない日々を送っている。そして逆説的なことに、それはたとえば歴史上の大事件が起きている(と、のちに評価される)日々においても、やはりそうなのだ。
大きな何かが起こっているときでも、その日々は平穏に見える、という捉え方もできる。その一方で、日々は常に平穏なのであり、ドラマとはのちの編集、俯瞰によって初めて出現するものに過ぎない、という捉え方もある。後者の考え方は一種の死生観で、日記文学と私小説の土壌になっていると思う。
西村賢太の日記で、最も “ 文学 ” から離れている、いわば夢から覚めたように読めるのは、自身が出演したテレビ番組で使用されていた写真のクレジット、キャプションについての不満が述べられている部分であった。そこでは事態の経緯、状況が説明され、不満の根拠が論理化されている。不満そのものは私的なものだが、それは社会における居場所を主張するためのテキスト、短い論説となっている。
日本文学の本質的なところにエッセイズムがある、と言われて久しいが、エッセイには二つの意味がある。ひとつは通常使われる、いわゆるエッセイ。もうひとつは論説、論文。この二つの落差には、ときに戸惑う。しかし書く立場からすると、それはほんの一歩の距離しかないのかもしれない。“ 私性 ” に徹しつつも、社会はすぐそこにある。他者がいるわけだから、それとぶつかったとき、勝とうとするなら “ 私 ” の視点を離れなくてはならない瞬間もあるわけだ。
そしてしかし「勝ちたい」と思うのもまた、“ 私 ” なのだ。あらゆるロジック、論説はその原点に “ 私性 ” が存在する。それはロジックの破綻や偏向を意味しない。原点にはどうしようもなく、抜きがたい “ 私性 ” があると認めることが論理の出発点であり、それを忘れないことが日本文学、すなわち純文学というものだろう。
西村賢太は「女が買いたい。小説を書きたい」と記す。社会的認知を排除し、それが及ぶことのない “ 私性 ” の原点、すなわち日記において、この二つはまったく等価である。それがまるでわかってない、自称文学者の「ブログ」なるものを読まされるのは無為そのもの、今の時代の単なる不幸だ。
池田浩
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■