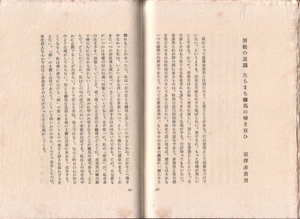
男根の意識 たちまち驢馬の啼き狂ひ 富澤赤黄男
富澤赤黄男と安井浩司。この二人には共通するイメージがある。「孤高」というイメージである。そして「孤高」とは限られた少数の尊称ゆえ、「孤高」同士何らかのシンパシーがあるとしても不思議ではない。にもかかわらずこの二人の距離は、近いように見えて実際は遠いと感じられる。それは、安井が赤黄男を単独で論じた文章を評論集に探すと、この小論と『もどき招魂』に収められた「赤黄男の三句」の2本のみだからである。後者にしても単独とはいえ評論というよりもエセーで、本格的な赤黄男論とはとても言い難い。
赤黄男は、戦前に始まる新興俳句運動における俳句革新の最終走者として、太平洋戦争開戦と同時に処女句集『天の狼』を刊行し、戦後の前衛俳句に多大なる影響を与えた。その前衛俳句を先導した高柳重信が唯一師と仰いだのが赤黄男であり、1951年には『天の狼』の改版を重信自らが刊行するとともに、翌1952年には赤黄男と重信が手を携えて、俳句における詩的美学を追及した同人誌「薔薇」を創刊している。
一方の安井が重信の弟子になるべく「俳句評論」の門を叩いたのは、赤黄男が死んで2年後の1964年のことである。であれば赤黄男と安井の間に直接的な交流はなかったろうが、当時の安井が、俳句と詩の間の壁を取り払い詩的言語による俳句形式の新たな可能性を探ろうとした道行きと、赤黄男が「俳句は詩である」と宣言し、新興俳句の理論的な展開を担おうとした軌跡とが、ともに相似た軌道を描いているのもまた事実である。
安井はこの『聲前一句』において赤黄男を語るに際し、他の俳人を語るのとは明らかに違い極めて慎重である。その文章は、次のとおり唐突な疑問で始まっている。
私にとって富澤赤黄男とは何だろう、と思うことがある。だが依然として決着をつけていない。というよりも、決着を可能なかぎり延ばしたい。要するに、もっと時間が欲しいことである。
(『聲前一句』より)
『聲前一句』は、安井の俳句形成過程に存在した俳人の一句を取り上げ、当の俳人が安井の俳句思想に何をもたらしてきたかを、その一句を道標に確認する作業として書かれている。ゆえに安井はこの『聲前一句』を書くことで、消すことのできない影響を残した俳人達に対し、自らその決着を付けることを目的としている。であれば、冒頭の「決着を可能なかぎり延ばしたい」とは、安井にしては不可解な言葉だ。さらに先回りしてこの小論の結びに目を遣ると、本来語られるはずの決着に代わって新たな疑問が提示されている。
私は遂に俳句における「眼」の第一義というものの強さと弱さを思わざるをえない。「眼」の主体とは何であろう。こういう問いかけの中に、しんじつ存在したのは、写生俳人なんかではなく赤黄男その人だけだったような気がしてくる。
(同)
この冒頭と結びに置かれた疑問は、『聲前一句』にとってあるまじき、決着の先延ばしと取られかねない。また他にも、「・・・気がする」「・・・と信じたい」「・・・かもしれぬ」「・・・知れないことだ」「・・・ような気がしてならない」というような、断定には至らない語尾が安井の文章には珍しいくらい数多く見受けられる。察するに安井の胸中では、赤黄男という存在が確信には至っていないように思われる。
このような赤黄男に対する複雑な感情の原因を、安井自身は、「かつて、赤黄男はわが師・耕衣に訝しい、訝しい、を言葉としたという。その訝しさはもう弟子たる私自身にも墜ちてきたような気がする」と明かしている。赤黄男が「訝しい」と評した耕衣とは、安井が重信に先駆けて最初に師事した永田耕衣のことであるが、二人は(耕衣は赤黄男より2歳年上の)ほぼ同世代である。そのうえ二人とも伝統を墨守する俳句に馴れ合うことを潔しとせずに、それぞれが独自の俳句革新に挑もうとした点で、道は違えど同じ頂を見据えていたと言っても過言ではない。そうした共通項にもかかわらず、一方がもう一方を「訝し」がるにはそれ相当の考えあってのことと思われる。
耕衣は戦後しばらくして、西東三鬼の推挽により山口誓子の「天狼」に加わっている。三鬼も誓子もともに新興俳句運動の主導的立場にあった俳人であるが、赤黄男と耕衣を結びつけたのは重信である。1958年に創刊した「俳句評論」において、重信は二人を創刊世話人に連ねさせている。赤黄男は重信の意向に従い、「俳句評論」に集った若手俳人達を指導する立場に身を置き、第一回「俳句評論」賞の審査員などにあたった。一方で耕衣は、自らの主宰誌である「琴座」と平行しながら、「俳句評論」から吸収した言語実験にも果敢に挑戦した。赤黄男は創刊から4年後、闘病の末に早過ぎる死を迎えるが、「俳句評論」における二人の交流はほとんどと言っていいほどなかったようだ。
耕衣に対する「訝しい」という赤黄男の評言が、いつ頃のことであったか安井は明らかにしていないが、それは耕衣の人間性を評してではなく、その俳句作品に対してのことであるのは間違いあるまい。赤黄男は俳句に対する考察を論理的な文章ではなく、「雄鶏日記」(「旗艦」1947~1948)・「モザイック詩論」(「火山系」1948~1950)・「クロノスの舌」(「薔薇」1953~1954)といった、アフォリズムと言うべき短文によって表現した。であれば「訝しい、訝しい」にしても、思わず口をついて出た軽い感想というよりも、赤黄男の厳しい審美眼による確信的な評価であると言っていい。赤黄男は「訝しい」という一言で、耕衣俳句に対する違和感を表明すると同時に、同世代の俳人として耕衣という存在を認めていたに違いない。では赤黄男は耕衣俳句のいったい何を「訝しい」と評したのだろうか。
だが待ってもらいたい。赤黄男とわが師の間にあるものは、時間の近代的短絡ゆえの歪みであり、赤黄男と私の間を焦立たせるのは時間不足のせいであると信じたい。改めて思い返せば、運命とはそれも一つの真理の代弁者であろう。かつて生前赤黄男の、もしやその生身の体温に一瞬たりと触れることがあったら、私は一疋の狂える驢馬と化していたかも知れぬ。
(『聲前一句』より)
「だが待ってもらいたい」とは安井の赤黄男に対する反論の狼煙であろうが、反論と言い得るほど論理的なわけではなく、「時間」という一語を持ち出して「言い訳」を装うかのように書いている。つまり、赤黄男と耕衣の間に横たわる断絶と呼び得るほどの深淵にしろ、赤黄男俳句の理解に対する安井自身の焦燥感にしろ、それぞれの齟齬が「時間」に起因しているのを、半ば仕方ないことと諦観しているようだ。が、しかし、ここで安井が持ち出している「時間」とは、「短絡」や「不足」といった、数や量に還元し得るほど単純なわけではない。いささか唐突かもしれないが、つい最近朝日新聞に掲載された「原発事故が問う時間観」という記事の中で、宗教学者の山折哲雄は、日本人が独自の近代化を成し遂げた要因として、二重の時間観の併用を指摘しているが、そうした「時間」観が、安井の言う「時間」を理解するのに適していると思われるので、その部分を以下に引用する。
日本人は仏教の輪廻(りんね)転生の思想から影響を受け、四季や自然の移り変わりに社会の変化を重ね合わせ、循環的な時間を生きてきた。幕末から明治以降は西欧の進化論的な直線的時間観も採り入れ、右肩上がりに進歩する科学技術を駆使して急速な発展にも対応したが、「次第に時間とともに人間は進歩するという考えが絶対視されるようになった。」
(2013年3月18日日付「朝日新聞」朝刊より)
安井が言うところの、赤黄男と耕衣との間にある「時間の近代的短絡ゆえの歪み」とは、日本人の根幹を形作ってきた「循環的な時間」が、学問的教養として西洋から輸入された「直線的時間観」によって、矮小化される過程で生じた文化的な齟齬と捉えることができる。耕衣が「天狼」において取り組んでいた「根源俳句」とは、「存在の根源(生命の根源)を追求する根源精神によって貫かれた俳句(山本健吉による)」であるが、耕衣はこの「根源」を「東洋的無」と捉えたうえで、さらに禅的な諧謔を俳句表現に取り入れた。つまり、仏教的な永劫回帰の生命観を俳句の思想に据えた耕衣を「循環的な時間」とすれば、「俳句は詩である」というテーゼのもと、フランス詩から輸入した象徴主義的方法論を俳句に取り入れた赤黄男とは、「直感的時間観」によって「俳句」を「進歩」させようとしたと言えよう。こうした対立関係は、むしろ赤黄男からの一方的な「齟齬」といった方が正しいと思われる。なぜなら耕衣に赤黄男の「俳句=詩」に反対した痕跡は見られないばかりか、赤黄男没後の「俳句評論」にあって、耕衣はこうした俳句における「詩学」を重信から学び、自家薬籠中のものとして自身の句作に使いこなしたからである。
安井は、赤黄男の耕衣に対する「訝しさ」を、当時の赤黄男が試みていた詩的言語による俳句革新という主知主義的な西洋文学が、耕衣における「根源俳句」という東洋文学を認めなかったことに起因したと考えているのは間違いない。そうした背後には、近代文学に取り憑いた、「進歩」という西洋特有の観念があった。この進歩への熱望が知的であればあるほど、理不尽極まりない戦地を体験した赤黄男にとって、西洋直輸入の文学思潮はさぞかし魅力的に映ったことだろう。その反面で宗教的な匂いを漂わせる耕衣に対しては、戦争で無力を露呈するばかりだった宗教同様に、得体の知れない観念の遊び人のような「訝しさ」を抱いたとしても不思議はない。このように二人を隔てる「時間の近代的短絡ゆえの歪み」とは、俳句革新という同じ山の頂上を目指しながらも、それぞれ大きく隔たった別々のルートを辿るしかなかった二人にとって、運命として割り切るしかないものだった。安井に二人に対する良し悪しはない。あるのは運命に対する虚無感だけだと言えよう。
では安井にとって赤黄男とは何か、という冒頭の問いに戻りたい。先に引用した「私は一疋の狂える驢馬と化していたかも知れぬ」に続けて、安井は赤黄男との「無縁」という運命について次のように言及する。
だがそこへ導きのなかった私は、いよいよある訝しさを承接しつつ、そういう頒たれた運命のまま、これまた一つの別真理を道に延べていることを自認するほかはないのである。だが、みな誰もがいつかは得体の知れぬ処へ屈服していくだろう。
(『聲前一句』より)
運命は運命として受け入れるしかないもので、それ以上でもそれ以下でもない。その一方で安井は、「誰もがいつかは」自ら選んだ道として「得体の知れぬ処へ屈服していく」ことが必要なのであると言い切る。「だろう」という含みを持たせた語尾ではあるが、「だが」という書き出しが確信を導いている。つまり「得体の知れぬ処」とは、安井にとって欠くべからざる存在の謂いであり、自らの俳句のためには「進んで屈服すべき」対象であると言える。俳句においてそれは「師」に他ならない。言うまでもなく安井にとって「師」たるべき存在は、耕衣であって赤黄男ではなかったということだ。
耕衣が俳句に探ろうとした「宗教」に対し、赤黄男が俳句に措定した「詩」とは、宗教ほど俳句形式との相性がよかったとは言い難い。赤黄男の「俳句とは詩である」という独自のテーゼは、次第に赤黄男を困難な結果へと導いていく。そもそも赤黄男は、第一句集の『天の狼』においてすでに、俳句作品としての早過ぎる頂上を極めてしまったとも言える。その後第二句集の『蛇の笛』では、赤黄男の形式的特徴である一字空白が技法としての成熟を見せ、そのテクストはより「詩」へと近付いていくこととなる。が、「詩」へと近付けば近付くほど、皮肉にも作品が俳句形式から遠のいていったのもまた事実だ。『天の狼』は、俳句形式の境界線ぎりぎりに踏み止まった上で、その内側から境界線を押し広げようと試みた句集ではあったが、『蛇の笛』や、それに続く第三句集の『黙示』では、俳句形式そのものが俳句の領域を逸脱している。
掲出句の〈男根の意識 たちまち驢馬の啼き狂ひ〉(*筆者注)は『蛇の笛』に収録された作品で、上句と中句の間に意図的な一字空白がある。この一字空白の技法は赤黄男の独創ともいえるもので、このように句の途中に意識的な「ため」を作ることで、読者は一句を上から下ヘと一気に読み下すことを妨げられ、同時にこの空白によってもたらされた「意味的空白」によって、解釈を中断された読者は文字通り俳句空間に宙吊りにされる。この「意味的空白」が何を意味するか、あるいはしないかは宙吊りにされた読者に委ねられるが、その一方で俳句空間は非日常的かつフィクションナルな「詩」へと昇華される。
草二本だけ生えてゐる 時間
月光や まだゆれてゐる 絞首の縄
偶然の 蝙蝠傘が 倒れてゐる
冬蝿や 空(クウ)にひらいた土偶の目
蛇よ匍ふ 火薬庫を草深く沈め
(以上『黙示』より)

一見して俳句形式と呼び得るのは形ばかり残った五七五の韻律だけで、現出した世界は日常とは異質の空間に占められた、つまり自然とは存在様式の異なる人工性によって支配された、それこそ「詩」としか呼びようがない世界である。しかし、これらのテクストには常に、俳句にもたらされた「詩的」効果と引き換えに、「なぜ俳句なのか」という根源的な問いが投げつけられることになる。『黙示』は病魔と闘う赤黄男を励ますべく、弟子の重信によって性急に編まれた句集であるが、その困難な結果を重信は次のように書いている。
率直に言うと、この『黙示』の作品の大半は、いわゆる抽象化への傾斜が大きく、かなり安定性を欠いているようである。これは、(中略)いつまでも同じところにとどまるのを欲しない赤黄男の性格からすれば、あるいは当然の変貌でもあったろう。決して停滞も後退も許されなかったのである。そんなわけで、この『黙示』の作品も、それほど長く書き続けられはしなかった。「薔薇」が終刊号を出すと、それと運命を共にするように、俳人としての富澤赤黄男も遂に沈黙の彼方に消えてゆくのであった。
(朝日文庫版『富澤赤黄男集』解説より)
重信によれば「薔薇」の終刊、つまり『黙示』刊行の4年前から、すでに赤黄男は俳人として沈黙のうちにあった。それは、一字空白という技法がもたらす「詩」によって、俳句形式が徒に内向を強いられ、外部との自由な交通を閉ざされる運命にあったことの証左であろう。外部への欲望を失った言葉にとって、停滞と沈黙が避けられないのは止むを得ない。がしかし、安井にとって赤黄男の俳句的不運は、そのように冷静に片付けて済む問題ではなかった。なぜなら重信が書いているとおり、「決して停滞も後退も許されなかった」のが赤黄男だったからである。運命とは赤黄男に与えられた偶然の類ではなく、赤黄男自ら選択せざるを得なかったことだったのである。安井は、赤黄男の俳句に対するスタンスを痛いほどよく理解できたからこそ、「遅かれ早かれ啼き狂うことが驢馬の道である(『聲前一句』より)」と、他人行儀な断定でこの文章を終わらせることができなかったのだ。
ところで、どうしたことか、私はこの句の前だけにおいて事態が急迫する。私はこの句を冷ややかに正視することが出来ない。そこで狂える者は、他人ではなく、なんと昨日のわが阿父のような気がしてならない。狂える驢馬を見据える眼の主体は次第に血走り、充血する。
(『聲前一句』より)
安井にとって赤黄男とは、詩や前衛の代名詞でもなければ、ましてや実験や技法の喩でもない。それは常に赤黄男の署名とともに掲げられた一句として眼前に現われる。安井は、眼前の一句のなかで狂った運命を演じている赤黄男を、「冷ややかに正視することが出来ない」のだ。なぜなら「わが阿父」と言うとおり、安井にとって赤黄男は俳句における肉親とも言うべき「おじ」の存在に他ならなかったからである。そしてそれこそが、冒頭の問いに対する安井自身の正直な答えだったはずだ。ならば、この啼き狂う驢馬とは赤黄男の自画像であり、それを見据える「眼」の主体とは、赤黄男以外にあり得ないのではないか。赤黄男は、「俳句における「眼」の第一義というものの強さと弱さ(『聲前一句』より)」として、安井の俳句思考に欠かせない問題として存在する。そこでは見える見えないが問題なのではない。「眼」が自らの主体をかけるに相応しいほど正直だと、赤黄男が自らの運命として引き受けた事実こそが問題なのだ。(了)
*注:朝日文庫版『富澤赤黄男集』、『定本富澤赤黄男句集』ならびに書肆林檎屋版『富澤赤黄男全句集』では、〈男根の意識 たちまち驢馬啼き狂ひ〉となっている
田沼泰彦
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
