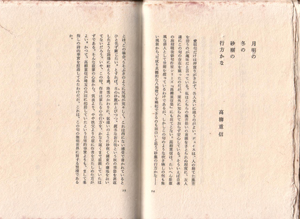
月明の
冬の
砂塵の
行方かな 高柳重信
『聲前一句』に収録された35篇の散文をその形態から眺めてみると、一見して俳句の世界で言うところの「評釈」であると見える。大方の文学作品がそうであるように、俳句作品も「読み」によって初めて作品として成立するものではあるが、それは17文字という極めて短い詩形であるがゆえに、その「読み」は読者によってかなりの振幅がある。というよりも俳句は読者の数だけ解釈があると言うこともできる。俳句作品の「評釈」とは、そうした読者の個性に委ねられた解釈としての「自由」を担保に、あらかじめ「親しみ」を持って作品を鑑賞するための、いわば俳句的慣習として機能してきたと言ってもよいだろう。
そうした機能において、「評釈」に問われるのは評者と作者との共感であり、評者にとって要はいかに作者のひととなりを理解したうえで作者の代弁者に成り得るか、という巧妙な「なりすまし」の詐術だろう。そこに他者という「審美眼」の入り込む余地はほとんどと言ってもいいほどない。つまり、俳句は伝統的に「批評」という行為を慣習のもとに自ら遠ざけてきたと言うことができる。なにもいまさら「第二芸術」と言うつもりはないが、「批評」という「審美眼」が手ぬるくなればなるほど、俳句に限らずあらゆる言語作品は「文学」から水をあけられる。文学にとって厳しい「審美眼」こそ不可欠な所以であろう。
『聲前一句』の著者である安井浩司の狙いとは、俳句を作品足らしめるための「読み」という前提を十分理解した上で、「評釈」という慣習的な作品読解が、どこまで文学行為としての「読み」に迫り得ることができるかを、あえて「評釈」の形態を装うことによって、俳句自らの問題として問い質すことにあると思われる。「評釈」を装うからには、その選句からして恣意的な身振りを通した方が都合がいいと言えるだろう。安井が取り上げている一句は、ほとんどがそれぞれの俳人の代表句ではない。むしろ安井にしか取り上げることができない句と言ったほうがいい。この高柳重信作品の一句「評釈」において、安井はそもそもの選句における「心得」を、その冒頭から読者に打ち明けている。
愛唱句だけは押売りがきかず、各人大いに違うのがよい。ヂョイスは、人の捨てた塵芥を拾うのが趣味だと言っている。私はこちらの塵芥拾いの意図をさとられぬ程度に、友人達にこの句の存在を窺ったのだが、案外に知られておらず安心している。
(『聲前一句』より)
「塵芥拾い」とはずいぶんな喩えだが、安井は高柳重信を師として、また同時に俳句の前衛を切り拓いていく同士として、数少ない尊敬し得る俳人と認識していたのは間違いない。この程度の揶揄で重信の真価が揺らぐはずもない、と言うのが安井の正直な気持ちであったろう。さらに邪推ではあるが、安井の心中にはおそらく、文学という土俵においては師であろうと弟子であろうと、読者として作者とは対等であるとの思いもあったのではなかろうか。いずれにしろ、「俳句評論」に集った重信の数多い門下生の中でも、安井ほど重信の本質を捉えていた弟子はいなかったのではないかと思われる。それは安井が書いた重信論を読みさえすれば、誰でもが納得するのではないだろうか。
安井の長篇評論は、『もどき招魂』(1974年・端渓社刊)と『海辺のアポリア』(2009年・邑書林刊)の2冊にまとめられているが、その中で重信に関する評論は、前者に「道化の華―高柳重信論」と題する1篇が、後者に「俳句形式の彼方―高柳重信の作品の性格について」・「『罪囚植民地』について」・「高柳重信の世界―その熾烈なる軌跡と業績」と題する3篇がそれぞれ掲載されている。このうち最後に挙げた「高柳重信の世界」は、重信の急逝直後に書かれた追悼文であるが、それ以外はいずれも重信の存命中に書かれた重信論である。本人に直接聞いたわけではないが、おそらく安井が今までに書いた重信に関する長篇の評論は、これら全部で4篇ということになろう。
安井の重信論は、4篇すべてが重信作品の本質にまで届く透徹した眼差しに貫かれており、余計とも思えるような考察は見当たらない。そればかりかそれぞれの論を比べて読んでみても、重複するような結論は全くといっていいほどない。つまりこれらを読みさえすれば、重信作品はもとより俳人重信の本質を理解することができる。そして安井が重信を論じることで描き出すこうした本流は、当然のことながら一人重信を越え出た俳句形式全体へと及んでいる。
安井が初めて書いたと思われる重信論「道化の華」は、自筆年譜によれば1972年に発刊された「俳句評論」131号に掲載されている。それは安井が36歳のときで、重信主宰とも言うべき同人誌「俳句評論」に参加してから8年目のことである。安井はその論を、「高柳重信とは、結局、俳句にとってなんだったのだろうか」という極めて単刀直入な疑問文で書き起こしている。その大方の評論を読めば分るが、安井は論じる対象に対して常に、その正面から対峙することを自らの流儀としている。なぜなら安井にとって論じるとは、対象の本質を掴み取るための行為以外であり得なかったからであり、本質を掴んではじめて、論じることが自らの文学に血肉をもたらすと確信していたに違いない。
それは、遂に、高柳重信という一回性、いな、重信という虚実の、ただ一人の私有にあるという一点にのみ、多行形式の意味があるということの以外に、私は答えようがないのである。(中略)重信が二人あってはいけないのである。おそらくは、一回性の前に全ての一回性が滅びつつ、なお最後の一人であることに、あの《亜流の精神》の最高の面目があるのではなかったか。私は、多行形式を、もっともらしい属性を振りかざしつつ、その効率のよさを説明する手合いは、何にもまして愚かしさの極みである、と思っている。多行形式こそ、無効で、不毛で、不能で、重信一人で終息して果てることにのみ、面目の全てがあるのではないか。はっきり言い切ってしまえば、俳句の一行が滅ぶとき、多行も滅ぶはずである。だが、多行が滅んでも、一行は滅ばない、という何とも馬鹿げた、しかし恐るべき理屈を烙印のように背負ってかきあげるところにのみ、いささかの多行精神の意味があったのである。
(「道化の華」より)
対象を論じる場合、まずその独自性に着目することが自然な成り行きであるが、安井は最初に重信を論じるにあたり、多行形式という重信独自の俳句表記に焦点を合わせている。つまり冒頭の疑問は、「多行形式は俳句にとって何なのか」と読み直すこともできよう。重信の多行形式とは、本来一行で表記されるのが当たり前の俳句作品を、意図的に改行して表記する方法である。そう書くと一句を正方形の色紙に墨書する場合に数行に分けるではないかと言われそうだが、それはあくまでも「便宜的」なお話であって、重信の多行形式は形式という言葉が付随するとおり、重信が俳句形式のひとつとして試行した方法で、そこには方法論としての明確な意図があると言ってもよい。さらに言えば、重信以前にも一句を数行に分けて表記した俳人はいたという話を聞くこともあるが、それは多分に恣意的(=気紛れ)以上ではなく、そうした表記を文学の方法として企図し作句したのは重信を嚆矢とするということだ。
安井もそうした師の俳句形式に対する考えには、十分過ぎるほど意識的だったはずである。「道化の華」の本文前に掲げられた、「悪い形式といふのは、吾等が変へる必要を感じ、そして自ら吾等が変へる形式のことである。(ヴァレリイ)/悪い形式といふのは、吾等が変へる必要を感じない、そして自ら吾等が変へない形式のことである。(ブルトン・エリュアール)」という二つの序詞からも、安井がこの重信論を俳句における「形式」の問題として語ろうとしていることが分かる。
しかし、そうした論点の明確さから遠ざかるかのように、その語り口は複雑というべきか難解というべきか、あえて言うと苦汁をなめるかのような苦々しい言い回しである。誤解なきように言っておくが、安井の論理にある種の曖昧さや逡巡が見られると言っているのではない。引用文からも分かるように、安井は重信に関する思考の全てを曝け出している。が、安井にとって思考とは、結論という形として掴み得るものではなく、掘り下げれば掘り下げるほど新たな確信へと姿を変えていく。それは考えが中途半端なのではなく、中途半端な確信に安心して思考を放棄し、結論めいた「正解」で論を取り纏めることを潔しとしない、安井自身の厳しさに起因しているのである。とかく「韜晦」と言われ敬して遠ざけられてきた安井の散文であるが、それは決して韜晦さを意図して書かれたわけではなく、自らの思考に対しどこまでも厳格な態度を貫こうとする真摯さ故の結果なのだ。
とはいえ引用文において安井は、重信の多行形式俳句に対し、一つのあからさまな断定を下している。換言すれば、「多行形式とは重信唯一人に意味のある形式である」ということであり、つまり結論を急げば、「重信が滅びれば多行形式も滅びる」ということであろう。重信以外の同時代俳人の多くは、さらにポスト重信とも言うべき多行形式試行者のほとんどを含めて、「多行形式の必然性はどこにあるのか」と、まるで免罪符を求めるかのように多行俳句の理論付けを模索し続けてきた。しかし安井は、そうした行為そのものを「愚かしさの極み」と断じている。
さらに、「俳句が滅びない限り一行は残るが、多行は滅び得る。が、そうした運命を背負ってなお書き続けるところに、多行の意味がある」と付け加えている。重信亡き後で、なお多行形式による俳句を実践している者には、身も蓋もない言い方と受け止められようが、安井の思考には確固たる覚悟が滲んでいる。ちなみに、筆者もここ数年に亘る安井浩司との付き合いの中で、顔を合わせるたびに性懲りもなく、多行形式の意味やら可能性やらを直接尋ねてみたりしたが、そのたびごとに、「多行は重信ただひとりのものだから」という、違えることのない答えを耳にするばかりだった。
安井のこの「重信=形式」論からは、俳句の底流を流れる「必滅」とでも言うべき思想を読み取ることができる。重信にしても、多行形式にしても、俳句という永遠性の中で、いつかは滅びる存在としてこそ意味を持つ。そうした重信即多行形式の本質を、安井は「演ずる」という行為に見出し、重信=「俳優」という喩にまで辿り着く。
高柳重信の本質は、何にもまして、演ずる(*傍点)ことにあった、とみなければならない。ここに俳壇という虚構があり、舞台がととのえられるとき、そこでは、もはや〈俳優〉の出現を待つばかりである。神もどきの翁が、神招ぎの虚実を演ずるように、重信は、いっぱしの俳優としての、自己演出と自己劇化を行なうばかりなのであった。(中略)近代の俳句が、おもえば俳句形式の思想のもとに、すぐれた俳諧師を産みつつも、ついに俳優としての、奇てれつな主体〈不在〉の人格がうまれたことはなかったのである。
(「道化の華」より)
中略以降は、重信の第二句集『伯爵領』を引き合いに出して語っている。『伯爵領』は、架空の領主である大宮伯爵を原作者に設定し、領地の地図までもが物語の舞台として添えられた多行形式による句集だが、こうしたフィクションは現今の俳句ではさして珍しい方法とは言えなくなった。しかし、俳句において作者という主体は、「俳諧師」としての明確な実在を伴うべきものだったはずで、そこに「主体不在の人格」=「俳優」を仮構したのは、重信が初めてだったと言えよう。本論の最後で安井は、「俳優は、滅ぶべきものの中にあって君臨する」というカミュの言葉を引用し、重信=多行形式の栄光を、いつかは死ななければならない俳優としての、「その劇中の一瞬にこそあるものだ」と断言し、俳句における「必滅」を演ずる「道化」として、ひとまず重信の方法論に決着をつけている。
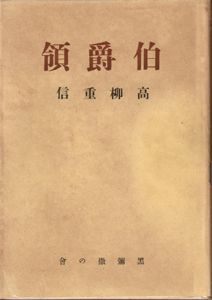
「道化の華」掲載から5年後の1977年、安井は「俳句評論」第174号に、「俳句形式の彼方」と題する長編としては2作目の重信論を書く。「高柳重信の作品の性格について」という副題が示すとおり、ここでは前回の形式論からさらに奥へと踏み込み、重信の作品テクストそのものの読解から、重信における世界構築(=創作)の本質を探っている。安井は本論において、重信の本質に迫るべき方法を「発(あば)き」と呼んでいる。「私はいま高柳重信論に関して、方法という言葉の不可能と不利を思い、この辺で、重信論に関するかぎり、『方法』という言葉を切り捨てるべきことである」と、大方の評論で半ば当たり前に行なわれている仮説の論理的な積み重ねによる「構築」を放棄し、むしろ「解体」のなかに重信の正体を「発き」出そうとしている。
であるならば、この論は「発かれた」断片の集積という、いわゆるパッチワークとして読まれるべきかもしれない。それは極めてポストモダニズム的な読解であると言うことができよう。逆に考えれば、安井にそうした読みを強いた重信という存在そのものが、その後の現代思想から現代芸術に亘る広いジャンルを席巻したポストモダニズムを予見していたと言っても過言ではないだろう。そうした「発き」の断片をいくつか引用してみたい。
この処女作(〈身をそらす虹の/絶巓/処刑台〉のこと*筆者注)を最後に、すべてこれ、自身に対する言いなだめ、もしくは魂鎮めの呪術様式を図ってきた
氏(重信のこと*筆者注)の俳句作品の言葉を組織し、最後にその言葉を認知するのは、親が子を嗅ぎ当てるように、血が認知する、としか思えないプリミティブな、かつ本態的なものがある。
氏の多行形式にうかぶ言葉や、さらに氏の俳句風景を逆算するかぎり、人間精神史の鬱積したところを暗澹と流れる血のようである。それは、激つ血を圧えに圧え、どこまでも人の嘆きを運び伝えようとする血のようである。
(以上すべて「俳句形式の彼方」より)
「言いなだめ」「魂鎮め」「呪術様式」「血」「嘆き」といった多分に民俗学的な用語で語られているため、とりわけ知的な論理性から遠いような気がするが、こうした断片的な「言い当て」を繋ぐ思考の軌跡を辿れば、自ずと安井の深い洞察の流れが浮かび上がってくるだろう。そして当然のことながら、洞察が深ければ深いほど、重信をめぐる問題は安井が重信を問う意味へと絞られてくる。「それをまずは先に答えておくなら、重信を問いつめることは俳句形式の独特の思想を問いつめることに全く等しい、ということである」と、ここでも安井は惜しみなく断言する。そして、「俳句という定型詩において、俳句形式とは自分にとって何なのか、ということを、しんじつ作品行為そのものの主題として俳句を書いた人は、氏が初めてであろう」と、重信の主題と自身の主題を重ね合わせる。
ここで注意すべきは、「俳句形式とは自分にとって何なのか」とは、「俳句形式とは何か」と違うということである。それは自ずと、「重信とは何か」=「俳句とは何か」というより原理的な問いを招き寄せる。
私は、高柳重信を問うことは、俳句とは何かを問うことだと言った。ただし、くどいようだが、俳句形式とは何かではなくて、俳句とは何かである。俳句形式とは、そういう問いの中で屹立させようとした、氏が自らの形式にかかわる方法的な言葉であることを断わっておく。
(「俳句形式の彼方」より)
「重信とは何か」=「俳句とは何か」という思考を辿るに際し、安井は重信の初期詩論である「敗北の詩」の一部分を引用している。それは「僕は、俳句形式の発生そのものに、この敗北主義をひしひしと感じる」で始まる重信による「俳句認識論」で、極めて大雑把に捉えれば、俳句というジャンル選択に潜む無意識な敗北主義という動機こそが、俳句の性格を決定する重要な要素であるという。
だが安井はこの論を一歩掘り下げ、「俳句=敗北主義」という客観的認識の裏側に潜む、重信自身の主観的な敗北をも発き出そうとしている。
俳句が敗北の詩であることと、そういう敗北の認識の中で、更に、俳句そのものに対する敗北という精神をもうひとつ含みもっていた。俳句それ自身の存在論とでもいうべき俳句の健康に対する敗北である。そういう二重性は、重信その人にとって敗北の敗北とでも言うべきものであった。
(「俳句形式の彼方」より)
この「敗北の二重構造」と安井が言うところに辿り着きさえすれば、重信と俳句との関係までは時間の問題であろう。これに続けて安井は畳み掛けるように、「重信にとって俳句とは何か」という、本論における極めて本質的な思考を導き出す。
俳句とは、氏の敗北の論理に対して、二重の敗北を痛く認知させるほどの勝利的な形式かもしれないのである。こう述べて、私が言いたいのは、重信の敗北の精神とは、逆説というよりも、むしろ氏の健康を支えるひとつの正説へ通ずるものではないか、ということであった。氏は、敗北の論理によって見事に救済されることが出来る。
(「俳句形式の彼方」より)
この一文に続けて安井は、「そこにしか重信の本質はありえない」と付け加えている。また、引用した部分には、「もしかしたら」という前置きがある。いずれも本質に至り着いたにしては物足りなさを感じさせる記述であるが、安井にとって本論の終着点は、あくまでも重信の「作品」の性格が孕む「テクスト」の本質であり、重信という俳句作家の存在論的本質ではない、という思いがあったためと思われる。だから次に進むべき思考の在り処は、「いささか謙虚に高柳重信の作品の原点とでもいうべきところへ戻りたい」と安井をして書かしめる。安井はそこで、重信の「作品の原点」=「テクストの本質」を、そのものズバリ「言いなだめ」ということばで表現する。「言いなだめ」という言葉に字義以上の意味は無い。「言いなだめ」として説明した部分を以下に断片的に引用する。
反抗と否定と、そこへ、言いなだめの心を加えることによって、この三位一体が高柳重信の聖なる精神だったように思えるのである。
重信にとっては、俳句はどこまでも言いなだめの様式として在ればよかったのである。
それは、マイナスの負荷を背負った己の血を言いなだめることである。鬱積の、しかも、そこに暗く激つ血をなだめることである。
わが国の定型詩人、つまり、このような血の人間が定型詩と出会ったとき、そこにはじめて稀有のすぐれた詩作品が導き出されるのではなかろうか。(中略)そういう暗闇の血、虐げられた血の運命、もしくは血の継承というものが、言葉の世界の細道を通って、ひそかにあるような気がするのである。
(以上すべて「俳句形式の彼方」より)
この「言いなだめ」とは、そもそも「重信とは何か」=「俳句とは何か」に対するひとつの答えとして提示されたものではあるが、安井が指摘するように、それは重信という一俳人はもとより、俳句というジャンルを優に越え出て、定型詩の全体にまで及んでいると言う。さらにそれは、定型詩という空間的な広がりはもとより、「血」という時間的な深みにまで到達していると付け加える。安井自身は、「もちろん、これは、別途に扱うべき私の予見的テーマであり」云々と、敢えて結論として断言することを回避し慎重な姿勢をとってはいるが、こと重信と俳句という範疇にとどめるかぎり、安井には動かし難い確信があったはずである。それは本文中の「ときどき、私の胸中に、氏は心底において俳句は嫌いなものではないか、という苦い思いが一瞬よぎることがある」という苦渋の表明がほのめかしていると思われる。「言いなだめ」とは、安井にとって、そうした苦しみと引き換えに到達した、何物にも変え難い確信に違いないのだ。
長過ぎる回り道をしてきたが、話をこの辺で『聲前一句』に戻しておいたほうがよさそうである。とはいえ、重信の一句に対する「評釈」を読むための前提として、こうした遠回りをするとしないとでは、受け止め方に隔たりが生じてしまうと思ったからである。たかだか500字を超える程度の小文とはいえ、安井が重信に関する文章を軽く書き流すはずがない。たとえ深読みと誹られようと、表面的に読んで分かったつもりになるよりはましであろう。逆に言えば、分かったつもりで読み流してしまうような陥穽が、意図的かどうかは別にして安井の文章のところどころには潜んでいる。
月明の
冬の
砂塵の
行方かな
砂塵の行方かな――とは、この場合、うそぶきのように尻尾が荒々しく、これは西にない感受で書かれているとひと先ず断じたい。とすれば、冬の砂塵がとびつつ、真冬なお月明という秋の季語を裏返したような語感に耐えうる処、降雪のかわりに、気違いのように砂吹く関東の大地をおいてないだろう。いや、この時、作者は寥たる心の行方を、かなり遠くまで直視していたはずである。
(『聲前一句』より)
振り返るに、「俳句形式の彼方」が「俳句評論」誌上に掲載された同じ年に『聲前一句』が刊行されていることから、この重信の一句評釈は「俳句形式の彼方」が書かれる以前のものと推測することができる。つまり、「道化の華」と「俳句形式の彼方」という2本の本格的な重信論に挟まれたこの掌論は、安井の中で重信に対する思考が深まる途上で書かれたことになる。と言うよりも、安井が重信と俳句の双方に亘る本質的な関係を見出しつつあった、ある種の手応えを感じて書かれたと言ってもよい。
俎上に挙げられた一句は、重信の第四句集にあたる『罪囚植民地』に収録されているが、それは単独刊行句集ではなく、すでに絶版になっていた2冊の多行形式句集『蕗子』と『伯爵領』を再収録し、合わせて『黒弥撒』と題され1956年に刊行されている。安井は、俳句総合誌「俳句研究」(1982年3月号)に掲載した評論「『罪囚植民地』について」のなかで、「『罪囚植民地』の諸作と、次の『蒙塵』の諸作に、高柳の真の代表秀作が含有せられているように思われる」と書き、とくに、「一巻としての緊張感は高い」として、前者をより高く評価している。その中でも安井は特に次の二つの句をあげている。
日が
落ちて
山脈といふ
言葉かな
しづかに
しづかに
耳朶色の
怒りの花よ
(『罪囚植民地』より)
「私なりに厳密に読んでいるつもりだが、これ以前(*傍点あり)の全作品は、この二作の高みに及ばないようだ。多行形式の充足性、というよりも自己完結性としての全円がムダなく閉じられ、完璧な自律を獲得している」(「『罪囚植民地』について」より)という多行形式の特性を見据えた重信作品の本質的評価の一方で、『聲前一句』ではそうした俳句形式や方法論とは別の観点から、それが多行形式であるという事実すら遠ざけつつ、重信が創出した世界そのものを真正面から捉えようとしている。
それを安井は、「この句のような吹き晒しの何も無い風景から、可成り具体的な〈地理〉を喚起できる」として、「砂塵の行方かな」という切れ方に注目する。つまり、「砂塵の行方」の行き着く先が「どこか」明確な場所ではなく、「行方」という動きを伴った方向であることによって、現出する世界に予定調和的な結末を仮構するのではなく、不可視の風景というべき未完の世界を創り出そうとする。また言うまでもないが、それは明確な場所が喚起する明確な叙情ではなく、どちらかと言えば「前途」や「行く末」といった「行方」の象徴作用による、世界構築の叙事と捉え得ることができよう。「可成り具体的な〈地理〉」とは、象徴によって今まさに世界が立ち上がりつつある「俳句という舞台」を指している。
こうした極めて文学的な世界こそが、紛れもなく重信の世界に他ならない。「これは西にない感受で書かれているとひと先ず断じたい」の「西」とは、もちろん「砂塵の行方」の元である強い風を日常とする、「関東」に対する「関西」の「西」であろう。が、それだけでは当たり前過ぎて、「行方かな」という切れ方を「うそぶきのように荒々しい」とわざわざ読者の前に晒すこともなかろう。ここは重信という俳句の「東」を象徴する存在の対比として、安井がもうひとり師と仰ぐ神戸在住の永田耕衣を、俳句の「西」なる存在と仮定してみてはどうだろう。ともに「文学としての俳句」という頂点を目指して、かたや「東」から「思想」というルートを登っていった重信と、かたや「西」から「宗教」というルートを辿った耕衣。こうした二つの登山道を常に見据えながら、己の辿るルートを模索する安井の思考を想像するに、あながち見当違いとも言えないのではないだろうか。
いささか飛躍し過ぎたが、話をもとに戻せばこの「評釈」の勘所が、「いや、この時、作者は寥たる心の行方を、かなり遠くまで直視していたはずである」という一文にあるのは間違いない。ここには、安井の中で次第に抜き差し成らぬ存在へと変貌しつつある、師たる重信の本質が像を結び始めている。それは、「道化の華」で描かれたフィクションを演じる俳優としての重信から、「俳句形式の彼方」における「二重の敗北」の果てに、「言いなだめ」という俳句原理を受肉した重信への変貌と言い換えてもよい。安井は「砂塵の行方」に、抜き差しならなければならないほどに、より遠くまでを直視しなければ済まされない、重信と俳句との相克を感受したと同時に、安井自身と俳句との、これから先に待ち構えているであろう困難としか言いようのない道行きを重ね合わせていたに違いない。
かつて、高柳重信が埼玉の戸田に起居していたという日常的事実よりも、まして名指しの詩的事実を捏造してみたわけだが、これは、この句の無明世界に対する冒涜であるか。
(『聲前一句』より結びの一文)
日常的であろうが詩的であろうが、俳句なる無明世界に事実を持ち込むことは、俳句的に言ってはなはだ興趣を削がれることには違いない。ましてやそれが捏造されたフィクションであり、リアルとしての自然とは相容れないものであるならなおさらであろう。しかし、安井はこの時すでに、重信の俳句世界が「無明」なる煩悩や迷妄とは無縁であることに気付いていた。「かなり遠くまで直視していた」との断定はそうした意味である。
そのうえで安井は、逆説的に「無明世界に対する冒涜であるか」と問い掛けてみせた。つまり、この句が一般的(=慣習的)な「評釈」では恐らく、「無明世界」として心地よく読まれて終わるであろうことを、あえて「捏造」して見せたわけである。安井にとって、そうしたテクストの字面になりすました評者の御都合主義的な「評釈」こそ、重信に対する冒涜と考えていた。そして、そうしたいわゆる「評釈」の取り澄ました自己完結を戒めると同時に、自らがその陥穽に落ちることのないよう自戒を込めているのである。われわれ読者は安井の厳しい審美眼とともに、自らへの厳格な視線を晒す恐ろしい文章の存在を、今一度認識しておくべきではないだろうか。
田沼泰彦
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
