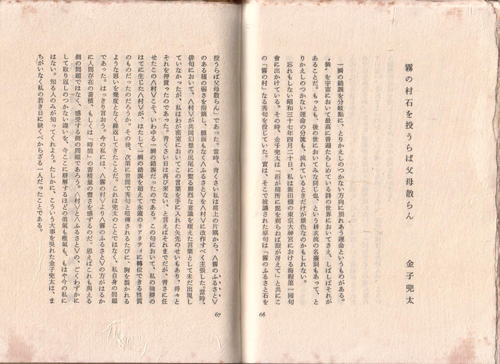
霧の村石を投うらば父母散らん 金子兜太
『聲前一句』に登場する35人の俳人のうち、現代俳句における「前衛」として括り得るのは18人である。そのなかには、西東三鬼・高屋窓秋・山口誓子といった、戦前からの新興俳句運動に携わった俳人も含まれるが、誓子のように92歳という長寿を全うした俳人は、その長い句歴を「前衛」という一言で総括するのには無理がある。1919年生まれの金子兜太は今年で94歳になるが、彼が「前衛俳句」に関わったのは、戦後復員して沢木欣一の「風」に参加してから、第三句集『蜿蜒』刊行までの20年余りと思われる。
この20年が長いかどうかは別として、金子兜太の一際長い俳句人生を語る際に、「前衛」という言葉は必ず付きまとうのも確かであろう。安井浩司は兜太を語るに際し、兜太が紛れもない「前衛」俳人だった頃の代表句を掲げている。が、その書き出しは、「一瞬の錯誤を分岐点に、とりかえしのつかない方向に別れあう運命というものがある」と、安井の数多い評論の語彙としてはあまり見慣れない「運命」という言葉で始まっている。
その「運命」というべき「一瞬の錯誤の分起点」となったのは、「忘れもしない昭和三十七年四月二十日、私は飯田橋の東京大神宮における海程第一回句会に出かけている」(『聲前一句』より)と語り出されるエピソードである。同人誌「海程」の創刊は、兜太の年譜によれば昭和37年の4月であるというから、この第一回句会はおそらく創刊記念として開かれたものに違いない。その特別な句会になぜ安井は出かけたのか。後に安井が在籍することになる「俳句評論」は、これより4年前の昭和33年にすでに高柳重信によって創刊されており、俳句革新を目論む文学的前衛の拠点として多くの若手俳人が集結していた。
「海程」と「俳句評論」は、前衛的な同人誌として一つに括られるが、俳句の世界で「前衛」といえば、それは伝統俳句の対抗勢力という意味であり、「前衛」そのものの多様性が問われることはほとんどない。しかし同人誌とはいえ、それぞれの主宰的存在であった兜太と重信では、「前衛」としての資質はもとより、「文学」性の有様そのものに大きな違いがあった。
簡単に言えば、俳句主体を社会との関わりのなかで表現する「社会性俳句」を主導した兜太は、俳句における「文学性」を、作者という主体による「社会批評性」と捉えた。彼が「造詣俳句六章」(1961年角川書店「俳句」に掲載)において唱えた「造型」とは、主体がメタファーを通して対象のイメージを感得し、それをそのまま俳句形式によって表現するというもので、兜太にとっては自分という主体こそが、俳句創造の最重要ファクターだった。それは、花鳥諷詠という自然崇拝を旨とする伝統俳句に対し、作者主体による人間中心主義と言ってもよいだろう。
一方で「俳句評論」を主導した重信は、俳句の原理を俳句形式と捉えることで俳句に対する批評の射程を定め、俳句を文学テクストとして読み解くために、言葉の象徴性や視覚性といった海外の文学理論を積極的に取り入れた。重信にとって俳句とは、日常における人間性や社会性とは相容れない、純粋な文学様式のひとつであり、自然崇拝や人間中心主義とも異なる、言うなれば言語中心主義であった。
このように兜太と重信の間には文学的な隔たりがある。二人を前衛として一括りにするのは俳壇状況論的な見方に過ぎない。つまり「海程」と「俳句評論」は似て非なる共同体であり、両者に対し二股を掛けることは、そもそもが無理な話であった。「前衛」を自認する俳人であれば、「海程」か「俳句評論」かのいずれかを、運命共同体として選択する必要があったと言うことだ。安井が「俳句評論」に参加するのは、この「海程」創刊記念句会より遅れること2年後の昭和39年である。高校時代から安井を知る俳句仲間の故大岡頌司は、このときすでに寺山修司の推挽のもと重信との知遇を得て「俳句評論」の門を叩いていたが、生前本人から聞いたところによると、当時の安井は「海程」からの誘いをしきりに受けており、「放っておくと入りかねない勢いだったので、むりやり袖を引っぱって重信のもとに連れて行った」らしい。つまり、安井が「海程」の創刊記念とも言うべきこの句会に出かけた背景には、気持ちの一部に「海程」という選択肢もあったということであろう。
安井の自筆年譜からもうかがえるように、若いころの安井は俳句ジャンルから飛び出して自由詩の同人誌や演劇活動に参加したり、また俳句実作だけではなく評論といった散文の執筆にも精を出していた。安井のように純粋に考えることが好きな性格が、「社会性」という実存主義的な問題へと引き寄せられたとしてもなんら不思議ではない。だからといってもし安井がこのとき「海程」に入っていたら、などと想像を働かせてみても、安井本人はもとより兜太においても、その後の俳句人生に影響したかどうかは神のみぞ知るでしかない。「とりかえしのつかない方向に別れあう運命」と言えども、「流れているときだけが景色」であり、「後の世においてみな同じ」(以上『聲前一句』より)と安井が書いている通りだろう。そうした前提を踏まえたうえで、「一瞬の錯誤」とはいかなる「運命」をもたらしたのか、当の「海程第一回句会」でのエピソードを語った部分を引用する。
その時、金子兜太は「沼が随所に髭を剃らねば眼が冴えて」と共にこの「霧の村」なる秀句を投じていた。実は、そこで披講された原句は「霧のふるさと石を投うらば父母散らん」であった。当時、青くさい私は席上の片隅から、〈霧のふるさと(ふるさとに傍点)〉のある種の弱さを指摘し、臆面もなく〈ふるさと〉を〈村〉に改作すべく主張した。当時、俳句において、〈村〉が共同幻想の尻尾に繋る鮮烈な意識を咥えた言葉として未だ出現していなかったが、私はわが密室においてこの言葉を手に入れた矢先のせいもあり、得々とそれを押売ったのであった。
(『聲前一句』より)
「一瞬の錯誤」とは、この〈村〉のことだと、安井は述懐している。そして、「私の強弁の果てに生じた〈村〉が、はたして一瞬の錯誤を超えて永遠のリアリティに転位できる性質のものだったのだろうか」と、昔日の自分の考えに自ら疑義を突きつけている。こうした疑いそのものから、すでにしてその間違いを確信していることが十分うかがえるであろう。
今の私には、〈霧の村〉より〈霧のふるさと〉の方がはるかに人間存在の蓄積、もしくは「時間」の蓄積量の豊かさを感ずるのだ。思えばこれも与える側の問題ではなく、感受する側の問題であろう。
(『聲前一句』より)
安井が問題にしているのは、〈村〉がいいか〈ふるさと〉がいいかという二者択一の是非ではない。要は、テクストの創造者(=与える側)とその読者(=感受する側)の、どちらの視点で作品を考えるべきかという、文学的な主体の有様を問うているのだ。安井は句会当時、たまたま語彙として新鮮味を見出していた〈村〉という言葉に、より理性的なイデオロギー(=共同幻想)を感受し、兜太の「社会批評性」により適した言葉として改作を提案した。それは、「わが密室においてこの言葉を手に入れた矢先」との一文から推察するに、作品の創造者という与える側の立場に立った提案だった。
『聲前一句』の刊行年(1977年)から推し量るに、この文章は当の句会(1962年)から少なくとも十数年を経て書かれたと思われるが、その間に安井が薫陶を授かった重信は、「作品は書かれたらもう作者のものではない。作者は一人目の読者にすぎない」(高柳蕗子「父の俳句」より)と言って、俳句における「感受する側」(=読者)の「与える側」(=作者)に対する優越性を示唆していたと言う。そうした師の教えに導かれた安井は、俳句形式から作者という創作主体を抹消しようとし、作者に代わる読者という読む行為による作品創作の可能性を、「構造」と名付けて俳句形式に召還しようとした。
こうした十数年における俳句に対する認識の深化が、安井をして兜太の代表句に対する前言の撤回を書かせたと言えよう。しかし安井はこの文章で、一言たりとも「一瞬の錯誤」の言い訳をしようとはしていない。もちろん認識の深化は安井自身の孤独な思考の賜物であろうが、そのうえで「こういう大事を呉れた金子兜太は、まちがいなく私の若き日に欠くべからざる一人だった」と、兜太に対する感謝の言葉でこの文章を締めくくっている。
それは、「青くさい」と自ら言うところの、当時無名の若手俳人だった安井の「押し売り」を、句会という大勢が見守っていたであろう公の場で受け入れた、兜太の俳人としての度量の大きさに対する安井の敬意の表明と読むことができよう。そうした兜太の人間的な恰幅のよさが魅力となって、「海程」が「前衛俳句」を代表する結社へと成長し、「前衛」の嵐が去った後もなお、その周りには信奉者の人垣が絶えることは無かった。では、兜太の俳句作品自体に現れた「前衛性」とはいかなるものなのか。兜太が「前衛俳人」と呼ばれた頃に刊行した第一句集『少年』・第二句集『金子兜太句集』・第三句集『蜿蜒』から、代表的な句をそれぞれ五句引用し、その「前衛性」を概観しておきたい。
原爆許すまじ蟹かつかつと瓦礫あゆむ
吾が顔の憎しや蝌蚪の水にかがみ
刈り草に吾れ伏し睡る貧者の村
青草に尿さんさん卑屈捨てよ
少年一人秋浜に空気銃打込む (以上『少年』より)
わが湖あり日蔭真暗な虎があり
果樹園がシヤツ一枚の俺の孤島
華麗な墓原女陰あらわに村眠り
朝はじまる海へ突込む鴎の死
彎曲し火傷し爆心地のマラソン (以上『金子兜太句集』より)
三日月がめそめそといる米の飯
人体冷えて東北白い花盛り
沼が随所に髭を剃らねば眼が冴えて
無神の旅あかつき岬をマツチで燃し
鶴の本読むヒマラヤ杉にシヤツを干し (以上『蜿蜒』より)
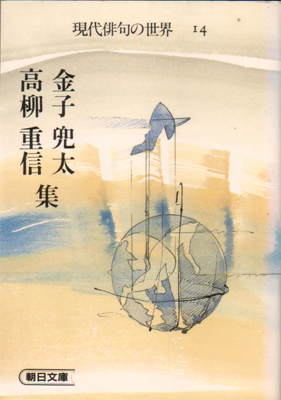
ブログに掲載された金子兜太略年譜によれば、第一句集『少年』の刊行は昭和30年(1955年)、兜太36歳のときと決して早い方ではなかった。19歳で全国学生俳句誌「成層圏」に参加したり、加藤楸邨の「寒雷」に籍を置いたりと、戦後27歳で復員してすぐに日銀に復職するなかで、平行して俳句活動も活発に行ってきた兜太ではあるが、「前衛」として俳壇に頭角を現すのは、34歳で神戸支店に転勤となり関西の前衛俳人との交流が始まって以降である。そして忘れてはならないのは、兜太における「前衛」が「社会性俳句」として始まったということだ。
ここに挙げた15句は、いずれも兜太が社会性俳句として作ったと思われるが、一言で社会性俳句といってもテクストに現れる「社会性」はまちまちで、社会における明確なターゲットを見据えた批判もあれば、社会との関わりの中の自己を描出した作品もある。が、多様な社会性を支えているのは、あくまでも作者という主体に他ならない。つまり、社会性俳句を作品として成立させるためには、そのテクストのなかに作者という主体が明確に存在しなければならないのである。掲出した10句に、「吾」・「わが」・「俺」といった主体を明示する代名詞が登場したり、たとえ言葉で明示されなくても、動作主としての主体(動作を仮託された場合も含む)が隠しようのない存在として明らかなように、社会性俳句において主体は、常に顕現を余儀なくされるのだ。
このように考えると、兜太にとっての社会性俳句とは、自身の欲望を十分過ぎるほど満たし得る器であったはずだ。では兜太の欲望とは何か。前掲のなかでも兜太の「前衛」を代表する一句である〈彎曲し火傷し爆心地のマラソン〉を見てみよう。それは、「彎曲し火傷し」てもなお、自己を表現したい一心で走るマラソンランナーの欲望である。つまり「爆心地」とは欲望のエネルギーの総体を意味し、兜太の強い自己表現欲の象徴である。
そもそも文学行為自体が自己表現という作者の欲望を源泉とするわけだが、兜太の場合は自己表現に対する欲望の強さと、長寿という肉体性としての時間とが相俟って、俳句ジャンルに君臨し続ける結果を俳句史に残すことになった。それはたまたま幼少より身近に俳句があったというだけで、言うなれば何でも受け入れるその無邪気さこそが、兜太をして前衛やら社会性やらへと向かわせる原動力となったのである。そこに文学性という物語を書き加えることは可能であるにしても、兜太と前衛俳句、兜太と社会性俳句、さらに言えば兜太と俳句との間にさえ、文学が入り込む余地はほとんどないと言っていい。
曼珠沙華どれも腹出し秩父の子 (『少年』より)
兜太最初期の代表作として人口に膾炙している一句であるが、この句から「前衛」や「社会性」という言葉を想起するのは困難だろう。高柳重信を中心とした「俳句評論」が、「俳句形式」への問い直しを始めるにあたって、無季・定型破壊という「反俳句的行為」に打って出たのとは、あまりにかけ離れているとは言えないだろうか。この句には「曼珠沙華」という季語もあるし、「切れ」という技巧による「取り合わせ」の効果が句を俳句たらしめている。まさにこの一句は、前衛俳句がアンチを突きつけた「伝統俳句」そのものである。しかし、兜太の読者にしてみれば、この一句ほど金子兜太という俳人を雄弁に語る作品は他にはないと思うに違いない。
安井が改作を迫った表題句に話を戻そう。句会に投句された原句と言われる〈霧のふるさと石を投うらば父母散らん〉は、「霧のふるさと」=「父母」を「散ら」そうとして、作者=兜太という主体が「霧」めがけて石を放ったと考えれば、句の構造自体は単純と言ってもいい。つまり、霧の立ち込めたふるさに石を放るという行為は、「父母=権威」の破壊を象徴している。さらに言えば、「霧のふるさと」=「父母」ということは、兜太にとっての権威とは己を育んだ源郷に存在しているという意味であり、そうした権威は霧のように見た目は曖昧だが、触知し得る確かな存在として示されている。つまり兜太にとって権威とは逃れ難いものとして認識されており、それを破壊する行為とは何かと言えば、いわゆる青春時代に誰でも経験する巣立ちの儀式の象徴であり、この句は自身を社会的存在と意識し始めた青春時代の回想と読むことができる。
このように単純なのは構造だけでなく意味もまた然りで、とかく「前衛」というと評釈を寄せ付けない難解なイメージがあるが、この句に限らず兜太の句の多くは、無意味を含めて意味や象徴の明確な読解し易いテクストである。句会での安井もおそらくこうした解釈のうえに立ってなお、「ふるさと」と「村」にこだわったと思われる。比較の問題ではあるが、仮名表記の「ふるさと」にはノスタルジックな叙情を喚起する効果があり、一般名詞としての「父母」との相性は極めてよく、象徴作用によって容易に結び付くことができる。一方で「村」は、「群(むら)」と同源であることから、物の様態を示す働きがあるため、叙情を喚起するには向いていない無機質な言葉である。
しかし、「村」という言葉が無機質であればこそ、そこに叙情のアンチテーゼとしての「思考」が入り込む余地がある。安井が「村」という一語に、「共同幻想の尻尾に繋る鮮烈な意識」を見出したのは、当時の社会主義的な時代背景を抜きにしても、極めて自然な成り行きであったと言えよう。「思考」は「観念」の記録を積み重ねる行為であり、そこに「感情」の入り込む余地はない。けだし「思考」と「叙情」は相容れない。当時の安井にとって、「ふるさと」と「父母」という叙情を掻き立てる言葉の組み合わせは、冷静な思考を弱めるだけの作用にしか思えなかった。「〈霧のふるさと〉のある種の弱さを指摘し」とあるのは、叙情に流されることで主体の批評性が弱まると考えたからに違いない。
俳句における「前衛」とは、俳句が本質的に遠ざけてきた「作者」という与える側の「主体」を、作品テクストに半ば強引な形で顕現させようとした文学行為であると言うこともできる。そこには、近代以降の文学における作者主体の優位性が投影されている。しかし、俳句とは本来、作家主体を表現するものではなかった。むしろ感受する側としての「読者」の「読み」によって、初めて作品として成立するものとも言える。そこにこそ作者の意図を超えるものとしての、「俳句形式」という必然性が出来すると言える。安井の俳句に対するラディカルな思考が、そうした俳句原理へと至った結果、あらためて「一瞬の錯誤」をして、「これは兜太のことではなく、私自身の問題であった」と言わしめたのである。
田沼泰彦
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
