
くるしくて はるかのはな は ひらくかな 野田 誠
太平洋戦争を挟む戦前戦後にかけて吹き荒れた俳句革新の風は、結果として「伝統対前衛」という俳句史にとって都合のいい対立構造によって図式化されるに至った。都合のいいとは、この対立が「伝統の勝利」という誰もが納得する結末を前提にしているからで、そのため前衛陣営は、伝統という名の正統に対するアンチテーゼという大雑把な切り口で総括され、「前衛俳句」という俳句の境界をも越え出ようとした文学的多様性は、問い質すべき価値のない共同幻想として、自由というロマンチシズムの彼方へと追い遣られた。
「前衛」とは一過性の熱病に過ぎず、その多様性を云々してみても、所詮は伝統至上主義が作り出す俳句史・俳壇史からは、いずれ抹消されるのは致し方ないかもしれない。いわゆる「前衛俳句」が、多様性としての様々な才能を呼び集め、瞬く間に俳壇にバベルの塔を打ち建ててみせたことは、かつて銀幕を飾った名優たちの競演よろしく、色褪せたとはいえ今なお輝いて見えないことはない。が、それもまたロマンチックな幻想に過ぎない。現に競演の熱気を頁の余白に残す数々の前衛俳句句集にしても、ひところ高騰の極みにあったその古書値は、ここ数年におけるニーズの衰えとともに下落の一途を辿り、いまや一部の好事家の収集癖によってのみ、かろうじて底値が支えられているというのが実情だ。
「野田誠を書くことが、私情の延長点に埋火を吹くことでしかないとしたら、以下を恕されよ(『聲前一句』より)」と、前衛俳人野田誠を語るこの文章の冒頭で、安井浩司は読者に対し異例とも思える許しを乞うている。安井にとって野田の俳句作品とは、普遍的な評価に耐えうるテクストではなく、個人的な好みでしかないとでも言うのだろうか。言うまでもないが、安井がこの『聲前一句』で書いているのは、俳人とその俳句テクストとの間に交差する美の評価だ。それはあくまでも安井個人の審美眼によってもたらされるには違いないが、少なくとも安井自身は、この己の審美眼に対し絶対とも言うべき普遍性を確信している。そのうえでなお私情云々と言い訳するほどに、野田誠という俳人とそのテクストは、安井が私情を注ぐに足るどのような俳句的価値があるのだろうか。
安井はかつての野田が、「私達の眼前にかりそめにも“兄者”としての存在格を主張していた」ことを引き合いに、「今は姿をたたんだ鳥海多佳男、鎌田矩夫、船川渉、故松岡緑男等もくるめて、彼等が何者かである以上に、たしかに私たちの兄者風情であった(以上『聲前一句』より)」と、戦中派世代の前衛俳人の名前を並べる。彼等は均しくみな、高柳重信を中心に集結した「俳句評論」の創刊同人であり、重信が提示した象徴主義的な美学や俳句形式への方法論的アプローチといった「文学」を、俳句作品として体現すべく多様な俳句実験に勤しんだという意味で、「前衛」と呼び得る俳人達と言えよう。
野田は、安井を始めとした戦後派俳人の兄的存在の中でも、抜きん出た存在だったようだ。野田の第一句集『敗走』には、重信の門下生が句集を刊出する際の約束事でもある、重信本人による序文が掲載されているが、五頁にも亘る長い序文は門下生の中でも特別と言えよう。
思うに、それは、あの戦後の、燃えようとして燃えることが許されず、消えようとして消え去ることが出来なかつた、人間の生命のたとえようのない悶えの中で、生まれ育つてきたものであつた。たとえば、富沢赤黄男・僕・そして野田誠は、その時それぞれの死地を脱して、それぞれに戦後という時期を迎えていたのであつた。
(中略)
不毛の底に身をよこたえながら、無意味の意味を切実に創りあげようとする、強すぎもせず弱すぎもしない、いわば生きた人間の内部からの突きあげが、僕たちに同じような方向を与えたのであつた。それが同時に、僕たちの、自分自身を愛する愛し方でもあつた。
(野田誠句集『敗走』より高柳重信による「序」の抜粋)
重信の書いた数多くの散文には、あからさまな伝統俳句批判はほとんど見当たらない。多くはこの序文のように、ナルシスティックと思えるほど執拗に自己を追い駆ける欲望に満ちている。重信の周辺に身を置いた俳人の多くが、こうした重信の「自分自身を愛する愛し方」に共感するあまり、伝統へのアンチテーゼという狭量な文学性を意味する「前衛」という呼称を思ったほど好まない。今なお彼らの多くが、「重信も俺も前衛ではない」と断言するのは、敗者を意味する「前衛」に対する嫌悪ゆえであり、それが「前衛」自らが「前衛」の検証を拒否するという不幸を生み出していると言えよう。が、それはひとまず置いておき、安井の私情の先で燻っている野田誠という埋火を探ってみたい。
私が「俳句評論」のかなり高揚した酒宴で野田誠に初めて出会ったときのことである。どうしたことか、時も半ばに彼は早々といかにも淋しそうな身振りで横になってしまった。(中略)俳人に水平の論理はない。斜めでもいいから背骨は天地を指すことだ、と思っていた私には、少壮俳人のあの横臥は、何とも不思議であった。横たわりの演技だけが、イロニイと呼びたき唯一の彼の方法論だったのだろうか。
(『聲前一句』)
安井は野田にまつわるこのエピソードを、章の三分の一に当たる行数を割いて記述しているが、エピソードそのものの面白さを伝えるのが目的ではなく、野田の俳句にまつわる何事かを象徴させようとした違いない。また、「俳人に水平の論理はない」にしろ、「斜めでもいいから背骨は天地を指すことだ」にしろ、それは俳人としての野田の人間性を評しているというよりも、その作品テクストに対する言及のはずである。それを明らかにするため、『敗走』から掲載順に数句を引用する。
ひろしまや蝌蚪には深き地の窪み
子守唄 風に聞かせて 原爆墓地
ひろしまよ ゆうべいちまいの花の黙(もだ)
黍枯れて 夜は 恍惚と墓標群
黍枯れて アスハオンナヲステニユク
暗い沖から くらい眼をした鳥が来た
ケロイドや 目に乾燥の花ためて
まさにこれから 老いた列島 傷かがやく
原爆症死また。棒の尖にて皿まわり
ぬかるみに嵌った俺の眼を 愛す
ひろしまと書けばすなわちその文字燃ゆ
十年や わが韜晦は 風に聞け
ある日見知らぬ街角曲る古風な楽隊
弔砲を 柩の中で われ聞けり
おさらばの 地球の 裏の 軽気球
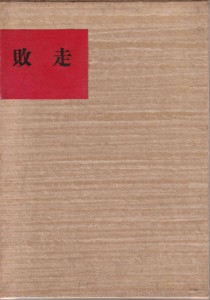
「ひろしま」「原爆墓地」「ケロイド」「原爆病死」という言葉から、野田が故郷の広島で原爆を体験していることが窺われる。しかし、だからといって野田の句には、当時の俳壇を賑わせていた「社会性俳句」のような、社会主義的なイデオロギーへの傾倒は見られない。たとえば同じ原爆を詠んだ句でも、社会性俳句の中核として活躍した金子兜太の有名な一句、〈湾曲し火傷し爆心地のマラソン〉(『金子兜太句集』1961年)は、原爆に対する批判意識によって句が成立している。だが野田の原爆詠からは、おそらく身近な人の命を奪い去ったであろう当の原爆に対する怒りは片鱗もない。むしろそこには、原爆という究極の不幸をも耐え忍んでしまう、そうした自分自身への愛しさすら感じられる。
野田は、原爆被害者という非日常的不運を背負った自分を、あえて無為なる日常性を希求する存在としてネガティヴに描こうとしている。そこには自分自身に対する皮肉な視線が感じられる。しかし、それが自嘲的であればあるほど、「イロニイ」としての言葉の強度は増すと言えよう。と同時に自らを、ロマンチシズムのもとで反語的に飾り立てることも可能となる。〈まさにこれから 老いた列島 傷かがやく〉は、野田が自嘲の果てに辿り着いた、自己肯定の一形態として読むことができる。だからこそ野田は、「いちまいの花の黙(もだ)」となって、自らの不運を声高に罵ろうとはしない。不運とは折り合いをつけた上で、ひたすらそれに耐えてみせることの方が、野田の体質には合っていると言ってもよい。
そうした野田の忍耐は、いわゆる戦中派世代に特有のもののようだ。先に引用した重信の序文にあるように、それは「人間の生命のたとえようのない悶えの中で、生まれ育つてきたものであつた」に違いない。そして「それが同時に、僕たちの、自分自身を愛する愛し方でもあつた」と言うとおり、自愛というべき代償によって、野田は自らの不運をモチーフとした俳句をひたすら作り続けた。野田の俳句にとって不運という逆境こそが、願ってもない演出手腕の見せ所なのだ。そこには戦中派のしたたかさが叙情として息衝いている。
『敗走』は、己が淋しさへ淋しさの衣を幾重にもかぶせることによって、自己の青春をひたすら慰めることに尽きた書物である。それが、青春の奪回を、即慰藉の儀式に変形しなければならなかった戦中派の最も悲しい部分の露呈であった、と私が言ったとてもう何も始まらぬ。
(『聲前一句』より)
安井は、野田を始めとした前衛俳句の戦中派世代を、兄として正面から見据えたうえで、その俳句能力を冷静に評価すると同時に、その作品テクストを厳しく読み解いている。その評価にしろ作品読解にしろ、「戦中派の最も悲しい部分の露呈」という結論に対し、それ以上何も付け足すことはない。そのうえでさらに安井は、「そのか弱い部分へ誰も墨を塗ることは出来ないだろう」と突き放したように書き付ける。つまりこの野田誠の章全体が、戦後派の前衛俳人である安井浩司による、戦中派前衛俳句の総括になっているのだ。
ここで改めて「戦中派」と「前衛俳句」について確認しておきたい。終戦から2年が過ぎた1947年、すでに前年「群」・「薔薇(第1次)」という2冊の俳句誌を創刊していた高柳重信が、富澤赤黄男のもとを初めて訪ねた。このときより、俳句の近代化を唱えた戦前からの新興俳句運動が、伝統との対立構造のなかで俳句形式の純粋実験を試行する「前衛俳句」として再スタートを切ったと言えよう。
ただし、この「前衛俳句」を牽引したのはあくまでも重信その人で、戦前派として太平洋戦争勃発と同時に処女句集『天の狼』を刊行していた赤黄男は、重信の師として第2次「薔薇」(1951年創刊)に加わり作品欄の選者を務めたとはいえ、「前衛俳句」の先陣を切ったと言うよりも精神的支柱の役割を与えられたに過ぎない。戦後文学としての「前衛俳句」は、重信が創刊した同人誌「俳句評論」(1958年)のもとに結集した、少壮の戦中派俳人によって支えられていたのである。
「俳句評論」創刊時、重信はすでに4冊の単独句集を刊行していたが、戦中派の前衛俳人が自らの句集を世に問い始めるのは、その大方が「俳句評論」創刊後に集中している。主な個人句集を刊行年順に並べてみる。鎌田矩夫『火』(1952年刊)、加藤郁乎『球体感覚』・松岡緑男『風炎』(以上1959年刊)、野田誠『敗走』・島津亮『記録』(以上1960年刊)、船川渉『黒漫漫』・東川紀志男『陸橋』(以上1961年刊)と、さながら百花繚乱の有様を呈している。だが、これら戦中派のほとんどが処女句集一本のみか、せいぜい第二句集までで前衛としての俳句活動に終止符を打っている。
もちろん加藤郁乎のように、昨年83歳で亡くなるまで、たとえ細々とではあっても俳人として執筆活動を続けていたのも紛れもない事実ではあるが、郁乎が前衛俳人として俳句の最前線に切り込んだと言えるのは、処女句集の『球体感覚』と第二句集の『えくとぷらすま』のわずか二冊である。それは野田や島津であっても同様で、確かに二人ともここに挙げた句集以外にも何冊か個人句集を刊行してはいるが、「前衛」として評価され得る句集と言えばこれらに絞らざるを得ない。
比較の話をするわけではないが、戦後派として括られる安井は、一昨年刊行された『空なる芭蕉』が15冊目の単独句集であるし、同世代の大岡頌司にしても享年62歳という短命にもかかわらず、生前は全句集を含めて12冊の句集を刊行している。そしてそのいずれもが、その時々の文学の最前線にコミットし得る成果として、若手俳人に対し多大なる影響を与えてきている。こうしてみると、野田誠を始めとする戦中派の前衛俳人がいかに短命であったかが分ると言うものだ。
ある意味で、俳句というものは、自らの生命が、自らの生命の絶えだえとした継続を願いながら、自らを言いなだめ、自らを励ますはかない燃焼でもあろうか。だから、こうした句集に残るのは燃え尽きた灰ばかりである。そして、一握・一握の灰を手にしながら、そのかすかな温もりに、過ぎし日の、ありし日の生命のはかない燃焼を再現することこそ、まさしく、句集を読むという言葉にふさわしい行為であろう。
(野田誠句集『敗走』より高柳重信による「序」の抜粋)
俳句に必敗の美学を重ねていた重信にとって、『敗走』はその題名からして自らの美学に対する共感と映った。「燃え尽きた灰ばかり」が残る句集とは、重信の脇を固めた戦中派にとって快い褒め言葉だったに違いない。しかし、安井にとってその言葉は、野田の俳句作品を極めて冷静に評価していると同時に、野田誠という前衛俳人の行く末を正確に暗示していると捉えられたはずである。さらにそれが、安井に前衛俳句の末路を予感させたとしても、なんら不思議な話ではない。
だからといって安井は、そうした“兄者”を頭ごなしに見下すことはない。「文学は、こういう時こそ抜群のデモクラシイを発揮し、すこぶる優しい表情をなす」と、あからさまに擁護こそしないが、字義通り優しく見守ってあげようとする。「集中、私はこの仮名文字によるアラベスク風の一句しか拾えないという断定にいたる(以上いずれも『聲前一句』より)」のは、野田が「前衛俳句」という自らの俳句的短命に殉じようとした覚悟に対する、後続世代からの敬意に満ちた返礼であろうか。
くるしくて はるかのはな は ひらくかな
『敗走』の世界には確かに敗者の美学が満ちているが、それは敗者の開き直りでも負け犬の遠吠えでもない。勝ち目が無いということは苦しいことには違いないが、野田はあえて「くるしくて」と心をさらけ出す。「はるかのはな」とは、敗者であるがゆえに愛すべき野田自身のことであろう。それは勝ち目からあまりにも遠く離れ過ぎていて、「はるか」という形容詞でしか表現できないが、「くるしくて」と口に出せば、必ず花開くと野田は信じている。主格の格助詞「は」の前後にある一字空白が、野田の確信の深さを表している。その確信こそを安井は、「紛れもなく野田の肉体の秘所」だと書き継いでいるのだ。
文学という世界がそうであるように、俳句という世界には勝ちも負けもない。あるとすれば、己という世界の中に限っての、己自身を相手とした勝ち負けであろう。しかし、文壇や俳壇には、勝ちと負けとが当たり前に存在する。俳壇での勝ち負けは俳句史の一行に書き加えられ、めったなことでは書き換えられない。俳人たるもの、己と俳壇のどちらで勝ち負けを決めるか、必ず選択を迫られる。まれに才能と度量に恵まれた、例えば重信のように、いずれにおいても勝負する者が現れるが、野田はそうではなかった。
野田は、早々に俳壇に背を向け、己との勝負のみに徹した。野田は、いずれにしろ勝負は始めから負けると分かっていたが、それが俳壇を選ばなかった理由ではない。むしろ負けると分っていたからこそ、あえて己の中での勝負を望んだと言えるだろう。己の中の勝負に関する限り、勝てば喜びにありつけるほど単純ではない。負けることで得られる喜びにこそ、野田は己を賭けるべきと確信したのだ。
安井は、そうした野田の確信に、現世での勝負にかまけてとかく見失いがちな、「前衛」としての矜持を認めたのである。だからこそ安井は、自らの「前衛」を常に確認するために、「ゆえに私は『敗走』をふところに仕舞いおき、あの日の野田誠の横臥をいつまでも、忘れぬであろう」と書き留めたことである。
田沼泰彦
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
