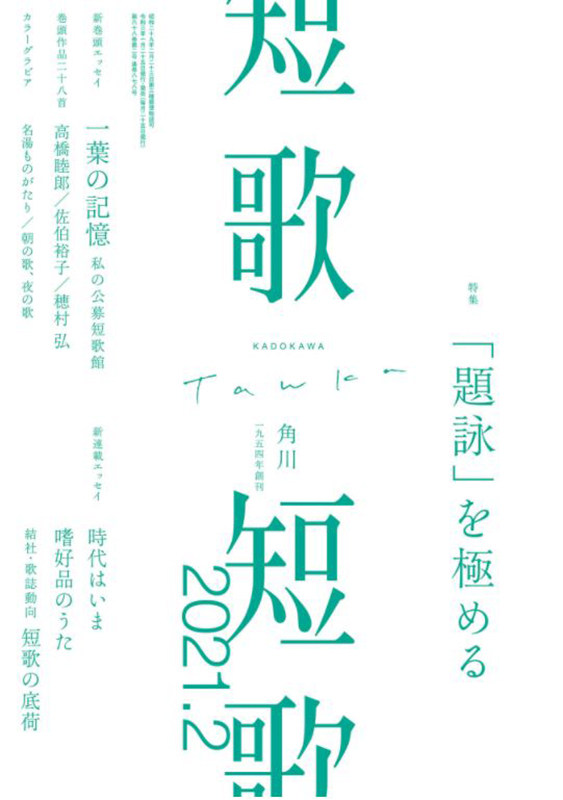
今号では特集「「題詠」を極める」が組まれています。明治時代頃まで俳句では運座(句会)で季題などを出して大勢で句を詠むのが一般的でした。幕末天保時代頃には運座で一番優れた句に景品を出すお遊びの句会が盛んになり子規派によってそれらが低レベルの月並俳句と批判されたことはよく知られています。ではこういった句会の源流はやはり短歌にあるのでしょうか。歴史的に言えばそうなのでしょうが俳句と短歌では質が違うでしょうね。
歌合は、左右で歌を発表し、優劣を競う遊び、あるいは儀式であった。そこには必ず題が存在している。その題は、競うための土俵の役割をしていた。
この時代、相撲や競べ馬、賭弓などの行事と同じ次元で、歌合は行われたのである。相撲なども、日本文化の典型のようにいわれることがあるが、土俵という枠を設けて、技を比べあうものである。
また、競べ馬も、現代の競馬とは違い、二頭で競い合った。賭弓についても、二人で弓を射って、勝った方には、賭物が与えられ、負けた方には罰の酒が課された。こうした催しは、いずれも晴れの儀式といっていいだろう。
加藤孝男「「題詠」の歴史と意義」
特集巻頭に加藤孝男さんが総論「「題詠」の歴史と意義」を書いておられます。短歌は日本の伝統文学なのでその気になれば千年近く前にまであっさり歴史を遡れるところが便利というか恐ろしいところです。古代から近世までは娯楽の少ない時代でしたから歌合がお遊びの要素を持っていたのは間違いありません。また平安時代には歌は歌人の知性や感性すべてが試される表現でした。なので歌合には選りすぐりの歌を出していた。歌人たちのプライドがぶつかり合う場でした。
ただ「晴れの儀式」――つまり源流に神事があるのは無視できないでしょうね。加藤さんは日本最古の和歌集である「万葉集にも題詠は存在した」「後に和歌の題として多く詠まれる雪月花は、題のなかでもトップクラスである」と書いておられます。古代から平安中期くらいまでの和歌は風景描写が多かった。それが変わってくるのは平安中期から鎌倉初期頃です。
さて、こうした題詠がいつ頃定番化したかといえば、院政期である。その典型的なものは『堀川院百首和歌』(中略)であろう。これは組題という形式のさきがけになっている。(中略)
たとえば「恋」のテーマも、かなり細分化されている。「初恋」「不被知人恋」「不逢恋」「初遇恋」「旅恋」のように、結題といわれる二つ以上の題を組み合わせている。(中略)
藻塩焼く浦べに今夜旅寝して我さへこがれ人を恋ひつつ 藤原隆源
「旅恋」の題詠である。塩をつくるための藻塩を焼いている。そんな風に恋焦がれるあの人を思いながら、浜辺で今夜は旅寝をしている、という歌なのだ。定家も、この『堀川院百首和歌』に大きな影響を受けた一人であった。(中略)
来ぬ人をまつほの浦の夕なぎに焼くや藻塩の身もこがれつつ 藤原定家
も、隆源の歌に触発されたと考えていい。(中略)定家の歌では、来ない人を待っている女性に、なり変わって詠んでいる。(中略)定家によって、旅寝の男の心情から、男の訪れを待つ女の心情へ歌は転換されてしまった。そして、掛詞や歌枕などを自在に使って、一首を表現したのである。もうこのあたりで題詠は、一つの極点に達したのだといえなくもない。
同
『万葉集』から『古今和歌集』を経て『新古今和歌集』の成立までには四百年近い時間が流れています。この間の和歌の変遷は凄まじいものがありました。『古今』は和歌で初めて春夏秋冬の部立てを設けた勅撰和歌集です。和歌の神事という側面は俳句にはほとんど受け継がれませんでしたが春夏秋冬の部立ては今では俳句の専売特許のようになっています。つまり俳句は古代的な風景描写(雪月花)に近しい表現でありだからこそ子規は『万葉』に注目したところがあります。俳句革新の成果を活かしやすかったのはもちろん短歌の基層がそこにあると考えたのです。
では『万葉』の風景描写中心の和歌と『古今』以降の和歌の何が一番違うのかといえば「恋」でしょうね。『古今』の「恋」の部立ては収録歌も多く非常に目立っています。恋を言い換えると「わたしがこう思うこう感じるこう考える」の自我意識表現が『古今』以降主流になるということです。これは現代まで変わっていません。
俳句が虚子的に言うと「花鳥風月」の表現であるのに対して短歌の基本は自我意識表現です。もちろん現代では様々な短歌が詠まれていますがある程度短歌を量産しようとすれば自我意識に頼らざるを得ない。コロナや政治批判や失恋や老いを歌うにしても歌人の自我意識を表現するから歌を量産できる。
大局的に見れば俳句は風景描写で短歌は自我意識表現となるわけですが現代では短歌の自我意識が変化せざるを得ない時期に差しかかっています。戦後文学の時代は歌人たちは社会に対立するような明確で強い自我意識を持つことができました。風景描写に仮託しても強烈な自我意識で風景を喩化して独自の表現を生み出すことができた。しかし現代では社会に対峙できるような強烈な自我意識を維持しにくくなっている。私の生活を詠むことはできますがそれが社会と対峙するところまでには至らない――パブリックな表現になり難くなっています。
そのため短歌で人間存在共通の幼年時代を詠ったり私にしか関わりのない極私的な風景の見え方や感じ方を詠う歌が増えています。それはそれでこれからの短歌の一つのトレンドになると思います。ただ私の表現を極私にだけ向けていたのでは限界がある。どこかで私と社会が対立し拮抗し合うようなパブリックな表現も取り戻してゆかなければならない。でないと短歌の社会的存在意義が薄れてしまう。
短歌の一種の社会化の方法が自我意識の極限的肥大化による客体化であり続けるのは今後も変わらないと思います。いわゆる絶唱です。ただ絶唱は基本的に対社会の敗北の歌でありまた意図的に詠むとパターン化しやすい。ここぞという時にしか使えず多用すれば表現が平板になってしまうところがある。時代時代の新たな言語表現と私性が結びついて初めて歌を量産可能なある時代固有の社会的表現が生まれます。
そんな方法の一つのヒントに加藤さんが定家の歌で指摘なさったペルソナがあるかもしれません。定家は隆源の歌に触発されて――一種の本歌取りして――「来ぬ人をまつほの浦の夕なぎに焼くや藻塩の身もこがれつつ」を詠んだ。隆源の歌は私の心情独白ですが定家の歌は「来ない人を待っている女性に、なり変わって詠んでいる」。
もちろん短歌では自分で体験していない震災や家族のいざこざなどをまことしやかに詠めば批判を受けることが多い。しかし定家が実践したようなペルソナ手法による歌は私性の枠組みを超えて透明な何ごとかの本質に届いている気配があります。その究極的な歌は実景かどうかいまだ議論がある「見渡せば」でしょうね。歌合の初源にあった神事に触れているような気配です。なかなかに高度な技法となりますがそういった過去の富を活用するのも短歌には許されています。
高嶋秋穂
■ 加藤孝男さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■










