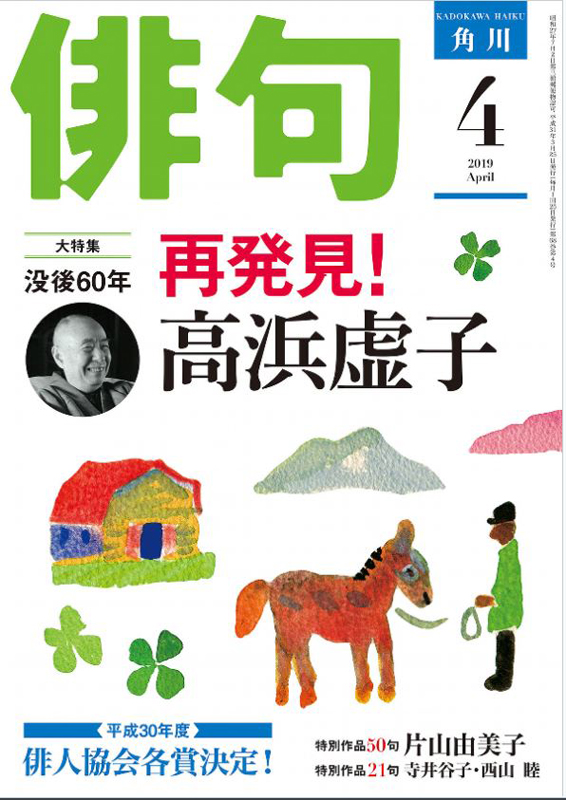
高浜虚子が偉大な俳人であるのは間違いない。ただ虚子を論じる際、必ず俳壇の粘り気のある闇がついて回るものまた間違いのないことである。高校の国語や日本史の教科書を開くと虚子は正岡子規の弟子であり、河東碧梧桐と同列に解説されているのが普通である。しかし俳壇では違う。虚子こそが近現代俳壇を代表する俳人であり、子規も碧梧もそのほかの優れた俳人も、虚子以下の同列として扱われることが多い。簡単に言えば俳壇内と俳壇外では虚子の評価が大きく異なる。どちらが正しいのかと言えば、評者が俳壇に属しているのか属していないのかによって決まる。俳壇村の見解を正しいと信じこむのは勝手だが、それによって失われるものも多い。
文学の世界で高く評価される作家の仕事は、大別すれば二種類に分かれる。最初に新たな文学を始めた人と、優れた文学作品を生み出した人である。俳句で言えば芭蕉が最初に新たな文学を始めた人、というより俳句を文学として確立した人である。芭蕉が神格化されるほど高く評価されたのはそのためだ。子規も新たな文学の創始者である。明治維新後の近現代俳句の基礎を作ったのは子規である。虚子はそれを受け継いで一般化した。新文学の創始者とは言えない。
優れた文学を生み出した作家はどうだろう。俳句では江戸後期に現れた与謝蕪村が俳句中興の祖ということになる。その作品レベルはとても高い。蕪村は明治初期までほとんど評価されていなかったが、子規らによって注目され、今では芭蕉に次ぐ偉大な俳人という評価が定まっている。子規は自分たちの俳句革新運動は蕪村の試みを一歩進めただけだと書いたが、子規俳句革新、すなわち近現代俳句の基礎は蕪村文学の延長線上にある。
では虚子は優れた文学作品をたくさん生み出したのか。子規代表句を口にできる人は多いが、虚子代表句をすぐに挙げられる人は一般社会では少ない。まだしも碧梧の「赤い椿白い椿と落ちにけり」の方が一般によく知られているかもしれない。勝負は決まっているかのように思われるのだが、俳壇村では一般社会の常識というか評価基準が通用しない。「流れゆく大根の葉の早さかな」といった、虚心坦懐に読めばどこが名句なのかねと首をひねってしまうような句が、一万ページを超えるような神秘化された評釈で論じられている。
俳壇という場所がまったく信用できないのは、作品の評価基準が極めて恣意的だからである。江戸はもう二〇〇年近く前なのでザックリ捉えることができるが、芭蕉を頂点とした蕉門と蕪村を代表とする天明俳句が作品・理論両方で屋台骨になる。明治維新以降なら子規を中心とした子規派(「ホトトギス」初期)、それから4S、新興俳句、人間探求派、重信門の前衛俳句と兜太の社会性俳句が大きな柱になる。そうなるはずなのだが、俳壇では虚子「ホトトギス」が異様なほど過大評価されている。重信前衛は完全無視だが、それほどではないにせよ、新傾向俳句を始めとする俳句界を泡立たせた前衛的試みはほとんど論じられない。
作品について言えば、中村草田男や永田耕衣らの作品は近現代俳句で突出している。しかし俳壇では加藤楸邨の方が偉大であり、耕衣は俳壇外の作家や読者によって支持されているだけだ。まず特集などが組まれることがない。
誰からも信頼される文学の〝壇〟は、客観的かつ公正な文学史認識と作品評価によって支えられる。しかし俳壇村ではどちらも失格だ。俳壇村の文学史認識は歪んでいる。作品評価はさらに歪だ。芭蕉、蕪村を偉大な作家とすることに異論のある村人は少ないだろうが、子規と虚子になるともう激しく主観が混じる。作品評価になると、おらが村のその片隅の部落長の作品が一番で、なぜなら公私両面でとってもお世話になっているからということになる。これは結社という名の部落に属している村人だけではない。インディペンデントを自称する結社フリーの村人であっても、結局は非常な身内贔屓だ。
俳壇村では上から下まで客観的でも公正でもない。文学なら過去の優れた作家も現代作家と同列に論じられるはずなのに、俳壇村が重視するのは徹底して現世である。今現在俳壇村で力を持っている俳人が一番偉いのであり、文学史的にも作品評価の面でも、目を覆いたくなるようないい加減な批評で褒めちぎる。雑誌で過去俳人を特集しても、その系譜上、ということは結社後継者の現主宰をヨイショするのが主眼である場合が多い。そして村長か部落長が亡くなればたいていの場合、その功績はあっという間に忘れられ、次に控えていたナンバー2だか3だかが現世の王様になる。俳壇村では誰もが取るに足らない現世利害に従って行動する。そしていつしかそれにすら気づかなくなる。村人になるには通過儀礼が必要で、その通過儀礼を意識的にであれ無意識にであれ受けてしまった者は、村の特殊性に気づかないまま一生を終える。
といったことを、虚子を論じる際には頭の片隅に入れておいた方がいい。虚子は偉大な文学者だが、今の歪んだ俳壇を作り出したのも虚子だからである。ただこの歪みは江戸時代の、芭蕉死後から俳壇の常態として続いていたのであり、その意味で虚子は俳句の申し子かもしれない。虚子がいなくても俳壇は今と大同小異だったはずで、そのあたりから虚子文学を考え、俳句と呼ばれる文学の特異性を考えた方がよい。
江戸時代には俳句は庶民の高尚なお遊び芸だという暗黙の了解があった。現代の俳壇村は口を開けば俳句は文学だというが、誰が見たって江戸時代と変わらない。現代でも実態を直視すれば俳句はお遊び芸の習い事文芸である。誰が見たってそれが俳句の基本。これについてはやっきになって文学と二項対立させない方がいい。俳句は絶対に文学一色に染まらない。真っ先に身内の俳人が裏切って結局はお遊び習い事文芸が幅を利かせる。俳句が文学となる要件はお遊び文芸と文学を対立させるのではなく、むしろお遊び文芸とは何かを考えそれを極めることにある。徹底してやればお遊び文芸の裏側に突き抜けるはずである。
みささぎのお衾あれば霜の花
力学的海鼠くくるに銀の紐
ふりはじめの雨にもどるか冬土筆
水鳥のあの世の水を灯しけり
ふくろふや母には蝋燭の火傷
雨の日の芹の青きに深入りす
紫雲英野のひかりは盥母がゐる
おぼろ夜の垂れ絹だれもまもらない
神は野にかげろふ座りして遷る
(鳥居真里子「だれもまもらない」)
特集の虚子論を引用して、もっと具体的に虚子文学について書こうかと思ったのだが、止めにする。俳壇について書くと疲れる。老いも若きも偉い俳人もヒラ俳人も俳壇というわけのわからない場所が好きなはずがなく、むしろ嫌っているわけだから、多少なりとも変わった方がいいのだが、何を書いても何をしても変わらないだろうという徒労感が強い。俳壇に雁字搦めに取り込まれていることすらわかっていない俳人が多いわけだから、外からの視線で相対化するしかあるまい。
ただ優れた俳句作品はやっぱりいい。鳥居真里子さんの連作「だれもまもらない」は秀作だった。「雨の日の芹の青きに深入りす」は記憶に残る。俳句のセオリーを少しだけ超脱した書き方である。「だれもまもらない」連作には写生俳句では表現できない時間が流れている。
岡野隆
■ 高浜虚子の本 ■
■ 鳥居真里子さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■









