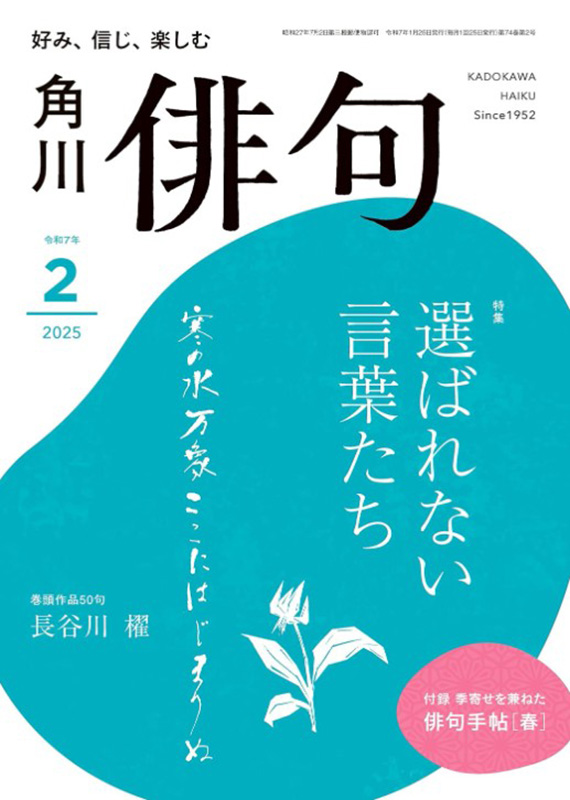
句誌でも歌誌でも自由詩の雑誌でも同じだが、頭っからパーッと読んでゆく。どの詩誌もメインは作品である。ただ小説誌が小説がメインコンテンツだというのとはちょっと違う。詩誌に掲載されるのはいずれ歌集、句集、詩集に収録される(だろう)作品の一部である。全体像は見えない。特に俳句は短歌、自由詩と比べても部分的作品からは全体像が見えにくい。
短歌は基本わたしはこう思う、こう感じるの自我意識表現だから入院されているんだな、お元気で飼い犬と散歩しておられるんだな、など作家の日常が手に取るようにわかったりする。自由詩は何でもアリの表現だが、何でもアリというのは自発的自由の制限と同義である。だから詩の書き方に特徴が出る。たいていの詩人が一定の書き方で詩をまとめるのでその書法からおおまかに詩人が何をしようとしているのかがわかる。
俳人もある書き方を選ぶとそれでずっと go on になるのが常ではある。同じ結社に所属していると主宰と同じような書き方になってしまうこともしばしばだ。ただ短歌や自由詩と異なり句集ごとに大きく変化することは少ない。テーマがあると言えばあるのだが非常に微細でよほどその俳人の仕事を丹念に追いかけていないとわからない。
それもそのはずで俳人は生涯に一万を超える俳句を詠んだりする。次々句集が出る。歌人もかなりの歌を詠み残すとはいえ俳人には敵わない。もちろん小説や自由詩でそんな数の作品を書けるわけがない。ではなぜそんなに大量の俳句を書けるのか、書くのかと言えば作家が自己の無意識層を探っているからである。いい俳句を意識して書こうとして書けるなら世話がない。というのが俳句の難しいところだ。即詠や書き飛ばしで名句が生まれることもしばしばである。俳句を手なずけるのは非常に難しい。
ゆく秋の水のなかより水の声
湯の宿の湯の神さまや初時雨
梟のふくろふを呼ぶ夜となりぬ
能面の湯宿に掛かる湯ざめかな
石投げて石に当りし十二月
亀井雉子男「狐火」16句より
今号でダダッと頭から作品を読んでいって視線が止まったのは亀井雉子男さんの「狐火」16句だった。亀井さんの良い読者ではないが16句にまとまりがある。引用の句すべてが「水」「湯」「梟(ふくろふ)」「湯」「石」を繰り返している。同じ言葉の繰り返しなのだがくどさがない。もちろん意識的手法だろう。
夜神楽の鬼に色気のありにけり
ふるさとのおむすび山も眠りけり
雪女日暮の辻を曲りけり
閉校の日時計に春立ちにけり
同
「けりかな」俳句は詠嘆の理由が見あたらなければ凡句になりやすい。しかし「神楽」「おむすび山」「雪女」「閉校」と読者の心を遠くに誘う単語が的確に使われている。蕪村を感じさせる俳句である。
命みな粒子となりて冬天へ
地球ごと暮れゆく街の枯野かな
言霊の絶叫凍て空へ劈くる
天の子の駆け降りくるか朽野
どの人も透けて見えたる冬日かな
狐火の方へ腑引かれをり
樹々から光球燦々二月尽
辻村麻乃「ゼロポイントフィールド」12句より
もうお一人、ページをめくる手が止まったのは辻村麻乃さんの「ゼロポイントフィールド」12句だった。「粒子」「地球」「言霊」「天の子」とあまり俳句では使わない言葉が並ぶが前衛の意識はないと思う。連作タイトル「ゼロポイントフィールド」にあるように、何もないゼロポイントにすべての句が引っ張られ引き上げられている気配だ。上空の一点から見下ろしたような句だと感受すればよい。
亀井さんと辻村さんの俳句で手が止まったのは、お二人とも構えが大きいようで小さいからである。多くの俳人はある書き方の中で表現内容を豊富にしようとする。季節の移ろいを書き自分の日常を書き社会事象や天災などにも目を配ってバラエティ豊かな俳句を詠もうとする。しかしそういった表現内容=意味内容の広がりが俳句の要になるのかというとそうではない。俳句は構えが小さい方がよい。しっかりとした求心点を持つ方が逆説的に表現内容=意味内容が広がる。逆に言えば表現内容=意味内容に心を砕く俳句は俳句群を束ねる強力な求心点が曖昧になる。
あまり良い読者ではないので推測に過ぎないが、亀井さんも辻村さんも俳句を量産できる作家だと思う。乱暴なことを言うが俳句を量産できない作家は俳句という表現の入り口にすら立っていない。特に前衛を気取る作家はそうだ。難しげな俳句を書いているだけで句を量産できない。書けばいいというものじゃない、作品の質がすべてだというのならかつての高柳重信や加藤郁乎、安井浩司らに比肩していると誰もが認めるような句を書いて見せることだ。前衛は俳句表現の最先端なのだから前衛を気取るだけの頭の悪い俳人には無理だ。
もちろん単に俳句を量産するだけで良い句が書けるわけではない。ただ求心点を持っている作家は意識の裏側に抜ける可能性がある。俳句は徹底して逆接の文学である。スリッパで俳句の後ろ頭を叩くことができる作家でなければよい句は書けない。
鶴山裕司
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


