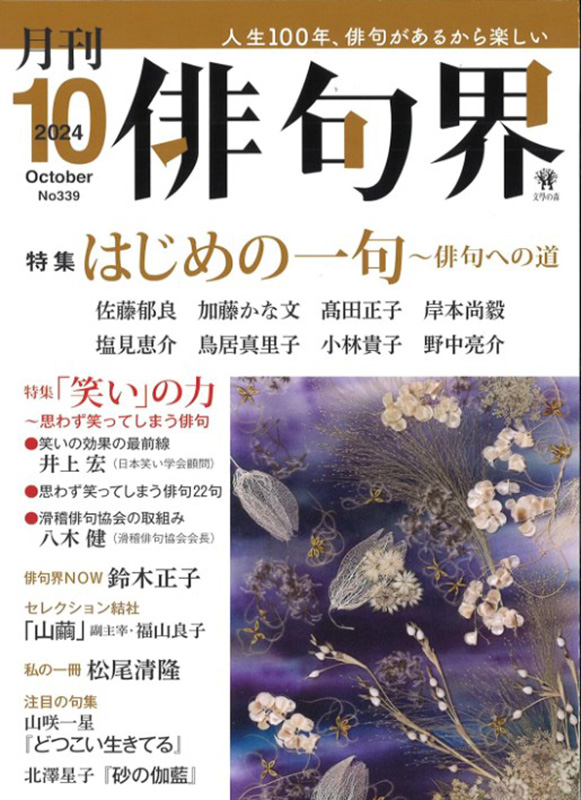
わずか11ページだが「特集 笑いの力」が組まれている。日本笑い学会顧問の井上宏さんと滑稽俳句協会会長の八木健さんが執筆者。井上さんはノーマン・カズンズ著の『笑いと治癒力』などを引用して笑いが健康に良いことを力説しておられる。八木さんは俳人なので俳句の滑稽を論じ「思わず笑ってしまう俳句22句」を選んでおられる。
そもそも「俳句」の「俳」とは「滑稽」という意味である。(中略)
ところが、この百年余、俳句からこの一番大事な本質である「滑稽」が失われていると感じて、滑稽俳句協会を平成二十年に設立した。協会は、超結社の集まりである。
かつて、昭和二十一年に仏文学者の桑原武夫が「俳句は芸術というは、おこがましい。せいぜい第二芸術だ」とこきおろした。これに対して、文芸批評家の山本健吉が「俳句は滑稽、即興、挨拶という独自のテーマを持つ立派な芸術だ」と反論したのだった。
昭和二十二年、民俗学者でもあり、国文学者でもあった柳田国男は「人を楽しませるものが芸術なのに、今や俳諧(滑稽)という言葉の意味が判らない時代になった」と俳壇の状況を嘆いた。
しかし、平成になって俳壇を見回した時、桑原や柳田に指摘された当時の状況と、さほど変化はないんじゃないかと思った。俳句からは「俳」が消え、人を楽しませるものではなくなっているではないか。
俳句に滑稽を取り戻したい。滑稽を追究してみたい、これが滑稽俳句協会設立の動機となった。
八木健 滑稽俳句協会の取組み「俳句は滑稽」
サラッと読めばおっしゃる通り。八木さんが書いておられるように「そもそも「俳句」の「俳」とは「滑稽」という意味」だが、俳句はじょじょに滑稽要素を削ぎ落としていった。昭和俳壇はもちろん平成、令和になってもその傾向は強い。だから元の「俳=滑稽」を取り戻そうじゃないかという主張である。
ただ申し訳ないがほぼ全ての俳壇内議論と同様に、俳句に「滑稽を取り戻したい」という主張は瑣末なテニオハ的お遊びである。原理的思考になっていない。
桑原武夫が「俳句は芸術というは、おこがましい。せいぜい第二芸術だ」と批判したのに対し、山本健吉が「俳句は滑稽、即興、挨拶という独自のテーマを持つ立派な芸術だ」と反論した話が出てくるが、この桑原と山本の議論、ぜんぜん噛み合っていない。桑原は俳句は二流の芸術だと批判したのである。それに対して山本は俳句には滑稽、即興、挨拶があるから「立派な芸術だ」と反論した。が、それは問題の審級の混同に過ぎない。
桑原の「第二芸術」という批判には当然だがまず「第一芸術」が措定されている。それは何かと言えば小説、自由詩、戯曲などの自我意識文学である。作家独自のアイディアや感性によって生み出される唯一無二の芸術作品を桑原は「第一芸術」と措定した。山本が主張した「滑稽、即興、挨拶」がたとえ俳句独自のものであっても(そうは思えないが)それによって俳句が桑原措定の第一芸術に昇格するわけではない。山本は桑原の批判の要点が見えていない。あるいはあえて問題の審級をズラして俳句には独特の特徴がいくつかあるので「立派な芸術だ」と強弁しただけのことである。
桑原の指摘をまたなくとも俳句は決定的に作家の唯一無二の自我意識表現を欠落させている。俳壇内トリビアリズムではテニオハの使い方にも作家独自の自我意識が表現されていることになるがそれは井の中の蛙の戯れ言だ。小説も自由詩も戯曲も真剣に読まず茫漠と狭くてぬるい事大的俳句万能主義、俳句最強幻想に浸っているからそんな戯言が吐けるだけのことである。
俳句の滑稽要素は俳句が桑原的な第一芸術、つまり明治近代以降の自我意識文学ではないことから生じたものである。ピラミッド型の結社ではなく座がそれを象徴する。『猿蓑』などの完成度は高いが、蕉門俳人たちは日常的にお遊びの座を開き膨大な俳句を詠み捨てていたはずである。俳句文学として見れば芭蕉元禄と蕪村天明時代に俳句は極めて質の高い表現となったが、その間も俳句はずっと座のお遊び文芸だった。明治の子規門も同様で俳句の基本はお遊び文芸だと言えるほどである。ただ俳人たちが必死に遊ばなければ優れた滑稽句は生まれない。
俳句が絶対的に五七五に季語の有季定型形式でなければならないのは言うまでもない。それに反発するのは無駄だ。そしてこの俳句定型を守れば必ず膨大な類句・駄句が生まれる。季語がある限り嬉しい悲しい寂しいといった自我意識表現は花鳥風月によって写生的に表現するほかないからである。この無限に続くかのような類句・駄句の海を活性化させるのは意外性である。滑稽はその大きな要素だ。有季定型の凪いだ海を活性化させる。
では座のお遊びの、滑稽によって俳句は本質的にどういった表現を目指しているのか。それは俳句が桑原的第一芸術、明治近代以降の自我意識文学ではまったくないことを真正面から受けとめれば自ずとわかるはずである。意外性は人間の言語的無意識層から生まれる。言語的無意識層の奥深くから言葉を呼び出すことができればそれはある本質を射貫く。俳句が滑稽だけでなく絶望と紙一重の諧謔を有している理由もわかるだろう。
俳句が滑稽を失ったのは近・現代俳人たちが中途半端な自我意識文学幻想を受け入れてしまったからである。小説、自由詩、戯曲と同質の文学に憧れそれを夢見たからである。桑原に反発するのは矛盾だ。むしろ桑原が第二芸術論で喚起した第一文学定義に毒されている。俳壇では無限ループのように桑原の第二芸術が言及され俳人たちに都合のいい理屈をこねてそれは間違いだよねで終わるのが常である。しかしなぜ執拗に無限ループのように言及され続けるのか。要は未だに桑原の第二芸術論すら超克できていない。もっとちゃんと物事と考えた方がいい。
岡野隆
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


