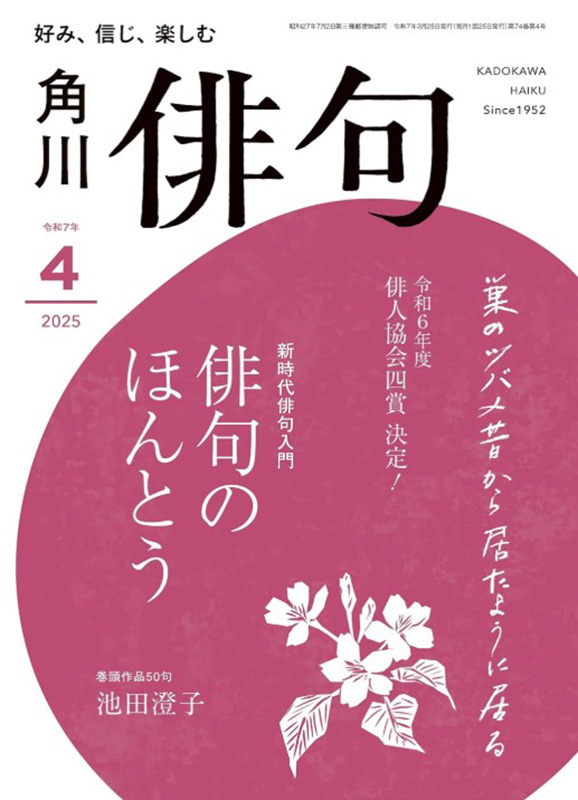
今号から栗林浩さんの「戦後八十年 還って来なかった兵たちの絶唱」が短期集中連載されている。反戦俳句は戦中の新興俳句(京大俳句)が有名だがこれは戦没者の句を取り上げた評論である。反戦の意識はなく、杓子定規に言えばいずれも戦争翼賛句である。
戦後八十年になる。日本は稀有に長い平和な日々を楽しんでいる。世界に目を向ければ、大きな戦争や紛争が起きていて、それを他人事のように見ていやしまいか。いまや国民の九割が戦後生まれである。
平和のために俳句が大きなことを成せるとは思わないが、この時機に、戦争で亡くなった俳人たちの俳句を通して、戦争を思い起こし、平和を確認することも必要ではなかろうか。戦場から還って来れなかった兵士たちの絶唱にも似た俳句を読み、当時の状況を再認識したいと思った。
栗林浩「戦後八十年 還って来なかった兵たちの絶唱」
有意義だがなかなか難しいテーマである。戦争は起こるときには起こるとしか言いようがない。後から振り返れば原因や前兆はいくらでも指摘できるが、長い時間をかけてある国や集団がどうしようもなく追いつめられた際に戦争という最後の手段を選択する。利害対立が極限まで高まった時に起こる衝突であり究極的利害解消方法だと言えないことはない。その意味で戦争は外交の一種であるというのは正しい。
すがすがし暴風のあと月清し
これでよし百万年の仮寝かな
大西瀧治郎
大西瀧治郎は特攻の生みの親だそうだ。終戦の翌日割腹自殺したが介錯を禁じたので二十時間苦しんで亡くなったのだという。大西は特攻隊の兵士たちに「君たちは神である」と言い、また「特攻は外道である」とも言ったのだという。要するに大西には選択肢がなかった。物資欠乏の中で少しでも敵に被害を与えるために特攻という手段が生み出されたわけだが、それが無益かもしれぬと分かっていながら大西海軍中将は上層部の命令に従って兵士らを送り出すほかなかった。
靖国で会う嬉しさや今朝の空
古野繁実 中尉
ちるために咲かうとあせる若桜
溝川慶三 軍曹
即菩薩即煩悩のこの日かな
岡部三郎 伍長
あす散ると思ひきれぬ桜かな
小屋哲郎 軍曹
潔く散れや筑波の若桜
末吉実 中尉
大君のみ為に死ねと言ひし母強し
山田勇 少尉
出撃や特攻日和蟬の声
岡安明 少尉
出で立つや心もすがしるりの色
亥角泰彦 少尉
散る花の心を問うな春の嵐
千葉三郎 一飛曹
こういう俳句を読んで厳粛な気持ちにならない人は少ないだろう。これらの句を詠んだ人が自分の父親や兄弟だったらと考えると胸が痛む。
僕は一九八〇年代に大学を卒業したがあの頃はまだ左翼が社会主義思想と直結していた。講義で散々反天皇制を叩き込まれたわけだが今ではそう簡単じゃないと思う。靖国問題一つ取り上げても、古野繁実中尉のように死んだら靖国に祀られるのだと考えていた若者が大勢いた。遺族もそう思っていた。中韓を中心に靖国アレルギーは根強いがそれは極東裁判で一切戦争責任を問われなかった天皇制への反発であるのは言うまでもない。靖国神社の門には天皇家の菊の御紋がある。天皇訪中は実現したが日帝時代に皇国主義を強制された韓国への訪問は今後も難しいだろう。ただそういった政治とは別に、靖国に祀られると思って戦死した人たちの遺骨を別の施設に移すのはなかなか困難だと思う。
さてこれからがまあ本題である。特攻で戦死した兵士たちの俳句は揺れる心を垣間見せながらお国のために死ぬことを肯定している。こういった俳句は銃後で書かれた翼賛俳句・短歌よりも戦争というものをまざまざと身近に感じさせてくれる。一兵士に選択権はない。死ぬとわかっていても突撃と命令されれば突撃し、飛行機やボートで敵艦に体当たりせよと命じられれば結局それに従う。それが戦争であり兵士であるということだ。
詩人の鮎川信夫は『戦中手記』を書いた。鮎川は出征に際して「じゃあ」とだけ言い残して南方の激戦地スマトラ島に派遣された。『戦中手記』で兵隊になるのは楽だという意味のことを書いている。つい昨日まで頭でっかちだった文学青年がそう簡単に兵隊になれるわけがない。しかし日本軍はその方法を作り上げていた。徹底した暴力による服従である。鮎川は上官から何度も殴られたと書いている。そうした圧倒的暴力の中で兵隊になっていった。鮎川の親友・森川義信はそんな一兵卒として亡くなった。鮎川はマラリアに罹患して帰国することになったがそうでなければ確実に戦死していたはずだ。もし戦争が起これば再び似たような仕組みが出来上がるだろう。詩人の石原吉郎も入隊と同時に死を覚悟している。
戦没者の俳句や短歌を読んでかわいそうだと思うのは大事なことだ。が、戦争になれば多くの若者に逃げ道がないことを周辺資料を読むことで理解するのも大事だと思う。文学は豊かな世界の上澄みであり母国が戦争に巻き込まれれば何の役にも立たない。大声で母国の政治的・軍事的危機を唱えている人たちは熱烈な愛国者であり、いったん事が起これば多少の苦悩を見せながらすぐに戦争翼賛に回るに決まっている。戦争になれば愛国者の方が生き残れる可能性が高まる。兵隊に取られたら愛国の士として勇ましく死ぬか黙って死ぬかの二択だ。どちらも悲惨であるのは変わらない。
戞々とゆき戞々と征くばかり
網膜にはりついてゐる泥濘なり
蛇よぎる戰にあれしわがまなこ
富澤赤黄男
冷雨なり眼つむり步く兵多し
空爆の衝動快く憩へり
葬り火か飯を焚かむと來て禮す
片山桃史
富澤赤黄男と片山桃史は新興俳句俳人である。赤黄男は明治三十五年(一九〇二年)生まれ、桃史は大正元年(一二年)生まれで十歲年下だった。戦争は日中戦争から太平洋戦争へと続くわけだが、初期に兵隊に取られた者は中国戦線に送られた。盧溝橋事件直後は激しい戦闘が起こったがすぐに日本軍と国民党、共産党軍の三つ巴の膠着状態になり中国戦線の日本軍の戦死者はさほど多くなかった。しかし南方に送られた兵隊の多くが戦死した。赤黄男は生き残り桃史は東部ニューギニアで戦死した。
赤黄男や桃史は戦地から日野草城の「旗艦」に俳句を送り掲載された。特攻隊兵士の辞世の句に比べるとおしなべて穏やかな句だ。戦地の悲惨を描いているがギリギリの所を衝いている。それもそのはずで、従軍兵士だから大目に見られることはあっただろうが当局批判などできるはずもなかった。赤黄男の方が観念的だが両者とも基本は叙景句である。
俳句や短歌に限らず多くの兵士が遺書を書き残した。俳句、短歌の辞世が散文遺書より切実だということはない。文学の問題として考えれば俳句は確かに新興俳句俳人らを中心に日中戦争から太平洋戦争初期にかけて反戦句を生み出した。社会主義者たちを除けば積極的に反戦の姿勢を鮮明にしたのは新興俳句俳人たちだけだったと言える。
ただ戦後にまで当局批判を持ち越した俳人はほとんどいない。新興俳句俳人たちの反戦句は必ずしも新しい俳句の姿として根付かなかった。俳句の問題としてはそれも考えてみなければならないだろう。「戦争は俳句にならない」と言った虚子の言葉をよく考えてみる必要がある。晩年の金子兜太は「アベ政治を許さない」と揮毫して平和のシンボルのように持て囃されたが僕は多少疑っている。従軍俳人だが戦後の長い時間の中でその経験が取捨選択され元からの反戦へ転化していった気配がある。兜太は血の気の多い人だった。
大上段のスッキリとした声は疑わしい。文学の無力を知り尽くしている者ではなく文学によって力を得た者ではなければあっけらかんとした社会批判はできないんじゃないかと思う。戦前戦中に文学青年は文弱の徒と呼ばれ蔑まれた。その通り、戦時下の文学者など役立たずだ。だがいつの時代でも弱者の王になりたがる者はいる。僭王だが政治家など本物の社会的強者の末席には座らせてもらえる。
鶴山裕司
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


