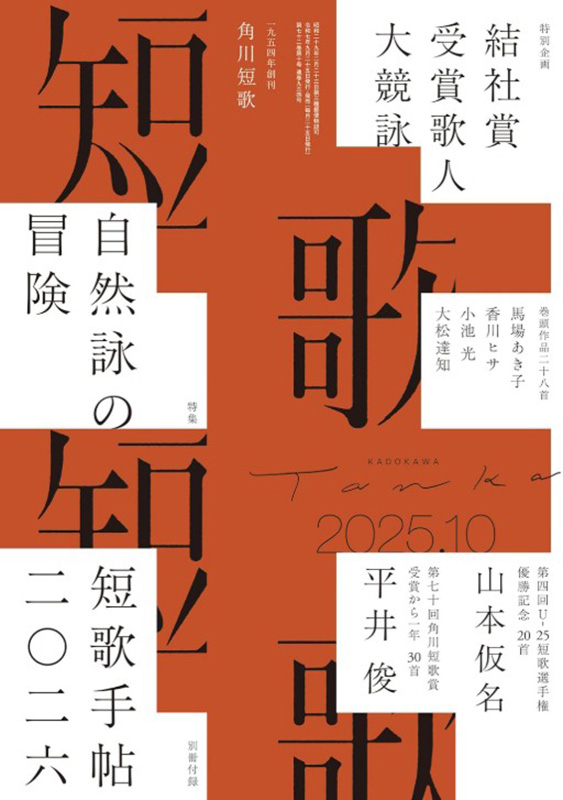
毎回楽しく読ませていただいている坂井修一さんの連載「かなしみの歌びとたち―近代の感傷、現代の苦悩―」第七十回は「生命現象としての河野裕子」です。河野さんについては短歌の王道を踏まえつつ俵万智さんの口語短歌の先駆を成すような鋭い私性を表現した歌人というイメージがあります。しかし坂井さんの連載を読むとデビュー当時は高く評価されていたわけではないようです。
発想の上でも語法の上でも、支離滅裂という感じがするんです。一首々々、助詞を削り、あることばを曲げ、また真っ直ぐにして、作者の若さに同情して読んでいかないとついていけない気がします。少女期の甘ったれはまあよしとしても、それがどうにも受けとめかねるという感じがするんです。たとえば、こういうのはしょうがないと思うんですよ。「青年でも少年でもない顔なりき」とか「ぎんがぎんがまぶしい夜だ」とかね。そうかと思うと「塩もて洗ふのどの痛みは」という倒置法で、妙な技法を見せてみたり、あるいは「蒼穹の影のさやけき」などと、古色蒼然たる語法が出てくる。そういう乱れというか、短歌形式を自分のものにしていない、ありうべき未熟さを許すか許さないか、あるいはその後に可能性を認めるか認めないか、という問題が残ると思うんです。
塚本邦雄『短歌』一九六九年六月号
河野さんは昭和四十四年(一九六九年)に「桜花の記憶」五十首で第十五回角川短歌賞を受賞しました。その際の塚本邦雄の選評(座談会発言)です。ちなみに塚本以外の選考委員は斎藤史/宮柊二/近藤芳美/玉城徹/山本友一。「ううっ」と唸ってしまうような歌人ばかりですね。
塚本は河野さんの短歌をボロクソに批判しています。しかし「可能性を認めるか認めないか、という問題」では可能性を信じて賞を授与したわけです。また河野さんは塚本の厳しい選評に奮起したと思います。
塚本の選評を読むとちょっと懐かしい感じがしますね。一九八〇年代くらいまではこういった厳しい批評は珍しくありませんでした。言いたいことをハッキリ言うのが文学の世界のコンセンサスでした。しかしそれがじょじょに変わってきた。他者の作品を批評する際は誉めるのが基本になったと思います。
自信のない若手作家をチア―アップするのはいいことです。しかし誉めてばかりでいいものか。世代が違えば理想の作品にギャップが生じるのは当然です。塚本も河野さんも前世代とは異なり後進世代とも距離があるからある時代を代表する歌人になった。新人賞はそれがぶつかり合う場でもあります。選者もまた試されているのです。でなければ新人――新しい人・才能――を選ぶ意味がない。少なくとも選考委員が自己の作品に似た応募作を高く評価するのは危うい。それをやり続けると作家も文学も堕落する。
角川短歌や短歌研究新人賞はさすがに敷居が高いですが歌壇にはいろいろな新人賞があります。受賞作を見ていると塚本ではないですが「甘ったれ」た作品だと言いたくなることもある。それはプロ歌人ならわかるはず。「続かないと思うけど一縷の可能性を信じる」くらいのことを言ってもいいいんじゃないかな。
金魚屋でも新人賞があり小説家の辻原登さんが選者です。辻原さんがいつもおっしゃっているのは「新人を勘違いさせるな」ということ。才能のない者に引導を渡すことも仕事の内だと考えておられる。厳しい批評でへこたれるならそれまで。
伴侶とは何と身近な悲しみか 口きかず三日、影だけ歩く
一日ひとひ死を受けいれてゆく身の芯にしづかに醒めて誰かゐるなり
考へても仕様がないんだ転移してまた転移して喰はれてゆくこの身
今日夫は三度泣きたり死なないでと三度泣き死なないでと言ひて学校へ行けり
手をのべてあなたとあなたに触れたきに息が足りないこの世の息が
いずれもよく知られた河野さん晩年の作です。河野さんは五十四歲で乳癌が見つかり手術を受けましたが再発して六十四歲で亡くなりました。『葦舟』や『蟬声』といった歌集を読んで僕も泣きました。可愛そうだと思ったからでは必ずしもありません。河野さんの歌人としての業の深さに打たれたからです。
俳句は〝人に非ず〟の表現で作者(俳人)ではなく常に俳句が主体です。そのため彼岸から此岸を見るような句を詠むことができます。しかし短歌はどこまで行っても自我意識表現。彼岸を描くことはできない。悟りなどないというのが短歌の悟りだと言っていい。それは『伊勢物語』の
昔、男、わずらひて、心地死ぬべくおぼえければ、
つひにゆく道とはかねて聞きしかどきのふけふとは思はざりしを
から変わっていないと思います。死が怖い死にたくないだけどもう助からない間違いなく近いうちに死ぬと歌を詠み続けた河野さんは短歌の王道を行った歌人です。
鶴山裕司
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


