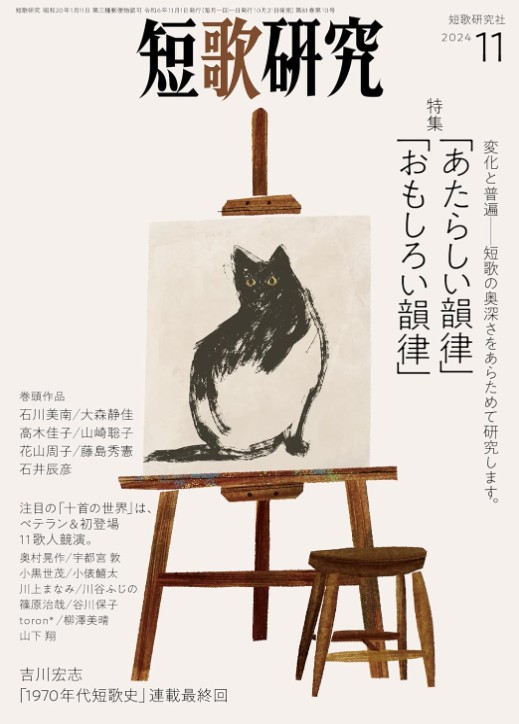
特集は「あたらしい韻律」「おもしろい韻律」。大岡信先生的に言いますと韻律は短歌の場合は五七五七七の文字ブロックの連なりで俳句では五七五になります。「けり」「かな」「や」などの終助詞や間投助詞を使うこともありますが(切れ字ですね)中国や古典欧米詩のように行の終わりを同じ音で揃える音韻ではありません。ですから韻律は定型とも呼ばれます。新しい韻律や面白い韻律は定型を崩すこととほぼ同義ということになります。
「あたらしい」とは、いかにも良さそうな希望のありそうな言葉だが、新しさとは古いものと比較したときにあらわれるものなので、本当にあたらしさについて語ろう述べようとするならば古いものが土台というか前提になる。新しいつもりで発表したものが、実は古いものより遅れているとわかると、はずかしい。じゃあ古いものというのはどこをどう参照するのかと考えると、自分なんかの手に負えるのか不安になってくる。
工藤吉生「赤坂、息」
言語的新しさは古い用法と比較した際の相対的差異だというのは工藤吉生さんが書いておられる通りです。口語が全盛になると文語を使うのが新鮮に感じられたりします。ただ短歌が古典伝統定型詩である限りまったく新しい韻律が成立し得ないのは言うまでもありません。
短歌の韻律にはひとつの背理がある。というのは、五七の韻律を派手に捨て去ろうとすればそれだけ、その音のつらなりは短歌とは隔たった別の何かになってしまう、というものである。それは定型詩というものがみずから選んだ宿命であり、それゆえ、定型詩の韻律に本質的な「あたらしさ」はありえない、というか、あるはずがないのだ。
弘平谷隆太郎「リリカル/きらきら/だんだん畑」
歌人の皆さんは『万葉集』には五七五七七の韻律ではない初期歌がたくさん収録されていることをご存知だと思います。『万葉』巻頭は雄略天皇の歌でまだ文字がない時代ですから口承で伝わった歌も『万葉』にはかなり収録されています。『万葉』後期になると五七五七七に統一されてゆくわけですが狭い意味での韻律を言うと様々な切り方が見られます。五/七五七七で切ったり五七/五七/七で切る歌もあります。五七五/七七で上の句と下の句が分かれるようになるのは概ね『古今和歌集』時代からです。
なぜ「五」「七」なのかは日本語の特性が大きい。名詞を「の」「は」「が」「や」などの助詞・接続詞・格助詞などで繋げば五と七の文字ブロックが据わりがいい。初期歌謡(最初期ではありません)は口誦の無際限的五七の繰り返しであり文字流入後にそれが反歌(止め・終わり)を伴うようになり今の短歌韻律(形式)が成立したのも言うまでもありません。
本題に戻りますと弘平谷隆太郎さんが書いておられるように「定型詩の韻律に本質的な「あたらしさ」はありえない」わけですから「あたらしい韻律」「おもしろい韻律」は五七五七七を壊して新しい形式を作ることではなくその制約の中で新し味のある韻律を作れるのかということですね。
短歌において「韻律」の基本は音数律だが、句跨り、字余り、字足らず、韻を踏む、一字空きなども含まれる。それらの技法の効用と、理屈ではなく五感によって感知される揺らぎをもたらす韻律の秘密を、すっきりとした言葉で説明するのはかなり難しい。
尾崎まゆみ「歌に蛇が来るということ」
とはいえ尾崎まゆみさんが書いておられるように短歌の韻律には既にほとんど無限のバリエーションがあります。もちろん韻律だけでなく意味もそこに重なってくる。
まあ無責任なことを言えば優れた歌であれば誰も五七五七七の韻律が守られているかどうか気にしない。ただそういった歌は破調であっても五七五七七定型の雰囲を決して逸脱していません。指折り数えて韻律を揃え短歌を作る歌人はいないわけですから達観的になりますが韻律は短歌を統御する大気圏のようななくてはならない枠組みということになりそうです。
川の向こうに私と同じようにいる傘をさす人、どう、桜は
工藤咲「バヤリース」(「短歌研究」2024年8月号)
幽霊だったはずの気持ちが実体になってしまって、あぁ、もう はい
イルカーン「疎遠」(「短歌研究」2024年9月号)
マグカップを紙に包んでいるときの紙の手触り 信じていいんですね
道券はな「雲間」(「短歌研究」2024年10月号)
特集で萩原裕幸さんが選んでおられる三首です。三首とも「、」までは一気に書かれています。五七五七七の韻律はまったく使われていないわけですが短歌でないとは言えません。「どう、桜は」「あぁ、もう はい」「信じていいんですね」の最終部が一番重要な歌のストレス(強調・力点)であるのは誰にでもわかります。
正岡子規が短歌について達観的に書いています。短歌は大別すれば「五七調」と「七五調」に分けることができる。五七調は尻が重く七五調は軽い。そのため七五調は口誦の歌謡と相性がいい。「遊びをせんとや生まれけむ 戯れせんとや生まれけん」(『梁塵秘抄』)や「まだあげ初そめし前髪の/林檎のもとに見えしとき」(島崎藤村『初恋』)など口に滑らかな作品は尻軽の五七調です。
この達観的分類はニューウェーブ短歌にも当てはまりそうです。決定的なことを言わずはぐらかし虚空に抜けるような効果を狙う場合は大局的な意味での七五調。ちょっと社会的テーマが入り込んでくると尻重の五七調になりがち。圧倒的に大局的七五調が多いと思いますがそれが現代的な新たな韻律(の主流)でしょうね。
鶴山裕司
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


