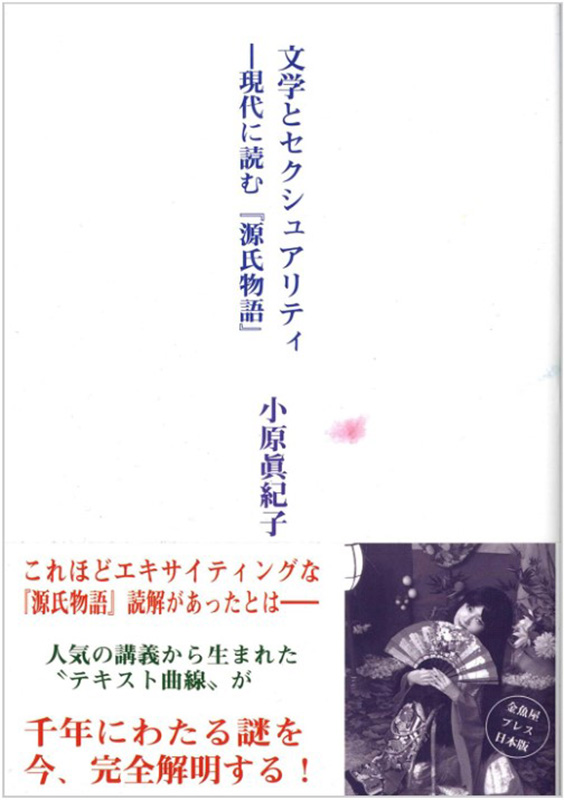『風字硯』
さて、今回は平安時代の硯、風字硯。「風」の字の形に似ているのでその名がある。
平安時代は『伊勢物語』などを嚆矢として、『古今和歌集』『源氏物語』等々まで続く国風文化全盛期である。明治維新以降に鉛筆や万年筆が普及するまで、日本人は墨汁をつけた筆で紙に文字を書いていた。千年以上に渡って墨とそれを擦るための硯はなくてはならない文房具だった。
じゃあ筆、紙、硯、墨のいわゆる文房四宝の歴史がハッキリわかっているのかと言うとそうでもない。小野道風らの能書家が書いた書の断簡などは大事にされて現代まで伝わっているが、どんな筆と墨、硯を使って書かれたのかは判然としない。道具は何かを作るためにあるわけで、時代とともにどんどん改良されてゆく。今も同じだが日用品は使い勝手が悪くなれば廃棄されてしまう。よほどの優品でなければ後世にまで残らない。陶器の風字硯は中級から下級の貴族が私的に使った物である。
例によって文房具は中国からもたらされた。ただ中国でも文房具の歴史はおおよそしかわかっていない。詳細にたどってゆくとややこしくなるのでザックリまとめると、古代殷時代(紀元前十七世紀頃~一〇四六年)から文字はあった。動物の骨に刻まれた亀甲文字や青銅器に彫られた金文などである。当然下書き用の筆や墨の原初的道具はあったはずだがよくわからない。ただ当初は黒い鉱物を磨り潰して膠や漆で溶いて墨にしていたようだ。今のような形の筆が普及したのは春秋・戦国時代頃だと言われる(紀元前七七〇~二二一年)。孔子、老子、孟子らの諸子百家が活躍して膨大な量の文書を残した時代だから当然ですな。竹簡(細長く切った竹の札)に鉱物を磨り潰した墨で文字を書いていたわけだ。竹簡、墨、筆を大量生産するシステムがあったのだろう。
司馬遷は竹簡に『史記』を書いたが前漢末頃には紙が普及し始めた(紀元前二〇六~起源八年)。松や油を燃やした煤を固めた固形墨(松煙墨、油煙墨)が普及したのは後漢時代頃である(起源二五~二二〇年、以下AD)。この頃ようやく今と同じような文房具が出揃ったわけだ。晋時代には書聖・王羲之が現れた(三〇三~三六一年)。これ以降の文房具は百花繚乱で様々な遺物が遺っている。
硯に注目すれば、古来端渓と呼ばれる硯が珍重される。この端渓硯が登場したのは唐時代初期である(六一八~九〇七年)。端渓と呼ばれる渓谷から硯に最適な石が発見されたのだった。紫禁城最高の宝物が王羲之の書であることからわかるように、中国では書を日本以上に珍重する。当然文房具にもうるさいわけで、墨が擦りやすくて発色が良く、かつ筆に墨をつけても筆鋒(筆の先)が痛まないのが良い硯とされた。硯は石製、陶器製、銅製があるが端渓石で作られた硯が最も使い勝手が良かったのである。
日本では古墳時代になってようやく文字が象嵌された鏡や刀が現れる(三~七世紀頃)。文字が普及したのは聖徳太子の飛鳥時代である(五九三~七一〇年)。文字を使いこなせなければ文明は発展しないわけで、日本で初めて文書(文字)を使った治政を行った聖徳太子が今に至るまで偉大な先人と尊敬されている由縁である。この時代、どんな文房具を使っていたのかは判然としないが、東京国立博物館に伝・聖徳太子所用の硯が所蔵されている。猿面硯である。

【参考図版】『陶硯(猿面硯)』
須恵器、木枠に漆 長二〇・九×巾一一・七×厚一・三 奈良時代 八世紀 東京国立博物館蔵
古代日本では地理的に近い朝鮮文化の影響が非常に強かった。朝鮮では大きな壺などを作る時に丸い木槌で内側を叩いて陶土を伸ばす。内部にデコボコの青海波のような模様が残るわけだが、猿面硯は大壺の破片を成形して硯の形にしたものである。猿の額の皺のようなので猿面硯。伝・聖徳太子所用硯は漆を塗った木枠に須恵器の陶片が嵌め込んである。
猿面硯は数が少ないので骨董の世界では珍重される。しかし時代判定がとても難しい。今のような形の硯が普及する前に、比較的平らな石や瓦、陶器の破片を代用品として墨を擦ることがあったのは確かである。そういった硯は転用硯と呼ばれるが、伝来している猿面硯は木枠などに須恵器が嵌め込まれている。この木枠と中の須恵器の時代が一致しないことが多いのだ。須恵器の全盛期は古墳時代だが、たいていの猿面硯の木枠(漆塗り)部分は古くても室町時代以降の作である。
伝・聖徳太子所用硯は最も古い猿面硯の一つだが、木枠は飛鳥時代ではなく奈良時代作だと推定されている。須恵器の青海波模様が消えかかっているのでよく使われたはずだ。須恵器部分だけなら聖徳太子時代の物かもしれないがよくわからない。そういったところが厄介なのだ。古い形の硯なのでいつの頃からか聖徳太子所用とされて伝わった可能性がある。江戸時代頃に古玩趣味の一貫として須恵器を加工して漆塗り木枠をあつらえた作もある。そういった作品は須恵器部分が硯として使われた形跡があまりない。

【参考図版】『平城京跡出土硯』
『平城京出土陶硯集成Ⅱ-平城京・寺院―』より 奈良文化財研究所刊
日本で硯が普及し始めたのは奈良時代である(七一〇~七八四年)。平城京跡の発掘調査では断片を含めて千点以上が見つかっている(転用硯は含まない)。律令制が確立されて大勢の官吏が文書を制作していたことがわかる。中国では端渓を頂点とする石製硯が普及していたが、面白いことに平城京出土硯のほとんどが陶器製である。いかにも焼物大好きな日本人らしい。
新羅が朝鮮を統一するまで(六六八年)半島は新羅、高句麗、百済の三国時代だった。百済王朝が滅びて大勢の貴族らが日本に渡来して帰化人となり、飛鳥時代に様々な文化を伝えたことはよく知られている。平城京跡出土の陶硯は固く焼き締めた須恵器だがその製法や形状は半島の様式である。新羅土器と総称される。渡来人が固くて頑丈な陶器の製法を伝えたのである。
年号などが入った硯は皆無なので制作時代は断定できないが、初期は円面硯と呼ばれる脚がついた丸い形の物が多かったようだ。直径二五センチほどの大きな物もある。真ん中の平らな部分で墨を擦って周辺の溝に墨を溜め、何人かの役人で共同使用したのだろう。小さい円面硯も多いが硯が量産されるようになって個々人が所有できるようになったからではないか。また羊の頭が付いた珍しい硯も何点か発掘されている。明らかに日本人好みではないので帰化人陶工の作である。羽を陰刻した蓋のある鳥型の硯も見つかっている。大量に擦った墨が乾かないようにするための工夫である。
石製より陶器製の方が使い勝手が悪いはずだ。しかしこれだけ大量の陶製硯が残っているということは十分実用に耐えたのだろう。渡来人陶工から製陶技術を学んで、器用な日本人が工夫して使いやすい硯を生み出した可能性がある。
しばしば平城京跡から新たな木簡が発掘されて話題になるが、それらは荷札などの使い捨てである。公式文書では聖徳太子時代からすでに紙が使われており平安時代に広く普及した。硯も奈良時代のような円面硯がすたれ今と同じような長方形の形状になった。ただし石硯はやはり高級品で、いわゆる普及品には陶製硯を使っていたようである。いずれにせよ中国に五〇〇年以上遅れて日本でも平安時代に筆、紙、硯、墨の文房具が揃ったわけだ。
骨董は読むものだが今回紹介する風字硯は読むのがそれほど難しくない。裏側を見ると沈んだ緑色に発色している。これは今の愛知県東部あたりの猿投窯の特徴である。猿投窯は日本で最古の窯の一つ。日本では中国のように朝廷用の陶磁器を専門に作る官窯制度はなかったが、初期猿投窯は官窯的性格があったと言われる。同じく愛知県の渥美、常滑窯も初期は官窯系でそれがじょじょに民間向けの日用品を焼くようになった。
表を見ると真ん中に丸い跡がある。この部分だけ釉薬がかかっておらずここで墨を擦ったのである。黒ずんだ部分は墨が沁み込んだ跡だろう。かなり長期に渡って使われていたことがわかる。この時代の墨は現代のそれよりだいぶ柔らかかったようだ。
猿投窯は日本で初めて器体に釉薬を塗ってから焼く施釉陶を作ったことで知られる。この風字硯は施釉と自然釉(窯に入れた製品に高温度の薪の灰が降り積もってガラス質の釉薬になる)を組み合わせて作られている。表側に釉薬を塗り、墨を擦る部分だけ釉薬を雑巾などで丸く拭っている。それを裏返し、釉薬がかかっていない部分にトチンと呼ばれる素焼き円筒形の窯道具を置いて窯で焼いている。裏側の緑色の部分は窯の中で降り積もった自然釉。それが垂れて口縁部分で玉になっている。

『風字硯』表
長一七・八×巾一三・九×高二・七(最大値) 平安時代 十~十二世紀頃か

『風字硯』裏

『風字硯』釉垂れ

『風字硯』の焼き方
風字硯は平城京跡からも出土しているので時代判定が難しい。ただ初期の風字硯は釉薬がかかっていない焼き締めである。施釉と自然釉の組み合わせだから製陶技術が進んだ平安時代の作なのは間違いないが、手の込んだ制作方法の割には手慣れている。大量生産された平安中・後期くらいの作ではなかろうか。『古今和歌集』(九〇五年上奏)から『源氏物語』(一〇〇〇年頃成立)頃の作と推定される。どこかにこれは紀貫之や紫式部の物ですと書かれていれば重要文化財クラスだが、んなことあるわけないですよね。
今年はNHKの大河ドラマの主人公が紫式部なのでちょっとした『源氏物語』ブームである。ただま、わたくしが言うのも僭越ですが、紫式部と殿上人・藤原道長の身分差を越えた恋物語というストーリーはいくらなんでも無理がある。はっきり言ってあり得ない。道長をモデルに『源氏物語』が書かれたというのもどーかなー。生々し過ぎて幻滅しそう。『伊勢物語』の主人公に擬される在原業平、あるいは業平のパトロンだった融の大臣(源融)の方がまだモデルに近いんじゃなかろか。
ただ『源氏物語』で有名だが、『紫式部日記』以外に実人生に関する資料がほぼ存在しない紫式部を主人公にしたドラマを書けと言われれば誰もが悩むだろう。恋愛モノの大脚本家・大石静さんが紫式部と道長のかなわぬ恋物語というフィクションを中心に据えたのもわからなくはない。要は紫式部物語という設定自体に無理がある。彼女は道長の娘で天皇妃だった彰子の局を彩った女官の一人に過ぎない。皇妃は彰子だけではなかったから、道長は娘の権威を高めるために紫式部や和泉式部、赤染衛門、伊勢大輔ら当時最高の知性を持った女房たちを取りそろえたのだった。
明治維新以降に歴史小説というジャンルを確立した森鷗外は「歴史其儘と歴史離れ」というエッセイを書いている。小説で史実そのままを表現することはできないが、かといって史実から離れると歴史小説の意義がなくなってしまうという主旨である。それはその通りで徳川将軍が女で大奥が男たちに設定されたドラマもあった。人気を博したがここまで来ると江戸時代の男女の格好をした現代人が活躍する、ちょっと淫靡なSFパラレルワールドファンタジーである。
鷗外の「歴史其儘と歴史離れ」という問題提起は現代でも有効だが、ほかならぬ鷗外が書いた可能な限り史実に即した小説を歴史小説、現代小説では表現しにくい愛や倫理などを過去の時代を舞台にしてストレートに表現した小説を時代小説と区分することはできる。時代小説やドラマは痛快だが現実味は薄い。ただフィクショナルな要素が歴史小説と時代小説を分けるわけではない。最も重要なのは各時代固有の社会の枠組みである。いつの時代でも社会的制約や圧迫は非常に強い。それでもそこに現代と変わらぬ普遍性を見出すのが歴史小説である。それはわたしたちが遠い昔に書かれた小説に見出す普遍性と同質である。
たとえば平安時代から江戸時代に至るまで日本は家長制度で男子が家を相続した。そのため女性の地位は低かった。この枠組みは動かすことができない。では女性に力がなかったのかというとそうとは言えない。この世に男と女しかいない以上、封建社会の表の顔が男であっても女はその足元を突き崩し男たちの言動に大きな影響を与えることができた。それでは男女不平等で面白くないというなら現代小説を書いた方がいい。もちろん昨今の平等風潮に棹さしているわけではありません。文学の話をしている。
瀬戸内寂聴さんらの『源氏物語』論を読んだが、最も優れた『源氏』論は小原眞紀子さんの『文学とセクシュアリティ―現代に読む『源氏物語』』だと思う。なぜこの本が優れているのかと言えば明快に『源氏』の作者が女性という前提に立っているからである。要するに戦後的な男根主義文学風潮とそれに反発した戦後フェミニズムと完全に無縁だ。多くの女性と浮名を流した光源氏物語は江戸封建時代の知識人(男)たちから軟弱な風紀紊乱小説と見做されていた。男も女もなにかっていうとすぐ泣きますしね。しかし高位の姫君たちの嫁入り道具は源氏模様で彩られ、その人気が衰えることがなかった。それがなぜなのかを完全解明している。
小原眞紀子著『文学とセクシュアリティ―現代に読む『源氏物語』』
光源氏の時代の貴族にとって一夫多妻制は普通だった。後継ぎをもうけるのも貴人男性の大事な仕事であり、それは江戸幕府の大奥と同じように必要とされていた。批判しても意味がない。もちろん現代女性と同じように当時の姫たちが思い悩んでいたことはほかならぬ『源氏物語』に書かれている。『源氏物語』では女性の側からしばしば男の身勝手が厳しく批判される。ただ紫式部の視線は異性だけでなく同性に対しても厳しい。
光源氏は前の東宮后・六条御息所と恋仲になる。しかし御息所の元に通う途中で身分の低い夕顔という女性の元に沈没してしまう。前東宮后という高いプライドを持つ御息所と打ち解けられなかったのである。それに対して夕顔は噂に名高い貴公子光源氏に「実際に会ってみるとたいしていい男ではありませんね」という意味の歌を詠みかけた。小原さんは「男が溺れるほど女に求めるもの、少なくとも男にとっての女そのものがすなわち「邪気のなさ」だとするなら、「邪気」とはすなわち男性性である、といえるでしょう。生まれてから死ぬまで男たちが捉えられ、逃れられない制度性です。男が女に求めるものは、この制度性の脱却でしょう。たとえ一瞬のことであろうとも」と書いている。御息所のプライド=邪気は光源氏が属する男社会のそれと同じだった。
また光源氏の寵姫の一人末摘花は、はっきりブスだと書かれている。関係を持った光源氏もちょっと後悔する。しかし彼は晩年に至るまで末摘花を手厚く庇護した。その理由は彼女が少女のような純な心を持つ女性だったからである。光源氏が理想のプリンスなのは彼が女性たちの美質を的確に見抜いて愛することができたからである。
女性に助けられることもある。『須磨』『明石』は『源氏物語』前半部のクライマックスだが、謀反の疑いをかけられた光源氏は須磨に隠棲する。次いで明石に居を移して明石の君に出会い中央への復帰を果たした。この明石の君は光源氏の一人娘・明石の中宮を産み、彼女が今上帝の后となり皇子をもうけたことで光源氏の権勢は盤石になった。明石の君は没落貴族の娘だが天皇の祖母になったのである。「身分や不遇をものともせず、持ち合わせた資質や運命のエネルギーで天上にまで駆け上がってゆくのは、女性なのです。男は生まれた身分に最後まで縛られ、せいぜい一生懸命に努力して、じりじりと出世してゆくほかはない。源氏は主人公として、このような女性性の持つポテンシャルを深く理解している」と『文学とセクシュアリティ』にある。『須磨』『明石』では海と女性という根源的テーマが表現されている。
ただ光源氏は浮世離れしたプリンスではない。晩年に光源氏は異母兄の朱雀院から皇女・女三宮を賜った。が、女三宮は柏木と密通して薫を産む。稀代のプレイボーイ光源氏は寝取られ男になってしまった。それだけではない。光源氏に密通を悟られた女三宮は出家し柏木は密通を苦にして亡くなってしまった。現世の苦悩が光源氏に襲いかかる。小原さんは「『源氏物語』にはしばしば幻滅のパターンが示される。すなわち光源氏、藤壺、玉鬘など神話的に登場した人物が徐々に現実化し、それについての幻想=イリュージョンが滅する方向へと物語が動く。これは説話的なるものから近代小説へという文学史的な推移を先取りするものでもある」と書いておられる。それがさらに顕著になるのが光源氏死後の物語、『源氏物語』掉尾の『宇治十帖』である。
『宇治十帖』は紫式部の作ではないという議論がある。が、小原さんは「別人が書いたにしては、思い切った設定の変化がある。変わっているから別人が書いた、というのは素人の発想。本編の人気や出来にあやかろうとする別人なら、むしろできるだけ本編に似せて書こうとする。また光源氏には劣る、と言い切った主人公二人を持ってきて、なおかつ本編の読者を惹きつけ続けようとするのは、相当な自信がなくてはならない」と論じている。その通りだが、それはともかく『宇治十帖』は不義の子・薫と光源氏の孫・匂宮の物語である。
薫は生まれつき身体から不思議な芳香を放つ青年である。出生の秘密に悩む薫は幼い頃から仏道に惹かれているがゆえの芳香の設定である。匂宮は薫がうらやましくてたまらず、常に香を焚きしめた着物を着ていることからの命名だ。二人は親友でライバルだが『宇治十帖』で薫は二度も匂宮に女を取られる。
薫が女性と結ばれないのは出生の秘密に悩んで仏道に深く帰依し、彼岸的悟りを希求する青年だからである。しかし生きたまま悟りを得られるわけがない。彼の心を女たちが揺さぶる。最初は宇治に住んでいた大姫・中姫の姉妹。薫は大姫に強く惹かれるが、姉妹のことをつい匂宮に話したことで匂宮に中姫を奪われる。薫は大姫を妻にしようとするが彼女はそれを拒み衰弱して亡くなってしまう。薫を嫌っていたからではない。大姫は薫の理想の女性そのものだった。「大姫は、薫との結びつきが幻滅に終わることなく、永遠なれと願っていた。それがある意味で成就したことが感動をよぶのではないか。(中略)それは普通の人々には理解しがたく、女房たちは非難していました。しかし当の薫は、わかる気がすると思ってしまうのです。つまりは肉体的に結ばれるまでもなく、二人はすでに通じ合っていた」(『文学とセクシュアリティ』)とある。
薫は嘆き悲しむが、中姫から父・八宮には別腹の妹がいると聞きその女性を見出す。『源氏物語』最後の姫、浮舟である。しかし薫が浮舟を宇治の別荘に囲っていると洩れ聞いた匂宮にまたしても浮舟を奪われてしまう。匂宮は薫の中途半端な彼岸志向を現実に引き戻す役割を担っている。現実界に属する匂宮は女性たちと結ばれるが理想への希求を手放せない薫の恋愛は悲恋に終わる。薫は浮舟を大姫の「人形」として求めたとハッキリ『源氏物語』に書かれている。薫にとって浮舟は理想の代理に過ぎない。では当の浮舟はどうか。
浮舟は薫の思い人でありながら夜陰に紛れて訪ねて来た匂宮に強引に妻にされてしまったことに悩み、宇治川に身を投げる。しかし死にきれず横川の僧都と呼ばれる高僧に助けられその姉の尼君の元で意識を取り戻し静養することになる。やがてそれが薫の耳に入り、彼は浮舟の不義を許し、匂宮のちょっかいを排して取り戻そうとする。この時代の女性たちの運命は男次第である。ましてや浮舟は父・八宮から認知されず母親が再婚した身分の低い常陸守の養女となった女性だ。殿上人の薫の意向に逆らうことなどできない。が、自殺未遂した浮舟の心はすでに薫からも匂宮からも離れている。
今は限りと思ひしほどは、恋しき人多かりしかど、こと人びとはさしも思ひ出でられず、ただ、
「親いかに惑ひたまひけむ。乳母、よろづに、いかで人なみなみになさむと思ひ焦られしを、いかにあへなき心地しけむ。いづくにあらむ。我、世にあるものとはいかでか知らむ」
同じ心なる人もなかりしままに、よろづ隔つることなく語らひ見馴れたりし右近なども、折々は思ひ出でらる。
紫式部『源氏物語』『手習』
『源氏物語』は薫が浮舟を取り戻そうと奔走する『夢浮橋』で終わる。現実と非現実(イデア)を橋渡しするようなとてもいいタイトルだ。が、実質的な小説の終わりはその一つ前の『手習』だろう。浮舟は尼君の元で手習、習字のお稽古ではなく思いついた事柄を次々に紙に書く日記のような文を書いて過ごしている。恋しいと思った男たちのことはもう思い出されず、ただ自分が死んだと思っている母親がどんなにか悲しんでいるだろうと思う。浮舟が思い出すのは母親を中心にした女たちのことばかりである。浮舟が会いたいと願うのは母親だけだ。この箇所の『源氏物語』の記述は美しい。
小原さんは「教養を何も身につけていない浮舟は、ただひたすら手習をします。詠んだ歌を書くのです。『手習』には他の登場人物のものとともに、浮舟の詠んだ歌がたくさん出てきます。いわゆる上手い歌ではないかもしれません。ただ死の境を越えていまだ現世にとどまる自身の心情を一貫したテーマとして、繰り返し書いている。それは教養主義的な物語を離れた、他でもない文学者の姿に酷似しています」と書いている。『宇治十帖』の主人公は薫だが、大姫や浮舟の姫たちに紫式部のいわゆる恋愛観が強く反映されている。彼女たちは男たちとの恋愛を経て男たちを本質的に拒絶した。

『源氏物語絵巻』『夕霧』
平安時代末期
平安時代末に作られ今は国宝に指定されている『源氏物語絵巻』『夕霧』断簡に硯が描かれている。石硯で中国から将来された端渓かもしれない。立派な硯箱に筆といっしょに納まっている。皇統に連なる殿上人は当時最高級の石硯を使っていたのだろう。平安時代後期から実在の人物そのままを描く似絵が現れるが、高僧らの似絵でも調度品として描かれているのは石硯である。陶製硯が描かれた絵はない。ただ『源氏物語』では匂宮が宇治の別荘を訪ねた際に「あやしき硯召し出でて」、浮舟に「峰の雪みぎはの氷踏み分けて/君にぞ惑ふ道は惑はず/木幡の里に馬はあれど」という歌を書いて与えたと書かれている。「あやしき硯」は浮舟のような中・下級の貴族が使った国産の陶器製だろう。
滋賀県大津市の石山寺に紫式部が使ったとされる硯が伝来している。珍しい形をした二面構成の石硯で中国製かもしれない。観光資源になっているので物言いにくいが、まああくまで伝承である。紫式部は中宮彰子の女房で女性たちが争って『源氏物語』を読んだのだから、紙や墨、硯を潤沢に提供されていた可能性はある。ただ書跡一つ残っていないのに硯だけが紫式部所用と特定されるのは無理がある。
『源氏物語』は四〇〇字詰め原稿用紙で二四〇〇枚の大作である。一五〇枚あれば単行本になるので今の感覚では十六冊分の単行本を書いたことになる。平均寿命の短い当時のことを考えれば驚異的筆力だ。しかし人間の能力は今も昔もさほど変わらない。作品を書くには膨大な時間がかかる。千年以上前のお方だがわたしたちに馴染み深い実質的専業作家だった。
当たり前だが物書きにとっては書きやすい文房具の方がいいに決まっている。しかし高価な文房具を揃えればいい作品が書けるわけではない。紫式部さんは書くので頭がいっぱいで、文房具は端渓でもあやしき硯でもどーでもよろしと思っていたでしょうね。
鶴山裕司
(図版撮影 タナカユキヒロ)
(2024 / 4/ 23 24枚)
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■