 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
十四、『三四郎』第四章 広田先生の引っ越し
a:ロスタイムー中勘介の『犬』―
ではこの勢いで第四章突入! という時になって、不意に俺の腰がブルブル震えだした。かと思うとピロリロパー、ピロリロパーと情けない声でわめき始めた。
「あんた、鳴ってるよ、呼び出し音」
そうなのだ。これは、俺たちが常時ポッケのなかに携帯することを強いられている、通信機である。ピロリロパーは、仕事の合図。しかし、こんな重大な任務に就いている俺たちに、さらに呼び出しをかけるとは管理局もまあナンタルチア、サンタルチアである。
「はい、あの俺たちいま」
大変にお取りこみ中なんですが、という暇も与えず、
「ただちに向かってくれ」
管理局の課長あたり、おそらく田所さんあたりの声が飛び込んできた。
「ですからね、俺たちいま、その反聖文のですね」
「それはわかっている。わかっているが、うちは常時人手不足なんだ。そして事は一刻を争うんだ」
有無をいう暇すら与えらぬまま、俺たちは『三四郎』から強制ワープさせられた。これは、管理局の装置で行われる操作で、ひとつの作品から別の作品へと一気に虚構パトロール隊員を移送する手段である。緊急時にのみ取られる措置であった。
「立て籠もりだ。無理やりにでも引きずり出して連れて帰ってくれ」
「立て籠もり? 何日目です?」
「もう四日だ。四日も飲まず食わずだ。作品内の食い物を食った気になってるだけで、身体は衰弱しきってるはずだ」
変な話だった。
「だって、強制リセットされるはずでしょ?」
そうなのだ。丸一日一つの作品に籠っている読者=体験者は、生命優先の観点から強制的にリセットされて現実に帰される仕組みになっているはずなのだ。
「それが、こいつ、リミッターを解除したようなんだ。どこかの馬鹿が、そういう装置を開発したみたいでな。出所はわかって、開発者は逮捕された。でも、すでに販売された装置の回収は難航してるんだ。だから、この装置によるリミッター解除を受け付けないように、現在VRのプログラムも変更しているところってわけだ。だから、こいつが最後の未帰還者となるはずなんだよ、現在のところ」
「わかりました」

実際にはイタチごっこで、こっちがプログラムを変更しても、ハッカーは連中はまたすぐにこれをかいくぐる手法を編み出してくるから、こいつが最後ってわけじゃないだろう。
いずれにせよ、作品内で死者を出すわけにはいかない。それは、作品を穢すことでもあり、当然わが社のVRシステムの評判に大きな傷をつけることにもなるわけだから。
「で、ここはどこです。俺たちがいま送られてきたのは、なんて作品の中なんですか?」
「わからんか? 中勘介の『犬』だよ」
「ああ、あれね」
それまで黙っていた高満寺が、ふいにわかったような頷き方をした。
「よくいるのよね。『犬』に中毒しちゃう奴」
「そう。今回の立て籠もり犯、お客様のプライバシー保護規定があるから仮にT氏としておくが、T氏も完全な『犬』中毒者だよ。半年前におそらくは偶然にこの作品に入って以来、他の作品には目もくれなくなって、ずっと入り浸ってたんだ。そして、それが極まって今回の自殺未遂に至ったわけだ」
とにかく急いでくれ、と管理局のおそらくは田所さんらしき声の持ち主は焦っていた。
「君たちだって、時間がないんだろう。文脈もあらすじもすっ飛ばしていいから、とにかく可及的すみやかに仮称T氏を連れ出して、本務に戻ってくれ」
可及的すみやかに、ってどこの政治家なんだ、あんたは。
中勘介が大正十一年に発表した『犬』は、日本文学史のなかでもかなりいびつな奇譚のひとつといってよいだろう。あの『銀の匙』の作者の書いたものとは思えないほど、官能と情欲がほとばしる怪作である。
舞台は十一世紀の印度。回教徒による攻撃にさらされた町クサカの街のはずれの森で行に励んでいた婆羅門の苦行僧と、邪教徒に穢されて身ごもった孤児の娘をめぐる物語である。
苦行僧は醜い。『どこもかしこも腫物と瘡蓋と蚯蚓腫れとひっつりだらけで、膿汁と血がだらだら流れている』ような姿をしている。苦行僧が身のうちに秘めている強烈な性欲を象徴するのが、彼のいる草庵のそばにある芒果樹とそこに絡みつく葛蘰の描写である。『その逞しい幹に這い上がったおそろしく太い葛蘰は、ちょうど百足の脚のように並列した無数の纏繞根を出してしっかりと抱きついている。その二つの植物の皮と皮、肉と肉がしっかりくいあってる様子がなんだか汚らしい手足と胴体が絡みあったようないやな感じを与える』とあり、この様こそがいわばこの小説全体の要約となっているといってもよい。
あろうことか、娘は苦行僧に問い詰められて、自分が毎夕森の猿神の像に願掛けに来ている理由を告白する。なんと、娘は、自分を穢して身ごもらせた邪教徒の隊長ジェラルドに恋をしていたのであった。ジェラルドは、苦行僧とは真逆の『「眉の濃い、目の大きな」「背のすらりと高い、品のいい、強そうな・・・」』若者、すなわちイケメンである。娘は猿神に、ジェラルドとの再会を祈念するために通っていたのであった。
告白を聴いた苦行僧は、七日の間湿婆に詫びをして罪業を解くために自分の草庵に通うことを要求する。そして自分の草庵のなかで裸になって聖水を浴びるように命じる。そして苦行僧は、それを外から覗く。苦行僧が見るのは『丸々した長い腕、くぼんだ肱、肉のもりあがった肩、甘い果のようにふくらんだ乳房、水々しい股や脛、きゅっと括れた豊な臀』などである。

嫉妬に狂った苦行僧は、毘陀羅法という術を用い、屍体に鬼を宿らせたものを操って、ジェラルドを殺す。そして、娘には腹の子を堕してやると迫り、気を失った娘と交わりを持つ。かくして、苦行僧は苦行僧であることをやめてしまう。
『「わしはもうなにもいらぬ。わしはもう苦行なぞはすまい。なにもかも幻想じゃった。これほどの楽しみとは知らなんだ。罰もあたれ。地獄へも堕ちよ。わしはもうこの娘を離すことはできぬ」』
娘を誰にもとられたくないと思った苦行僧は、呪文を唱えて娘を犬に変える。そして自らも犬となり、『「どうでももう己のものだ。いつでも自由になる」』とうそぶく。そんな風に官能にとち狂っていく苦行僧の姿を描いた作品である。
「どこだ? T氏はどこにいる?」
見まわしたが、どこかに人間が隠れ潜んでいる気配はなかった。
「同化モードでしょ。あの犬になってるに決まってるわ」
高満寺が指さしたのは、狐色をしたきゃしゃな雌犬を背後から襲っている、『がっしりした骨組み、瘡蓋だらけの皮膚、額のわれた相の悪い顔、睫毛のない爛れた目、そして相変わらずの臭い息』をした醜い犬だった。
「あんな姿になってまで・・・」
「ばかね。ああなることで、かえって興奮するのよ、こういう引きこもりタイプは。自己イメージと、作品内の描写が奇妙に符合するのかもしれないわね。さあ、引き剥がすわよ」
「よしきた。早いとこ片付けよう」
一、二の三で俺たちは飛びかかった。俺は雌犬を引き離す係。そして、その雌犬に『蛭のようにへばりついていっかなはなれない』醜い犬を、そこに完全同一化している読者から引き剥がす係が高満寺である。
「ぎゃっ、やべ、やべて。やべさせないでぇ」
情けない悲鳴が上がった。完全同化モードになると、読者と登場人物の一体化が極点まで進んでいる。つまり、読者はもはや読者であることをやめて、完全に物語の登場人物と化している。だから、そんな読者を引き剥がすのは、並大抵のことではない。高満寺の腕力をいまほど頼もしいと思ったことはなかった。
ねじれた木の根のような二の腕の筋肉、もりもりと膨れ上がった胸筋。そして、額に流れる汗。べりっ、べりっと音を立てて、読者仮称T氏から、醜い犬がはぎ取られていった。
「お客様。これで読了とさせていただきます。ご利用ありがとうございました」
泣きじゃくる仮称T氏を、丁重にお見送りした。四日間の断食で、実際苦行僧のごとく痩せこけていた。戻ったら即座にまずは脱水症状から回復させるための点滴をぶち込まれることだろう。
お客様とはいいつつも、リセットモードを勝手に解除した罪には問われることになる。おそらく、当分の間は物語体感が禁止されることになるだろうから、仮称T氏は、苦しく悶々とした日々を過ごすことになるだろう。まさに苦行僧そのものとなるわけである。
などと言っている場合ではないので、即座に再転送を管理局に依頼して、俺たちは『三四郎』第四章へと回帰した。まったく、この大事な時に、とんだ時間ロスである。
b:偉大な暗闇
「『三四郎の魂がふわつき出した』という書き出しが、おもしろいじゃない。池の女、あるいは絵の女に魂を抜かれかけてる感じがよく出てるもの。学問なんかどうでもいい感じになっていることが感覚的に伝わるわよね」
「そうだね、『講義を聞いていると、遠方に聞こえる』ってあるくらいだから間違いない。そんな三四郎を、与次郎は『「いかにも生活につかれているような顔だ。世紀末の顔だ」』と評する。三四郎は、秋の訪れとともに、『ふわふわして方々歩』きはじめる。田端、道灌山、染井墓地、巣鴨監獄、護国寺、新井薬師など、東京を周遊する。そして『ふわふわすればするほど愉快に』なる。講義にも身が入らなくなる。そして、千駄木を訪れたときに、与次郎と一緒に歩いてきた水蜜桃の男に会う」

「ここで、やっと水蜜桃の男が、広田だってつながるわけよね」
二人は広田のために貸家探しに来ていた。三四郎が石の門がある家を紹介する。与次郎が家主に交渉するために不在になったときに、三四郎と広田が会話する。
「広田は奇妙なことを言うよね」
「そう、『不二山を翻訳したことがありますか』って、わけがわからないわよね」
「続けて『自然を翻訳すると、みんな人間に化けてしまうからおもしろい。崇高だとか、偉大だとか、雄壮だとか』と、人格上の言葉になることを指摘する」
「三四郎は続きがあるものだと思うのだけど、話はそれきりなのよね。だって、広田ったら、今度は小石で地面に落書きをし始めるんだもの。期待させといて肩透かしを食らわせる感じよね」
このとぼけた感じも、VRで読書=体験してみるとよくわかる。でも、体験してみても広田の落書きはなんなのかよくわからない。その落書きは三四郎には、燈明台に見える。
「燈明台ってのは、文字通り燈明を載せるための台で、今でいう街灯だよね。でも、広田に確かめないから、ほんとうにそうだったのか曖昧なままになる」
だから、VR体験者にも、広田の絵はなんだか要領を得ない奇妙な模様にしか見えない。
そこへ、与次郎が戻ってきて、その石の門がある立派な屋敷を見ることになるが、家賃的にとても借りれる値段ではない。与次郎が広田の絵を見て、何を描いていたのかと問うが、やはり広田は答えない。三四郎が『「燈明台じゃないですか」』と聞くと、広田も与次郎と一緒になって笑う。
「だから、結局何を描いていたのかは曖昧なままに放置されたまま、燈明台の話題に移っていく」
「そう、謎は解決されないままなのよね」
「最初、与次郎が燈明台を野々宮に比較するよね。そして、『外国じゃ光ってるが、日本じゃ真っ暗だから』という。それから、古い寺の隣の青ペンキ塗りの西洋館、そして九段の燈明台の隣にできた偕行社の新式の煉瓦作りの比較となる」
「時代錯誤アナクロニズムの話よね」
「そう、日本伝統の古いものと、西洋式の新しいものが併存している明治の状態を、広田は『これが日本の社会を代表している』という。これは漱石がよく口にしていた内発的ならぬ、外発的開化のなせるわざだということになるわけだけど、結局何を描いていたのかわからず仕舞いになるから、読者=体験者たるわれわれにも、広田が描いている絵はよく見えないままで終わるわけだよね」
「たぶん、読んでるだけだと、その辺は見過ごしちゃうけど、体験してみると、曖昧にされた部分がなんかもやもや感として残るわよね」
翌日、三四郎のところに与次郎がくる。まだ広田の引っ越し先を探しているという。広田は独身であること、洋行をしたことはなく、西洋は写真で研究していること、高校で英語を教えていること、著述はなく、時々論文を書くことはあるがまったく反響はないことを与次郎は告げ、それでも彼は『偉大な暗闇だ』という。
なぜ「偉大な暗闇」なのかといえば、それは周りの人に見えるように光を発しないから見えないということになるのだろう。すぐれた哲学者なのに、世にでる気がまったくないわけだ。だから、自分が『先生を一つ大学教授にしてやろうと思う』と与次郎は胸の内を明かす。
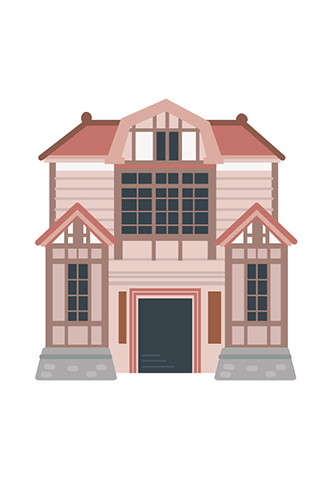
「こういう展開を受けてさっきの落書きのことをもう一度考えてみると、もしかしたら、これは広田の重要な特徴なのかもしれないって思えるね」
「どういうこと?」
「広田は、自分の思想もこれ見よがしにはひけらかさないし、それを書物という形で世に問うこともしないわけだろ。すべて他人には見えない自分の内側に仕舞い込んだまんまなわけだ」
「それを与次郎は「偉大なる暗闇」と呼ぶわけよね」
「そういう生き方っていうか、姿勢が、なんでもないような落書きの正体まで明かさないというところまで一貫しているっていうことなんじゃないかな」
「落書きの正体まで明かさないなんて、そういえば不思議よね」
c:三つの世界、全部取り
夜遅く与次郎が帰り、三四郎は母から来ていた手紙を読む。小作人である新蔵が蜂蜜をくれたこと、平太郎がおやじの石塔を建てたこと、そして三輪田家が、娘のお光さんを、大学を卒業したら嫁にもらって欲しいと言ってきていることなどが書いてある。
「お光さんの話題について、『案のごとく三輪田のお光さんが出てきた』と三四郎は書いているよね。きっと書いてくるだろうと予期していたわけだ」
「期待していたのかしら」
「うん、故郷に安全牌が確保されていることは、三四郎にとっては心の支えなんだろうね。これで東京で失敗しても故郷に帰ればよいし、東京で別の女とうまくいけば軽く捨ててしまえばいいという虫のいい考えがあるように思うな。小心者の小狡さって感じだけど。
手紙を読んで三四郎は三つの世界について考える。あるいは妄想する。
ひとつめは故郷熊本。明治十五年以前の香りがする世界だよね。そこに関して三四郎は、『すべてが平穏である代わりにすべてが寝ぼけている。もっとも帰るに世話はいらない。戻ろうとすれば、すぐにもどれる。ただいざとならない以上はもどる気がしない。いわば立ち退き場のようなものである』って述懐しているだろ? やっぱり、にっちもさっちも行かなくなっって、立ち退かざるをえなくなったときには、戻るつもりもあるっていうことだよね」
「もちろん、無意識だろうけど、さんざん馬鹿にしておきながら、ひどい話よね」
「第二の世界は学問の世界。ここに住む野々宮や広田のような人は、世俗との接触を断ち、貧乏でも大平に暮らしている。『現世を知らないから不幸で、火宅を逃れるから幸いである』と三四郎はこの世界の人たちを評する。
第三の世界は三四郎が近づき難いと感じている世界。つまり、東京の現実世界。さんさんとして春のごとくうごめき、電灯があり、銀匙があり、泡立つシャンパンの杯があり、『そうしてすべての上の冠として美しい女性がある』世界である。三四郎は、『自分はこの世界のどこかの主人公であるべき資格を有している』と思っているけれど、『自分が自由に出入りすべき通路』がふさがれているように思い、不思議の感に打たれている」
「どうして、女性のいる世界の主人公の資格があるなんて思えるのかしら」
「やっぱり、エリート意識のせいかもしれないね」
「それで、結局どの世界を選ぶと言うことはできず、三四郎は一番虫のいい選択を妄想するのよね」
「そう、『要するに、国から母を呼び寄せて、美しい細君を迎えて、そうして身を学問にゆだねるにこしたことはない』。全部取りってわけだ」

第一の世界も、第二の世界も、第三の世界も全部いただきます、っていう腹積もり。当然、第一の世界に確保してある安全牌に過ぎないお光さんは、第三の世界から美しい細君を迎えた暁には用済みとなってお払い箱という算段なわけだ。
「ほんと、虫のいい話だわ」
「しかも、虫の良さはそこで終わらないんだ。さっきの妄想だと第三の世界を一人の女性で代表させることになってしまう。でも、美しい女性はたくさんあるのだから、『自己の個性を全からしむるために、なるべく多くの美しい女性に接触しなければならない。細君一人を知って甘んずるのは、進んで自己の発達を不完全にするようなものである』とまで考えるんだから」
「池の女も、野々宮の妹よし子も全部欲しいってわけね。汽車の女に馬鹿にされたことへの反動かもしれないわね」
「これをして、三四郎のハーレム構想と呼んでもよいかもしれない。あるいは、ハーレム妄想か。まあ、妄想するだけで、実行する勇気はもたないわけだけどね」
「やっぱり『よほど意気地のない方』なわけね」
「言いたい」
「うん」
「では、どうぞ」
高満寺が、大きく息を吸い込み、そして吐き出した。
「わりゃあ、どごゆんな! なんでんしっとっとぞ!」
(第19回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月15日に更新されます。
■ 遠藤徹新刊小説 ■
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


