
学園祭のビューティーコンテストがフェミニスト女子学生たちによって占拠された。しかしアイドル女子学生3人によってビューティーコンテストがさらにジャックされてしまう。彼女たちは宣言した。「あらゆる制限を取り払って真の美を競い合う〝ビューチーコンテストオ!〟を開催します!」と。審判に指名されたのは地味で目立たない僕。真の美とは何か、それをジャッジすることなどできるのだろうか・・・。
恐ろしくて艶めかしく、ちょっとユーモラスな『幸福のゾンビ』(金魚屋刊)の作家による待望の新連載小説!
by 金魚屋編集部
1.ブロークン・ヒールズ
すべては、クーデターから始まった。
「わたしたちは恐れを知らない」
マイクから放たれた第一声がそれだった。
黒いウェディングドレスを来た女子学生たちによってステージが占拠されていた。チュールスカートのミディドレス。頭にも黒いベールをかけている。両手を腰に当てて整列し、仁王立ちした黒い花嫁姿たち。
まるで華麗だけど凶悪なカラスの集団という趣。
黒いドレスは彼女らの「戦闘服」なのだ。
この「戦闘服」の意味について、彼女らはこう説明している。
《白いウェディングドレスは、従属の証。
純潔、純粋、清楚をあらわす白。
それは、あなたの色に染まります」というメッセージ。
さらに「わたしはあなたの所有物です」という意味へとつながる。
だからわたしたちは、黒く塗る。
純白のウェディングドレスに憧れる心性に死を!
わたしたちが自立するために!
従属を拒絶するために!
ジェンダーギャップを、否定するために!》
「だから強い。気をつけることね」
マイクが奪い取られた。
学園祭恒例行事のミス・キャンパスの開催を告げようとしていたわが友から。口八丁手八丁の名司会者である男、口から生まれたともっぱらの評判の口先男である稗田亜礼。その稗田から、
「ちょっと、お貸しなさい」
とマイクを奪ったのは黒いドレスの橋田由香だった。この大学で知らぬ人はいない武闘派フェミニズム団体ブロークン・ヒールズの代表にして、恐れを知らぬ論客であった。
「えっと、そのマイクは」
稗田は、おずおずと自分のマイクに手を伸ばそうとした。
「およしなさい!」
橋田由香は、稗田の手を払いのけた。
「それ以上の接近は、セクハラ行為として糾弾しますよ」
男を委縮させる手榴弾のような言葉だった。これによって、本来の司会者であった稗田は手も足も出なくなった。ミスキャンの舞台となるはずだったステージは、完全に制圧された。クーデターを起こしたフェミニズム団体ブロークン・ヒールズによって。

ブロークン・ヒールズといえば思い出されるのは、文学部槍杉教授を退職に追い込んだ体当たりの誘導作戦だろう。この功績で橋田由香は本学のみならず、他大学のフェミニスト団体からも多大な支持を受けるにいたったのだった。
文芸評論家として名高かった槍杉多郎の周辺には以前から、パワハラ、アカハラ、モラハラ、セクハラの噂が絶えなかった。いわばハラスメントのデパート状態である。けれども槍杉教授の隠蔽工作は微に入り細をうがった慎重なもので、なかなかボロが出なかった。彼の文芸評論もまた、作品の微細なほころびを丁寧にあぶり出して、あたかも寄生虫のごとくそこから作品内に入り込み、食い散らかし、挙げ句の果てに名作を駄作へと蹴落とすという類いのものであった。世に認められている名作の小さな傷をこじ開け、こじらせ、台無しにするというある意味疫病感染的な技法であり、書き手たちからは、極悪ウィルスと煙たがられていた。
「このままではラチがあかないって思ったんです。これ以上犠牲者を出しちゃいけないって」
後のインタビューで橋田由香はそう語った。
「だから、わたし自身が標的となることを選択したんです」
橋田は槍杉のファンを装って、研究室を訪れた。
「実際には、あの人の本は虫酸が走るような陰険さに満ちたものでした。随所に散見される女性観も表面的にはフェミニストを装った、性差別主義者のものでしかありませんでした」
本を抱えてサインを求めに来たミニスカートにぴちぴちのTシャツ姿の橋田由香を見て、即座に槍杉は罠にかかった。
「先生の最新刊『「古典文学」はすべからく駄作である!』、とても感銘を受けました。先生の鋭いメスの前には、シェイクスピアもドストエフスキーもプルーストも恐れおののき、ジョイスは逃げまどい、ダンテやセルバンテスは土下座し、夏目漱石や森鴎外もまた涙を流し、命乞いしながらひれ伏すしかないんですね。世界がひっくり返るような衝撃を受けました」
「ほほう」
槍杉は、獲物をみつけた狐の目となった。
「そうだろうとも、うん」
橋田のみごとなよいしょに乗せられて、槍杉は自分の批評眼の鋭さについて誇らしげに語った。
「だいたいねえ、一流なんて言われてるものは全部胡散臭いわけでね。ほんとは穴だらけなのに、それを神様みたいにみんな祭り上げてるわけよ。見るべきところから目を背けてねえ。イワシの頭も信心からってわけだ」
「ええ」
「その欺瞞っていうか、虚飾っていうか、無批判な信仰っていうかさ、そういう愚かさをね、ぼくはさ、ほら、どうです皆さん、これがほんとうに名作なんですか? って具合にね、全部目に見えるかたちにしてさらけ出してあげてるわけだよね」
「なるほど、となると真の一流は、この世に先生一人ってことになるわけですね」
「あれえ、そうなるかなあ」
「そうですよ、そうとしか考えられません」
「ふふ、そう思うかね」
「だって、先生はシェイクスピアよりもゲーテよりもダンテよりもえらいわけですから。やっぱり世界一ってことになりますよね、必然的に」
「はは、そうかな。世間のやつらはそうは言わんけどね」
「それは、やっかみじゃないですか。先生の知性の鋭さに、みんな嫉妬してるだけなんですよ」
「それはね、まあぼくだってそう思わないことはないんだよ。ぼくの価値は不当に軽んじられている。ぼくはこんなちっぽけな大学でくすぶっているべき人間じゃないんだってね」
「ノーベル批評賞を受けるべきですね」
「いや、文学賞でいいよ。ぼくの評論はすでにしてひとつの文学作品なんだから」
「うわ、すてき。じゃあわたしいまノーベル文学賞受賞者・・・、であるべき方とお話をしているわけですね」
槍杉はふふっとほほ笑んだ。
「そうだね、まあそうなるね」
「感激です、握手してください」
(のちに、その時の槍杉の手の感触を橋田は「ウナギ寄りのへびに触れた感じ」と形容した。「ぬたぁべちょぉキモォ、って感じでした。触れた瞬間寒イボが全身にわきました。いえ、相手に見られるわけにはいかないので皮膚の裏側全面にわかせましたけどね」)
槍杉は、橋田のてのひらを撫でまわした。
「やわらかいねえ、君の手は。いいねえ、若い子は。ふん、シェンケルなんかもほら、むちむちしてる」
「シェンケル?」
「そう、ドイツ語でね太もものことさ」
「あら、先生どこ見てるんですか」
「触れてあげようか?」
「え、いまなんておっしゃいました?」
「いやいや、なんにも言ってないよ」
「そうですか」
「まあ、いいか座り給え」
槍杉は気づいていないのだが、彼の一挙手一頭足、さらに一言一句にいたるまでが、橋田の胸元のブローチ型カメラを通して、インターネットに流出していた。衆人環視のもとにさらされていたわけだ。この時点ですでに、視聴者による判定はアウトだった。
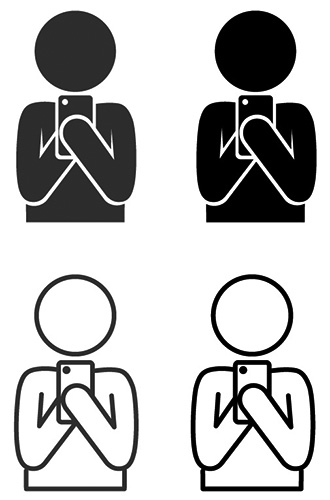
「ところで君、オレンジジュースは好きかな」
槍杉は、橋田をソファに座らせると、冷蔵庫から瓶に入ったジュースを取り出した。
ネット上の映像には、他のメンバーによって、
「出たあ、これがかの有名な昏睡レイプ用特製ジュース!」
というキャプションがインポーズされた。
「わあ、うれしい。いただきまあす」
グラスになみなみと継がれたジュースを受け取る橋田由香。グラスを口元へと運んだ時だった。申し合わせ通りにドアをノックする激しい音が響いた。
「誰だ、こんな時に!」
いらつきながらドアを開ける槍杉教授。そこにはブロークン・ヒールズのメンバーたちがいた。ネットのカメラは、彼女らの内の一人のカバンに仕込まれたものへと切り替えられた。
「なんだね」
「先生、わたしたち論争を挑みに来ました」
「論争? 学生風情の君たちが?」
あからさまにバカにした表情で応じる槍杉。
「ええ、そうです」
「君らの知力じゃ話にならんだろうが」
槍杉はあからさまに彼女らを見下す目をした。抵抗するウサギをあなどる狐の目だった。
「でも、わたしたち先生の批評スタンスにすごく違和感を感じるんですよね。大事な根幹のところを見ないで、細部のあらを探し、そこから強引に入り込んで大事な根幹を台無しにするような議論を展開される。それって、批評じゃなくて、相手の隙を突く卑怯な攻撃だって感じるんです」
「ははははっ」
槍杉は高らかに笑った。
「それはね、君たちの読みがいかに浅いかってことを暴露しているだけなんだよ。とにかく今日は忙しいから、また今度来なさい。いいね」
「何に忙しいんですか先生?」
「誰かいるんですか?」
口々に問いかけるメンバーたち。
「うるさいな、とにかく今日はだめだ。また今度来なさい。できれば集団じゃなく、個人で来てほしいな。そのほうがじっくり」
「じっくり、なんですか?」
「決まってるだろ、じっくり意見が交わせるって言ってるだよ」
「そうですか。でも、女子学生を部屋に入れるときは研究室の扉は全開にしておくきまりじゃなかったですか」
「知ってるよ」
「いま、誰かいるんじゃないですか?」
「いや、いないいない、誰もいない」
「さっき、誰か入っていくのを見た子がいるんですけど」
「ああ、ちょっとサイン貰いに来た子がいたけど、すぐ帰ったよ」
「そうなんですね」
「そうなんだよ、とにかく帰ってくれ」
バタム!
あわてて扉を閉めて戻ると、テーブルの上には空っぽになったグラス。そしてお約束通り眠りに落ちた橋田がソファにぐったりとなっている。
当然これは仕掛けなわけで、仲間が注意を惹きつけている間に、橋田は証拠品であるジュースを用意してきた瓶に移してソファの後ろに隠した。そのうえで、眠ったふりをしているだけだった。もちろん胸元のブローチはちゃんと槍杉が移る角度に調節してあった。
橋田に近づく槍杉の顔が徐々に大写しになる。殺したウサギを見下ろす飢えた狐の目をしていた。
しどけない姿で眠っている橋田をじっくり見まわしてから、槍杉は一度ドアの鍵を掛けに戻り、ついで三脚につけたビデオカメラをセッティング。
「ははは、愚かな女子学生め。いや、橋田由香。お前があのちょこざいなブロークン・ヒールズのメンバーだってことは最初からわかってたさ。だけど、単身ここに乗り込んできたのが運の尽き。残念ながら、お仲間たちはもう追い返したしね。いいかね、わたしの前で恐れおののき、涙を流し、命乞いするのは文豪たちだけじゃないんだ。すべてのメスブタどもも同じなんだよ。さて、それではいまいましいフェミニズムの徒を、ぶひぶひ鳴かせ、わたしの足下にひれ伏させてやるとするかな」
槍杉は、獲物を食らう狐となって橋田に挑みかかろうとした。ところがである。挑みかかろうとした槍杉の目の前で、昏睡していたはずの橋田がぱっちりお目々を開き、がばちょっと身を起こした。
虚を突かれてうろたえる槍杉教授。
「インディアンサマー!」
橋田の意味不明の大声にぎょっとなる槍杉。どうやら言い間違えたらしい橋田は、こほんと咳ばらいをして言い直した。
「ご愁傷サマーっ!」
まったく低劣だった。レベルが低すぎるダジャレだった。高尚なものを求めてやまない槍杉の心が砕ける音がした。次いで橋田は、心底憐れむ口調でこう告げた。
「これで先生の教授生命も批評家生命もジ・エンドですね」
スマホの画面をかざされ、そこに自分の姿が映っていることを知った槍杉は激昂、
「ま、まさかお前、一部始終を!」
「ええ、ごらんください。現在のところ三万ビューですね。書き込みはもう読み切れないほどありますし。録画もされていますから、もう言い逃れも不可能でしょう。後ほど、先生の悪名高いビデオコレクションも改めさせていただきますよ」
「くそっ、止めろ、すぐに映像を止めろ」
「もう遅いんですよ、先生。覆水盆に返らず、腹水あふれて生き返らずです。全部流れちゃったんだから」
「このメスビッチが!」
「えっ、なんですか、それ? 日本語と英語スラングのごちゃ混ぜとは、批評家ともあろうお方が情けない言語センスですね」
襲いかかった槍杉の腕は、みごとな手さばきでひねり返された。奇妙なかたちに歪む槍杉の腕。あまりの痛みに槍杉はうずくまって呻いた。そう、彼女は柔術の使い手でもあったわけだ。
「わたしたちはすべての女性に護身術を広める活動もしているのよ。卑劣な暴力から女性たちが身を守るためにね。わたしは師範の資格も持っているんですよ」
「い、痛い。暴力反対。は、放してくれ」
そもそも暴力を振るおうとしたのが自分だったということを槍杉教授は完全に忘却しているようだった。この都合のいいスタンスは、彼の批評の根幹をなすものでもあった。
「まったく卑劣漢ね。あなたのことはこう呼ぶべきね。根腐れディック! どうかしら、こちらも日本語と英語スラングの組み合わせよ」
部屋の鍵を開けると、ブロークン・ヒールズの仲間たちが雪崩れ込み、槍杉の部屋のなかを大捜索。
「やめろぉ、やめてくれぇ」
頭を抱える槍杉だが、昏睡している女にしか手を出せないへたれである。おろおろするよりほかはなかった。
やがて、疑惑のビデオ数十本が書棚の最下段の本の裏側から発見された。ただちに警察に通報がなされ、翌日、槍杉は教授職を解任された。むろん、批評家としての名声も地に落ちた。ノーベル賞級であったはずの彼の著書はすべて絶版となり、古本屋の百円コーナーに並んだまま背表紙が日焼けしていく宿命を負うこととなった。
いまは田舎町でキャバレーの呼び込みをしているという噂もある。それが案外性にあっているのか、とても生き生きした姿なのだそうだ。まあ、これは根拠の薄弱な情報なので、嘘かほんとかわからないわけだけど。ほかにも借金がかさんでマグロ漁船に乗っているという噂もあるが、そんな激しい肉体労働が務まるとはとても思えなかった。
これが、橋田由香が身体を張ってなしえた偉業のひとつであり、この大学に行動派フェミニズム団体ブロークン・ヒールズありということを世に知らしめた出来事でもあった。
でも、槍杉教授の目がくらんだのもむべなるかなだ。こんなこと口にしたら「このルッキズムの輩めが!」と橋田に思い切り叱られるに決まっているんだけど、凜としたお顔、そして白豹のごとく引き締まったお体に、黒いウェディングドレスが絶妙に似合っていた。ダーククイーン降臨!って感じ。しもべのカラス軍団を引き連れて。
とはいえ、橋田由香の武勇伝はとりあえずこれでおしまい。
ここは再び現在です。
占拠されたミスコン会場から実況中継でお送りしまぁす。
「本日、この会場にお集まりの皆さん」
橋田由香ははりのある声で訴えかけた。
「わたしたちは、思想なき本学執行部が不当にも開催を許可した、ミス・キャンパスというイベントに対する抗議活動を続けてきました。署名を行い、勉強会を開催し、学内デモもぶちかましましたァ!」
そうだあ!
いいぞ橋田ぁ!
差別主義者どもをぶちのめせぇ!
支持者からのどよめきがあがり、橋田は笑顔で手を振る。アイドルみたいに、っていったらまた怒られるわけだけど。
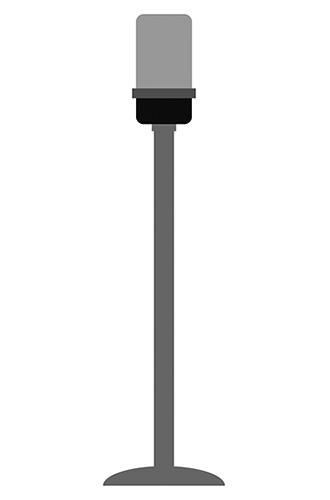
「それでも、『伝統行事だから』などというふざけた返答しか出せなかったクソな大学、『女性のうわべではなく内面を評価するイベントです』なぞとふざけた偽りの声明を出した実行委員会、てめーらぶっ殺ーすっ! それらすべてにわたしたちは怒り心頭に達し、ブチギレ怒髪天を突き、爆発する活火山となって本日このような占拠行動に及んだ次第なのです。さあ、わたしたちのこの折れたヒールで踏みつけられたいやつがいたら、前へ! 前へ!」
ドンドンドンドン!
彼女にならって、黒いウエディングドレスの一団がステージ上で地団駄を踏むがごとくに、折れたハイヒールでストンプした。そう彼女らのシンボルは、折れたハイヒールなのだ。《見栄えのために女性にだけ不自由な歩行を強いるのは女性蔑視であり、女性支配の象徴である》と彼女らは考えている。だから、ハイヒールのヒールをたたき折ってパンプス状にしたものを履くのが、出動時の特徴なのである(残念ながら、そんなブロークン・ヒールに踏まれたいと願望する不逞の輩はかなりの数実在するらしいけど)。
いいぞ橋田ぁ!
踏みつけてやれぇ!
ルッキズムの徒を踏みつぶせぇ!
セクシズム撲滅ぅ!
ぼくたちが何ヶ月にもわたって準備してきたこのイベントはもはや風前の灯火だった。
「しかし、橋田さん」
なんと勇猛果敢にも立ち上がった漢(ル、おとこ)があった。
司会者ということで、安っぽいスーツに身を包み、首元には真っ赤な蝶ネクタイをつけたある意味滑稽な姿の稗田亜礼。七三に分けた地味な髪型に、地味な容貌の、中肉宙背の男。さきほど、不意に舞台に現れた黒い集団に囲まれ、あっという間にマイクを奪い取られた、ふがいない男。
ただし、侮るなかれ、この男には類い希なる才能がひとつだけあった。トーク力である。とにかく話がうまいのだ。新入生のころから毎年司会に抜擢されているのも、その話術の巧みさゆえだった。
とはいえ、しょせんはミスコンの司会者。思想などなにも持ち合わせてはいない。そんな稗田が無謀にも、フェミニズム理論の権化に論戦を挑んだのだった。
お前気は確かなのか?
お前も踏みつけられたい口なのか?
稗田の蛮勇に、なぜかぼくが痛みを感じた。確かに稗田がかなりの論客であることは認めるけれど、相手があの才女では勝ち目はないように思われた。
ちなみに、ぼくと稗田は幼稚園からの親友だったりする。ぼくはどちらかというと奥手な方だったけど、稗田は幼い頃から口が達者で外交的だった。奥手だったぼくとは対照的に、誰とでも話せるタイプだった。
「君は特別な存在なんだから、元気を出せよ」
そんなことを言われたのは中学三年の時だった。
はあ? である。
頭大丈夫ぅ? である。
「なんだそれ?」
まったく言っている意味がわからなかった。
その時のぼくはそれどころじゃなかった。
深い悲しみのなかにいたからだ。
「知らないのかい? 君の親はなんにも言ってないの?」
「だから、なんのことだよ」
「それなら、やめとくか」
それきり、その会話は終わりになった。だけど、稗田はその時ちょっとだけこんな告白をした。
「ぼくはね、語り部の家系なんだ。主君の家にお仕えして、その歴史を語り、現在を盛り上げ、未来への希望を膨らませる。そんな言葉を贈りつづけるのが仕事なんだって教わってきた」
「そんな家系があるんだね」
とにかくどうでもよかった。それは、あゆみを、篠田あゆみを失った直後のことだったからだ。
「わたし死にたくないわ」
病床であゆみはぼくにそう言った。
「じゃあ、死なないでよ。ずっといっしょにいてよ」
「うん、いっしょにはいたい。死なないでいたいよ」
そう言って泣いた。ぼくも泣いた。三日後あゆみはぼくを裏切った。いっしょにいてくれることをやめたからだ。
それ以来ぼくはずっと深い喪失感のなかにいる。稗田は、そんなぼくにずっと寄り添い、大学受験の時もしつこくぼくの進学先を聞き出し、ぼくが受けたすべての大学をいっしょに受験しすべてに合格した。ぼくが受かったのはこの大学だけだった。すると、もっと上のランクの大学に幾つも受かっていたにもかかわらず、稗田は迷わずぼくと同じ大学の同じ学部に入った。理系科目も得意だったのに、文学部に入ったのだ。
「なんでだよ。お前、もっといい大学行けたのに」
「いいんだよ、それが俺の人生だから」
ところで、と稗田は言った。
「俺、ミスコンの実行委員になったから。お前も賛助会員に登録しておいたからな。お前も来いよ」
「なんだよ、勝手に」
「必要なんだよ、お前が。お前がいれば、どんなイベントも盛り上がること必定だからな。っていうか、きっと何かが起こるんだ。何かすごいことがさ」
再びの、はあ? であった。
「何の話だよそれ?」
「ああ、いやなんでもない」
手を振って稗田は立ち去った。その時、言っとくけど、ぜんぶお前のためだからな、とそんな言葉が聞こえたような気がした。でも、そんなはずはないだろう。とにかく、いい奴なんだ、稗田は。だけど、橋田に挑むのはいかがなものかなと思うけど。

「お言葉ですが橋田さん、このイベントは実際、参加した多くの女子学生から就職に有利だったと評価を受けてもいるんですよ」
アア、挑んでしまった。稗田のやつ、勝ち目のない論法で立ち向かいやがった。どういうことだ。やられたいのか、あるいはやりこめられるのが楽しみなのか?
「つまり、女子アナになったとか、キャビンアテンダントになったとか、そういう話でしょ?」
「ええ、まあ、それはそうですけど」
言葉に詰まった稗田は、さらにも墓穴を掘った。
「そういえば、日焼け坂四四のメンバーである西野由香さんも、このイベントの出場者だったんですよ」
「へっ!」
鼻でせせら笑われた。
「つまりは、このイベントに出場することで、容姿や見かけが優れているというお墨付きが得られるってことでしょうか?」
「もちろん、それもあります。ただ、このミスコンの審査は決して表面を見るだけではなくてですね」
「お黙りぼんくらバスタード!」
橋田の和洋混淆した一喝に、稗田はすくみあがった。
「そもそも、女子アナとかキャビンアテンダントという職種そのものが、ルッキズムをそのまま肯定する愚かな仕組みだという大きな、ビッグ・アンド・ラージな前提を、あなたは見損なっていますね。いわんやアイドルおや」
急に古臭いフレーズも飛び込んできた。
「いや、そこまでいうと、社会の仕組みが」
稗田の言いたいことはわかった。たかが一弱小大学の文化祭イベントだ。社会の枠組みを超えることなんてできない。その枠内で楽しんで何が悪いのだ。こんなのたいしたことは無かろうとそういいたかったに違いなかった。
しかし、無論のこと橋田由香の前でそんな屁理屈をこねたところで、まさに屁にすぎないことは明白だった。
「そうなのです。社会の仕組みそのものが過っている。だから、高等教育機関としての大学の使命は、そうした歪みを是正する方向へと向かうべきなのです。そうではないでしょうか、皆さん?」
そうだ!
無論だ!
稗田の蛮勇は、つまり燃え上がる橋田由香に油を注ぎかけるだけに終わったというわけだった。
「さあ、これでおしまいです。本年この時をもって、この学園の恥辱的伝統行事であり、致命的ミスであったミスコンは終了します! そうミスコンのミスは、間違いを意味するミスなのです!」
よく言った!
いいぞ!
橋田由香万歳!
そんな盛り上がりのただなかだった。まるで降ってわいたかのように、三つの影がステージ上に出現した。
「はーい、そこまでぇ」
「主役交代きゅん」
「これよりこの場は私たちの管轄下に入る!」
声が上がった。新たな犠牲者の登場か? また橋田由香のブロークン・ハイヒールの犠牲者となりたい者が出現したようだった。
皆が見た。
解散寸前だった聴衆がその方向を見た。
橋田由香もその方向を見た。
で、ぼくも見た。
(第01回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『ビューチーコンテストオ!』は毎月13日にアップされます。
■遠藤徹の本■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


