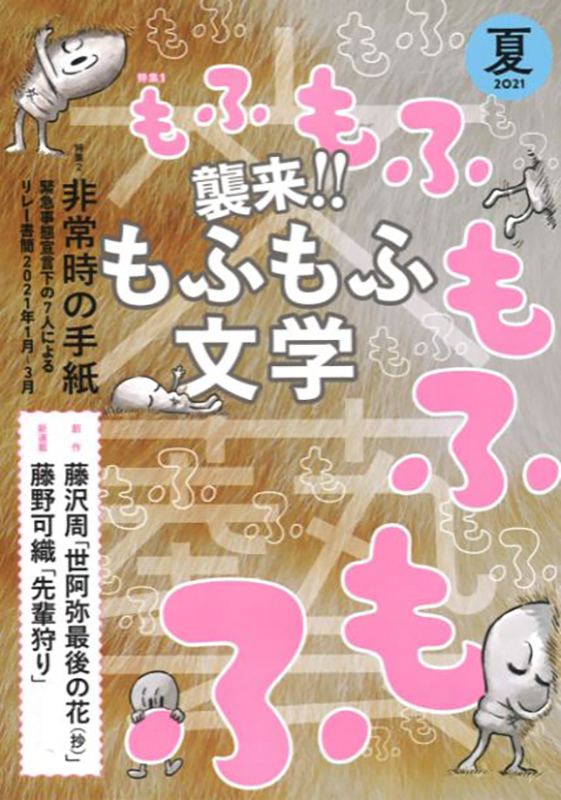
この夏は蚊帳をつらなかった。天から吹き流れるようなあの大きい蚊帳を。つらないまんまに、夏がすぎてしまった。(中略)
あぁ、またか。
身を起こしてガラス戸を開ける。思いのほか寒々しい風が流れてきた。秋のはじめのような肌ざわり。(中略)ここは東北で、私は蚊帳をつったことがない。生まれてから一度も。だから、蚊帳をつらなかった、などと私が思うはずがない。でも、いつもしていたはずの何かをしないまま時の過ぎてしまった遣りきれなさは、目を覚ましても身体に残っていた。(中略)
きのう浜辺に、はまなすが咲いていた。だれもいない砂浜に、海風に揺られて赤い花が咲いていた。その花びらのような色の空だ。明けはじめた東の空は、はまなすみたいな色だった。
今日青函トンネルをわたります、と英里子に連絡すると、やっとか、と返事が来た。
藤代泉「ミズナラの森の学校」
藤代泉さんの「ミズナラの森の学校」の主人公は沢渡静子。二十代後半の若い女性である。「沢渡静子って名前が、さわた・りせこって聞こえたから、りせっ呼ばれているんですよ」とあり、作中では「りせ」の愛称だ。
りせは大学三年生の時に同級生の英里子に誘われて「ミズナラの森の学校」に行った。北海道の中ほどの奥まった山間地にある小さな教育施設で「不登校の子や、さまざまな事情で養育の困難な家庭の子たちを受け入れる、全寮制の施設」だった。りせと英里子は春休みの一ヶ月をボランティアスタッフとして学校で暮らし、英里子は卒業すると学校に就職した。
りせは学生時代から付き合っていた「ぽっぽ」というあだ名の男と同棲し東京で塾講師をしていたが、仕事を辞めるのと同時に彼と別れた。それを英里子に告げると「よかったらこっち、ひと月くらい来ない?」と誘われたのだった。りせは学校を訪ねることにした。ただし直行せず電車を乗り継いでゆっくり北上していった。「旅をしている、というよりは、漂泊しているような感じがする。(中略)俗世を捨てて諸国をめぐる、漂泊の僧みたいに」とある。
引用は小説の冒頭である。「この夏は蚊帳をつらなかった」とあるが実際の季節は五月。またりせは夏に蚊除けの蚊帳を吊った経験などない世代だ。ただこのような記述は以後何度も小説の中に現れる。りせは他者の記憶を自分のものとして受け入れてしまう感性を持っているのだ。統合失調症などの精神の病ではない。「何かをしないまま時の過ぎてしまった遣りきれなさは、目を覚ましても身体に残っていた」とあるように、自己とは何か、自分のやるべきことは何かを摑み切れていない不安にスリップするように他者の記憶が紛れ込んでくる。
また北海道に渡る前の東北の宿でりせは海岸を散歩する。「はまなすが咲いていた。だれもいない砂浜に、海風に揺られて赤い花が咲いていた。その花びらのような色の空だ。明けはじめた東の空は、はまなすみたいな色だった」とある。このようないわゆる〝詩的〟な表現も小説には頻出する。ではミズナラの森の学校がユートピアのような世界かというとまったくそうではない。むしろ逆である。
自分の部屋の窓から外を見ていたりするときに、バス停から雪道を歩いてやってくる学校帰りの椿君の姿が見えることがあった。こちらに気づくと屈託のない笑顔で大きく手を振る。とたんに厭な感情が湧き、じょうずに答えることができなくて、いつも小さく手を振りかえした。(中略)
私がよくこうして、窓から身を乗り出して外を見ていたからだろうか。椿君が、自分の部屋から身を乗り出して、こちらを見上げるときがあった。りせちゃん、そう言って笑う。(中略)自分が不快な気持ちを持って彼を見下ろしていることがたまらなく厭で、ふつうに接することができたら、と思った。
同
物語は現在のミズナラの森の学校の生徒やスタッフと、七年前、りせが大学生の時にボランティアで滞在していた時の記憶が輻輳しながら紡がれる。椿君は七年前の生徒で母親が新興宗教にのめり込んで育児放棄してしまい、養護施設を経てミズナラの森にやってきた。りせと知り合った時は中学二年生だった。いつも首にネックカラーを巻いていた。しかし首を怪我していたわけではない。
椿君には「さくら」という名の姉がいたが幼くして亡くなってしまった。母親はすぐに散る「さくら」という名前を付けたせいだと思い、息子の「椿」も首がポトリと落ちて死んでしまうのではないかと恐れた。そこで幼児の頃から首にネックカラーを巻かせたのだがそれが彼の発育を妨げ、本当に首からネックカラーを外せなくなってしまったのだった。
りせは椿君がなんとなく苦手だった。扱いにくい生徒だったからではない。その逆で、彼が「人懐こく、だれにでも近寄ってゆく」のが厭だったのだ。りせは椿君の言動に母親にネグレクトされてかえって良い子になってゆく子供の痛ましさを感じていた。もちろんその姿はりせの子供時代に重なる。椿君ほどではないがりせもまた複雑な家庭で育ち、その重荷を全身で受けとめてしまう繊細な子供だった。
椿君はミズナラの森を出て全寮制の高校に通い始めたが、乗っていたバスが東北自動車道で事故を起こして亡くなってしまった。七年前、りせが勉強を教えていたときに彼は「さくらが死んだみたいに、ぼくもそのうち死ぬんじゃない? ぼくもお母さんも、そればっかり思ってるから、叶うんじゃないかな」と言った。りせは思わず「ふざけんな、お前たちの思う通りになると思うなよ」と口走った。意志に反して声に出てしまった言葉だった。りせは「ときどきこういうことがあるの。思ってもいないことが、口から」と謝った。
しかしりせの言葉は現実にはならず、椿君は彼の言葉通り不慮の死を遂げてしまった。椿君の母親は全国で開催される新興宗教の集いで娘のさくらを亡くした悲痛を講演して廻っていたが、息子が亡くなっても彼女が口にするのは相変わらず娘のさくらのことだけだった。しかしそれまでミズナラの森に学費さえ支払っていなかったのに、息子が死ぬと母親は学校に多額の寄付をした。母親の言動は彼女には一貫しているのだろうが他者からは支離滅裂だ。そこにあるのは絶望だろうが、彼女にも他者にもわからない質のものである。現実が思い通りにならないのはりせの方だということでもある。
ゆなちゃんは寝転んだまま数の子の方を見る。
「だいじょうぶだよ」
いつもと変わらない声で言う。
「いたくないよ。ぜんぜんいたくない」
英里子は私の鞄からティッシュを持ってきて、と友弘に指示して、ほかの子たちもわらわらゆなちゃんの所に寄ったり、車から救急箱持ってくる、と走り出したりした。数の子は動揺した目になっていた。身じろぎひとつできないでいる。硬直したまま動かない。私は数の子のそばに寄り、ちょっと来て、と声をかけた。ほとんど無理やりに皆のもとから引き剥がすように連れて行った。(中略)
私は数の子の、視線を落とした顔をしばらく眺めていた。
ずっと抱えているんだろうな、と思った。自分でも止めることのできないものを。抱えたまま生きてきたんだろうな、と。この人もまた、そうなんだ。今もずっと、しんどいんだろうな――数の子の視線の先にある地面のほうに目をやると、しっとりとした土から縦横に這うように草が伸びている。しっかりと地面に張った根からいっせいに芽吹いた若い草の色だった。
同
りせが訪れた現在のミズナラの森にはボランティアの大学生が先に滞在していた。口数が少なく生徒の面倒も見ようとしない。ほぼ一日中パソコンの前に座ってミズナラの森のHPを作り直している。おまけに偏食で、最初の日に冷蔵庫を開けて食べられる物は数の子しかないと言ってそれを食べ始めたので数の子というあだ名がついた。卒業の単位か就職の箔付けに必要だからミズナラの森に来たという感じの青年だ。
このつっけんどんで気難しそうな青年に、なぜかゆなちゃんが強い興味を示した。特別支援学校に通っている小学五年生の女の子だった。ゆなはなんとか数の子と仲良くしようとするが、彼はにべもない。ただ生徒たちと公園に行ってボール遊びをしている時に数の子が蹴ったボールがゆなの顔を直撃してしまう。大事には至らなかったが初めて数の子は感情を露わにした。動揺した。その姿を見てりせは「ずっと抱えているんだろうな」「自分でも止めることのできないものを。抱えたまま生きてきたんだろうな」「この人もまた、そうなんだ。今もずっと、しんどいんだろうな」と思う。
数の子は当然ゆなに謝るが、だからと言って彼とゆなの間に友情や愛情が芽生えるわけではない。またりせはこの事件をきっかけに少しだけ数の子と仲良くなり、ミズナラの森に昔からある調律の狂ったピアノを数の子が演奏し、りせがギターを演奏する。その合間に二人は言葉を交わし、自分たちが受けた過去の傷も少しずつ告白する。が、心を通わせるといったところにまでは至らない。ミズナラの森にいる生徒もスタッフも、多かれ少なかれ何かを「ずっと抱えている」。それを解消し、霧散させてしまうのは不可能だ。狂った調律は修正はできても根本からは直らない。
「さっきね、エゾリス、いたんだ」
ずっと会いたかったけど、会えなかった。でも、やっと会えたんだよ。かわいかった。(中略)
「松くんもいつか会えるかもしれない」(中略)
ゆっくりしていいからね。
そう声をかけて、私はちょっと掃除してくるから、と掃出し窓をあけた。
窓の向こうはすっかり霧が晴れて陽が射していた。水を含んだ校庭は眩しく光を照り返す。遠くつづく丘陵の樹々は、エメラルドみたいな色の葉をつけて、しずかにゆれている。空は澄んで青かった。よく晴れた日の、湖みたいな色だった。
ふいに、だれかの作ったしゃぼん玉が、ふわりと飛んでゆくのが見えた。小さな丸がいくつもうかび、光を受けていくつもの色をふくんで、たちまち色味を変えてゆく。しずかな風にのって、たゆたってゆく。
「見て」
だれにともなく、ふとこぼす。
「しゃぼん玉」
目のまえには、ふわふわと、ちいさな虹色の丸がいくつもうかんでいる。
きれいだった。
同
松くんという生徒が新たに入校してくる。彼は言葉を発しない。りせを含むスタッフも無理に話させようとはしない。狂った調律を抱えた者たちは自分でそれを修正し自からの意志で音を出すまで放っておくしかない。
「遠くつづく丘陵の樹々は、エメラルドみたいな色の葉をつけて、しずかにゆれている。空は澄んで青かった。よく晴れた日の、湖みたいな色だった」「だれかの作ったしゃぼん玉が、ふわりと飛んでゆくのが見えた」といった記述は純文学ではそれほど珍しいものではない。人間のどうしようもない苦悩を春夏秋冬の季節の巡りや大自然の美に溶解させて、なし崩しにしてしまう手法を純文学作家たちは手垢がつくほど多用してきた。
しかし藤代さんの「ミズナラの森の学校」での自然や美の使い方は従来の純文学小説のそれとは違う。最初から自然描写は滅びの美として援用されている。英里子は学長が寄付集めに奔走しなければミズナラの森はすぐに立ちゆかなくなると言う。学長は「銀河鉄道に乗って」「星屑集め」をしているのだとも言う。浮世離れした理想だということだ。数の子は親からピアノの英才教育を施されるのが嫌でたまらず、年老いた調律師が来てピアノを弾けない時間が救いだったと言う。その老調律師は「坊ちゃん。これは私から、坊ちゃんへの宿題です。調律とは、なんでしょう」という謎かけを発した。
銀河鉄道の行き着く先も、調律とは何かという謎かけも解かれることはない。ただその見えない未来と解けない謎が、儚い自然の美となって表現されている。その意味でこの小説では最初から自然がある種の絶望として援用されている。答えらしきものに近接しながら決して辿り着かない絶望と空虚の裏返しとしての美と言っていい。その意味で地味な作品だが「ミズナラの森の学校」は〝攻め切った〟小説である。中途半端な救いは設定されていない。
ただ最初から自然描写を〝詩的〟という審級として援用すると、それは決して〝詩〟に飛躍してくれなくなる。詩に飛躍させるためには逆接的な言い方になるが詩的要素を排除しなければならない。リアリズム残酷小説の窮極点でなければ詩と呼ばれる観念の上昇は起こらない。絶望としての詩的要素の援用は有効だが、それはいつか詩に飛躍しなければならないのではなかろうか。
大篠夏彦
■ 藤代泉さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■







