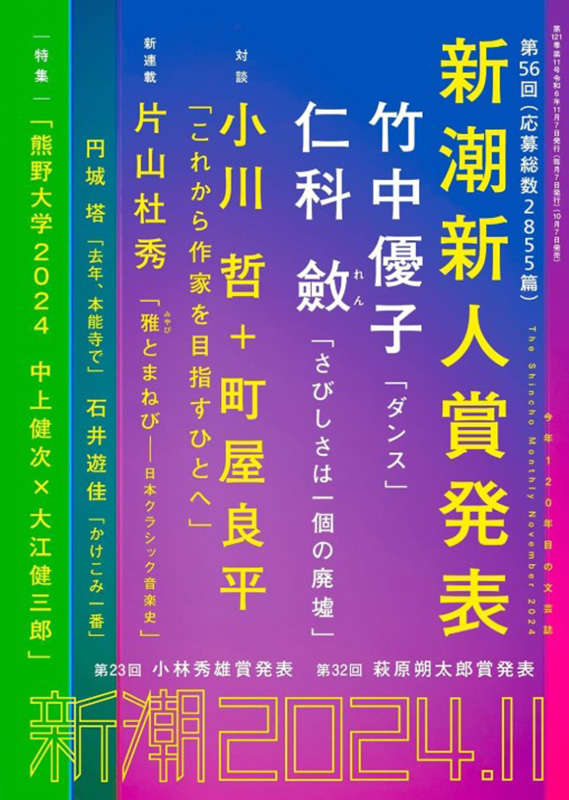
お笑い芸人という職業がありますよね。
あの人たちを、ワタシはとても尊敬しています。人を笑わせることって、大変なことだと思うからです。小学生のころのワタシは、今日はどうやってクラスの連中を笑わせようか、明日はどうしようかと日がな一日そればかり考えて過ごすような子どもでした。じぶんは天性の道化と信じていたんです。
笑いを取れる人には、じぶんが意図しない偶発的なふるまいによって笑いを呼び込んでしまう人と、刻苦精励、長い下積みの末にお笑い芸を身に着けた人の二種類がいます。ご存じのとおり、お笑い芸には落語のようにあるていど「型」の確立されたものと、漫才などの「自由型」があります。いずれも精錬をきわめた芸だと思いますが、そのつどネタを考え、仕込まなくてはいけない「自由型」はやはり大変です。そんな中でも秀でた芸人さんは、じぶんが意図しない偶発的なふるまいさえ巻き込んで笑いを呼び込んでしまえる人でしょう。
弱冠どころか一七歳で新潮新人賞を受賞された伊良刹那さんの「海を覗く」は、作品全体がひとつの笑話として読める、おそらく近年まれに見るユニークな小説です。
おちょくっているのか。ご本人や編集部はお怒りになるかもしれません。けれどワタシは本気で褒めているのです。この作品をイロニーとしてのユーモア小説と読めなくして、どこに小説としての存在意義があるというのでしょう。そう言われることがもし作者の想定外だったとしたら、さっき申し上げた「じぶんが意図しない偶発的なふるまいによって笑いを呼び込んでしまう人」だというほかありません。ちなみに選考委員のみなさんの選評を読ませていただきましたら、ひとり大澤信亮さんが「冗談のような仰々しい文体で、観念的な世界が繰り広げられる。実際、私はところどころで大笑いしながら、それを読まされてしまう言葉の強さに、作者のたしかな才気を認めた」と書かれていて、大いにわが意を得ました。
ストーリーはシンプルです。高校生の速水圭一は美術部員で、一年先輩に部長の矢谷始、同学年に山中春美の二人、部員はこれだけです。速水は同じクラスの北条司という男子の美しさに打たれ、絵のモデルになってくれと頼み、承諾を得ます。恋する速水でしたが、北条は山中と交際をはじめてしまいます。絶望した速水は北条を殺して自らも死のうと企てるのでしたが……というお話。
ありえないようなストーリー展開の中で描かれる速水の内面描写は、描写というよりその観念的な思考をひたすら追い続けることに注力されます。ただひとり信頼関係、というより依存関係で結ばれる先輩、矢谷との会話は、とりわけ美についての観念的な議論とリアリティのまったくない応答の身ぶりがほとんどを占め、そこに二人の心理描写をからませる独特の表現になっています。
「随分と美に秀でた男だな。生きることと陶酔することとを明確に区分できるとはね。僕らは普段主観と客観、主体と客体を分け隔てて考えたがるものだけど、北条はそれらが相互に影響を及ぼし合うという関係、認識と対象は離隔できるものではないという現象学的事実を理性ではなく感性で認知している。ゆえに尊敬も軽蔑もせず生きられる。それが正当か有益かは扨措き、こういう青年は凄く稀有だ。大切にするといい」
「ええ。近々部室に呼びますから、部長のことも紹介しますよ」
「いや、それはやめてくれ」
「どうしてです?」
矢谷は一息おいてから
「君は芸術家とは何だと思う?」と訊いた。
[中略]
「芸術家は美を創造しなければいけない。でも、今この世界に鎮座する美意識は、まるで俺の生まれるより先に一般化された、公明正大な、民衆の格率のように思えてならないんです」
(伊良刹那「海を覗く」)
こんな会話がずっと続きます。大澤さんでなくても笑ってしまいますよね。
観念的だからわるいと言っているのではありません。ワタシなんて、はるかに観念的で抽象的な妄念で頭はいつも暴発状態。けれどこの作家のほぼすべてが虚ろな、と言っては言い過ぎだとしても、テオドール・アドルノの「アウシュヴィッツの後に詩を書くのは野蛮である」というあまりにも有名なことばを知らないのかな、と思わせてしまう無邪気とすら言いたくなる美学談義を含めた叙述は、それ自体がイロニーとしてのユーモアであると読んだとき、今日の日本の文学表現が置かれている状況とその中での斬新さをよく示している、と感じるのです。
「人が人を愛するなら、時として愛を愛と呼ぶために人を殺せる。人を愛せる人間は、同時に人を殺せる人間だ。[中略] 愛ゆえの残酷が可能なら、残酷ゆえに愛が可能になる」
(同)
自殺とは死の意志的な獲得ではなく、自身の死を明け渡してもよいと思えるほど愛し、依存した何かに、死を委託し分かつようにして殺される、本質的には意志を放棄する無意志な行為である。
(同)
観念の遊戯の遊具箱からふと見つかったのか、作家自身の経験の中から絞り出すようにして生まれたことばなのか、わからないところがかえっていいのかもしれません。
浜辺へと引き返す最中、二人は黙っていた。時間が普段の加速度的進行ではなく、ゆるやかな坂を一定の速度で下ってゆくように過ぎてゆく。ゆったりとした心地のよい沈黙が、足元の白波のように漂っていた。この沈黙を、この世に二人のみが共有しうる限りなく死に似た沈黙を、やっとのことで紡いで言葉にしてゆくために生きることが、愛ではないのなら一体何であるのか、速水には判断がつかなかった。
(同)
風景描写になると、こんな感じです。
遠浅で内海ということもあり、波の荒々しさはまるでなく、翠玉を彷彿とさせる花緑青色がせせらいでいる。清冽な海面は静止しているようにも見え、微細で緻密な反射をあげる様だけが海としての証左であった。水平線はなだらかに空を分かち、遠くに見える山々が存在すら疑われるほどに朧気で、海が世界を遮断させているように思われた。陸の雑多な感じや、町並みの生活を臭わせる音と無縁な世界が、決して解けない糸で編み出されて遍満と展開されるその姿の明媚さは、蒼海だけでなく、白い真砂と珊瑚の欠片、近づいても遠鳴りに聞こえる青々とした風浪の音、鼻腔や髪を戦がす潮の気流にも散見された。
(同)
一見して抒情的にも耽美的にもみえますが、何を描こうと文章の質は変わりません。この作品で中心化されている速水自身の外面描写だけは一切ないのも、登場人物がどんな環境で生きてきたのか、北条を除いて背景が描かれないのも頷けます。意味がないからです。前景も後景も無用だからです。ご本人が好きだという三島由紀夫のような、行間から匂い立つ耽美性を求めてのことでしょうか。でも伊良さんの文章は、三島には似ていません。いまどき三島のパロディなんてつまらない。それに三島を読んで顔をしかめることはできますが、笑うことはできませんから。くり返しますが、これは作者への褒めことばです。
中でも、矢谷と同じ美術関係の予備校に通う棚橋美穂が矢谷の彼女・七瀬唯との間に割り込み、かれと出来てしまうに至るエピソードほど微笑ましい箇所はないと言ってよく、作者の才のきらめきをひとしお感じさせる場面です。
「私はいいの。矢谷くんが私のことを愛してくれなくても」
「そう。でも君は勘違いしてるよ。僕は君を愛してる。これが愛じゃないなら、今までもこれからも、僕が人を愛することはないだろう」
[中略]
「そうでしょ。矢谷くんは何も愛さない人でしょ。だから安心できるの。だってあなた、私のことなんて、いいえ、何一つ真実らしいものなんて、見てないじゃない」
街灯が棚橋の美しい髪を艶めかしく照らした。矢谷は、何もかもを愛するということは、何一つ愛さないことと等しいのだという陳腐な通説がいかに正当か、ようやく気がついた。だがその気づきの遅 さに後悔するような人間ではないから、ただ綺麗な髪だけを眺め
「案外長続きするかもね、僕たち」
と悪戯な笑顔を浮かべてみせた。
(同)
かてて加えて興味をひかれたのは、難読漢字の多用です。「扨措き」「態々」「為人」「顫動」「随に」「諄い」……そういえば前回、すばる文学賞を受賞した「泡の子」について触れましたが、その作者・樋口六華さんも一七歳。資質も文体も異なりますが、難読漢字を頻繁に用いる点で共通するのはどうしてでしょうか。いまや当たりまえの風景となって溢れるネットことばや同世代〝界隈〟のことば遣いへの反動なのでしょうか。
伊良さんがこれからどんな作品を生み出していくのか。真似手もないだろうそのユニークさによって本作は新人賞にふさわしい小説と思いますが、企まずして人を笑わせる資質をもった人が一流のお笑い芸人になるのはかえってハードルになるように、正しい自己認識がよりすぐれた作品を生むとは限らないところが文芸というものの面白さです。でも、伊良さんが打ち出したこの方向は、間違いなく日本語による文学表現の新しい可能性を開こうとしています。まだ土中に眠っているであろう種子を、大きく育ててほしいと思います。
萩野篤人
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


