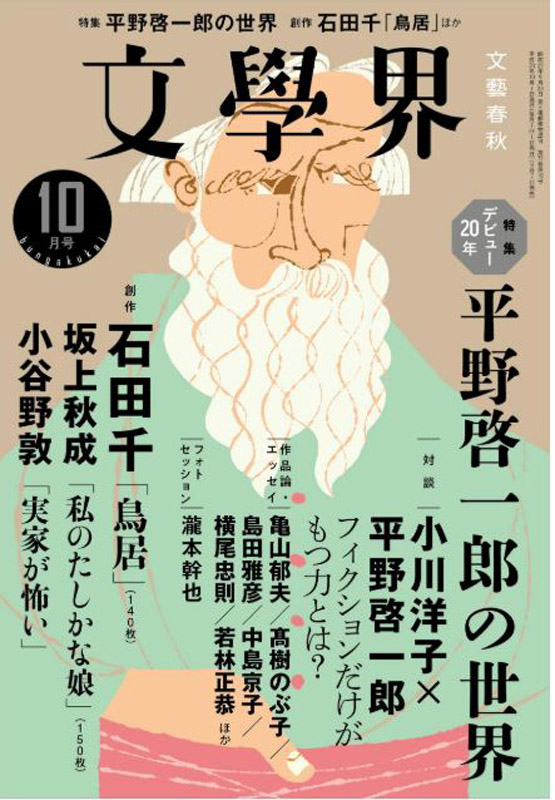
文學界掲載作品を読んでいると、うーん、文學界に書くとこうなるかぁと思うことがしばしばある。んなこと書きたくないが、他のメディアでは気楽に書いていた作家が文學界となるとしかつめらしくなる。文体も変わったりする。
もちろん物事にはいい面と悪い面がある。文學界スタイルがあるということは、文學界が一定の文学伝統を守っているということだ。それには意味がある。一方で簡単に文學界スタイルを真似られるのは、それがステレオタイプ化していることを意味する。これはあまりいいことではない。
純文学小説文体は誌面を見ればすぐわかる。ベタッと文字が詰まっていて会話がない。つまり一人称だろうと三人称だろうと作家による心理独白体小説である。この文体で読者に読んでもらうには四百字詰め原稿用紙三十枚程度、マックスで五十枚が限界だと思う。読者だけではない。作家もそうだ。心理独白体小説は内面に下るしかない。純粋に人間内面心理を描くなら三十枚もあれば必要十分だ。
小説の会話部分は、当たり前だがその内面をうかがい知ることのできない他者と主人公が交わるから会話なのである。そこには自己と他者の闘いがあり、言葉によるエロチックな心の交錯がある。しかし少しずつしか他者の内面はわからない。だから物語が長くなる。
それとは逆に心理独白体小説は、原則として自己の心理の、それも過去の心理の回想である。他者が出てきても会話を必要としない小説では、すでに他者が内面化されている。人間は他者が発した言葉を即座に内面化できないわけだから、書く段階で他者の発した言葉(あるいは言動)はすでにある程度の結論に行き着いている。小説は長くならない、はずなのだ。
心理独白体小説は私小説と言っていいが、戦後のある時期までは短編小説がほとんどだった。それが長くなったのはいつ頃からだろう。様々な理由があると思う。その理由を言い出すとまた叱られそうなのでやめておくが、作家もメディアももっと原理原則を考えた方がいい。
特殊な実体験がなければ私小説は書けないというのは、本当であり嘘でもある。西村賢太さんは現代日本を代表する私小説作家だが、大正昭和初期の私小説作家とは比べものにならないほど作品を量産している。それが可能なのは、彼が私小説とは何かを知的原理として把握しているかである。原理を把握しないで心理独白体小説をなぞるように書くと、んーまたかーという文學界的私小説になってしまう。
永遠に眠っているつもりだった、むかしむかしの貝たちが、新幹線の振動に、まぶしそうに泡をのぼらす。駅じゅうに、ちいさなあぶくがはじける。潮の気配は、ますます濃くなっていく。
品川に来るたび、息苦しさで、かえってらくになるような、淡い色の海底を思う。空は、あおく突き抜けて、入道雲はくっきりとしろい。宿場や街道のにぎわいに、うりざね顔の女、まえのめりでひょいひょいといく股旅すがたの男。そんな一瞬の連想で、いまが逸れた。
(石田千「鳥居」)
石田千さんの「鳥居」は、主人公の未知子が雲雄と三浦半島の三崎に一泊旅行に行く物語である。三崎で地元神社の夏の例大祭を見るのが目的だ。未知子も雲雄も中年に差しかかっている。二人は恋人のような、そうではないような微妙な関係だ。引用は冒頭近くの叙述だが、主人公の心が古代的方向に傾いているのがはっきりわかる。舞台は現代に設定されているが、すでに現実が内面化されている。
このあいだ雑誌にのってた旅の記事、読んだよ。がんばってるなあって思った。いい仕事しろよ。もうすぐ死ぬのに、よけいな気づかいもいっていた。自分の仕事は、本を読んだり書いたり写真を撮ったりは、いまもできているのかしら。お金は、大丈夫なのかしら。(中略)
いつから悪くなったのか、どこにいるのかたずねもしないで、またよけいなことをいった。どうしてあんな、つまらない負けん気が沸くのか。あんなのは、ただの仕返しだった。最後のつもりでかけてきたのに、最後まで、いいたいことをいわせず黙らせた。たのしかった時間を、また汚した。
(同)
雲雄と旅行に行く前に、以前付き合っていた男が未知子に電話をかけてきて、もうすぐ死ぬんだと言う。ほかの女に入れあげてひどい別れ方をした男だ。しかし主人公はふっきれない。元恋人に気持ちが残っているからだとは必ずしも言えない。未知子自身が死というものに少しずつ近づいている。でなければ死と再生の儀式である神社の例祭を、今付き合っている恋人とわざわざ見に行く必要はない。中年だが男女だから二人はセックスする。若い頃より淫靡で濃厚かもしれない。しかしそれは死と再生のために必要なのだ。ではどんな質の死と再生が旅行によって実現されたのだろうか。
すぐうしろに雲雄がいる。かゆくて腫れぼったい足のあいだの暗がりは、すこし明るい。よれよれになったワンピースで、雲雄のすぐそばに立っている。潮の匂い。まえを見たまま、背を押しつけ、しがみつく。
うおおおおおおお。
雄たけびをあげると、お神輿は一気に駆け上がった。ヨイセーのかけ声は、吐息と歓声にめくれて、和合のむつまじい余韻があふれる。十一時十五分、お神輿はめでたく本殿に達した。みんなで同時に届いた。
(同)
三崎の神事は担ぎ手たちが神輿で町を練り歩き、神社に着いてもセックスの前戯のように本殿に到達するのを遅らせ、焦らせ、担ぎ手と観客が疲れ果てようとする瞬間に一気にクライマックスに達する。これがこの小説の頂点だ。ではこれによって主人公と雲雄の関係は変わったのだろうか。主人公の心性は死と再生をしっかりと自分のものにしたのだろうか。
この小説は最初からそこを目指していた。死と再生のテーマに沿って冒頭から現実世界が内面化されていた。テーマはそれしかなかった。つまりそこまで書かれていないと百四十枚もの私小説を読み続けた甲斐がない。結末で茫漠とした死と再生のテーマが表現されているなら、永遠循環のように小説が冒頭に戻ってしまうだけだ。つまり雰囲気小説で終わってしまう。
さて、どうなんでしょうね。
大篠夏彦
■ 石田千さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■







