 一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
純文学からホラー小説、文明批評も手がけるマルチジャンル作家による、かる~くて重いラノベ小説!
by 遠藤徹
(六)象の背中(三)
「そうだ、あなたもこれは知っておいた方がいいでしょうね」
などと種山が前置きをし始めたのだ。焦ったのだが、もう遅かった。
「長老がひどくふさいでいるのは、二人の日本人にひどいことをされたからだという可能性がある。でも、実はカレン族そのものが受難の民でもあるんですよ」
「受難、ですか?」
ほらあ、こうやって聞き流せない話にもちこまれてしまうのだ。だって、もうここまで聞いたら寝てる場合じゃないじゃない。
「そうなんです、もともと彼らはビルマ、いまのミャンマーに居住していたんです。でも、ミャンマーの国家軍によるひどい暴力行為を受けた」
「暴力ですって」
いったい、なぜ。
「そう、いわゆる民族浄化ってやつでね、ビルマ族はカレン族やカレンニー族をミャンマーの国土から強制退去させようとしているわけです。さもなければ根絶やしにするってくらいの勢いなんですよ。そのやり方はひどいもので、殺人、強奪、強姦、それに強制労働まで多岐にわたっているんです」
こういう話を聞かされるたびに、自分がいかに平和ボケしているかを身につまされる。
「それで、本来はいなかったカレン族がタイにいるわけね」
「うん。でも、タイ側もカレン族を喜んで受け入れてるってわけじゃあないんです。むしろつらく当たってて、国外追放したりしてる」
「じゃあ、行くところがないじゃない」
「そうなんです。だから、まさに受難の民なんですよ、彼らは。その怒りは戦闘に向けられることになるわけです」
それは、わかる。 そう、怒りはたしかに、闘争心につながる。それはわたしもよく知っている。
「ほら、前に、象が地雷を踏んで足を吹っ飛ばされたって話をしたでしょ」
「ええ」
「あれは、そのカレン族とミャンマー政府軍との争いの中で、弱者であるカレン族側がゲリラ的な戦略として設置したものだったんですよ」
なんて悲惨な話だろう。自分たちを守るために設置した地雷を、自分たちの象が踏んでしまうなんて。

「でも、この村は少し違うようですがね」
「そうですか?」
「うん、おそらくはかなり古くからある村のようです。紛争以前から、ここに暮らしていると思われます。みんな落ち着いてて、穏やかですしね」
「確かに」
「それに、こんな不便な山奥じゃあ、タイ政府もわざわざ干渉しようという気にもならないんでしょうしね」
わたしだって、歓迎するからもう一回おいでといわれても、あの山を登るのはご遠慮申し上げたいところである。
「まあ、そんなわけで、長老が憂鬱質になるのも、やむを得ないのかもしれませんよ。同胞の苦難を思うだけで気が滅入るでしょう」
その後も、種山は延々と話し続けていたようだ。
だけど、瞼はどんどん重くなった。やがて瞼の扉が閉じられ、夢の世界へと旅立ったわたしにとっては、もうカレン族の神話だの、来歴だの、婚姻制度の特徴だのはどうでもいいことであった。真っ暗闇のせいでわたしがすでに眠ったこともばれなかったようだ。種山の話では、わたしは眠ったままであるにもかかわらず、
「うん、うん」
と相槌を打ち続けたため、聞いていると思って明け方まで話しつづけてしまったということだった。
渋面があった。わたしの目の前に。
その朝は、大きな困惑から始まった。
トイレがなかったのだ。明け方目を覚ましたわたしは、トイレを求めて村をさまよった。明け方まで話し続けていた(らしい)種山はゆすってもびくともせず、深い眠りの底に落ち込んでしまっているようだった。
わたしの表情を見て何事かをさっしてくれた少女が、にっこり笑って村の外の草っぱらを指さした。
「ええっ、野・・・、なの」
もちろん、通じない。だから、少女はただうなずいて、もう一度野原を指さすだけだった。丈の高い緑の草が一面に茂った野原であった。確かに、この高さの草があれば、しゃがんでしまえば姿そのものが見えなくなるだろう。
やむをえん、とばかりわたしはその野原へと歩を進めた。
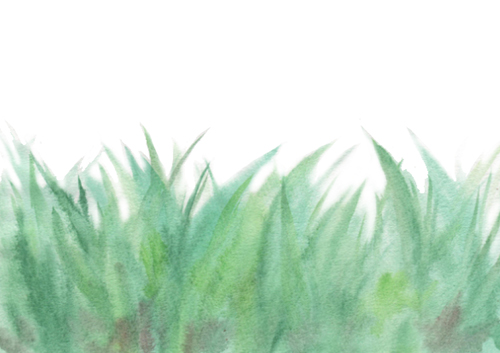
そして、悲劇はそこから始まるのであった。
なぜなら、そこに豚、がいたからである。
わたしが野原に足を踏み入れるやいなや、ガサガサガサガサと草をかき分ける音が四方八方から響き始めた。ぎょっとなったわたしが立ちすくんでいると、何頭もの豚がものほしそうな声で鳴きながらわたしを取り囲んだではないか。
そしてわたしは理解したのだ。この村の究極のエコシステムを。
地球環境を思いやるわたしは、ついに観念した。そして、豚どもが固唾を呑んで見守るなかで、草むらに沈んだのであった。
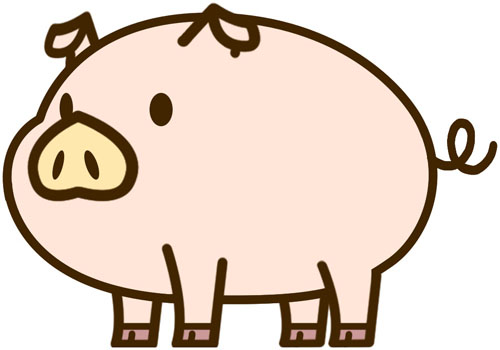
って、違うわ。その話じゃないって。水浴びは近くの川でさせられたとか、空飛ぶ鳥をブーメランで打ち落とす達人を見てしまったとか、そういう話じゃないって。折り紙の鶴を折ってあげたら、子供たちから神様を見るような目で見られたのはすてきな体験だったけど、そういう話でもないからね、いまは。そういえば、昨日の午後わたし一瞬気を失ったんだったっけな。切り出してきた竹をナイフでじゃかじゃか削ってる若者たちを見てる時に、一瞬太陽の光がギラッときたのだ。ナイフの刃に反射したそのギラッをみて、わたしクラッと来て倒れちゃったんだった。気がついたら高床式のあの部屋で寝てて、びっくりした。
「軽い熱射病じゃないか」
なんて種山が水を差しだしてくれたりして、おやおや意外とやさしいとこもあるじゃんこの〝もじゃ〟ちゃんなんて思ったわけだけど、ちがうちがう。その話でもないから。
そう、渋面の話だった。
「日本人はもうこりごりだ」
やっと会えた長老は渋面だったのだ。いろいろ話しかけた種山が引き出せた唯一の言葉がそれだったようだった。
「何も話したくはない」
そう言ってから、老人はうらい、うらい、うらいと幾度も叫ぶように口にした。そのうらい、うらい、うらいを耳にすると、村の者たちも妙に沈んだ表情になるのだった。
「長老の娘さんのことなのだ」
通訳のバボエ君が教えてくれた。
「ウライさん、美人でした。頭よかった。この村で、大学で勉強したただ一人の人」
「ええっ、そうなの」
そして、わかりにくいところのあるバボエ君の日本語を解読しつつ、バボエ君が村人から聞いてきたことを総合すると、ウライというのは長老が六十になろうというころに生まれた一人娘だったということだった。
といっても、奥さんは二十代の初めだったらしいけどね。それも第三夫人。やるなあ、長老。
でまあ、ウライさんは才色備わった完璧な娘だったらしい。ヨーロッパからやってきた文化人類学者の夫婦がパトロンになってくれて、バンコクのタマサート大学で科学を修めたのだそうだ。優秀な成績で卒業したが、パトロンたちが帰国する際に、いっしょにヨーロッパに行くのは辞退した。その理由は定かではないが、とにかく憔悴した感じで村に戻ってきたのだということだった。
むろん、それは長老にとっても村人にとっても歓び以外の何物でもなかった。彼らの世界観からすれば、ヨーロッパに行くことにも、大学に行くことにも大した意味はなかったからだった。
「でも、亡くなったのです。生きていれば、雪枝の次に好きな人でしたけど」
とバボエ君は悲しげに肩を落とした。
「でも、死んでしまったのだから、やっぱり雪枝が一番。ナカマユキエが一番好きです。わたしは」
と森に向かって叫んだ。あいつは、今頃東京でお猿のバブルス君とたわむれてるに違いないなどとは、口がさけても言えない感じだった。
「そうか! ありがとう!」
唐突に種山が割り込んできた。
「どういたしました」
謙譲語がやや苦手らしいバボエ君であった。
「おかげで、攻略方法を思いつきました」
種山は、にっこり微笑んで高床式住居のはしごを登って行った。
その夜、高床式住居の中でパソコンをカチャカチャ操っていた種山と、わたしのところに使者がやってきた。長老が呼んでいる、というのだった。
パソコンといえば、
「コンセントはどこなんです」
なんてその日の午後に尋ねたわたしであった。だって、高床式の住居である。トイレは野原(豚付き)、そしてシャワールームは川(魚付き)なのである。そして、パソコンはコンセントがなければ起動しないのである。
すると、天井天下唯我独尊ってな感じで、上を指さしてみせた種山であった。
「お日様にさしてるんですよ」
ははーん。もう驚かされはしないわたしであった。
よーするに、電源はソーラー電池ってことね。そういえば、藁ぶき屋根の上に、黒いカバーがかぶせてあったけど、きっとあれなのだろう。布っぽい感じだったけど、きっとそれでも電池なのだろう。
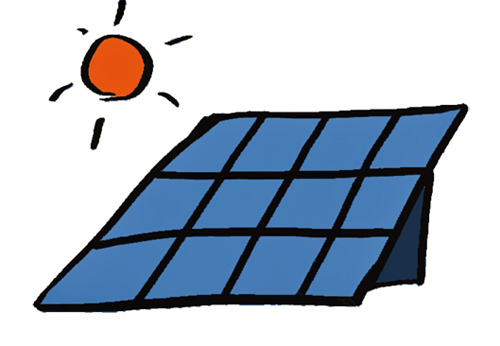
「ほら、うまくいきましたよ」
使者の後について、梯子に足をかけながら、種山はがらにもなくウインクをしてみせた。してやったりって感じなんだろうけど、やっぱむりむり、もじゃにウィンクはどうしても、あわないって。取り合わせ的に。
「見ましたのことあったか、さやか」
あわてて駆けつけてきたバボエ君と、ちょうど降りたところで出くわした。
「いいえ、なんのこと。見るっていったって、ここテレビもないんだもん」
いったい何を見ろっていうのだろう。もうずいぶん長い間「笑っていいとも」すら見てないっていうのに。
「すごかったです。わたし初めて本当に見ました」
「だから何を」
「霊です。幽霊です。神の使いです」
「へえ、そうなの」
こっちはやっと長老から呼び出されたのだ。そんな妄想に付き合ってる暇はない。そう思ったのだが、
「あれでしょ、象に乗ったやつでしょ」
種山が横から嬉しそうに口を出してきた。
「そうです、そうです。白い象でした」
というわけで、バボエ君の話を再び要約してみると、
日暮れごろ、村は大騒ぎになったのだという。暗くなり始めた広場にふいに光が射したのだ。そしてやがて光は、白い象となった。そして、その象には一人の娘が乗っていた。
「ウライ・・・、ウライ・・・」
村人たちが集まってきて、指さした。怯えつつ、あるいは感動しつつ口々にそう呟いた。
「そうなんです、わたしも見たのことである。あれはウライですた」
バボエ君も興奮して付け加えた。
やがて長老も現れて、村の中央に現れたわが娘の姿に呆然となった。ウライはただ微笑むばかりであったが、最後になにかをささやきかけた。その言葉に長老は驚いてウライに、何かを問いかけたが、ウライはもはや答えなかった。そのまま、象の姿も、娘の姿も次第にぼやけて消えて行った。
「ははあん」
すぐにぴんっ、ときたので振り返った。
「なんかやったでしょ、種山先生」
「うん、やった」
頭を掻きながら、もじゃがうなずいた。
「実はね、今朝長老の部屋にもう一回押しかけてったんですよ。追い返されるのは百も承知でした。でも、目的は他にあったんですよ」
「何です? 無駄足ってわかっててわざわざ出向くなんて」
「隠し撮りですよ」
なんでもないことのように答える種山。おいおい、仮にもあんた教員でしょうが。
「って、先生そんなご趣味をお持ちだったんですか」
「いや、趣味とかそういうんじゃなくってさ、ほら昨日行ったときに、長老の部屋に飾ってあったでしょ、娘さんの写真。そいつを隠し撮りしてきたんですよ」
「へえ。先生のタイプだったんですか、ああいうのが」
「だから、違いますって。その画像をこのパソコンで彩色し、民族衣装を着た全身像を構築した。これを、さらに3D化して、白い象の上に乗った姿にアレンジして広場に投影したんですよ。いわゆるホログラムってやつですね」

簡単なイリュージョンだけど、どうしても、この場合ほかの方法が思い浮かばなかったもんですからね、と種山。
「で、なんていわせたのよ。娘さんに」
それは、と少し口ごもり、
「あの二人が、無念を晴らしてくれる。彼らはそのために来た」
くらいの感じですかね、とちょっと照れくさそうに答えた。
(第17回 了)
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■







