 一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。
純文学からホラー小説、文明批評も手がけるマルチジャンル作家による、かる~くて重いラノベ小説!
by 遠藤徹
(六)象の背中(二)
「上野動物園とか?」
「確かに上野動物園は日本一古い動物園ですね」
「いつオープンしたんです?」
「一八八二年ですよ」
って、確か大政奉還が一八六七年(いやだろうなヨシノブ公、みたいなゴロで覚えた記憶がある。だからわたしのイメージのなかで徳川慶喜はいつだってしかめっ面なのだったりする)だったんじゃ? すぐに王政復古の大号令みたいな。
「明治の初めですか?」
「そうですよ。象は確かに開園後間もなく来園してますね。ライオンやキリンやカバが来るのはずっと後なんですけどね」
「じゃあ、正解ですね、わたし」

ちっちっ、と指を振る種山。なにその仕草。なんか、むかつく。なんか、不愉快。
「いいえ、残念ながら、不正解です」
「ってことはもっと前なんですか」
「うん。鳥獣戯画って知ってますよね」
「ええ、もちろん。マンガの始まりとかいわれてるやつですよね」
カエルが踊ってる姿を、教科書かなんかの挿絵で見た程度の記憶しかないけど。
「そう、作者は不詳なんだけどあれは十二から三世紀ごろに書かれたものと考えられてるんですよ」
「そこに象が?」
「ええ、かなり正確な描写になってるんです。つまり、この頃にすでに象は」
「日本にいたんですか?」
「いや、それはわからないけど、少なくとも象という動物の特徴はよく知られてたってことになりますね」
じゃあ、まだ日本に来てはいなかったってことかな?
「実際に初めてやってきたとされてるのは十五世紀ですね。足利義持への献上品として南蛮船が運んで来たらしい」
「ほんとですか?」
「でも、京の都で義持に謁見した後、朝鮮に送られたということになってるんです」
「謁見ですか」
苦しゅうない、近うよれ、と義光。ぱおーん、と象。どしどし。これ、近い、近すぎると義持。ぱおーんと象。どしどし。よせ、よさんか象、と義持。ぱおーんぱおーん、どしどし。わあお、とつぶれる義持。あらいけない、また妄想が暴走を。
「その次が、十六世紀末から十七世紀の初めのころで、豊臣秀吉や徳川家康にそれぞれ象が捧げられたらしいですよ」
ふーん、さすがは権力者たち。サルもタヌキもゾウと相まみえていたというわけか。わたしのなかでは、なんとなく戦国時代が動物園的な様相を呈し始めた。
「そして、吉宗です」
「吉宗って、暴れんぼう将軍ですか」
俺がやらなきゃ誰がやる 廻り道だぜ風が吹く~。いよーっ、サブちゃ~んって、違う違う。違うからね。別にわたしが好きだったわけじゃないから。再放送見まくってたのおじさんだからね。そりゃ、たまにはいっしょに見てたけど。だってテレビ一個しかなかったし。えっ、おじさんって誰かって? そりゃあ、わたしとお姉ちゃんのおじさんのことよ。つまりはわたしの父の弟。そして、わたしたち姉妹の育ての親ってわけ。どうしておじさんが育ての親かって? うん、まあいいじゃない、その辺は。個人情報だしね。個人情報。
「まあ、あれは創作ですけどね」
「で、どうなったんです?」
暴れん坊将軍だけに、象にでも乗ったか?
「っていうかね、オスメスのつがいでベトナムからやってきたんだそうですよ。でも、当時は鎖国中でしょ」
「出島ですか?」
「そう、ついたところは長崎だったわけですよ」
「でそこからは、長距離トラックとか?」
ってここで気がついたけど、ほんと象ってどうやって運ぶんだろ。トラックの重量制限越えてないのかな?
「もちろん当時はそんなものはありません」
「ってことは船か」
「でも当時の日本の技術じゃ、象を運べる頑丈さの船は作れなかったんですよ」
「うそ、じゃあどうしたの」
種山は少し嬉しげに答えた。
「歩いたんですよ」
ええっ、と今日一番の衝撃を受けるわたし。
「どこから、どこまで?」
「長崎から、江戸まで」
だそうだ。途中で京都に寄ったらしい。もちろん、天皇に上覧するためだ。で、天皇に会うためには位階が必要だったから、広南従四位白象とかいう位階をもらったのだそうだ。わあ、わたしより偉かったんだね、象さんたち。

「で、東海道中膝栗毛の倍くらい歩いた果てに江戸で吉宗に謁見したというわけです」
「野次喜多を超えたってことですね」
「歩数的にはね」
「すごい」
「君だってすごいですよ」
「ええ?」
褒められるのに弱いわたしである。
「何がですか」
「だって、とうとう歩きとおしたじゃないですか。標高千二百メートルの山を制覇したんですよ」
ほんとだった。突如として、眼の前に高床式の住居群が現れたのだ。感動の一瞬。そう、わたしは到達したのよ。ヒマラヤ並みに高い山のてっぺんへ。いえーっ、てほどでもないけど。
「わたし、連絡。つけてきちゃうから」
なぜか女口調でそういうと、バボエ君が駆け出して行った。なんという体力。これだけの山を登った末に、まだ走る体力が残っているとは。
「いよいよですね」
「まだですよ」
村のはずれの岩に腰を下ろしたわたしの隣に、種山もまたどっかと座りこんだ
「まだって?」
「ほら、象洞の話がまだ終わってないじゃないですか」
「ああ、もういいですよ。着いたし、暇つぶしの話は」
「だめだめ。最後まで聞かなきゃ」
これだから困るんだこの人は。とにかくしゃべりだしたら止まらないのだ。自分が話したいことは絶対最後まで話す、そういう人なのだこの人は。たとえばわたしと船の上で話をしてたとしよう。途中船がぐらついて、たとえわたしが海に落ちたとしても、この人は話しやめない。絶対話しつづけるね。「助けて」とか叫んでもきっとこの人ならこう答える。「もちろん、助けますとも。でも、まずはこの話を終えてからです」。おーい、それじゃ溺れちゃうんだよお、わたし。ごぼごぼっ。
「わかりましたよ。手短にお願いします」
溺れながら答えるわたし。うんうんとうなずく種山。
「でまあ、その象たちは浜御殿という将軍様お抱えの場所で飼育されたわけですがね」
「犬を飼うってわけにはいかないでしょうね」
「そうなんです」
なにせ、あの巨体である。そして、上野動物園の飼育係もまだ存在しない時代である。
「なにせ、食べる量が半端じゃない」
「どれくらい食べるんです?」
「草でも、葉っぱでも、果物でも、野菜でも食べてくれます。その意味では助かるんですけどね。でも、その量が問題なんですよ。なんと」
「どれくらい?」
「一日百五十キロ」
なんとお!
「一年で、五十四トンですよ、あなた」
「それはすごいですね。しかも、雌雄二頭ときたからその倍ってわけですね」
「いや、メスの方は、早くに亡くなったそうです。天皇にも将軍にも会えないうちにね」
「ってことは男ヤモメの象さんだったんですね」
「そういうことなんです」
いずれにせよ、食費がかさんで大変なことになった。
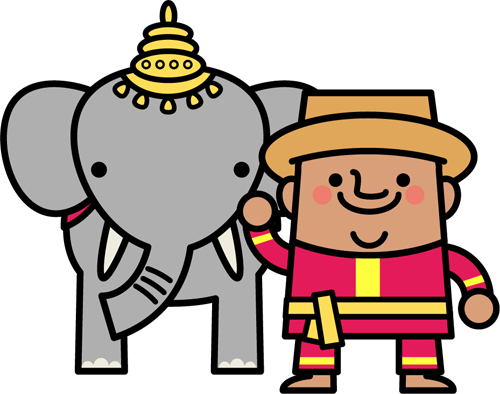
「でまあ、民間に払い下げられたわけです」
「民間っていったって、先生」
独立行政法人ってわけじゃなかろうし。
「うん、百姓の中野村源助という男に飼育が託されたんだそうです」
源助さんかあ。ほんといかにもお百姓さんって感じ。
「でも、源助さんだって、餌代には困ったわけでね」
「そりゃそうでしょうね。民間委託っていったって、ようはお祓い箱ってことですものね」
うなずく種山。やばいよ暴れん坊将軍、グリーンピースにいたずらされちゃうよ。っていうか、未知子さんに引き取ってもらわなきゃね、そういう場合は。
「でも、源助さんは、精一杯のことをした。象洞を作って売り、少しでも餌代を稼ごうと努力したんです」
でも、そんな努力もむなしく。結局象さんは死んでしまったらしい。
「で、なんですか、その象洞って」
早く核心に触れてくれとわたしは促した。そして、この話を終えてくれと。
「薬だね。万病に効くと謳っていました。特にハシカに効くってね」
「ほんとですか。ガマの油的なものですかね」
「うーん、どうでしょうね。ま、発想としては似てるかもね」
「どうやって作るんです」
「丸めて、そして乾燥するんですよ」
「だから、なにをです」
イラついてきた。
「早くおっしゃってください。丸めて、乾燥したものとはなんでしょうか」
「さっき見たやつですよ」
と種山は過ぎ来し道を振りかえった。
「えっ、まさか」
絶句するわたし。いえ、わたくし。
うなずく種山。
「そう、さっき君が蟻塚と間違えたやつです」
それは売れない。源助さん、それは売っちゃあいけないよ。
でも種山の話ではどうやら割と売れたらしい。越後や信濃の国にまで売れていったらしい。買うなよ、呑むなよそんなもん。それでも結局餌代には足りなかったということだった。
わたしたちは大歓迎された。
なにしろ、その証拠にインスタントラーメンを出されたくらいである。
ユキエ命の悲恋の人バボア君の解説によれば、
「都会でしか手に入らないわよ、インスタントラーメン。だから、大変に貴重品。この村では。振舞われるとは、大切な客人だけ。良かったねえ、てめえら日本人で」
だということだった。

コップンカァではあったが、そのラーメンはわたしに劇的な発汗をうながした。やけに辛かったのだ。むべなるかな。なにしろ汁が赤い。まぎれもなく、トウガラシの色であった。
ラーメンを運んできてくれた村の女の子たちはとてもかわいかった。虹色の横じまが入った白いワンピースに、綺麗な石のネックレス、そして同じく白のマフラーみたいな襟飾りをつけて、頭も白い頭巾で包んでいた。
男の人の装いはもっとシンプル。腰から下はだぼっとしたズボンみたいなのを履いてて、上半身は裸か、袖なしのチョッキみたいなのを着ている。誰もかれも飾らない感じで気楽だった。和也さんたちが、居ついたのもむりはないなと思った。
「歓迎はしてくれてるみたいだけど」
バボエ君の報告を受けた種山の額には汗がにじんでいた。残念ながら、苦悩のせいではなく、カプサイシンのせいである。そして、カプサイシンとは、トウガラシに含まれる辛み成分のことである。
「二人の日本人のことは、話したくないといってます」
「あら、それは困ったわね」
答えるわたしの額にも汗。むろん、困ったからではなく、カプサイシンのせいである。
「長老が深く悲しんでおられるから、なのだそうです」
「どういうこと」
「さあ、それはわかりませんが」
相変わらず種山は、汗まみれで微笑んでいた。
その夜わたしたちは来客用の高床式住居で寝かせてもらった。屋根は当然というか、ナチュラルな感じの藁葺。エコだわ、ほんと。ただ、高床式というだけあって、木で組まれた地上二ートルくらいの高さのところにある部屋まで、はしごでのぼらなければならないのがエレベーター慣れした都会っこには苦行ではあったけれど。種山とわたしのことを親子かなにかと勘違いしているようで、一室しか用意されなかった。とはいえ、相手が種山なのでわたしにはなんの心配もなかったけど。
「とうとう、現れませんでしたね、長老」
その夜のわれわれはちょっとした珍獣扱いだった。外国からの珍しい客ということで、入れ替わり立ち代わり大人たちが登ってきたのだ。わたしたちを見てはにかんだり、微笑んだり、恥ずかしがって逃げて行ったりした。上に上がりたがってぐずっている子供たちの声まで聞こえた。まさに、パンダにでもなった気分であった。
けれども、長老らしき老人は一度たりとも顔を見せなかったのであった。
「まあ、焦ることはないですよ、フェスティナ・レンテです」
などと、わけのわからぬことを口走る種山。
「えっ、なに?」
「いや、ラテン語ですよ。急がば回れっていうことわざです」
なんだよそれ。
「それなら、日本語で言えばいいでしょ」
「わかりました。急がば回れですよ」
「じゃあそうします。お休みなさい」
と眠ろうとしたのだが、変に話しかけたのがまずかった。
(第16回 了)
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■







