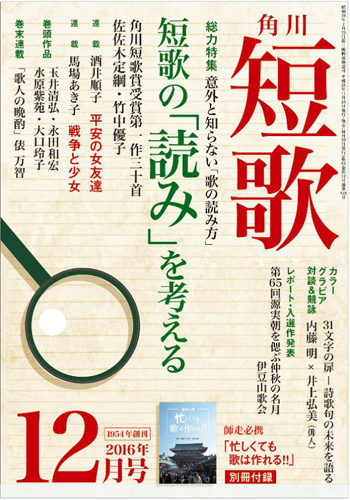
先月号は第62回角川短歌賞発表号でしたが今月号には受賞第一作30首が掲載されています。やっぱり佐佐木定綱さんはいい作家だなと思いました。ひと言でいうと書きぶりに無理がない。もちろん作品を書くのは大変ですが定綱さんには苦しんで生み出したという気配がありません。彼の散文もいい。この作家は質量兼ね備えた作品を量産できるでしょうね。論客としても期待できます。
玄関の外で蟬の声が聞こえ、気がついたときには美しいミンミンゼミを手に持っていた。飛ぶこともできないほどに弱っており、簡単に捕まった。
カエルの近くにそっと置いてみる。気がついたときには巨大な口から透明な翅がはみ出していた。(中略)
セミはまだ生きていて、部屋にはカエルの腹から響く、み゛ーみ゛ーというセミの音が満ちてゆく。抒情もなにもあったものじゃない。そこにあるのはどうしようもないほどの生と死だった。
しばらくののち、部屋は静かになった。カエルもぼくも音を立てなかった。晩夏のことである。
(佐佐木定綱「カエルのこと」)
受賞第一作にはエッセイが添えられていて、定綱さんはペットとして飼い始めたカエルについて書いておられます。内容的にも技術的にもほぼ満点のエッセイです。原稿用紙二枚弱(八百字弱)でこのくらいインパクトのあるエッセイを書ける作家はそうそういません。夏の終わりにペットのカエルに餌としてミンミンゼミを与えたのは事実なのでしょうが恐らく巧妙に脚色されている。俳人の高柳重信のエッセイを思い出しました。
重信は多行俳人として知られますが晩年に山川蟬夫名義で一行俳句に回帰しました。前衛俳人から正統古典俳人に転身する間際で亡くなってしまったのです。蟬夫名義で一行俳句を書き始めた際に重信は名前の由来をエッセイで解題しています。夏休みに鎌を持って草刈りをしている時にふと見ると木に蟬がとまっていた。悪戯心で鎌を振り下ろすと蟬は刃に貫かれてしまった。少年はそのあっけなさにショックを受けますが鎌で蟬を殺すのが止められなくなってしまう。次々に蟬を見つけては殺戮し続けたという内容です。
重信は蟬殺しを少年時代の思い出として書いていますが実際にはフィクションです。初期エッセイで蟬殺しの夢の話を書いているからです。蟬を鎌で突き殺した体験はあったかもしれませんがそれを重信は文学的に昇華している。言うまでもなく鎌で蟬を突き殺し続けるのは一行俳句を読み捨ててゆくという意志の表れです。技巧的にも思想的にも練りに練った多行俳句を生み出す寡作の作家から言語道断に俳句を書き捨ててゆく多作作家に舵を切ったわけです。同じような文学的昇華が定綱さんのエッセイにはあります。
定綱さんがエッセイで表現したかったのは「抒情もなにもあったものじゃない。そこにあるのはどうしようもないほどの生と死だった」ということでしょうね。また「部屋は静かになった。カエルもぼくも音を立てなかった」という相容れない二つの存在のありようです。このような認識は通常は残酷な写生的リアリズムにおもむくはずです。しかしそうならないところが定綱短歌の面白いところです。
君のいぬ部屋には音が足りなくていつもより多く蛇口をひねる
ふたとおりの人間のいる室内はふたとおりの音まとめてひとつ
同じ道歩けど違うもの抱え生きているなり十六夜の下
目に見えぬ思いとやらの具現化のように人らは歩いておりぬ
すれ違う通行人のような日々消えてゆくから君を愛する
空中でぶつかる鴉飛び去って我が目の前に黒き羽根落つ
ただ平ではなく高さ奥行きがあるアスファルトと知る寝れば
伸びきったまま戻らない電灯のひも思い切り引きちぎる夜
リビングに花束置いて冷蔵庫開けてビールを取らないでおく
いったい告白以後の愛とはなんだよかすかな呼吸を聴いてる
(佐佐木定綱「引きちぎる夜」)
定綱短歌の骨格は古典的です。文語体を使っているのはもちろん歌の内容は明らかに現実の出来事を反映しています。年長歌人が口を酸っぱくして言う「短歌は私を歌うものだ」という基本セオリーを踏まえていると言っていいでしょうね。ただ「ふたとおりの人間のいる室内はふたとおりの音まとめてひとつ」に典型的なように定綱短歌は現実から微妙な形で抽象に抜けてゆく。酔って路上で寝た経験を詠った「ただ平ではなく高さ奥行きがあるアスファルトと知る寝れば」にしても起伏のあるアスファルトの道路が何事かの喩として機能しています。この現実から抽象への抜け方が定綱短歌の最も貴重な点であり期待できるポイントではないかと思います。
現在の歌壇は口語短歌全盛ですがそれは新たな形で作家の私性を詠うための形態です。口語歌人の側から言えば〝仮想敵・文語体〟を使わずにいかに私性を詠うかという試みだということになる。そこには文語体短歌がずっと表現の基盤にしてきた現実への信頼感の喪失があります。社会的事件であれ個人的事件であれ出来事は決定的とは感じられずそれらは根を失ってふわふわしている。その何事かの終わりや始まりとは信じ切れない出来事の不確実性を逆説的言い方になりますが個の絶対的感性として微細な現実事象を手がかりに表現しようとするのが口語短歌の姿だと思います。
ただ現実事象を絶対と捉えきれない口語短歌は抽象表現になりがちです。他者にはわかりにくい極私的な現実事象を詠えば作家は平明に叙述したつもりでも表現としては抽象的に見えてしまう。希薄な現実感覚をより緻密に表現しようとすればかつての現代詩のような抽象表現になりがちなのも言うまでもありません。つまり短歌作品で〝口語(表現技法)〟が目立ってしまう。現代詩が今では自由詩の一流派として完全に終わってしまったことを考えればそれはリスクのある表現です。技巧的新しさは常に相対的なものであり短歌が口語一色になれば間違いなく文語表現が新しく見えてくる。口語の新しさ自体は一過性のものです。続いて三十年かな。つまり口語短歌に一生懸命になった作家たちが年取れば終わり。〝技法が目立つ〟のは手放しで良いことではないのです。
現実に立脚しながら抽象に抜けてゆく定綱さんの短歌は〝口語短歌の時代〟の新たな短歌表現となる可能性を持っていると思います。現実を信じ切れないのは口語歌人と同じですがベクトルが違います。現実の出来事はカエルの腹の中から聞こえてくる「み゛ーみ゛ー」というセミの鳴き声のようなものです。残酷な現実なのに抽象化されていて不気味である。ちょっと褒めすぎかもしれませんが活躍を期待してしまう歌人です。
雨の日の葉っぱのにおい 手のひらをひらいて橋の上に集いぬ
鳥かごを鳥が蹴るようにささやかな近況がある 水面に触れて
曇りの日のひかりのような水底を泳ぐ身体をくねらせながら
ひとの心をたやすく壊した夜に手をひかりの中にひらいて洗う
友達になりたいですと笑う子を傷つけたいから傷つける今
(竹中優子「表情」)
もう一人の第62回角川短歌賞受賞作家である竹中優子さんの作品も古典的骨格を持っています。ただかなりオーソドックスな印象がありますね。「曇りの日のひかりのような水底」といった表現は手垢のついた喩に感じられてしまうのが現代ではないでしょうか。現代短歌の詠いぶりは残酷な現実を露わに提示するか極私の現実を臆面もなく表現するかの両極に振れる可能性があると思いますがオブラートにくるんだような喩的表現はかえって現実の手触りを失わせてしまうかもしれません。
作品を通読すると竹中さんは何事かへの強いフラストレーションを抱えた作家のように感じます。ただそれがまだ十全に表現されていない。文学は一般倫理を表現するための芸術ではありません。「みんな偽善者で大嫌い」で始まる作品世界があってもいいと思います。
高嶋秋穂
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■



