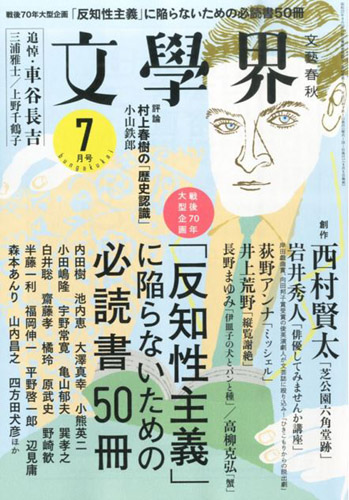
七月号巻頭は西村賢太の「芝公園六角堂跡」である。西村らしい私小説である。というより彼は私小説以外の小説を書く気がない。西村にとって文学とは私小説のことである。作品は「二〇一五年二月の、肌寒き夕方である」で始まる。過去の話ではなく、ほぼリアルタイムの舞台設定になっている。
主人公の北町貫多は芝公園近くのタワーホテルに、J・I(稲垣潤一)のコンサートを聴きにゆく。さして音楽好きではないが、貫多は中学二年生の頃からのJ・Iの大ファンだった。作品でもしばしばJ・Iの音楽について書いた。作家として有名になるとそれがJ・I本人の耳に入るようになり、コンサートに招かれるようになったのである。
貫多はJ・Iのコンサートを堪能し、コンサート終了後はステージに上がってJ・Iが使ったドラムセットを間近で見る。しばらくしてJ・Iが現れ、ドラムセットの前に座った貫多と記念写真も撮ってくれる。ファンにとっては夢のような時間だ、貫多はもはや名士なのだ。打ち上げではJ・Iの隣に座り、上機嫌で会場のホテルを後にしたのである。
その貫多は心の中で、
(さて――)
と呟いていた。(中略)
当然ながら、貫多はそこが――彼が今佇んでいる場が、大正期の私小説作家、藤澤淸造のまさに終焉の地であることは、はなから承知済みだった。(中略)
この私小説家の著作によって、貫多は確かに人生を変えられた。二十九歳の時以降、その著作を唯一の心の支えとして日々を経てていた彼は、やがて〝歿後弟子〟を自任し、自らも私小説を書き始めている。
この私小説家の著作を読まなければ、絶対に本腰を入れての小説書きなぞしなかったであろうし、またこの私小説家の無様な人生の軌跡を知らなければ、こんな、お利巧馬鹿ばっかりの書き手と編輯者と評論家による、くだらない凭れ合いのマスかきサークルの中で、それでも書き続ける意地なぞは、とっくに打捨ってしまっているに違いない。(中略)
と、事程左様に敬しつつも、はな、今夜のところは不遇で惨めな師のことはひとまずおき、現世の、明るく華やかな方面のみにどっぷり浸かってみたかった。
(「芝公園六角堂跡」西村賢太)
西村が昭和七年に満四十三歳で亡くなった私小説作家、藤澤淸造に私淑していることはよく知られている。日本における藤澤淸造研究の第一人者だと言っていい。作品中の主人公、貫多にもそれは投影されている。彼は華やかなコンサートの楽しさに浸りきりたかった。しかしコンサート会場のホテルが、師と仰ぐ淸造終焉の地に近いことも最初から意識していた。場所は特定できないが、淸造は芝公園内にあった六角堂内のベンチで行き倒れ凍死したのである。無名時代にはしばしば訪れていたその場所から、貫多の足は長い間遠ざかっていた。コンサートの興奮が醒めると、貫多の足は自然と淸造終焉の地に吸い寄せられる。貫多自身の現実に引き戻されるのである。
藤澤淸造に出会わなければ、西村が「絶対に本腰を入れての小説書きなぞしなかった」のは本当だろう。しかし「こんな、お利巧馬鹿ばっかりの書き手と編輯者と評論家による、くだらない凭れ合いのマスかきサークルの中で、それでも書き続ける意地なぞは、とっくに打捨ってしまっているに違いない」という言葉は真実であり虚偽でもある。西村はこの逆に、その気になればインテリたちに対していくらでも卑屈になることができる。傲慢になることもできる。それが西村の私小説である。決定的思念などなく、ある思念は次の思念によって簡単に打ち消される。そのような感情の機微を執拗に描き続けるのが西村の私小説だ。
何度も云うが、彼の場合、はなそれは藤澤淸造の、〝歿後弟子〟たる資格を得るべくの出発だった。そして依然その状態で書き続けていたはずであった。
しかし今は――何かその軌道が、おかしな方向に行ってしまっているのだ。(中略)
何の為に書いているのかと云う、肝心の根本的な部分を見失っていたのである(中略)
なれば、と云うのも妙なものだが、やはり貫多たる者、今があの〝墓前〟に還るときである。(中略)
その辺の純文学気取りのように、それらしき理屈を並べて、いっぱし〝書き手の苦悩〟をぶっても仕方がない。こんなもの、いくら机上で思案を重ねたって仕方がない。(中略)
根が案外の潔癖症にできてる彼は、このひとときのすべては久々にかの終焉地に立ったことによる、甘な、感傷の為の感傷ではなかったかを自問し、やがて口元に微かな笑みを浮かべた。
(同)
西村の私小説の大きな特徴に、〝文学的苦悩(書き手の苦悩)〟が一切ないことがあげられる。以前も指摘したが、批評にまとめるかどうかは別として、西村は過去の私小説について考え抜いた〝メタ私小説作家〟である。私小説は簡単に言えば、維新後のヨーロッパ文学の流入による〝自我意識の肥大化〟によって生まれた。ヨーロッパ的自我意識を表現の基盤としたわけだが、それはもちろん万能ではない。人が強い自我意識を行使すれば、必ず他者や社会との軋轢が生じる。苦悩はそこから生まれる。また苦悩が生じれば、救済を求めるのは一つの必然である。実際、島崎藤村らの自然主義作家から葛西善蔵ら私小説全盛期の作家に至るまで、多かれ少なかれ彼らは救済を求めている。
しかし救済など存在しないのである。もし現世的苦悩の全面解消を求めるのなら神(的概念)に帰依するしかないだろう。もちろん日本の作家たちはヨーロッパ的な神を受け入れることはしなかった。そのため私小説作家たちが措定する観念的救済(落としどころ)は、日本古来の輪廻転生や花鳥風月的諦念に収斂しがちがった。だがそれはかりそめの救済に過ぎない。私小説作家たちは、仮の救済にたどり着くことはあっても、そこからまた解決も救済もない現世的修羅の世界に舞い戻っていったのである。
ポスト私小説作家である西村は、私小説の本質が観念的救済にはなく、現世の修羅を描くことにあると認識している。「救済はない」というはっきりした断念から出発しているのである。そのため彼が描くのは現世的修羅であり、苦の世界である。しかし救済指向がない以上、その対局としての苦悩も本質的には存在しない。むしろ苦が世界の常態なのであり、それを描くのが世界を描くことだという姿勢が西村にはある。
貫多は自分の文学の「軌道が、おかしな方向に行ってしまっている」、「何の為に書いているのかと云う、肝心の根本的な部分を見失って」いると感じている。それを修正するために、藤澤淸造の「〝墓前〟に還る」ことを秘かに決意する。しかし早くもそれが、「久々にかの終焉地に立ったことによる、甘な、感傷の為の感傷ではなかったかを自問」している。決意し、それを反故にし、またそこに惹きつけられてゆくのが西村が捉える人間の本質である。
自分のふとんの上で、コートを着たまま目覚めた。頭を振っても、何の記憶も絞り出せない。破れた紙袋が傍らにある。鉱物事典が顔を出している。その下に隠れていた一冊を取り出す。私のミッシェル。フランス人だから本来ならミシェルだ。ミシェル・ド・モンティーニュ『エセー』の第一巻。
死と隣あわせだった数日、私の身体能力は、聴力を除いて、ふだんの数十分の一に落ちていた。少しの活字にもしんしんと目の奥が痛む。それでもミッシェルは私に囁き続けてくれた。おまえが生きるという、この絶えざる仕事とはな、それは死という建物を構築するようなものなんだ。生のなかにいるあいだ、おまえは死のなかにもいるのだ。
携帯がけたたましく鳴った。母の声が、深い水の底から湧きあがってくる泡のように、私の鼓膜を打つ。
「時々、おまえが私のことを疎ましいと思っているのやないか、という時がある」
「そんなこと」
その先が言葉にならない。私は観念して目をつむる。まどろみの中で、齧歯類の歯が私の夢をかじる。おかげで私の朝は真っ白になる。
(「ミッシェル」荻野アンナ)
荻野アンナの「ミッシェル」も私小説と言っていいだろう。「死と隣あわせだった数日」とあるのは、主人公の大腸ガン手術のことを指す。要介護状態の母親を抱えた私は、手術とその療養のために母の面倒を見ることができなくなり、思い切って母を入院させたのだった。私は自宅に帰ってきたが、母はまだ病院にいる。
引用は作品の末尾だが、主人公は「私のミッシェル」は十六世紀のフランスの哲学者ミシェル・ド・モンティーニュのことであり、彼の代表作『エセー』第一巻からその言葉を引用している。「この絶えざる仕事とはな、それは死という建物を構築するようなものなんだ。生のなかにいるあいだ、おまえは死のなかにもいるのだ」というのがこの作品の観念的な落としどころ、つまり救済(指向)だろう。
しかしすぐに病院にいる母親から電話がかかってくる。母は「時々、おまえが私のことを疎ましいと思っているのやないか、という時がある」となじり、娘の私は「そんなこと」と言って言葉を詰まらせる。私小説が始まるとすれば、この沈黙の後からだろう。「その通りだ」と「そうではない」が等価になるまで、作家は自分の心を抉らなければならない。
大篠夏彦
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


