 「詩人と呼ばれる人たちに憧れている。こんなに憧れているにもかかわらず、僕は生まれてこのかた「詩人」にお会いできた試しがない。・・・いつか誰かが、詩人たちの胸ビレ的何かを見つけてくれるその日まで、僕は書き続けることにする」
「詩人と呼ばれる人たちに憧れている。こんなに憧れているにもかかわらず、僕は生まれてこのかた「詩人」にお会いできた試しがない。・・・いつか誰かが、詩人たちの胸ビレ的何かを見つけてくれるその日まで、僕は書き続けることにする」
辻原登奨励小説賞受賞の若き新鋭作家による、鮮烈なショートショート小説連作!。
by 小松剛生
バーバリの真実
女の子は僕に「その時計はバーバリなの?」と訊いてきた。
僕はバーバリが何かも知らなかった。
「バーバリかどうかはわからないけど、なかなかに壊れないし良い具合だよ。それにベルトのとこの革が肌の色みたいに薄いとこなんか、ちょっと変わっていて気に入ってるんだ」
そう言うと彼女は首を傾げてしまった。
僕は確かに日本語を話したつもりだったけれど、どうやらうまく伝わってくれなかったらしい。
女の子にとって大事なのはバーバリかそうでないか、だけのように思えた。
そう思ったとたん行ったこともない彼女の部屋がバーバリでできているような気がした。
バーバリのテーブル。
バーバリの出窓。
バーバリの本棚。
そしてやっぱりバーバリの丸い壁掛け時計。
想像していたらその子の部屋を実際に見てみたくなって 「部屋に行ってもいい?」と言いかけてやっぱり止めた。
セックスが目的だと思われるのも癪だし、かといって「バーバリだらけの部屋が見たいから」と、本当のことを言うにしても胡散臭そうな目つきを向けられるような気がした。
そんな目つきをされるくらいなら死んだほうがいくらかマシだった。
今、彼女は注文したドーナツが来るのを入り口と注文カウンターの間でただ待っていた。
「あれ」
ふと僕は彼女と初めて会ったときのことをすっかり自分が忘れてしまっていることに気づいた。
外では昨日から曇り続けていた空からやっと雨が降ってきた。
「ねえ」
「なに」
僕は君とどうやって出会ったんだっけ。
そう尋ねようとしたけどひょっとしたらそれはずいぶんな失礼なのではないか。
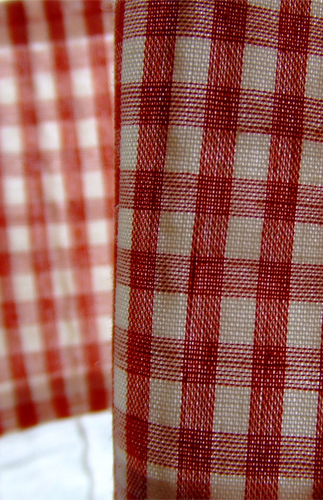
「どうしたの」
口をつぐんでいる僕を不思議そうに彼女は見ていたから、何か訊かなくちゃいけないなと思った。プロ野球の話でも振ろうかと思ったけど、残念ながら彼女は野球を知らない。犠牲フライと牡蠣フライを似たようなものだと思っている伏がある。
「あの雨はバーバリかな」
馬鹿なことを言ってしまった。
その質問が 「スプーンにひづめはあるんですか」と同じくらい的外れなことぐらいは僕にもわかっていた。
彼女は言った。
「いや、あの雨はバーバリじゃないよ」
バーバリの雨だったらもっと黒くて細長いはずだよ、と彼女は続けた。
「そうか、違ったかな」
「うん、違った」
彼女であればスプーンとひづめの関係性について怒らずに教えてくれるかもしれないな、とも思った。
ドーナツはまだ来ない。
このままずっと二人でドーナツを待っていたかった。
彼女もそんな気分になっていてくれればよかったけど、きっとそれはバーバリの雨が降るのと同じくらいの確率でしかないであろうことを考えると、僕は急に悲しくなってしまった。
「どうしたの」と女の子。
「いや、ドーナツまだかなって思って」
ああそうね遅いね、と彼女はうなずいた。
腕時計がかすかにカチカチと音を立てていた。
――きっと彼女にとってはこの時計がバーバリかどうかなんてどうでもいいんだろうな。
それだけはなんとなくわかった。
九月終わりのことだった。
おわり
羊飼いたちの沈黙
戦争を失くしたり癌を治したり愛を謳ったりすることはできないから、とりあえず僕は豆乳ラテをこぼさずに2階へと運ぶことに全力を注いだ。
渋谷は宮益坂の中腹にあるエクセルシオールカフェにいる。
平日であろうと夜はいつも混んでいるはずの店内が、その日に限ってやけに空いていた。
日曜日の夜8時、むしろ満席でもおかしくない時間帯である。
その事実に僕は無理やり納得する。
人生にはそういうことだってあるのだ。
昨晩にタクシーで間借りしているアパートに戻る途中、知らない番号から着信があった。
通話ボタンを押すと昔に呼んだ風俗嬢からだった。
「これから部屋に行ってもいいかな」と彼女は告げた。
「部屋番号は憶えてる?」
憶えてる、と電話口の声が言った。
僕が彼女について憶えていることといえば冬でも日焼けしたかのような肌の色と特徴的なしゃがれ声、細いくびれ。
ずいぶん前のことなのに思い出すことのできる自分に驚いた。
でも、それだけだ。
僕は単純に、お金を払わずに彼女と一晩過ごせるなんてラッキーだなと思った。
結局僕たちは昼過ぎまで寝て、遅い朝食代わりに近所のファミリーレストランでチキンカツサンドを食べていた。
食後にコーヒーを飲む時点で二人ともお互いへの興味をすっかり失くしていたように思う。
閲覧用の新聞をテーブルの上に拡げて社会面に目を通しているとき、彼女がぽつりとつぶやいた。
「羊は何匹殺されたのかな」
「ひつじ?」
「世の中でなにかひどい事が起きたとき、自爆テロとか空爆とか。もしそこに羊牧場があったとしたら何匹くらいの羊が犠牲になったのかってアタシは考えることにしてるの」
「羊換算ってこと?」
彼女はうなずいた。
僕は羊って牧場で飼うものだっけかなと頭を巡らせながら続きを促した。
「それでもしもあたしが彼らを飼う羊飼いだとしたら。そう思って悲しくなるようにしてる」
なるほど。
いろいろな考え方が世の中には存在するらしいことは知っていたけれど、そういうのもあるのかと感心してしまった。

もっとも頭の中でとはいえ、事件や事故をそのまま羊換算として勝手に彼らを殺すのもひどい話なのかもしれないけれど、少なくともそこには悲しみを共有しようとする姿勢があった。僕はといえば新聞を拡げれば昨日の野球の結果くらいしか見ないのに。それも広島カープの勝敗という、なんとも局地的な部分のみだ。
それきり彼女は黙ってしまった。
静かな悲しみだ。
羊と会ったのは小雨の降る10月半ばのことだった。
新宿西口のバスロータリーから歩いて数分の場所に建てられたホテルの玄関前にいた。
人、ではない。
羊だ。
彼は回転とびらの前でぼうぜんと立ち尽くしていた。
「何してるんだ」
僕の問いに羊は悲しそうな目を向けた。
その視線ひとつで僕は彼のことをすべて理解できるような気分に襲われた。
勘違いは種族間の隔たりなんてあってないようなものらしい。
「入れないんです」
「何かまずいことやらかして、フロントから締め出されているのか」
羊は首を振った。
「回転トビラに入ることができないんです」
タイミングが難しくて、と彼は続けた。
その間にも続々と他の通行人らはホテルのロビーへ向かうべく、ふるふると回る回転とびらに吸い込まれていった。
僕と羊は並んでその様子を眺めた。
「ひどい話ですよね」と、羊。
シャンデリアの内装がロビーの派手な印象に加担していることには間違いなく、なんだか向こう側が遠い世界の物語での出来事のようにも思えた。
「僕ら羊は最近とくに不当な扱いを受けている気がします。ある絵本では羊が人間を図書館に監禁してドーナツをたっぷり食べさせる話が描かれているんです。偏った食事で人間を太らせてから、ノコギリで切り刻んで食用にしてました。羊は人を食べたりしません。だいいち回転トビラにだってうまく入れない生き物が、どうやって人を監禁できるんですか」
確かに、と僕はうなずいた。
ひどい話だ。
僕は彼の毛深い肩をたたいて「わかるよ」と言った。
彼の悲しそうな瞳が何日か忘れられずにいた。
羊飼いに、僕はなれそうにもなかった。
豆乳ラテはこぼれずに済んだ。
戦争は終わったのだろうか。
そして。
世界に羊飼いはどのくらいいるのだろうか。
おわり
バケツを忘れる
今からこのお話を読もうとしてくださっている皆さまへ
この話は『小さじ一杯の答え』『スカートをぶつけた日』の続編に当たります。だからといって、読者の皆さまに「前の2篇も読んでください」などというしち面倒なことを言う権限が僕にあるわけではありませんが、いきなり今回のお話を読まれるかたにとっては、もしかすると意味のわからない事柄が出てくるやもしれません。そうして皆さまの貴重な時間を奪ってしまう可能性は十二分にあります。もしそうなってしまったかたがいらっしゃいましたら、この場をお借りしまして、お詫び申し上げます、
2015/02/28 小松剛生
雨の降る日はいつもより多く人が死ぬ。
その言い伝えを教えてくれたのは父方の祖母だった。
祖母の口調にはそれが迷信だと自覚していながらも、断定の響きがあった。
たまの連休に里帰りしたときなどにはときどきに、その響きに触れる機会があった。
それは大抵が早起きしてしまった明け方の、台所側で為された会話の上でのことだった。
「今日も雨が降りよるねぇ。人がようさん死ぬんね」
思えば当時、まだ思春期にさしかかろうかとする女の子に聞かせるにはいささか直接的すぎるような気もするが、その遠慮のない物言いはニワさんにとって新鮮だった。
不思議と少しも怖くなかった。
「人が死ぬんだ?」
「いつもよりかね。雨が降っとるからね」
すでにニワさんと同じくらいの背に縮んでいた祖母はそう言って、ぬか漬け用の壺からきゅうりやら茄子やらを取り出して、まな板の上でお世辞にも均等とは言えない大きさに切り分けていた。
とんとんとん。
さーさーさー。
包丁の音と雨音が混じって、まだ朝冷えのする台所の椅子で膝を抱えながら、それらに耳を傾けていた記憶が残っている。
とんとんとん。
さーさーさー。
思えば祖母のいる台所はいつでも綺麗だった気がする。
もちろんニワさんたちは立場的にはこの家屋のお客さんなので、来る時には祖母も埃をはたいて準備してくれていたであろうが、それにしても整理整頓がきっちりとついていた。
たしかに味噌汁のパックを容器代わりにしていて、覗いてみると中には大量の箸置きが積まれていたりすることもあった。
が、とにかく掃除そのものは行き届いていた。
――祖母はあまり疑問を抱え込まない人だったのかもしれない。

ニワさんの中にはひとつの哲学がある。
もっとも本人は哲学などという大そうなものだとも思っていないし、思想というにも根拠も何もない。
他に呼びようもないのでここでは哲学とさせていただく。
果たしてそれはなにか。
疑問を抱えない人のいる場所は基本的に綺麗だ、という哲学である。
あれこれと多く悩み、悩んだ末に出来上がった疑問をそのままにしてしまっている人ほど部屋は雑多と汚れていく。
決してその人が掃除をサボっているということではなく、では何をサボっているのかと訊かれれば疑問を溶かすこと、とニワさんは答える。
疑問を放っておいたままにして結晶化されてしまう段にそれが至ると、素人にどうこうするのは難しい。
ましてや片づけるのは至難の業だ。
普通の箸置き(へちまの形を模したタイプ)に見えるそれをどこにしまうべきか迷う時があるとする。
もしかしたらそれはへちまの箸置きではなく、箸置きの形をした疑問かもしれない。
それは疑問故にどこにしまうべきかもわからず、いつまでも中途半端な位置に留まり続ける。
そうしてその人のいるべき場所は雑然としたもので散らばっていく。
いくら掃除をしても疑問の結晶が散りばめられた辺りは傍から見れば物が散乱しているのと同じで、汚れて見えてしまう、というわけだ。
この考え(哲学)が当たっているかどうかは不明だが、かといって的外れなものではないような気もする。
決して長くはないニワさんの人生において、ひとつ明確に浮かんでいる哲学であることは確かである。
幸い、ニワさん自身もなるべく疑問を抱え込まぬよう生きてきた。
そこに立ち止まらぬよう、とりあえず何らかの答え(それが正解かどうかは別にして)やら決まりやらを着ける習性がいつの間にやらついていた。
おかげさまで彼女の暮らす部屋はきれいに片付いている。
さして掃除好きでもないのだけれど。
さーさーさー。
外では雨音が続いている。
湿気と黴臭さを含んだ布団に鼻をうずめたニワさんは眼だけを動かして、その汚い6畳ほどの部屋を見回す。
暗さのせいか、ヤニで黄ばんでいるはずの壁紙は今や白く輝いているようにも見える。
辺りにはこれでもかというほどの結晶化された疑問が所狭しと転がっている。
物は少ないが疑問は多かった。
初めて上がりこんだニワさんに対してその部屋の主は恥ずかしそうに「どうも自分の疑問は片づける気が起きなくてな」と坊主頭をぽりぽりと掻いた。
「汚いだろ」と主は羞恥心をごまかすように笑った。
「そうですね」とニワさんは言った。
このやろう。
きゃはは。
二人とも酔っていた。
泥酔していた、と言い換えてもいいだろう。
取っ組み合いになり、山垣さんの坊主頭を覗きこむ。
相変わらずきれいなつむじだ。
焼酎を1升空けた赤ら顔の彼がニワさんの顔を見上げた。
そういえばこの小さな先輩とあまり直接的に目を合わせたことがなかったことに、ニワさんは気づいた。
「俺、小さいだろ」
「そうですね」
このやろう。
きゃはは。
そのまま敷きっぱなしの布団に転がりこんだのが数時間前のことだ。
記憶はある。
ニワさんが暗闇の中にひとつの塊を見つけ、ぼんやりと寝起きの頭で考えながらもそれが自分の下着であることを思い出す。
もぞもぞと起き上がり、そこでようやく今の自分が生まれたままの姿であることも思い出す。
なんだか思い出してばかりで、ということは普段の自分がどれだけいろいろなことを忘れていたのかと思うと少し悲しくなる。
ほんとうに少しだけだ。
そんなことでいちいち悲しがっていてはたぶん、今頃思い出よりもたくさんの悲しみを抱えていなくちゃならない。
乾いた皮脂の臭いがする。
寝る前の夢心地のような何かから、その臭いが現実とやらを運んできてくれていた。
余計なことを、とニワさんは思う。
「起きたか」
まだ布団の中に身体をうずめながらも顔だけひょこりと出す山垣さんがいた。
彼もまた、皮脂の現実に帰ってきたばかりなのかもしれない。
「帰ります」
「そうか」
――シャワー、浴びるなら好きにしていいから。
そう言って再び枕に顔をうずめる。
小さく「はい」とだけ答える。
手を伸ばして下着を掴み、布団の中でなんとかそれを穿くことに成功したニワさんは浴室には向かわずにそのまま脱ぎ散らかした衣類の袖に手を通す。
部屋を出てから初めて腕時計に目をやると、時刻は午前3時半を指していた。
帰路は坂道になっていた。
文学君の言葉を思い出す。
――僕はカレーライスの次くらいに坂道が好きなんです。
――坂の途中にカレー屋でもあった日には。
あった日には、どうしたんだっけ。
ニワさんはその後の言葉を思い出そうと、ゆっくり坂道を下っていった。
割と急な坂道で、走り出したら止まれなくなりそうだと思わせてくれそうな坂だった。
もちろん止まれるだろうけど。
ニワさんは考え続けた。
文学君の言葉を考えることで、さきほどまでの事実を忘れようとするかのようにカレーライスと坂道について考えた。
答えが出ないまま下りの道は終わり、今度は上りに入った。
もちろん、というべきか。
カレー屋は見当たらなかった。
翌日の現場は水戸だった。
眠い目をこすりながらハイエースに道具を積んでゆく。
あの後、シャワーを浴びて少しだけうつらうつらとしているうちに目覚まし時計が鳴ってしまったので、結局ほとんど寝ていない状態である。
いや、あの小さな人の部屋で少し寝たけど、あれはあれ。
車に乗り込んでバックミラーを確認する。
とりあえず目の隈を隠すために薄くファンデーションを塗っただけの顔だが、かえってお化けのようになってしまった危険性はある。
危険はいつだってすぐそばにあるのだ。
現場に行く前に研磨工場に寄る。
現場の図面や情報から足りない道具がありそうなときは、ここで調達することにしている。
もっとも図面通りの現場なんてほとんどないので、持っていった挙句に無駄になることも多い。
先週はわざわざ9尺の脚立を持っていったというのに、疑問が固まっていた場所は足場からじゅうぶんに手が届いた。
山垣さんもすでに工場に来ていた。
「おはようございます」
「おう」
目の隈がひどかった。
お互いに昨日のことは口にしなかった。
どちらとも言葉にしなかったが、昨夜のことは無かったことになりそうだ。
その沈黙が心地よかった。
「隈、ひどいですね」
「うるせーよ」と、山垣さん。
「昨日のこと、憶えてますか」
口に出してから、女である自分が使うにはいささか卑怯すぎる言葉だったかなと一瞬だけ後悔した。
男である山垣さんにとってはどう答えようと後戻りできない問いかけだったかもしれない。
ニワさんのそれには答えず、逆に彼は訊いてきた。
「帰りはちゃんと帰れたのか」
「子どもじゃあるまいし、帰れましたよ」
「ならよかったじゃねぇか」
ああ。
そうか。
この人はたぶん、どこかに後戻りする気なんてさらさらないのだ。
アタシと寝たことを無かったことにする気もなければ、かといってその事実を無闇やたらに口にするほど下品でもない。
小さな先輩を嫌いにはなれない理由がそこにはあった。
それをなんと呼ぶべきか。
無垢?
ちょっと違うな。
それにしても。
――なんてやっかいな生き方なんだろう。
山垣さんは若手に指示を出しながら、自身も倉庫の奥へと消えていった。
その背中を目で追いながら、彼の部屋に疑問が多く転がっている様を思い浮かべた。
――雨の降る日はいつもより多くの人が死ぬ。
祖母の言葉がよみがえる。
なんとなく、ではあるが。
あの小さな人は長生きできないような、そんな気がした。
今より少し昔のこと。
文学君がウチにバケツを届けにやって来た。
それは他の何にも使いようのないほどに見事なバケツだった。
「どうですか」
胸を張る文学君の気持ちは今ではちょっとわからなくもないけれど、当時は彼と出会ってまだ日が浅かったニワさんは呆れかえるばかりだった。
「何なの、これ」
「何って、見てわからないんですか」
心の中で「見てわからないから訊いてるんだよ」と答える。
口にはしない。
「バケツ、ですよ。見事なまでにバケツでしょう」
確かに真鍮でできたそれは銀色に輝く外貼りされ、細く錆びついた取っ手は握るたびに容器の部分が重さでわずかに揺れた。
どこからどう見てもバケツであり、それ以外の何物でもなかった。
「あのね、文学君」
「はい」
「バケツを持ってきてどうしろというの、アタシに」
「いや別にどうということはないんですけど」
でも何だかわくわくしてきませんか。
たぶんこれを思い切り蹴飛ばせば、つま先の形に凹むと思うんですよ。そこらへんもバケツ的で、これを見ると僕らが今まで見てきたバケツってなんだったのかなって、そんな気がしませんか。
「しない」
「そんな冷たい反応しないでくださいよ」
文学君の数少ない良い点は、めげないところだとニワさんは思う。
「これこそが正真正銘のバケツなんだと思います。いいですか、バケツっていうのはそれ自身では何の役にも立ちません。これは容れ物なんです。何かを入れることで初めてその意味を見出すんです。たとえば」
「たとえば?」
「水、とか。雑草、どか。せん切りしたキャベツだとか、悲しみとかね」
「悲しみも?」
「もちろんです」
このバケツを一杯にさせるほどの悲しみとなると、どれほどの悲しみが必要なのだろうか。
改めてニワさんがバケツを手にとって眺めると、ちょうど窓から射し込む西日にあたって銀の乱反射が彼女の目を刺激した。
いつの間にかほとんど日は暮れかけていた。
「お腹、空きましたね」
何か食べに行きましょう。
そう言って文学君はバケツのことなど我関せず、居間に背を向けた。
「早く行きましょう。今日はカレーですよ」
「いつ決まったの」
「今です、僕が決めました」
ニワさんは呆れて、しかしもう反論する気にもなれずに仕方なく履き古したサンダルに足をつっかけた。
近所は住宅地でろくに飯屋もなかったので、駅前まで歩いていくことにした。といっても10分もかからない道のりである。暗くなりかけた道を、細身の二人がゆっくりと下っていく。
影が伸びてサンダルの間抜けな闊歩音が響いた。
「僕はカレーライスの次くらいに坂道が好きなんです」
「ふぅん」
「坂の途中にカレー屋でもあった日には」
そうだ、あの時に文学君にカレーの話を訊かされたのだ。
今の今まで忘れていた。
そしてやっぱり肝心な部分は思い出せずにいた。
水戸での現場仕事は意外にも早く片付き、明らかに寝不足のニワさんは帰りの運転を柴田君に任せることにした。
年は40歳を過ぎてニワさんよりもだいぶ人生経験豊富ではあるが、疑問拾い工としてはまだ3年目と浅いため「柴田君」と呼んでいる。
なんでも昔は短距離の選手として国体にも出場し、大会記録を出したときもあったらしい。
今では月に一度の別れた奥さんと娘に会いに行くこと、そのついでのパチンコ巡業が日課となったおじさんだ。
「寝てていいですよ」
「うん」
窓から眺める常磐道の景色はどこまでも変わらなかった。
眠気と共に昨夜の出来事が思い出される。
なぜか思い出したくないが、それでもつい思い出してしまう。
人間とはずいぶんと不便な生き物らしいということを少し自覚する。
無性に文学君に会いたくなった。
会って、また彼のバケツの話を訊きたかった。
カレーを食べたあの日、結局バケツはニワさんの部屋に置きっぱなしでそのままだ。
どこにしまったのかすらも忘れてしまった。
疑問を拾う日々を過ごすうちに、ずいぶんと冷徹な人間になってしまったのやもしれない。
そうならない人間もいる。
例えば山垣さんみたいに。
でもアタシは疑問を部屋に貯めておくことも嫌なのだ。
「寝てていいですよ」
もう一度、柴田君が言った。
「うん」
直後に「あ」と、柴田君。
閉じかけた目を開けると、フロントガラスにいくつかの水滴が落ちていた。
「雨だね」
「雨ですね」
「いつもより、ようさん人が死ぬんね」
ニワさんは小さく呟いた。
――そういえば、お祖母ちゃんは巨人が嫌いだったっけ。
好きな野球チームがない代わりに嫌いな野球チームは存在する、それもまた祖母らしいエピソードのひとつだ。
ワイパーが窓を擦る音に紛れてその呟きはすぐに車内に消えた。
「え、なんですって」とは柴田君。
「なんでもない」
ニワさんの頬にも水滴がついていた。
バケツから溢れ出るかのように、それはニワさんの頬を何度も流れた。
忘れていたはずの悲しみだった。
おわり
(第04回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『僕が詩人になれない108の理由あるいは僕が東京ヤクルトスワローズファンになったわけ』は毎月24日に更新されます。
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
