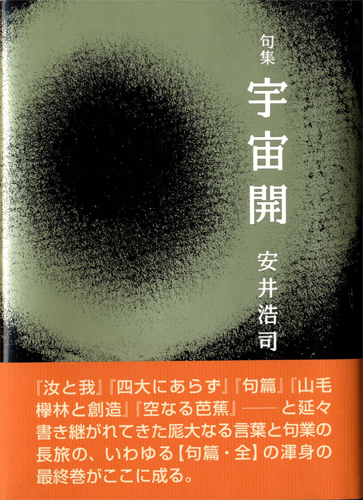
熱湯をこぼせば燃えて寒菫 (Ⅰ)
おびただし山蟬流れる最上川 (Ⅱ)
宙に切る十字に止まれや黒鶫 (Ⅲ)
山上乙女が帯を放れば天の川 (Ⅲ)
大山に押しつけ虹を曲げる尊 (Ⅳ)
かけじくへ躍れる貘や山河食う (Ⅴ)
行く春の空に懸かれる大連歌 (Ⅵ)
雪の花龍の鱗を散らしつつ (Ⅵ)
数茎の火力絞られ曼珠沙華 (Ⅵ)
夏鷲は養老山脈ひと掴み (Ⅵ)
岩壁を流れる絲水織る女 (Ⅵ)
霜道二本突き出す眼の蔵王像 (Ⅶ)
これらの作品は、安井俳句を読んだことのある方には親しみ深いものだろう。安井氏による一種の有季定型俳句であり、実際、作品の多くは季語を含む五七五定型に沿って書かれている。読者がこれらの句を読みあぐね、難解だと感じるのは、句が通常の俳句のようには現実を写していない(写生ではない)からである。しかしあえて言えば安井氏の俳句はそれほど難解ではない。難解に見えてしまうのは、安井氏の現実の捉え方が通常の俳人とは異なるからである。
安井氏の現実は、存在が現実世界で現象する(存在の輪廓を固着化させる)以前の状態を含む。簡単に言えば人間は現実世界以前に膨大な想像界を抱えている。通常は夢や幻想と呼ばれる世界である。ただこの想像界はまったくのフィクションではない。想像界は人間のインスピレーションの源泉であり、日々そこから新たな発見・発明が行われている。この生成システムはもちろん過去にも遡り得る。わたしたちが現実存在として認識している諸物はその源基を想像界に持っているのである。
この現実世界と想像界との関係を的確に認識すれば、現実世界の表現は可変的なものとなる。わたしたちは言葉(自然言語)による想像界のイメージ表現を、一般的に〝詩的表現〟と呼んでいる。詩人による詩的表現が人間を惹き付けるのは、そこに現実存在を遡る源基としての想像界が垣間見えるからである。しかし安井氏は〝詩的〟というレベルには満足しない。彼はそれを明確に〝詩〟として表現しようとしている。
「熱湯をこぼせば燃えて寒菫」、「数茎の火力絞られ曼珠沙華」といった作品は、現実存在の背後に蠢く想像界を断定的に表現している。寒菫や曼珠沙華は〝火〟を内包しているのであり、その姿(存在)は燃える火柱として表現し得る。凍える中で花開く寒菫や禍々しいほど赤い曼珠沙華の生命力は、想像界においては熱と光を放射し、やがて消えてゆく炎と同義だということである。意識と物の発生が同時(等価)であると認識すれば、その主客は転倒可能であり、夏の盛りに蟬の声で覆われた最上川は「おびただし山蟬流れる最上川」と表現できる。
観念の鯰絵掛けたる梅雨の寺 (Ⅰ)
天目山の秋抽象の旅人よ (Ⅳ)
雲雀野や無文字の神書を枕とし (Ⅵ)
抽象の輪を投げ孔雀捕らえんや (Ⅶ)
安井氏の方法は現実(存在)を絶対普遍のものとみなし(自我意識を絶対とすることでもある)、それを叙述する(写生する)ことを基本とする俳人から見れば観念的で抽象的だろう。しかし俳人たちは飽くことなく現実を描写・写生しながら、その奥に存在するはずの、ある原理を捉えようとしてきたのではなかろうか。俳句が単純な散文的描写ではなく詩であるとすれば、平明に現実界を叙述しているように見える写生作品は、その上位(あるいは下位)に、ある抽象的観念を保持しているはずなのである。
俳句文学の技法はシュルレアリスムのそれに似ている。シュルレアリスムの技法はロートレアモンの「解剖台の上での、ミシンと雨傘との偶発的な出会い」を引用してしばしば言われるように、〝遠きものの連結〟である。この技法はヨーロッパでニーチェ以降の神の不在認識から生まれた。前世代のマラルメらの象徴主義者(サンボリスト)たちは世界は神によって創造されたのであり、世界内存在には神の意志が表現(象徴)されているはずだと考えた。しかしシュルレアリストは神的意志を認めない。世界内の存在をランダムに組み合わせれば新たな〝創造〟が起こるのである。この揺るがしがたく固定化した、神の創造物であるはずの現実世界を揺さぶるシュルレアリストらの試みは、神の否定であると同時に新たな神の創出だと言うこともできる。相変わらず〝創造〟は起こるからである。
一神教的な世界の創出点=神を持たない日本では、シュルレアリストたちが試みるずっと以前からランダムな世界内存在の結合が行われてきた。俳人たちはほとんど無限の世界内存在を組合わせることで創造を行ってきたのである。実際、自在に世界内存在を組み合わせる(取り合わせる)ことができる作家こそが、俳句の名手だと言われてきた。しかし俳人たちの試みは原則的に現実世界に留まる。シュルレアリストたちのように、現実世界に揺さぶりをかけることでその背後にある想像界に赴こうとはしなかったのである。俳句が座の文学、つまり〝気楽な言葉遊び〟に堕落しやすい理由がここにある。
安井氏は俳句史上初めて、明確な意志を持って現実以前の想像界の存在(存在源基)をも俳句の取り合わせの対象とした作家である。この安井氏の方法は、俳句から遊びの要素を完全排除して、ほぼ純粋な文学として捉えようとする決意の表れでもある。正岡子規が書いたように、写生俳句は一句二句をようやくのことでひねり出しているようでは埒があかない。世界を詠み尽くすような勢いで俳句を量産しなければ意味がない。写生による多作によって、現実内存在を単純に組み合わせただけのような俳句表現がある無意識に近づくからである。作家の自我意識が作品を作り上げるのではなく、世界創造の機微が自ずから俳句の言葉となって現れるのである。
安井氏の文学は、子規の写生俳句に代表される俳句文学の主流(基本的方法)とそれほどかけ離れていない。多作によって一瞬の観念の高みを垣間見る写生俳句の方法を普遍化しようとしている。この試行は人間存在にとっては不遜なものである。しかし俳句はなぜ書かれるのか、俳句はなぜ文学であるのかを真摯に問えば、「抽象の輪を投げ孔雀捕らえんや」の句で表現されているように、その原理を鷲掴みにしようと試みる作家がいずれ現れねばならない。
『宇宙開』なる言葉は、遠い昔に或る公的な場で、己が文芸の序章を開くべく私語に近いかたちで発したままだったが、(中略)精神のコスモロジーが、そのまま俳句形式の宇宙開を促すべく、いま俳句未来の礎の願いを込め、却ってこの最終書を飾るにふさわしい書題のように思えた。
(句集『宇宙開』「後記」より)
「精神のコスモロジーが、そのまま俳句形式の宇宙開を促す」という言葉は安井文学の企図を的確に語っている。安井氏にとっての俳句形式は、現実世界でのささやかな喜怒哀楽や美醜を表現する小さな器ではない。人間の「精神のコスモロジー」すべてを表現できる巨大な文学形式である。そのため安井文学には原則的に、五七五や季語、あるいは切れ字などにまつわる俳句の諸規則は存在しない。それは限りなく自由な表現である。人間精神の無意識(想像界)をも含めた俳句制作を意識的に行った作家は安井氏が初めてであり、その試みは「俳句未来の礎」となるだろう。
ただ安井氏の文学は現在進行形で続いている。わたしたちは既存の安井文学だけでも充分にそれを「俳句未来の礎」とすることができるが、安井氏の求める〝礎〟はさらにその先にあるようだ。空から世界が現象するのは〝意識〟の発生と同時であり、それは本質的には無人称である(そのため神性を付与されることになる)。端的に言えば、安井氏は意識と物の発生の初源を捉えようとしている。作品を生み出す作家主体でありながら、作品から作家の自我意識をほぼ完全に消し去る無謀な試みが安井氏最後の戦いであると思う。
鵺一羽はばたきおらん裏銀河 (Ⅰ)
天文の明るさに在り冬すみれ (Ⅰ)
千社札人影もなく増える秋 (Ⅰ)
伐られても泰山木の影残り (Ⅰ)
天も地も似たこと起る厠火事 (Ⅰ)
崖の百合呼気と吸気の花ふたつ (Ⅱ)
睡蓮の息のふくらみ裂けはじむ (Ⅱ)
万象の母のかたちや臼きのこ (Ⅲ)
浮上して下に見えるや冬銀河 (Ⅴ)
鯰逝くすべて光であるまえに (Ⅵ)
天動の臼茸ひとつ回るかな (Ⅶ)
現実世界の諸物と、その背後に蠢く想像界の存在源基を取り合わせる安井氏の作品では、自我意識が作品表出主体になっている。現実界を絶対としないという意味で自我意識は相対化されているが、自我意識を軸に現実界と想像界の往還が捉えられているのは確かだからである。しかし安井氏はその先の表現を求めている。暗闇に灯りが点じて物が姿を現す一瞬のように、未だ〝自我〟という輪廓を持たない〝意識〟によって世界生成の機微を作品化しようとする。その一瞬は平明な叙述(写生)として表現される。「鵺一羽はばたきおらん裏銀河」、「浮上して下に見えるや冬銀河」のように、限りなく希薄化した安井氏の意識は通常は見えないものを見る。「天動の臼茸ひとつ回るかな」のように、世界の源基にはなんの変哲もない、だが世界樹とでも呼ぶべき「臼茸」が回転しているのである。
自我意識を限りなく空(無)にまで希薄化させて世界生成の機微を捉えようとする作品は、安井氏の句篇連作の目的である「新しいアニミズムの意志と、汎生命的なものの主宰性を呼吸しようとしている」(句集『汝と我』「後記」)ものだろう。誰のものでもないが、それ自体が意志を持つかのような世界生成の蠕動が表現されているからである。しかしそれが安井氏が求める高次の「絶対言語」そのものなのかどうかはわからない。ただ安井氏は、「結論から言えば、自分でもこの句集がどんな句集なのか、よくわからないんだな(笑)。こういうことは初めてですね。この前の『空なる芭蕉』までは、ある程度は自分で掴めた。でも『宇宙開』は、もやっとして掴めないんです」(『金魚屋インタビュー【『安井浩司俳句評林全集』出版記念】俳句と批評について』)と述べている。もはや自分(自我意識)の判断では良否を判断できない作品世界は、安井氏が進んでいる方向が正しいことを示唆しているだろう。
俳句文学では作品内で〝私〟という作家主体が表現されることは滅多にない。私が存在しないわけではなく、その逆に俳句作品はすべてが〝私〟の表現なのである。この意味で俳句文学は極限まで自我意識を肥大化させて、世界内(家族や恋人など狭い人間関係に限定せねば不可能ではあるが)に存在する他者はもちろん、自我意識までをも他者のように相対化して描く私小説と構造的には相似である。しかし私という表出主体を登場させない(表現において意識する必要のない)俳句文学では、私小説よりもさらにラディカルな探究が可能である。限りなく小さく希薄に私の自我意識縮退させて、世界内の諸物をほぼ完全に相対化できる可能性があるのである。
この意味で安井氏が、俳句をあらゆる事象を表現できる巨大な器として捉えているのは正しい。俳句文学は日本文学の基層に辿り着き得る可能性を持っている。またそのような基層を露わにするために、俳句は逆接的に極限まで単純な形式である必要がある。物と物を単純に取り合わせで新たな創造を行い、さらに原初の創造の機微にまで直截に表現を遡らせるのである。夾雑物が入り混じれば混じるほど俳句文学の固有性は脅かされる。つまり俳句文学はその構造的帰結によって、最小限度まで切り落とされた一定の形式を持つ。五七五に季語という俳句形式はその最大公約数である。しかし俳句文学の構造を理解していれば、基本的にどんなに奇抜な表現でも俳句として成立し得る。
深葛野を行く謎の老人ぞ (Ⅴ)
消えるまで沙羅を登りゆくや父 (Ⅶ)
「謎の老人」には安井氏の自負と自嘲が込められている。俳句文学で誰も為したことのない試みを行っている以上、安井文学は〝謎〟でなければならない。一方で安井文学は俳人の間にすらその理解者がほとんどいない、難解な〝謎〟として敬遠され続けることになる。しかし彼は「消えるまで沙羅を登りゆく」だろう。
安井文学が難解なのは、従来の前衛俳句のように俳句形式に揺さぶりをかけるのではなく、俳句文学の構造的ダイナミズムを表現しようとしているからである。未知の表現領域を求めるという意味での前衛は、安井文学における結果論的外皮に過ぎない。安井文学は俳句の王道を行くものであり、安井作品には俳句文学の最も重要なエッセンスが表現されている。
鶴山裕司
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■




