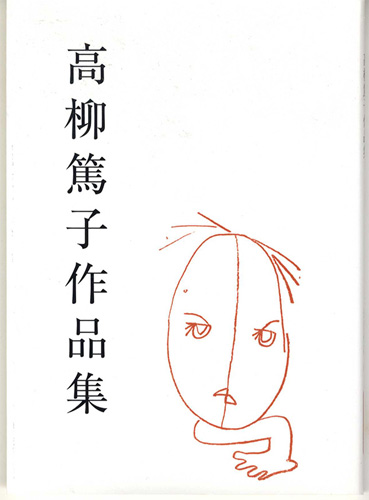
発行 二〇一九年五月二十四日
定価 一〇〇〇円(税抜)
発行者 鬣の会 代表 林桂
住所 〒371-0013群馬県前橋市西片貝町5-22-39
林桂さんの鬣の会から『高柳篤子作品集』が刊行された。岩片仁次編の「夢幻航海文庫」の一冊である。岩片さんは高柳重信の高弟のお一人で、重信前衛俳句運動の資料をまとめ、その意義を論じた個人誌「夢幻航海」を出版しておられる。今回の『高柳篤子作品集』も大きな視点で言えば重信研究の一環である。以前、同じく鬣の会刊行の『加藤元重句文集-戦後編』を書評で取り上げたが、重信がいなければ高柳篤子も加藤元重も作品が一冊にまとまることはなかっただろう。
巻末で岩片さんが高柳篤子の略歴を書いておられる。「本名は山本篤子、はじめは山本緋紗子と称し、ついで山本あつ子、高柳篤子。高柳重信と離婚後、広岡まり。本作品収録の大部分は、高柳篤子期の稿である」とある。
重信と篤子は昭和二十八年(一九五三年)六月に結婚し、十一月に長女蕗子(歌人の高柳蕗子さんである)が生まれた。今でいうできちゃった婚ということになろうか。昭和三十六年(一九六一年)五月に離婚している。離婚後重信は代々木上原の中村苑子宅に住み、「俳句評論」を刊行して本格的な前衛俳句運動に乗り出した(苑子とは籍を入れない事実婚だったようだ)。長女蕗子さんは戸田の高柳家に戻り、叔母の美智子さんが預かった。篤子は単身ニューヨークに渡り画家広岡まりとして活動することになった。
晴れた日も、急に荒れ模様に襲われることがあります。「無職で肺病の男に妹はやれない」という兄に彼女は引き戻され、軟禁状態になってしまいました。僕は呼び出され、落ち込んで死にそうになっている高柳に頼まれ、彼女への手紙を届けるポスト役を務めることになりました。(中略)そしてついに買い物に姿を見せた彼女に合図し、待機していた高柳に彼女を渡します。彼と彼女の道行き、戸田を避けて身を隠します。それは「女に書かすたびのやどの偽名かな」ではない。もっと差し迫っていたのです。頼ったのは、深谷の親戚筋か。
(岩片仁次編『高柳篤子作品集』所収「重信の友、加藤元重むかし噺」)
森や
谷ま
も
眠るとき
あかく
つらなる
こころの雪崩
(高柳重信 第二句集『伯爵領』昭和二十七年[一九五二年]より)
早稲田大学時代からの友人、加藤元重の回想によれば、「無職で肺病の男に妹はやれない」と篤子の兄に結婚を拒まれたことで、重信と篤子の恋愛はさらに燃え上がった。重信は第二句集『伯爵領』に「やまもとあつこ」を織り込んだ俳句も収録している。
重信は怜悧な理論家だったが、一方で熱いロマンティストでもあった。そのパッションが重信周囲に多彩な俳人たちが集った大きな理由である。若き日の重信にとって、篤子はそのロマンティシズムを燃え立たせる存在だったわけである。
じゃあなぜ二人は別れることになってしまったのか、ということになるわけだが、そこは男と女の話である。これ以上は立ち入らない。ただ重信は生涯に渡って、創作者の人柄ではなく、その才能に惚れる人だった。常住坐臥すべてが俳句の一種の文学狂だった。
重信の著作を読めば明らかだが、中期以降の重信は五七五に季語の伝統俳句の「白弥撒」に対し、自らの多行俳句(前衛俳句)を「黒弥撒」と呼ぶようになり、それは〝必敗の文学〟になるという予感を抱くようになった。最晩年には山川蟬夫名義で有季定型俳句への回帰を模索した。しかし当たり前だが重信は最初からある種の絶望を抱いて前衛俳句運動に乗り出したわけではない。
『高柳篤子作品集』所収「在ニューヨーク 広岡まり発書信」で、篤子は「私は「重信さんは病気で、もう命は長くない」と富澤(赤黄男)さんに言われました。でも病気のことより重信さんの態度がわがままというか、富澤さんに対してもオオヘイな口のきき方です。それを直してあげなければいけないと、自分よがりに思い込み(中略)「高柳重信という我が儘な青年は礼儀を知らないのです。何とかしてあの人を直してあげたいのです」と(橋本)夢道さんの奥さんにまで一生懸命に言いました。「あつ子さん、しかし彼はなかなか素晴らしい青年ですよ、天才だしね。」」と書いている。
若き日の重信には富澤赤黄男がいた。大正末から昭和初期の新興俳句の俳人であり、まったく前衛の意図なくして前衛俳人となった、ならざるを得なかった作家である。重信は赤黄男を師と仰ぎ先行者と認めることで彼自身の前衛俳句を育んでいった。初期重信の楽天的な前衛俳句運動は、伝統俳句と前衛俳句の違いなど知るか、といったふうにどっしり構えた赤黄男の存在に裏打ちされていた面がある。前衛俳人重信を毛嫌いする俳人でも赤黄男は無視できない。そして私生活では篤子との恋愛が重信のロマンティシズムを燃え立たせたのだろう。
文学狂・重信の場合、女性に惚れるといってもその才能とまったく無縁ということはない。篤子は初期の重信に決定的な影響を与えた一人だが、その作品をまとめて読めないと現実離れしたいい加減な神話にやりやすい。生前句集・詩集は一冊も上梓しなかったが篤子は気になる作家である。その全貌が明らかになるのは喜ばしい。
陽があたたまるとさびしがる耳
夢の裏から四角に朝が見え初めた
夜の緞子皮膚がちりりと寒くなる
焦げくさい音楽・兵隊靴の屍
部屋中を 8の字に歩けば途方にくれる
(昭和二十四年[一九四九年]~二十六年[五一年])
『高柳篤子作品集』収録の篤子最初期の作品である。十九歳から二十一歳にかけて書かれた。柔らかい書き方だが無季無韻であり、ある観念的イメージを明瞭に描こうとしているという点で明らかに富澤赤黄男の影響を受けている。
篤子が初めて赤黄男に会ったのは十六歳の時である。闇市が立ち並ぶ渋谷で風呂敷の上に句誌を並べて売っていた橋本夢道と石田波郷と知り合いになり、二人の勧めで赤黄男に会いに行ったのだと「在ニューヨーク 広岡まり発書信」にある。
篤子は「富澤さんは私を認めてくれました。富澤さんは重信さんにまわし読みにしました。左どなりに本島高弓さんがいました。私の二枚の詩はまわし読みになったのです」「富澤さんに書き送ったおかしな文章は「火山系」や「俳句世紀」という先生出版の本に活字になって載って、先生から送られてきました。ありがたさで心が真っ赤になりました」と回想している。
赤黄男が自らの作品の影響を受け、当時まだ珍しかった女流俳人の篤子を認めた――というか先物買いしたのは自然な成り行きだろう。ただどの創作者もそうだが初発の初々しさは一瞬で過去のものとなり、色褪せる。篤子は彼女なりにより正直な表現を求めてゆくことになる。
海つてすごいやわたしより青いや
魚も 猫も わたしも 子供も こんど鳥となる
足音は金の粉 わたしは胸にちりばめる
ママの目は 小さな藥ビン ゆすれば にがい水が出る
猫の尻尾は 鉛筆けずり 野原でまわせ 野原でまわせ
空から こぼれるネックレス あたしがさわると雨になる
ただ ラの音を ぱんと彈く だんだら縞の鳥がとぶ
何も無いよ ただ無いよ 無いよ 無いよ
「しんしん」と泣く しんしんと 左の耳
あたしぷつんとつぶす ぷつんと殺す
馬鹿ねと書きなさい髪と舌も出しなさい
えらい人のまわりはベタベタします・だからさようなら
赤いピストルほしいよ・赤いピストルほしいよ
あたしの耳はサナギ、あいつのことでいつぱいなの
生まれるまえ、ジュネーブで犬をしたり、モスクワで山羊もしてたの
次は年寄り、次の次に泣くのが あたしの番
(昭和三十二年[一九五七年]~三十五年[六〇年])
篤子二十七歳から三十歳までの作品である。昭和三十六年(一九六一年)に重信と離婚した後は書かなくなったようだ。いずれも伸びやかな表現である。少し悲しくなるが、重信との結婚生活は苦労の多いものだったことがわかる。そういった作者の心の機微がストレートに伝わってくる作品である。しかしこれらの作品は〝俳句〟なのだろうか。
これらの作品が自由詩として提示されているのなら何も問題はない。なぜなら自由詩は思想的にも形式的にも一切の制約がなく、作家が作品を「これは自由詩である」と宣言し、読者が「自由詩である」と認知すれば成立するからだ。観念原理を言えば自由詩は〝新しい世界に対応した新しい書法〟を持っている必要がある。しかしミニマムな要件としては作者の宣言で初歩の詩として成立する。短歌、俳句、小説、評論、戯曲のような表現であっても作家が自由詩だと宣言すればそれは自由詩である。
だが俳句は伝統的形式文学である。自由律や多行俳句の前衛表現だとしても、俳人なら俳句の原理を抑えていなければならない。五七五に季語の俳句定型(俳句形式)を破るからこそ俳句の原理を把握しておかなければならないのである。
わたしはどこから
わたしは
どこから來たのか
誰も知らぬ
でも 野原のオンベも
喘息持ちの井戸のトツシンも
晝でも夜でも わたしに親切です
遠い あなたを想い
燃えあがる悲しみに大きな熊星をつるした時も
あの人達は 大行進をしてくれました
それは
幽霊の軍隊みたいに静かだけれど
みんな
ダブダブズボンだけれども
鳴らぬラッパを吹く頬が キラキラ透いているのが とても
ありがたかつたのです
西のはずれにも
東のはずれにも もうさつきから
シベリヤ風がいつぱいです
わたしも
わたしが どこから來たのか解らぬけれど
でも
いまは あつたかい部屋が
自然に
わたしの爲に子供をつくつてくれました
わたしの爲に
夫をつくつてくれました
西の西のはずれに住むわたしの夫と
東の東のはずれだかに住むあなたと
いつか ふたりがトコトコと行き合つたらば その時は
コツンと夜でも 微かな音が
わたしに きこえるはずです
わたしは どこから來たのかしらない
けれども みんなはついて來るのです
昭和三十一年(一九五六年)、篤子二十六歳の時の自由詩作品である。重信とは結婚三年目だが、奇妙な形で別れの予感が表現されている。ただ俳句でも自由詩でも篤子の表現は素直でストレートだ。少女のような、子供のような純な心を失わなかった人のようである。
しかし子供はいつか大人にならなければならない。俳人なら俳句であらゆることが表現できるという幻想に近い野望に見切りをつけ、俳句の本質とは何か、何を俳句で表現でき、何が表現できないのかを絞り込んでゆかなければならない。詩人なら内容と形式を真摯に考える必要がある。
誰もが表現したい何かを抱えている。形式的制約のない自由詩ならそれを表現しやすい。しかし書く前には無限にあると思っていた表現内容は、二、三作書けばあっさり尽きてしまう。形式的制約がないからこそ、自由詩では独自の形式を生み出すことで詩の表現を更新してゆく必要がある。それができなければ詩集という形で作品はまとまらない。
「わたしはどこから」のような作品に技術的な批評をしても仕方がないが、あえて書けば、息せき切って書き始めたが途中で言葉が失速している。18/10/3/2行とじょじょに行数が減る四ブロックで構成されるが、このフェードアウトは意図したものではない。無意識のうちに、曖昧に観念を逃がしてやろうと空白行が増えている。作品を書いてしまった後に書き方の必然を意識して把握できなければ、プロの詩人にはなれない。フェードアウト詩法を使うなら頭の方はもっと長く、緻密に書く必要がある。でないと虚空に観念が消えてゆくような効果を十全に引き出せない。
重信初期に行動をともにし、公私両面で影響を与えた高柳篤子や加藤元重は、俳句と自由詩の間を行き来したが句集も詩集もまとめられなかった。確かに篤子の伸びやかな表現には一種独特の魅了がある。こういった伸びやかな表現を俳句に取り入れられればいいなと思う人も多いだろう。しかしまず間違いなく無理だ。
俳句である限り篤子的な表現は一過性のものになる。俳句を書き続ければ書き続けるほど、俳句は俳句以外の表現を嫌うようになる。撞着的な言い方になるが、俳句が俳句であるためには作品が俳句に似なければならない。そこを通過して初めて俳人はオリジナリティのある作品を継続的に書けるようになる。
重信は篤子や元重とは違い、大人に、プロの俳人になっていった。彼の周囲には加藤郁乎を始めとする俊英が集い、郁乎を中心に安井浩司、大岡晃司らが同人句誌「Unicorn」を創刊して「俳句評論」に離反する動きまで起こした。重信門では俳人たちの熾烈な戦いが繰り広げられていた。自由詩では大岡信や吉岡実といった現代詩の精鋭が前衛俳句に熱い視線を送り、「俳句評論」にもしばしば参加するようになった。篤子や元重ら初期同伴者たちが重信周辺から振り落とされていったのは必然だろう。文学に対する厳しさのレベルが違いすぎる。
ただ『高柳篤子作品集』や『加藤元重句文集』を読めば、まだ苦労を知らず、向日的な希望に満ちあふれた重信前衛俳句のアルケーをうかがい知ることができる。キャリアのある作家なら遠い昔のこととして忘れてしまっているだろうが、作家なら誰もが今はもう書かなくなってしまった人たちと、幼い議論と虚勢を張りながら過ごした時間を持っているはずだ。
『高柳篤子作品集』や『加藤元重句文集』はどこか懐かしい。作家として出発したからには頂点を極めるような覚悟が必要だろう。しかし作家の一番幸せな時期は作品集などまだ夢の夢で、自分が雑誌に発表した作品の評価に一喜一憂し、他者のささやかな作品に驚き嫉妬した、ドングリの背比べのような幼い青春期にあるのかもしれない。
鶴山裕司
(2019/07/24)
■ 高柳重信の本 ■
■ 金魚屋の本 ■







