No.7で『青年経』特集が組まれて以降、安井氏(以下敬称略)はさっそく第二句集『赤内楽』の創作に取りかかっている。No.8からNo.14に発表された安井の俳句は73句。そのうち約50パーセントの36句が『赤内楽』に収録されている。後年の、まず大量の俳句を書き下ろし、そこから選句するという安井の手法からいえば高い収録率ではなかろうか。
No.8からNo.14で安井は3本の評論を発表している。『落日の断章-または、わが俳句性論議』(No.8)、『類比考』(No.10)、『海程合同詩集』(No.14)である。このうち重要なのは『落日の断章』だろう。安井は方法的作家だが理論が先走ることはない。ある漠然とした予感に導かれて創作を行い、それが後に理論化されている。従って安井の場合、実作を重ねるほどにその理論が明確になっていくのである。処女句集『青年経』刊行後に書かれた『落日の断章』には、安井の理論的思考の深化が見られる。
俳句と私たち俳人は本質的には、化学的に分離される脂と油のようなものである。
これは、俳人個々の精神と、その俳人によって書かれた作品の実体とは、同質の精神風土にありながらもその作品の実体はすでに同時的でなく、独立の詩的価値をもつというたとえである。わかりやすく言えば、俳人と俳句は、本来はもっと自由な要素で絡み合っているというたとえである。
(『落日の断章-または、わが俳句性論議』 『砂』No.8 昭和38年[1963年]9月)
この評論の論旨は同人誌『黒』に発表された、『詩を含めた一切の創造的主体とは、存在論的証明の〈束縛〉に対する〈自由〉である』(『言葉と想像力に於ける抽象俳句の死角について』)という思考を敷衍したものである(『N0.013 『黒』』参照)。
『言葉と想像力に於ける抽象俳句の死角について』で安井は、人間の想像力はあらかじめ言葉によって規定されるが、想像力は言葉の無意識層全てを言語化できているわけではなく、さらなる想像力の駆使(『想像力の覚醒』)によって、新たな表現=『俳句の抽象的高次元化』が可能であると論じていた。それが『落日の断章』では俳人と作品はイコールではなく、作品は俳人の実存を離れた『独立の詩的価値をもつ』という思考にまとめられている。
また作品が俳人の実存を離れた『独立の詩的価値をもつ』のなら、『俳人と俳句は、本来はもっと自由な要素で絡み合』えるという理論が成り立つことになる。ただ安井の言葉と想像力を巡る思考が、人間の想像力は言葉によってあらかじめ規定されているという〝絶望〟を前提とした上での〝希望〟(それでも想像力には言葉の無意識層を言語化できる可能性がある)だったのと同様に、俳人と作品の関係にまったく制約がないわけではない。俳句文学固有の制約が考慮される必要がある。。
私は冒頭に「俳句は、自らを越えようとして止どまる詩である」と書いた。(中略)「止どまる」とは、物体間の諸関係が直観において破られ、超法則が関係の詩に定着したという事を意味するものである。
超法則が定着するまでには、それは一個の詩人の体験にしか過ぎない。
言葉に定着することによって、詩は独自の実体をもち、このときはもはや詩人の体験は消滅し、彼にとって体験の感動は失われるのである。
俳句は、この「体験の感動」を実に失いやすい詩であると思う。
それは、超法則とでもいうべき媒質が言葉に定着しやすい詩型であるという為であろう。なぜなら、数多い言葉の中から、最も少なく言葉を選び、選ばれた言葉それ自体がすでに詩型である、とさえ云っていゝからである。
ことばを換えれば、そのことは俳句が言葉以前において体質的にすでに、関係の詩であるという事を表明してることになる。
(同)
安井は想像力を駆使した直感的超法則が作品=俳句を生み出すのだと論じている。それは『一個の詩人』の特権的とも言える『体験』である。これによって『詩は独自の実体』を持つわけだが、それと同時に詩人の『体験の感動は失われる』。想像力による直感的超法則が言語化されてしまえば、どんなに奇矯な表現だろうと、それは誰もが共有できる作品として相対化(詩人にとっては客体化)されるからである。
また俳句は『超法則とでもいうべき媒質が言葉に定着しやすい詩型』だという特質がある。単語を二つ三つ取り合わせればすぐに俳句はできあがる。それは日本語においては『選ばれた言葉それ自体がすでに詩型である』こと、『俳句が言葉(の選択)以前において体質的にすでに、関係の詩であるという事』を示している。従って俳句で創作の『感動』を維持するのは並大抵ではない。定型によりかかった作句を創造行為と取り違えてしまいがちなのである。
はじめそこに俳句在りき、それに触れるという操作――これは個性の初歩的な発生の形であり、むしろ原始的な本能の発生の形であろう。こゝまでは至極当然な経験であるが、私たちの俳句的個性は、持続された形で現われている、という特殊な個性の形成要因がある。
持続――即ち、経験の連続によって得た体系ではなくて、一回性の巨大な経験によって作者の体質がデフォルメイションを蒙むった場合、それは物質の弾性原理のように原点に還る可能性があるのである。
そのことつまり、歪曲された「有機的体系」は、もはや個性ではなくて「性格」と呼んでいゝものである。
(同)
俳句文学では個人の『経験』の上位に俳句形式という『巨大な経験』があり、それにより唯一無二の「有機的体系」であるはずの作家の個性は変形をこうむる。それはもはや『個性』ではなく『性格』と呼ぶべきものである。安井はハーバート・リードの思想を援用して『性格は自己決定の要素が全くない』と書いている。つまり俳人が闘うべきなのは俳句が作家に強いる『巨大な経験』、すなわち俳句形式そのものである。俳句文学の『原点』は俳句形式(必ずしも五七五定型ではない)にある。
初期の安井の俳句論は用語法や論旨の運び方に無理があり、決してわかりやすくはない。しかしそのオリジナリティは高い。安井は他者の批評的成果を取り入れるのを最少限度に留め、ほぼ独力で思考を推し進めている。それが安井の俳論の完成を遅らせ、また一般読者の理解を阻んだ原因だと言ってよい。
また安井の批評はかなり早い時期から〝原理論〟へと向かっている。俳句界に限らないが、詩壇でも小説文壇でも批評の大半は〝状況論〟である。月単位、年単位で創作や批評の問題点を列挙し、結論をto be continuedで先送りしている。乱暴に言えばそれがジャーナリズムである。ジャーナリズムで仕事をするようになると、たいていの作家はそのような批評を書くことになんの疑問も持たなくなってしまう。
しかし状況論はすぐに色褪せる。短期間に雑誌連載された批評をまとめた本は、時間を経て読み返すと呆れるほど何も書かれていない紙の束だ。せいぜい当時の微細な〝状況〟を知るための参考資料にしかならない。しかし日々のジャーナルと無縁の場所で書かれた原理論は古びない。安井はある時期からジャーナリズムとは距離を置いた。あるいはジャーナリズムから疎外されていった。その理由は安井の原理論的指向にもあったと言うことができるだろう。
鶴山裕司
■『砂』No.8 昭和38年(1963年)9月5日発行■

【評論】
落日の断章-または、わが俳句性論議 安井浩司
俳句は、内から自らを越えようとして、そこに止どまる詩である。
越えようとして、そこに止どまるものは、外へ越えてしまうものより悲劇的でさえある。
自らに止どまり得ずに、越えてしまったものには、もはやそれを俳句と呼び、落日の栄光を与えることは出来ない。それらは、自由詩の一様式といわれてもいゝもので、何々律とか俳詩とか呼ばれるたぐいのものである。それらは、読者と作家との関係のように、俳句と共に瞬時的には感応し得ても、持続的には感応し得ない類であり、同性の名称と同性の詩論を与えることは出来ぬものである。
俳句は、文芸のあらゆるジャンルで(正に同性称を与えることは出来ぬ、といま述べたように)堅牢であり、ニヒルの容貌ともち、かくも特異であると言っていゝだろう。
俳句と私たち俳人は本質的には、化学的に分離される脂と油のようなものである。
これは、俳人個々の精神と、その俳人によって書かれた作品の実体とは、同質の精神風土にありながらもその作品の実体はすでに同時的でなく、独立の詩的価値をもつというたとえである。わかりやすく言えば、俳人と俳句は、本来はもっと自由な要素で絡み合っているというたとえである。
それでも私たちは、堅牢な形式に魅せられ、拒絶の精神にかくも偏執しているということは、それなりの因子が、俳句側にも、俳人側にもあると云わねばならない。
堀葦男氏は、この間の事情に、幾つかの例を挙げて有機的に述べている(海程二号「現代俳句講座」参照)。それには、「俳句を選ぶ理由」に答えて、短詩型と定型を求める親和的な体質を主なる因子として、それに関わりある要素を幾つか挙げている。
この事は、俳句を求める体質をそなえた俳人の個性に関する評言が少ない今日、貴重な参考意見であったように思う。
私は、そのような体質をそなえた俳人の個性が、持続されることによって、初めて成熟された個性を獲るものであると思っている。持続されることがなければ、それは単に体質にしか過ぎないからである。
「成熟がすべてだ」とはよく云いおうせた言葉であるが、いま私は、俳句の特性とでもいうべき短身の内部関係の前提をまず求め、更に成熟された個性に接近することによって、この断章を少しひろげてみたいと思う。
(俳句における特性は俳句性である――という言葉に食傷気味な私に、しかも充たされないまゝその言葉はいつも新鮮である。特性――いわば俳句であろうとする堅固な理由は、あらゆる俳論の前提である)
俳句をふくめて言葉の芸術は、いつも受け取られる場におかれることによってのみ、受動的に成りたっている。
私たち俳人の実感は、言葉に定着することによって俳句となり、かくも受動的に俳人と分離されて、その作品だけがもつ「独自の実体」が形成されてしまうのである。
そして、俳句における独自の実体の形式のされ方は、概して法則的である。と云っていゝのではなかろうか。法則的――いささかの危惧をもつ表現だが――その典型的な例として、かつての山口誓子の根源俳句における内面形成の法則性などは、このさいたるものであると言っていいだろう。
エリオットによれば、詩人とは白河の関のようなもので、詩とは単にそのような関所(媒体)を通過したものにすぎないと言っている。
俳句がその表現される実体を、概して法則的に作るという意味は、いわゆる俳人媒体の湿潤な完成が定型感覚によって飼いならされているという事が一つと、俳句は法則性を語るにふさわしい詩であるという事の二つの意味がある。
いま、俳句らしき言語群が俳句完体となるために、私たちの気を引く点は、後者即ち「法則を語るにふさわしい詩」ということではなかろうか。
しかし、法則を語るにふさわしい詩とは、実は何らか特例をもって存在しているわけではない。
ヴァレリイは、「レオナルド・ダ・ヴィンチの方法序説」という文中ですべての詩は関係(法則)を語るにふさわしい資格をもっている、と云っている。
詩において法則は、直観において語られるものである。
だがこゝでさらに言葉を加えれば俳句は、むしろ直観において破るのがふさわしい詩型である、と言いたくなってくる。
法則を破ることによって詩を語るとは、ベルグソンの言葉にもみられる「物体の偶然性を排除することによって関係づけられること」の意味にも近い。それは「超法則」とてもいうべき体系であり、その超法則こそ、直観において破ったところに得られ、詩人だけが味わう体験であろう。
こゝで私は、左記に拙著「青年経」跋文において、師永田耕衣に「超関係的関係」という啓示を受けたことに、限りない感謝の念をもつものであるが――。
俳句は、空間関係のゆきとどいた関係の詩である。
私は冒頭に「俳句は、自らを越えようとして止どまる詩である」と書いた。これはやや漫然とした云い方だったが、「止どまる」とは、物体間の諸関係が直観において破られ、超法則が関係の詩に定着したという事を意味するものである。
超法則が定着するまでには、それは一個の詩人の体験にしか過ぎない。
言葉に定着することによって、詩は独自の実体をもち、このときはもはや詩人の体験は消滅し、彼にとって体験の感動は失われるのである。
俳句は、この「体験の感動」を実に失いやすい詩であると思う。
それは、超法則とでもいうべき媒質が言葉に定着しやすい詩型であるという為であろう。なぜなら、数多い言葉の中から、最も少なく言葉を選び、選ばれた言葉それ自体がすでに詩型である、とさえ云っていゝからである。
ことばを換えれば、そのことは俳句が言葉以前において体質的にすでに、関係の詩であるという事を表明してることになる。
しかしこのような事は、至極あたりまえの事柄のような気もする。
私はいま、俳句においてポエム(書かれるべき詩)と媒質の射程距離が短いという事、つまり超法則的体系が比較的「肉体の詩としての俳句」に定着しやすいという事をのべた。
だがこのことは、何かアフォリズムのようなものの焼成過程と、比較的類似していることに気がつくものであるが、しかし例外はあっても、常に俳句をめざして完遂されるという事は、初章で触れたように俳人の個性――この成熟された個性を私は密室で俳句的個性と呼んでいるが――によってなされるからに他ならない。
(即ち俳人の個性は、俳人個々における俳句性であると考えていゝだろう。だが実際、関係の詩を関係づける個性とはどんなものだろうか)
俳句は、内から自らを越えようとして止どまる詩である。
そして、超法則的媒質が比較的「関係の詩としての俳句」に定着しやすいという特性をもっている。
この事は、見方によっては俳人の個性を閉め出しているようにも思える。それは、おびただしい類型感覚が氾濫し「独特な面白い作品」が少ない今日の事情を物語っているように思える。
個性は、その俳人個々においてすでに独自のものである。従って多くを語ることは出来ないが、いま一つの例をもって考えてみよう。
芭蕉奥の細道の有名句
荒海や佐渡に横たふ天の川
この句の原点は〈佐渡〉である。すでに創られたものに逆論法で云うと、〈佐渡〉がなぜ〈佐渡〉でなくてはいけないか、それを決定するのが芭蕉個人の個性であったのである。
芭蕉の個性によって強引に据えられた〈佐渡〉は、今もって私たちの(俳句的)個性の受容器にひゞくが、ボードレールが云った万物交感の趣きも、このような個性の存在論的信念に触発されて――つまりもっと物質的に強引になることによって――交感の趣きをもつものと云えよう。〈佐渡〉における交感の趣きは素晴らしい。
私はこの句など、物質間の超関係を「場」において簡明に描かれていると思い、さらに偶性の諸関係が必然性にまで昂められた典型作だと思うが、芭蕉における〈佐渡〉のこの必然性こそ、彼の〈俳句的〉個性によって選ばれ、言葉として運命づけられたものであると思う。
私は更に、「個性」そのものについて触れてみなければならなくなった。
ハーバート・リートは、「詩人の個性」(御與氏訳南雲堂刊)と題する評論の中で、
「個性の現実性、その活動力は(注・創作する力という意味)、自己が存続するという信念に依存するということ、その信念は、客観的証拠に支持を見いだすことは少ないが、生きる意志である――存在論的信念へ未来の洞察、経験の連続性にたいする信念によって可能となる」
とのべている。このことを要約すれば、
①個性は自律的であること。
②個性は経験の連続の上に立っている。
③それらは歪曲のきかない存在論的信念のようなものだ。
ということになる。
リートのいう個性は
「あらゆる個人のなかには、精神過程の一貫した有機的体系があって、われわれはそれを個人のエゴと名づける」
というフロイトの言葉を背景としているものである。
これらの言葉を前提として、作家側における俳句性――つまり成熟された俳句的個性とは、経験の連続によってつちかわれて来た超経験的な有機媒体である。フロイトのいう「一貫した有機的体系」によって、もはやいずれにも変形出来ない超経験的な存在論的信念であるということにもなる。
はじめそこに俳句在りき、それに触れるという操作――これは個性の初歩的な発生の形であり、むしろ原始的な本能の発生の形であろう。こゝまでは至極当然な経験であるが、私たちの俳句的個性は、持続された形で現われている、という特殊な個性の形成要因がある。
持続――即ち、経験の連続によって得た体系ではなくて、一回性の巨大な経験によって作者の体質がデフォルメイションを蒙むった場合、それは物質の弾性原理のように原点に還る可能性があるのである。
そのことつまり、歪曲された「有機的体系」は、もはや個性ではなくて「性格」と呼んでいゝものである。
俳人の、俳句における連続の経験は、もはや暴力をもって歪曲することの出来ぬ成熟された個性であり、それを私は俳句的個性と呼んでいる。
リートの評文にも見られる所だが、個性と性格は明確に分けられるべきだとして、性格は自己決定の要素が全くないとしている。
先にも述べたように、これが俳句とアフォリズムの、作者側の有機的体系を透かしてみた相違点である。つまりアフォリズムは反性とでもいうべきアイロニックな性格のうえに成立し、俳句はもはや反性と呼べぬ岩質な個性のうえに成立するものである、と云えるだろう。
俳句を選び、更に俳句の言葉を選ぶことは、己れの有機的体系を認識しようとする意志(未来の洞察でもある)であることは明らかとなった。(更に気の強い人は、関係詩に関係づけられる言語群こそ、俳句的個性を介することによって、思惟の完全抽象から、超経験的に存在論的に物質的に卑俗的に俳句に完遂されていくことを知るだろう)
すべて俳句的個性の恐るべき裁断力である。
私はそこそろ結びに迫られてきた。これはもっぱら断章のつもりで結論など考えずに書いてきたが、それでは無責任の感はまぬがれない。
以上のべたことを要約してみたい。
◎俳句という堅牢な形式に私たちがかくも偏執しているという因子は、俳句側の誘因と俳人側の素因にある、ということから、わが俳句性論議ははじまり、
◎俳句は関係の詩であって超法則的媒質は比較的言葉に定着しやすい詩型である。そのため作者の個性を見失いがちである。
◎だが俳句は、俳人の成熟された個性即ち俳句的個性を介することによって書かれたものである、ということであり、
◎しかし俳句的個性とは一回性の発現でなく、俳句を書く連続の経験の上に得る超経験的なもので、いかなる歪曲も効かぬもの、ということである。
◎更につけ加えれば、俳句と俳人の関係は以上のようなものであり、俳句がポエム(書かれた詩)であって且つ俳句であるために、どのような認識が必要かという素朴な論議をくり返しつゝ、私の持続的な信念の思いを表わして野孤禅の彼に捧げたつもりである。という事ぐらいになるだろう。
-完-
【作品】
茂林寺輪講(四) 安井浩司
父に勃ついま縞蛇で緊める寺
白の鳥列わたる採石工場の鏡 (②『赤内楽』)
硅肺や葦の方へと押される地蔵
こがねの箒振らん死鼠多き野に (②『赤内楽』)*1
弟産れ土筆の頭が狂い立つ
母へかの青蛇すすむ紐の神 (②『赤内楽』)
夜の潟の白帆繋がり産室の岩 (②『赤内楽』)
【註】
* 句の後に収録句集名と章を表記してある。数字①、②…は第1句集、第2句集…の略。
*1 定稿では『死鼠』に『しそ』のルビ。
■『砂』No.9 昭和38年(1963年)11月5日発行■

【作品】
崖の寺 特別作品 安井浩司
旅の絵本にとびでた誘蛾灯迅し
誘蛾灯ほど小さい頭で旅ゆく横町
青胡桃母透くまでの太鼓打つ (②『赤内楽』)
鐘ひびく地平の母へ紙着せん (②『赤内楽』)
道標へ曲りをつける種馬曲げて
剃刀ひかる林に倭人笑いちらす (②『赤内楽』)
吾児に白い耳たつ夜の灰神楽
九階この異な林ゆき鷹放つ
菩提寺へ母がほうらば蟇裂けん (②『赤内楽』)
青葦が鼻から吹きでる母との夜 (②『赤内楽』)
吹雪林わが産室の岩吠えて (②『赤内楽』)
水に鳥消される崖上の混声団 (②『赤内楽』)
春の城を縞蛇ころげ落ちる祖父 (②『赤内楽』)
崖の寺背おい来るわが青筵
菩提樹や垂れる足裏に湾を見て (②『赤内楽』)*1
鐘落ちきれぬ地平へ向う紙問屋 (②『赤内楽』)
紐にかかった鴉を喰べて午睡の木
屋根裏に麦刈る兄弟艦湧いて
墓にそそぐ春雪ふいに加留多取り (②『赤内楽』)
メーデーの山頂の椅子もたれる魚 (②『赤内楽』)
【註】
* 句の後に収録句集名と章を表記してある。数字①、②…は第1句集、第2句集…の略。
*1 定稿では『足裏』に『あうら』のルビ。
■『砂』No.10 昭和39年(1964年)1月5日発行■
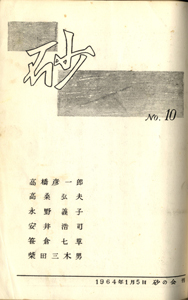
【評論】
類比考 安井浩司
俳句は短い!生来短身型というやつは、内部構造などを、やはりメカニックに複雑怪奇にしているらしい。そして、アナロヂイ(類比)による言葉同志の相乗関係の文体は、こんな複雑な機構から美しい緊張をつくって、存在と形式の見事な調和感を醸成している。せっかちなレトリシアンには用無しとばかりに、言葉の核だけで相乗効果と類感作用を一挙に図ろうというわけだ。このようにアナロヂイは、ナチュラルに合理的に、俳句においてこよなく愛されている。俳句はアナロヂイの詩だろうとは私たちドグマテストの物草だが、この辺で制動装置を引いておくのもいゝかも知れない。
詳しいことは知らないが、アナロヂイは、プラトンの思弁学の方法として初めて原典に記された言葉だったと思う。今日において、この類比analogyは、多様な意味の岐れをもって独立している。たとえばhomology(相同)という言葉に対立的資格を与えて、この二者が好んで使用されたり、プラトン的飛沫をあびて幾何学の抽象表現として遊ばれている。
私たちの俳句においてもこのアナロヂイは異った観念の映像群を交錯させたり、観念連合とはアウフレーベンに外ならない、と云ったような〝ウマイ〟了解を約束させてくれたりする。さらに見方をかえれば、俳句が短歌的抒情を拒絶するのに実に役立っているのだ。言葉のアナロヂカルな関係は俳句において見事にアンチロマンの形態を準備する。俳句は形式に厳しい詩であると共に、アナロヂイを愛する詩人こそ俳句を選ぶものだ、とこの辺で放言する効果も忘れないでおこう。
プラトンによれば、ヂアレクテイケイのいわゆる弁証法運動は、この類比(アナロヂイ)の原理による振子運動によって一挙に解決をはかろうとしている。
すべての人間は死ぬものである。
しかるにソクラテスは人間である。
ゆえにソクラテスは死ぬものである。
これは有名なアリストテレスの三段論法の例であるが、この対話体のアナロヂカルな思弁において、アナロヂイは、プラトン的な哲学原理から〈感性〉〈直観〉〈詭弁〉を加えて近代文明のアレゴリイの成立へと急ぎたがる。いまこゝで、ギリシャ哲学の方法なんぞ紐解こうとしているものではないが、私たちの賞味するアナロヂイが、思弁学上の主役を演じた時期があって、多くの原罪を負ったことも確かのようである。例えば、〈假説〉なんか最も純粋に近しくて永遠に遠い詩にしか過ぎまい、といったようなアフォリズムを生みだそうとしているのも、アナロヂイを愛する詩人の誠実さのためではなかったか。
高等学校教学書にもおなじみの、あのアキレスと亀の詭弁も、こんな意味で詩人を襲撃する迫力だけは持っていた。たとえば「万能の人」ヴァレリイは、かく絶叫したのは周知の通りである。
ゼノン!酷薄なゼノン!エレアのゼノンよ!この翼ある征矢でお前は私を射抜いたのか 矢は震えて、翔び、また翔ぶこともない!
(菱山修三訳)
著名な「海辺の墓地」の歴史的な一節であり、こゝには生命と純粋思考の相克が悲惨に叫ばれているものである。この四詭弁の考察は、生好みの説学者曰(いわ)く「躍動と純粋持続の直感的認識」にまかしておいて、私たちはもっぱら詭弁と仮説に隠蔽された悪魔的アナロヂイを了解し楽しむだけでいい。
薔薇 おお 純粋な矛盾 よろこびよ!
ある日、リルケの冷徹な眼は、物質の向うに存在と観念の見事な調和感を見ている。物質の内面に投影される思考と、その思考の流れる移動性は、詭弁はたとえ死んでも、類比操作をもって假説を残しまたその逆説を残して、現実性とか科学性とかいう言葉をもって掃き出すことのできない側面をもってしまった。
病雁の夜寒に落ちて旅寝かな 芭蕉
アナロヂイ談義も意外なところへ曲ってしまったが、つまりアナロヂイは、私たちの俳句の発想における基礎的認識のための具体的方法であって、それは先ず第一に言葉を用いなければならないからである。今こそアナロヂイは、その本来の思弁的方法を脱して、発想の原発的把握方法となってしまった。それらはもはや、物質間の類推とか、物質の特性を交換する方法とかといった意味ではない。それは、深く交感することであり、大げさに云えば発想の姿勢に働きかける創造的な一要素であると思う。私は、見事なアナロヂイのその調和感をみる一句として、右の芭蕉の作品が好きだ。アナロヂイは今日、その方法として二者衝突、異物衝突とかモダンにいわれているが、だがアナロヂイは本来発想における方法なのであり、芭蕉の句にもみられるように、そこには〈類比〉とか〈類推〉という概念はもはや無くなるものとみなければならない。感性の世界まで落ちた美しい関係が要求され、言葉と言葉に深い交感能力を呼びおこす方法といわれねばならない。
私は、現代俳句における琑末リアリズムの発想とその私小説風を忘れたい一興のために以上のことをアナロヂイに思いを寄せてみた。
【作品】
卍(まんじ) 安井浩司
木曜過ぎ黒枠の中に蟹闘う (②『赤内楽』)
爆死いま扉へつれだつ豆袋 (②『赤内楽』)
神の絲みみず紙の父を飼いならす
楡一身胎盤へ鵙遂げられず (②『赤内楽』)*1
火事跡の蓋(ふた)二人はらからの笑い (②『赤内楽』)*2
十字路に肉賭けて吹く風車
遠い母艦ふと球根に鶏乗ったり (②『赤内楽』)
夜陰にがばり共存を見る縞蛇
旋盤より低く過ぎつゝ遠野の者
ふるさとに黄な粉降る夜の母狂う
【註】
* 句の後に収録句集名と章を表記してある。数字①、②…は第1句集、第2句集…の略。
*1 定稿では『胎盤へ』は『胎盤への』。
*2 定稿では『火事跡の』は『火事跡へ』。
■『砂』No.11 昭和39年(1964年)3月5日発行■

【作品】
卍(まんじ)(二) 安井浩司
餅はこぶ虜囚船いま沖に糞す (②『赤内楽』)
末黒野を斜め斜めに誰かの父へ (②『赤内楽』)
草の葉の皿に眠る智歯のひとり
遠椅子に頭を置き蜜柑林過ぎつ
十字へ遂げる露の蛇この両端よ (②『赤内楽』)*1
十月垂らし競技場あゝ茸を殺す
林間鵜を忘れ埋めこむ斧一丁 (②『赤内楽』)*鵜→鴉
菩提樹や虜囚へ乗ったり笑い馬 (②『赤内楽』)
溺愛の便所を鎮めて楡の辺に (②『赤内楽』)
仏の腋を短く過ぎさる混成団
暗緑の産室時計を昇る父よ
肉いろの海土筆の反りの一絵本
餅の中ゆび熟すふと遠きいもり (②『赤内楽』)
蛇捲きしめる棒の滴り沖の火事 (②『赤内楽』)
【註】
* 句の後に収録句集名と章を表記してある。数字①、②…は第1句集、第2句集…の略。
*1 定稿では『十字へ』は『十字に』。
■『砂』No.12 昭和40年(1965年)3月15日発行■
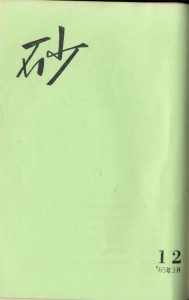
【作品】
卍(まんじ)(三) 安井浩司
氷山を痛みゆき内身に 熊が立つ
遠の岩へゆきしか苺い 馬齢おき
神連れて捺印もみけす 草の扉
青絵かの夜の出水を 蛇でまつ (②『赤内楽』)*1
近島哭くまま産衣より 狼はがす (②『赤内楽』)*1
ふとんに薬を泛かべおく朝の遠釣り
いちぢくへ二人の智歯の縊死おわる
両岸より夜ごと寄せくる苺籠
【註】
* 句の後に収録句集名と章を表記してある。数字①、②…は第1句集、第2句集…の略。
*1 定稿では一字アキなし。
■『砂』No.13 昭和40年(1965年)6月10日発行■

【作品】
卍(まんじ)(四) 安井浩司
雁の死へ加留多も遂げたり筵の上 (②『赤内楽』)*1
少年の翳の猟と地面喰う
彼の傘に鳥込めし日の突起いま (②『赤内楽』)
ちよ紙の陰唇を焚く白昼の坂
父娘となり逢う砂に疎林生えて
血をあげて白鳥ふり変わる番傘が (②『赤内楽』)*2
沼にでる赤黒の月手招かれて (②『赤内楽』)
雌馬が神ののこぎり沼を超え
花市や米いちめんに尿の乳母車
父を殺しに雑草をゆく快便の父
【註】
* 句の後に収録句集名と章を表記してある。数字①、②…は第1句集、第2句集…の略。
*1 定稿では「雁の死へ」は「雁わたる」。
*2 定稿では「番傘が」は「番傘に」。
■『砂』No.14 昭和40年(1965年)9月20日発行■

【作品】
卍(まんじ)(五) 安井浩司
跡をゆき霊柩車の吊るカレンダア (②『赤内楽』)*1
皿まわす中心の父ゆく救命船
毒茸握るてのひらに茄子緊められ
【註】
* 句の後に収録句集名と章を表記してある。数字①、②…は第1句集、第2句集…の略。
*1 定稿では「霊柩車の」は「霊柩車に」。
【評論】
海程合同詩集 安井浩司
これは海程作家一三〇数氏による作品集である。
現代俳句の一グループがこれほどの同人を擁しているという事は驚異的であり、私たち数名による同人誌「砂」を営む存在にとっては奇蹟的な人容でさえあろうか。山本健吉氏のいうような〈俳句連衆の存在〉はいまもっていえいえいと続いているのだろうか。もはや現代俳句において、かような連衆の共鳴物的イメージを本気で信ずることは出来ない私にとって、この作品集の前門において、先ずある種の戸惑いを覚えたのであった。
現代俳句に、かりに総体というアウトイメージが在り、それが実感として読者の裡に捉えることが出来れば、現代俳句は一応安定期を迎えたといっていいだろうか。このたびの海程合同句集は、現代俳句の総体に近い決算書の匂いがしないでもない。その着実な努力と歩み、という点でまことにおめでたい〈スーベニール〉であろう。だが、総体とは何か。いっぱしの文学者ならそれをオバケというかもしれぬ。文学の着実な歩みは、着実な類型をも創っていく。読者が、現代俳句の総体にまつわるある種の安定感を体得しながらこの作品集を読み了えてしまったとすれば、それは着実な類型を読み始めていたかもしれないのである。正直なところ私自身、幾ばくの胸さわぎを覚えることもなくこの作品集を楽しんだのであった。
無神の旅あかつき岬をマッチで燃し 兜 太
枕ひとつの流れの中に夜を迎える 紀音夫
現代俳句の奇怪な安定期とでもいうべき頃合いと象徴するように、この金子、林田両氏の既成作家が集中とりわけ目立つ。(そうだ、現代俳句はとてつもない安定期を迎えてしまったらしい。左様、この俳界に不安の遊撃手を試みようとする何人の新種たちが居るのか)
海程は、この両氏先輩に続く新人登場といった場面を楽しみに私が読んだのは当然である。だが、この金子、林田両巨峰は彼らの集団存在の中にあって、なかなか崩れどうもない印象を蒙ったのであった。
ありきたりの願望をもってしては、もはや俳句において第三存在は絶対に起きないのかもしれぬ。あるいは来るべき次代こそ、永遠に来ない世代ではなかろうか――という俳句土壌に同世代不毛と清潔感を同時にもつ私にとっては、私達以前の俳句作家へ組し、啓示などを仰ぐ事は実に不可解な事に思えてならない。
横道にそれるが、たとえばかつて唱えられた戦後俳句が形象造形の道を歩みはじめたとしても、それは造形の手を識っただけにすぎず、俳句表現論は「時」を得て「言葉」の中に確立されたなどとは申されない。
この作品集にはある種のイマジズムとでもいうべきイメージ偏重の詠い方が多いことを、どう解したらよいのか私はよくわからぬ。それは、正に好んでいう〈語る主体〉が、自意識とイメージ、すなわち障子と襖のサンドウイッチ的圧死のように思えるのだ。イメージを追いかけてみた韻律詩がどんなに手強いか。たとえば、序文中に金子氏が「俳句は韻律詩である」とのべたあとで「イメージが形象であるがゆえに、韻律と相反の関係にある」などといっている。だがこのような断定は(だいぶ老人に喜ばれる発言のように見えるが)現代俳句の未熟な表現において、この種のイマジズム過剰性を逆証明したことになるのではないか、とさえ思えてくる。むしろ〈イメージが韻律と調和の関係にある〉という措定において、定型詩の存在理由のひとつがあるのではないだろうか。それを妙に殺気立つことによって、現代俳句のイメージ荷重負担という甘い病気を過剰に産み放っているのだ。イメージ、それは想像力だけで済ますことが出来る代物でなければならない。本来は。
さて、お話は短く止めて、新作家より次のような作品を抽くとしよう。
重い瞼の海割って来る炭住少女 三佐夫
暗夜帰航の友とザボンの深部啖う 三 郎
いもうとの戸口過ぐテノールの黒人兵 弘 司
僕の余白残し骨壺並べ替え 弘 夫
扉に垂れるきらめく父の血綾取糸 伸 一
母の遠さの丘急がねば紙となる
子へ残す沃土蛇刺す幾重にも
突然に下駄箱を動かし愛の恐怖 隆 夫
飼育所にて男を擁す固き樹木
誰か射つ予感に白いハンカチたまる 秀 子
寝棺たなびくかの夕焼にめぐりあう 尚 志
四散の鳥をまなこに降らす伐採音 緑 郎
白髪を刈るヒロシマのまぶしい空
一般に海程がもつ正統ぶりの妙に安心した作品群のうちで、正統と異端(こんな実体なんぞ無いのだが)を同時に発想したような仲上隆夫氏の作品が集中、特に私を曳いた。氏の文体はまこと稚拙の匂いがする。だが、語るべき主体が、語られた〈言語主体〉にけんめいに超越されようとしている兆しを見逃すわけにいかなかった。
海程若人のややおとなしすぎた作品集、最後に〈装幀〉が良かったなどと付け加えておきたい。
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■
