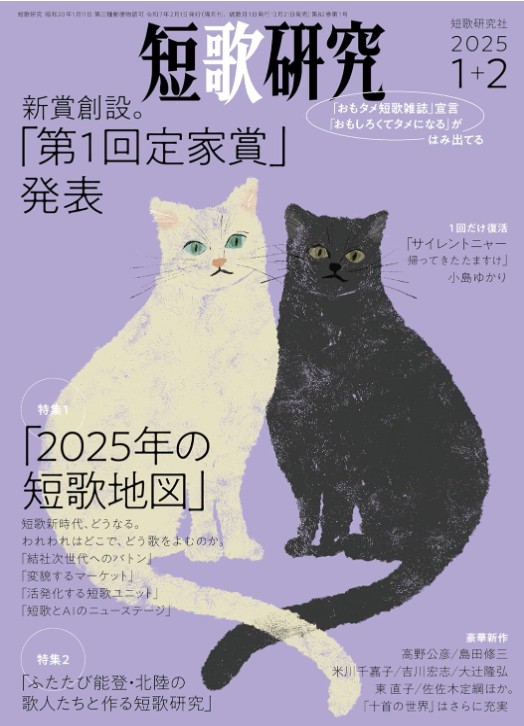
短歌研究社さんが新たに創設した「定家賞」の発表号です。「作者の第二歌集以降の作品」という規定で新人賞ではなく実績ある歌人に与えられる賞です。「定家賞」という賞の名前から言って当然でしょうね。楠誓英さんの『薄明穹』が受賞なさいました。
受賞者の楠さんも書いておられますが「定家賞」という看板はちょっと重い。柿本人麻呂や紀貫之も歌聖と呼ばれていますが藤原定家はやはり特別です。王朝和歌の掉尾を飾った大歌人であり誰もが知っている『小倉百人一首』の元になった『百人秀歌』を撰んだ人ですから。数ある賞の一つとはいえ〝定家に比肩せよ〟と言われているような気がしてしまうでしょうね。
とはいえ楠さんの『薄明穹』は優れた歌集です。『薄明穹』は『青昏抄』『禽眼圖』に次ぐ三冊目の歌集。短歌現代新人賞を始めとしてすでに数々の賞を受賞しておられます。一九八三年生まれとありますから今年で四十二歲。神戸生まれで仏教はもちろん茶道や華道・書道にもお詳しいようです。
名も顔もみな忘れはて草のなか茶碗のかけらも墓標となれり
うすく濃くかげの重なる林にて樹になる前の亡兄にあひたり
まなうらの兄の姿もくづれゆく魚鱗の雲ひとり見てゐる
楠誓英『薄明穹』三十首抄より
楠さんは一九九五年に起こった阪神・淡路大震災でお兄さんを亡くされたようです。引用は亡兄を詠んだ歌です。時間が経つにつれて死者の記憶が薄れてゆくことをその後ろ姿を見送るように淡々と表現しています。痛切な追悼歌ではありません。冷たいというより冷えている。
足もとに影を集めて立ちつくす昏き歩哨と夏の木立は
いつからが死後なのだらう滝壺にまはりつづけるボールのありて
転生をするならビルにはりついて踏まるることなき非常階段
空港まで海底を這ふ電線に夜ごとあつまる死んだ水夫よ
暗渠になる寸前のくらききらめきよ臨終のひとのまなこにも似て
同
楠さんにとって死がとても重要な主題であることがわかる歌です。「夏の木立」にも「海底を這ふ電線」にも死者が集まってくる。『死者たちの群がる風景』(入沢康夫)といったところでしょうか。冷えた視線の作家ですからもちろん死への恐怖は表現されません。「非常階段」は「時々はあの世へ行くのに使はれて非常階段に花蕊たまる」とも表現されるので自死と転生の象徴のようです。では転生はどうやって起こるのか。「いつからが死後なのだらう滝壺にまはりつづけるボールのありて」となる。死も転生も熱もなく起こり繰り返されると捉えられているようです。
真っ白な梯子は空に沈みゆくプールの面に流れゆく雲
屋上に鳩舎もちたし紺瑠璃の空にふれたる白鳩あつめ
同
こういった痴呆的ともいえるような歌が楠さんの一番の秀歌かもしれません。もちろん技巧的には完成されています。もっと言えば完成され過ぎている。スタイリッシュ過ぎると言ってもいいかもしれません。あまりにも完成度の高い歌はどこかいぶかしい。
選評「生の中の死、死の中の生」で穂村弘さんは「思えば、有限の宿命を与えられた人間にとっての必然的な希求という意味では、葛原妙子のアプローチなども驚くほどワンパターンだった。その作品世界では短歌という詩型の機能が極度に限定されている。実存を懸けた人間の必死の問いかけを造物主はスルーし続ける。だから、何度もでも繰り返さざるを得ないのだろう」と書いておられます。
楠さんが歌で人間の生死を巡る「必死の問いかけ」を表現しているのかどうかは別にして歌が「ワンパターン」に感じられる面があるのは確かだと思います。もっと正確に言うとスタイリッシュ過ぎる。ダンディ過ぎるということになるでしょうか。俗な言い方をすれば隙がなさ過ぎていぶかしいということです。
暗闇の深きところに手をのばすそれが一枚のドアでなくても
同
恐らく秘密のドアが開かれることはないのでしょうね。しかし暗闇の深いところに手を伸ばしそれを捉えたいという欲求はある。
技術的に非常に完成されていて内容表現も文句のつけようのない作品は素晴らしいのですが危うい。作者はそれまでに築き上げた作品世界が壊れることを恐れます。維持しようとすれば自己模倣に陥りがち。壊すには大きな決断が必要。自分が納得できる別の書き方を見出す必要があります。
とはいえ楠さんの『薄明穹』はこの歌集に賞を与えなければどうするというくらい優れた歌集です。願わくば大胆に崩れを見せてほしいものです。そうすればさらに多くの読者を獲得できると思います。
鶴山裕司
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


