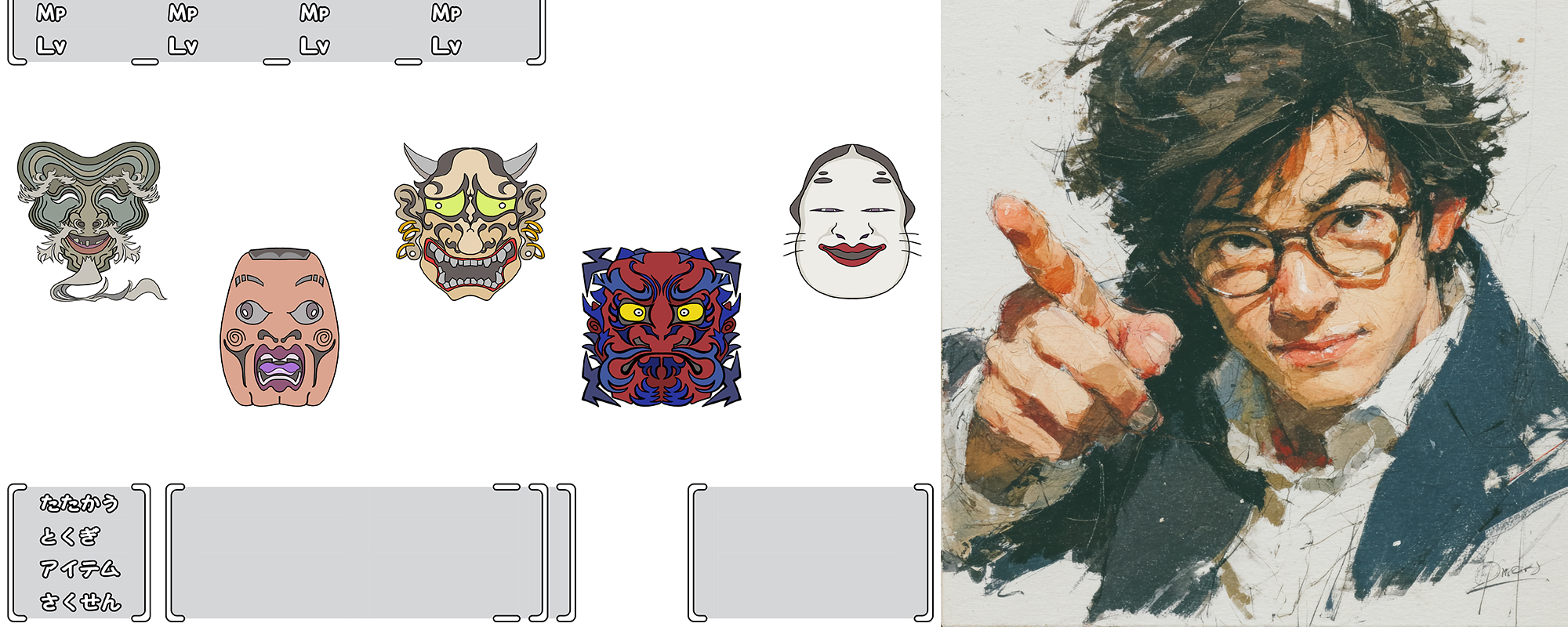
ルーマニア出身の能の研究者、ラモーナ・ツァラヌさんが「文学金魚」に綴るエッセイは、日本の伝統芸能を愛おしく、でもどこか新鮮な視線で捉えた、なんとも魅力的な文章なんだよ。能や人形浄瑠璃を、ただの学術の対象じゃなく、感情や記憶がキラキラと響き合う生きた文化として描き出すその手腕、ほんと素敵だよね。今回は彼女のエッセイから、ルーマニアの感性が日本の芸能文化とどう共鳴するのか、彼女自身の心の動きや、最近は夢中で日本語で小説を書いているという情熱について、ちょっと想像を張り巡らせてみたい。
ラモーナさんのエッセイに触れると、まず心を奪われるのは、彼女の日本の伝統芸能への深い愛と熱い思いなんだ。たとえば、『羽衣』のエッセイでは、天女の舞が放つ神秘的な魅力や、時間を超えた美しさを、ルーマニアの民話や神話とそっと重ねて語ってくれる。この視点、すごく面白いよね。彼女はルーマニアの文化、つまり物語や詩的な想像力が息づく土壌から、日本の芸能を新たな光で見つめ直してるんだ。能の舞台を、ただの演技の場じゃなく、宇宙の調和や人の心の奥を映す場所として感じ取ってる。ルーマニアの感性が持つ、ちょっと夢見がちな詩の心が、日本の繊細な美意識と手をつないでるみたいで、素敵だよ。
『小町風伝』のエッセイでは、演戯団コリペの公演を通じて、悲しみや喜びが国境を越えて観客の心に響く瞬間を、生き生きと描いてくれるんだ。ここには、ルーマニアから日本に移った彼女自身の経験が、そっと影を落としてる気がするよ。異なる文化の中で生きる彼女にとって、芸能は異文化をつなぐ魔法の架け橋であり、同時に自分の心と向き合う大切な時間なんだろうね。彼女の文章には、異文化を理解しようとする真剣さと、自分の気持ちを素直に見つめる優しさがある。ルーマニアの情熱的で内省的な感性と、日本の芸能が持つ繊細な感情の表現が、ピタッと重なり合ってるんだよね。
人形浄瑠璃の『近江源氏先陣館』や『日高川入相花王』を扱ったエッセイでは、登場人物の激しい感情の波に目を輝かせながら、その力強い表現を心から称賛してるよ。彼女は、登場人物の情念が観客の心にグッと迫る瞬間を、まるで自分がその場にいるかのように鮮やかに綴ってくれる。この感情への鋭い感性、実は彼女が小説に夢中になってる理由をチラッと教えてくれるんだ。ルーマニアの文学や文化には、人の心の奥をじっくり掘り下げる伝統があるから、彼女の小説への情熱もそこに根っこがあるのかもね。日本の芸能が持つ豊かな感情の表現は、彼女にとって新しい創作の火花を散らして、もっと深い感性を引き出してるんじゃないかな。
『綾鼓』のエッセイでは、能の復曲や改作がどんな意味を持つのか、伝統と現代がどう溶け合うのかを、丁寧に考えてくれてる。古典芸能が現代の私たちにどう響くのか、その中にどんな普遍的な人間の物語があるのかを見つける彼女の視点は、研究者を超えて、物語を紡ぐ人の心を感じさせるよ。小説を書くことは彼女にとって、異なる文化や時代をつなぐ物語を創る喜びそのもの。能や浄瑠璃を分析する中で磨かれた鋭い洞察力が、彼女の小説にどんな輝きを添えるのか、想像するだけで心が躍るよね。

ラモーナさんが日本語で書くこと自体、彼女の異文化への柔軟さと日本語への愛を物語ってるんだ。日本語って、論理的でもあり、詩的でもある、不思議な魅力を持つ言語だよね。彼女の感性とピッタリ寄り添ってる気がする。日本語で小説を書くって決めた背景には、言葉のリズムや美しさに心を奪われたからじゃないかな。ルーマニアの情熱的な感性と、日本の静かで繊細な美意識が交差する中で、彼女の小説はきっと独特な光を放つはずだよ。エッセイで見せる、感情の細やかな動きを捉える力は、小説でもキャラクターの心を豊かに描き出してくれるに違いないね。
彼女のエッセイ全体を通して、ルーマニアの感性は、日本の芸能文化を外から新鮮に見つめつつ、内側からじっくり感じ取ろうとする姿勢に溢れてる。ルーマニアの詩的な熱さが、日本の静かな美学と語り合いながら、彼女だけの特別な解釈が生まれるんだ。彼女の小説への情熱は、物語を通じて人間の心や普遍な出会いを描こうとする、胸の奥の強い願いそのもの。彼女がエッセイで言う「感動は全ての始まり」ってテーマは、彼女の創作の核としっかり結ばれてるんだよね。ラモーナさんのエッセイは、異文化の出会いが織りなす無限の美しさを教えてくれるし、彼女の小説がどんな物語を紡ぐのか、ほんと楽しみだよ。ルーマニアと日本の心が溶け合った新しい物語、早く読みたいって思っちゃうね!
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


